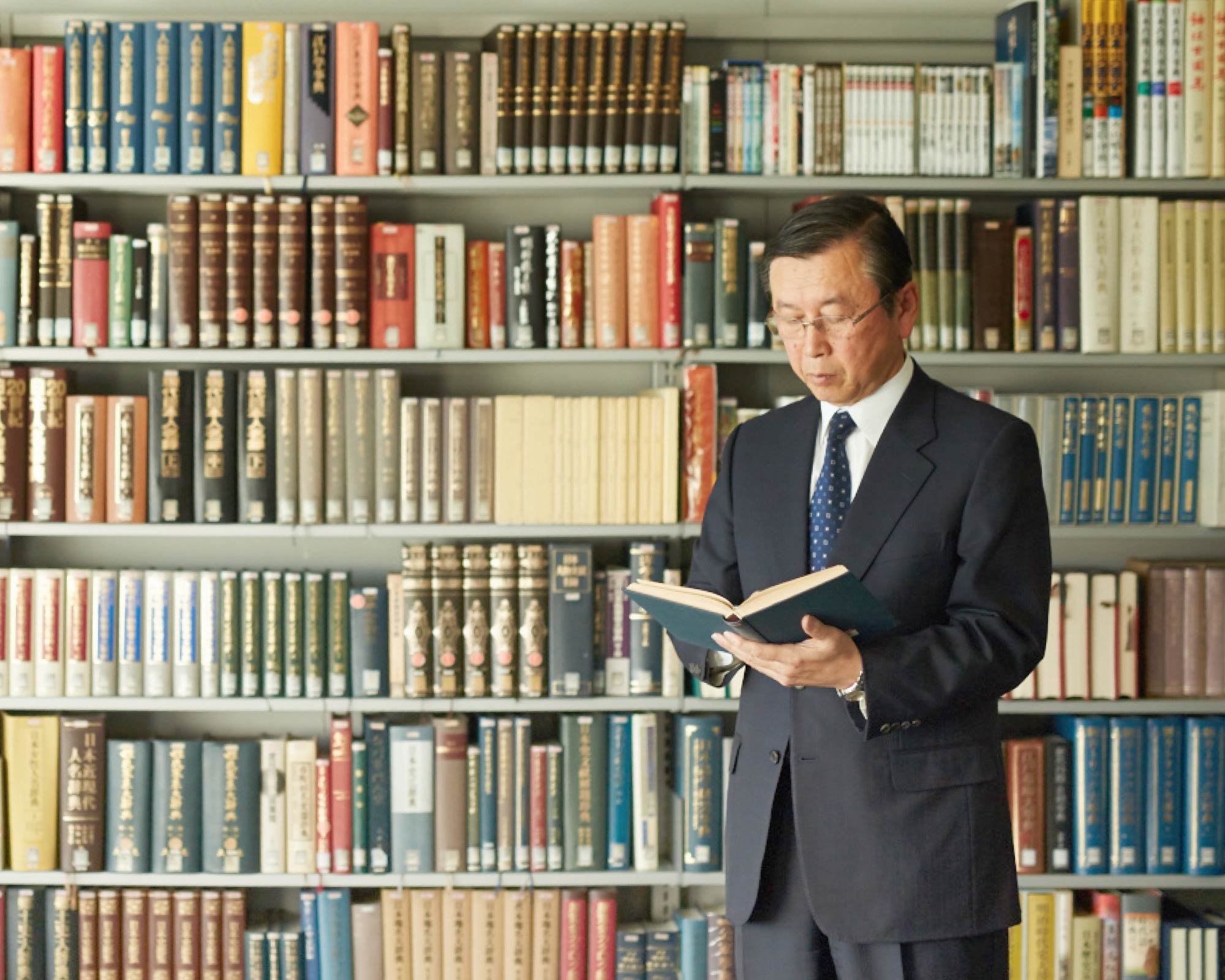- 國學院大學
- 國學院大學について
知の創造。 日本を見つめ、 未来をひらく
現在、社会構造の大きな変化、
社会変革が加速度的に進んでいます。
この現実を前に、人は自らの学ぶ意義を見出し、
主体的に生きながらも他者を尊重し、多様な背景を持つ人々と
共に生きていくことが強く求められているのです。
その中で大学に求められているものとは何か?
この問いに対して本学は、大学とは単なる知識の
伝達の場ではなく、教員と学生、また学生同士が共に学び合い、
既存の知を問い直し、知を創造する場であると考えています。
その実現に向け、建学の精神に基づいた日本と日本文化の
教育研究を柱にしながら、未来の共生社会を創り出す
人材を育成し未来をひらく大学へと邁進していきます。
問い直す 「知」を問い直し、新たな「知」の創造に挑む
絶対的な「知」は存在しません。
新たな資料の発見、新たな発想により「知」は変化と進化を繰り返します。
そのためには、既存の「知」を分析・検証し、熟考することが必要です。
「知」を不断に問い直すことが、新たな「知」の創造につながるのです。
共に生きる 多様な生き方を尊重し、認め合い、共に生きる
インターネットやSNSの発達によって世界は一つの共同体へと変化しつつあります。
このようなグローバル社会において、固有の言語・歴史・文化の違いを受け止め、認め合うことが求められているのです。多様な人々の生き方を尊重し、他者の課題を自らのこととして受け入れ、共に生きる姿勢が重要なのです。
学び合う 異なる価値観を持つ他者に寄り添い、学び合う
産業構造、社会構造の急速な変化によって、大学教育においても新たな学びのあり方が求められています。それは授業形態や授業方法の変化だけにとどまらず、
学生一人ひとりの学びに寄り添う姿勢が必要です。
こうした変化の中においても、教員と学生、学生と学生とが、それぞれの関わりをかけがえのないものと意識し、学び合うことが自身の成長へとつながるのです。
國學院大學は
不断の「知の創造」に挑んでいます。
-
教育
「問い直す」「学び合う」「共に生きる」 — それが國學院大學の教育目標。
國學院大學は、教養を身に付けるだけではなく、他者の個性を認め、力を合わせて共生しながら活躍できる人材の育成に取り組んでいます。私たちはグローバルな視点を持ちつつ、日本と日本文化を理解し、身に付ける必要があります。國學院大學には己の能力を遺憾なく発揮し、社会に貢献する意欲を持つ学生が集っています。 -
研究
大学の重要な使命は「知の蓄積」と「真理の探求」。国史・国文・国法から始まった本学の研究は、各分野の「日本」を牽引することがその使命です。日本と日本文化を研究し、国内外に発信することで、日本理解を推進しています。各事象を実証的に攻究し、国際日本学の雄となることを目指しています。
-
グローバル
社会構造の変化、IT技術の目覚ましい進歩によりグローバル化が加速しています。グローバルとは、自国文化への理解から多様性を尊重し、他者を理解することです。他文化との交流によって相違点を認識することに始まり、相手を受容し尊重する。そのうえで自身の変化をも受け入れる。このような真摯なその姿勢こそが國學院大學におけるグローバルです。
-
社会貢献・地域連携
社会や地域の価値創造への寄与は、本学の存在意義を証明するものです。さらなる貢献に向け、学生・教職員・卒業生といった人的資源、國學院大學が蓄積してきた日本への「知」や所有する史資料等の貴重な財産を生かして、共に学び合える社会の実現に尽力します。
-
経営政策
社会や人々から必要とされ続ける大学に求められているものとは何か。それは、どんな時代や社会においても活躍できる人材の育成です。学生の成長や生活に寄与するシステムの構築とともに、学生を支える教職員の能力向上を図る健全な組織作りに力を入れてまいります。
國學院大學は、2つのキャンパスを
拠点に活動しています。
RECOMMENDS
-
{{settings.title}}
{{settings.lead.title}}
{{{settings.lead.letter}}}
{{pages.title}}
{{articles.title}}
Language
SEARCH
{{section.title}}
-
{{item.tagline}}