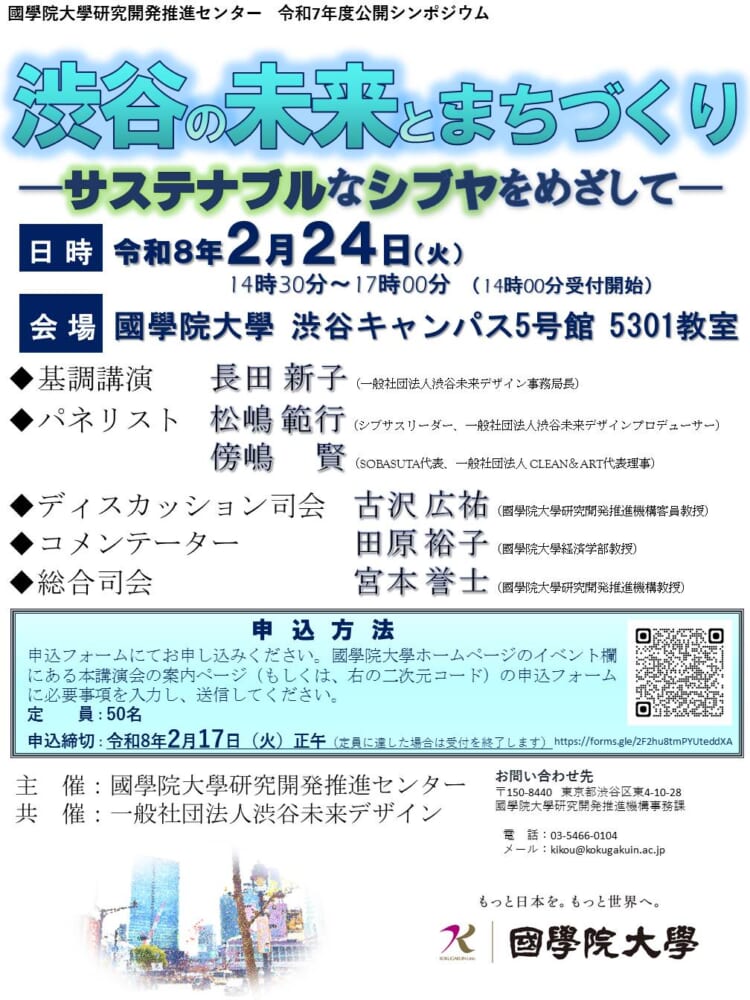現在の足尾・通洞地域と渡良瀬川。
今や、企業が社会的責任を全うすることは、いかなる事業でも当たり前の責務となった。サステナビリティ(持続可能性)の概念が重要になる中で、地球環境や地域住民の生活を守りながらビジネスを行うことは、絶対に破ることのできないルールと言える。
一方で、歴史を振り返ってみると、さまざまな事業活動が地域環境や地域住民に影響を及ぼし、公害として、今も問題として残っている事例がある。なぜこれらの問題は無くならないのか。そして、公害を無くすためには何が必要なのか。
「公害と向き合うとき、私たちは過去から学ぶことが必要です。大規模な公害を改めて見直すことで、企業のとるべき対応や振る舞い、あるいは公害を引き起こした時代背景や国策の影響が見えてきます」
こう話すのは、法学部の廣瀬美佳教授。公害問題などの視点から環境法を研究する同氏は、過去の事件から「今の企業がとるべき姿勢」が見えてくると考える。廣瀬氏の話をもとに、日本の“公害史”を振り返りたい。

長期化した公害事件、それを引き起こした企業の対応
――公害の歴史について、特にどのような点を学ぶべきでしょうか。
廣瀬美佳氏(以下、敬称略) 加害者側の事業者が「どう被害と向き合ったか」、また、被害者である住民や地域が「当時どんな状況にあったか」という点です。
まず加害者側において、公害対策として行うべき2つの柱があります。「発生源対策」と「被害(者)の救済」です。前者は、これ以上の被害拡大を防ぐこと、あるいはそもそも被害が起きないように予防すること。後者は、起きてしまったことへの損害賠償が中心になります。
この2つを誠実にできなければ、被害を増大させるだけでなく、企業としても何十年に渡り対応に苦慮することとなります。
その典型といえるのが、1880年代から100年近くにわたり続いた「足尾銅山鉱毒事件」と、1950年代に起こった熊本県水俣市での「水俣病」の集団発生でしょう。いずれも日本の公害の「原点」とされるものであり、歴史の教科書で見た人も多いはずです。
――この2つの事件には、どのような特徴があるのでしょうか。
廣瀬 詳しくは、後ほど振り返りたいと思うのですが、両者の大きな共通点は、事業者の「被害者対応の稚拙さ」です。簡潔に言えば、金銭の補償だけで話を解決しようとし、自分たちの非をなかなか認めませんでした。先ほどの2つの柱でいえば、「被害(者)の救済」をお金だけで済まそうとし、「発生源対策」を行わなかったのです。
分かりやすい例が、足尾銅山事件で締結された「永久示談契約」、そして水俣病で行われた「見舞金契約」です。
永久示談契約は、被害者側との示談の1つで、文字通り「この件を永久に蒸し返さない」という内容です。水俣の見舞金契約も似た内容のものでした。注目すべき点は、この示談締結時にどちらの事業者も「自らの事業が公害の原因」だと認めなかったことです。つまり、公害の発生源はそのままにしておきながら、今回の契約をもって、今後は一切話を持ち出さないという条件をつけたのでした。
だからこそ、見舞金契約では、あくまで“自分たちは加害者ではない”ということから、“お見舞い”という表現になったといえます。
――今となっては、非常に恐ろしい対応ですね。
廣瀬 その結果、逆に2つの事件は長期化して、足尾銅山は調停の成立まで100年近くを要し、水俣病は現在も事業者だったチッソが被害者救済の責務を負うほどになっています。不誠実な対応が、結局は企業を苦しめているのです。
だからこそ、私たちは歴史に学ばなければなりません。実際、そういった事例から学ぶことで、さまざまな企業の対応は誠実になり、改善されてきた面があるのです。
地域を支える企業だからこそ、訴えるのは簡単ではない
――もう1つ、被害者側が「どんな状況にあったか」を学ぶことも大切ということですよね。
廣瀬 そうですね。日本で民法が施行されたのは1898年で、足尾銅山事件は民法施行の前に起きたものでした。そのため、被害が発覚し、対応を企業に求める過程の半ばで民法が登場してきます。となると、それまでは法体系の整備が進んでおらず、被害者側が取れる手立ては十分に揃っていませんでした。
他の公害事件などを見ると、もし被害者が法律に基づき権利を行使できていれば、もう少し被害を小さくできた、十分な補償が受けられたかもしれないというものもあります。ただし、そこにも地域が持つ特殊な事情があるかもしれません。
たとえば、水俣病が起きた熊本県水俣市は、加害者となるチッソが町の経済を引き受けるほど大きな工場を構えていました。その土地の経済を支えている企業に対して、住民が疑義を呈することは簡単ではなかったでしょう。それが、事態を悪化させたのかもしれません。これは今の地方でも起こりうる問題です。
――ちなみに、日本での裁判における公害事件の捉え方は、どんな変遷をたどってきたのでしょうか。
廣瀬 その点で紹介したい2つの判決があります。1つは「大阪アルカリ事件」で、1916年に大審院(当時の最高裁)判決が下されたものです。工場が噴出する亜硫酸ガス・硫酸ガスの大気汚染による農作物の損害賠償が問題となり、工場側の賠償責任が認められました。今に至る「過失」の概念が示された重要な判決です。これは、予見可能性があったにもかかわらず、結果回避義務に違反した、という企業の責任を問うものです。

健在な頃の信玄公旗掛松。1906(明治39)年撮影。(長坂町誌上巻より)
もうひとつは「信玄公旗掛松(しんげんこうはたかけまつ)事件」で、1919年に大審院判決が下されました。武田信玄が旗をかけた、あるいは笠をかけたという言い伝えの残る松があったのですが、近くを通る国鉄の汽車の煙によって、枯死しました。そこで、その松の所有者だった原告が国に対して損害賠償を求めた裁判です。これは、公共性の高い国の事業であったとしても、原告の松を枯死させることは、社会的意義・目的を逸脱し適当な範囲を超えた権利の行使であるとして、「権利濫用」の法理が適用されて、原告が勝訴したのでした。
――民法ができたのは1898年ですから、それから20年ほど経った頃には企業側の過失を認める判決が下っていたのですね。
廣瀬 はい。とはいえ、時代が古ければ古いほど、まだ法律の概念や使い方が一般市民まで浸透しておらず、裁判に打って出ずに示談でまとめられてしまったケースもあります。そういった時代背景や、被害者側の状況も踏まえて見ていくべきです。
そしてもう1つ重要なのは、大規模な公害事件には、国策と無関係ではないものもあったということです。
足尾銅山事件の裏には、国策の影響もあった
――「国策と無関係ではない」とは、どういったことでしょうか。
廣瀬 それについては、日本の公害史を細かく振り返ると分かりやすいでしょう。日本で大きな公害問題が起こり始めたのは、明治以降、近代化されてからだと考えられます。それまで小規模なものはありましたが、大規模で広域的に事件化するのは明治以降でしょう。
今でこそ「公害」という漢字を使いますが、最初に発生したのは、鉱山採掘から巻き起こった「鉱害」です。その先駆けが足尾銅山事件であり、別子銅山、日立鉱山、小坂鉱山と、立て続けに鉱害問題が噴出します。これらは「四大鉱害事件」と呼ばれています。
――鉱害の連続発生と国策にどんな関係があるのでしょうか。
廣瀬 当時は明治に入ったばかりの頃で、日本は欧米に追いつこうと「富国強兵」「殖産興業」を掲げます。最初は生糸の生産に力を入れていましたが、次第に近代軍備や欧米からの技術を移植することを重視します。
この際、財源を確保するために国家的な保護を与えられたのが鉱山でした。つまり、政府も鉱山での事業を後押しします。そのため、上述の鉱山での事業が活発になるのです。
これ自体は問題ないのですが、鉱害被害が発覚した後も、事業を後押ししていたがゆえに、政府が鉱害を食い止める存在として機能していなかったら話は別です。実際、足尾銅山事件では、政財界との関係性があり、被害者らの訴えが無碍にされていた様子が垣間見えるのです。
――当時の時代背景などを細かく検証する意義がそこにあるわけですね。
廣瀬 はい。ですので、足尾銅山事件を軸に、まずは四大鉱害事件を紐解いていきたいと思います。
そもそも足尾銅山事件とは、栃木や群馬にまたがる渡良瀬川流域の広範囲に被害をもたらしたものです。1871年に足尾銅山が民営化されると、古河財閥が買収し、急速な近代化が進みます。
鉱害の発端は先述した1880年代で、1890年代に入ると足尾山塊から続く渡良瀬川で頻繁に洪水が起こるようになります。もともと洪水の起こりやすい川とはいえ、明らかにその量は増えました。
原因は、足尾銅山から排出される煤煙に鉱毒ガスが含まれており、銅山の木が枯れ、山が保水能力を失ったことです。はげ山になるほどの枯れようで、現在でもその面影が残っています。
さらに、洪水によって堤防が決壊すると、鉱毒を含んだ水が下流域に流れて、農地を汚染しました。結果、現地で作っていたコメは鉱毒の影響で収穫不能となったのです。これを発端に、社会問題化しました。

足尾銅山 本山精錬所跡の煙突。周辺には、今も山肌が露出している部分がある。
――先ほどのお話を踏まえると、この時点では事業者側は過失を認めなかったということですよね。
廣瀬 はい。この後、田中正造という議員を中心に、帝国議会などでたびたび足尾の鉱毒問題を訴えますが、なかなか進みません。
そういった中で、事業者側の古河鉱業(現:古河機械金属)が出したのが、先述した永久示談契約でした。1895年以降、被害を主張する村々と締結していったもので、ある契約では5000人を超える被害農民に対し、総額およそ3万円(現在の物価に直すと約1億1400万円)以上の賠償金を支払ったといわれます*1。もちろんそれなりの金額ではありますが、お金を渡すだけで、自分たちが原因と認めませんでした。
当時、鉱毒調査委員会なども立ち上げられましたが、洪水は渡良瀬川の治水の問題であり、鉱毒についても、もともと銅山の土壌に含まれていたものが洪水で出てきたという見解にしたのです。操業は原因ではないという考えで、発生源対策は行われません。だからこそ、以後も鉱毒問題が続いていったのです。
――それが長期化につながるということですね。
廣瀬 はい。なので、ここまでの話は序章で、事件は以後80年近く続きます。次回はその後の顛末と、加害者の対応を、別の鉱毒事件と比較しながら詳しくご説明したいと思います。
*1:森長英三郎『足尾鉱毒事件 上』(日本評論社)74頁以下参照。
次回は「鉱害事件の事態収拾のために沈められた村」>>
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
- 第1回 足尾と水俣が数十年にわたる大公害事件となった理由
- 第2回 鉱害事件の事態収拾のために沈められた村
- 第3回 水俣病の被害拡大はなぜ止められなかったのか
- 第4回 水俣病を止められなかった「企業城下町」の構造
- 第5回 私たちが公害の“加害者”にならないために必要なこと
廣瀬 美佳
研究分野
民法、医事法、環境法
論文
医療における代諾の観点からみた成年後見制度(2015/06/10)
平成25年法律第47号による精神保健福祉法改正と成年後見制度 ―医療における代諾の観点から―(2014/03/31)