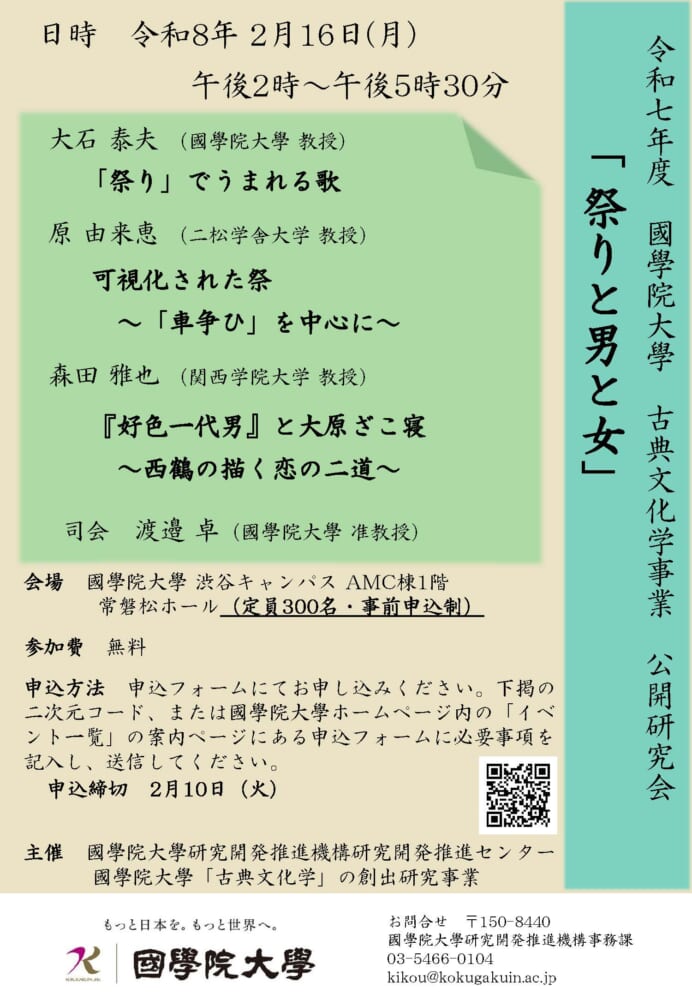日本の古代に興味がある人のみならず、広く歴史好きの読者を魅了しうる書籍が生まれた。笹生衛・神道文化学部教授(國學院大學博物館館長)による新刊『まつりと神々の古代』(吉川弘文館、 2023年)だ。
文献史学・考古学だけでなく、参照するのは人間の脳のメカニズムを捉えた認知宗教学や、気候変動の復元研究といった自然科学的な知見。そのうえで、自らも多くを学んできた民俗学──柳田国男・折口信夫による民俗学の神・霊魂観を、丁寧に、そして批判的に再検討しながら、新たな、いや古代本来のまつりや神々の姿をとらえようとしている。刺激的な一冊を上梓した笹生教授に、前後編の著者インタビューを行った。
日本の伝統的なまつりや神々、霊魂を論じるにあたって、民俗学が築き上げてきた成果は、とても大きいものです。現在に至るまで特に大きな影響を与えているのは、柳田国男と折口信夫による大正から昭和初期にかけての研究ですね。
柳田は「依坐(よりまし)」に宿る神、折口は神が依り憑く「依代(よりしろ)」という神の古いイメージを描きました。その場に神がいるのではなく、祭るにあたり神を招くというイメージですね。柳田・折口ともに、民間の習俗の観察や聞き取り、日本古典の精読に加え、当時最先端であったJ・G・フレイザーらによるヨーロッパ流の人類学を参考にしながら、こうした研究を進めていったのです。だからこそ学問としての奥行きが生まれ、現在に至るまで100年以上にわたって、長く参考にされ続ける学問的な枠組みを作ることができたのでしょう。二人の研究が偉大である所以です。
ただ、柳田・折口が打ち立てた枠組みを、後世の私たちはあまりに普遍化させて日本の古代の神々を考えすぎてきたのでは──そんな違和感が、『まつりと神々の古代』収録の論文執筆の動機としてあるのです。民俗学の研究成果に多くを依拠してきた古代日本の神・霊魂あるいは祭りや儀礼の考え方について、同じ枠組みで議論を再生産するのではなく、かつて柳田・折口が当時の最先端の学問を吸収しながら自らの研究に取り組んだように、100年後の我々もアップデートしなければならないのではないか、と。

たとえば皆さんも、パワースポットという言葉をよく耳にされるのではないかと思います。著名な神社などに足を運んだときに、やはりここは気の流れが違うという方もいるでしょう。また別の見方をすると、水源となる山の山麓や河川に面する場所に、古代の祭りの遺跡である「祭祀遺跡」が立地する事例が多くあります。特別な場所の雰囲気、その環境から人が直観的に感じる感覚と神・霊魂観は密接に関連しているのではないかと予想できます。実はこうした感覚は、柳田・折口の、「依りまし・依代」に宿り・憑依する神・霊魂観とは異なるものです。一方で古代の文献には「坐す神」(ますかみ)という表現が度々出てきます。これは、特定の場に居られる神という意味で、神の存在が、特定の“場所”と密接にかかわっていることを示します。
柳田・折口の考え方は、民俗学のみならず歴史学や考古学にまで大きな影響を与えました。その一つが大嘗祭(践祚大嘗祭)の解釈です。折口は、大嘗祭は、代々の天皇が「天皇霊」を継承するための祭祀であるとの考え方を提唱しました。しかし『まつりと神々の古代』で最新の文献・考古学研究を踏まえながら、奈良時代・古墳時代まで遡って再検討したように、大嘗祭を「天皇霊継承の祭祀」としてとらえる諸説は成り立たないことが明らかになってきています。日本の神まつり・祭祀と神々のとらえ方そのものを、全体的に、かつ具体的に再検討していくべきだと私は考えたのです。
だとすると、どのように再検討すればよいのか。『まつりと神々の古代』では、文献史学や考古学の新しい研究成果のみならず、認知宗教学や、気候変動の復元研究といった自然科学的な知見も参照しました。
先ほど場所・環境と神との関連性を話しましたが、日本の自然環境と神々との結び付きを、より具体的に明らかにするため、理化学的な手法による過去の気候変動の復元研究を参照したのです。私は若い頃から埋蔵文化財の発掘調査に携わるなかで、海浜に砂が一気に堆積したり、河川の底が浸食で短期間に低下したりする時期があったことをつかんでいました。そのようななかで、近年、過去の気候変動の復元研究と出会ったのです。その研究では、10世紀に社会が激変するきっかけとなっただろう激しい気候変動があり、それが海浜や河川などの自然環境に影響を与えていることが明らかとなってきました。
その詳細や、社会変化のなかで神輿や祭礼が生まれる経緯については以前のインタビューで話しましたので、ぜひ一読いただきたいと思います。いずれにせよ、神々のとらえ方とまつり(祭り)のありようが、どうやらこの10世紀に大きく変化していたようなのです。そして、10世紀に変化した神々のとらえ方や祭りのありようが、その後の神社や祭りの原形となり、現在につながっており、そのなかで民俗学が研究対象とする祭りも形作られたのです。このため、10世紀よりも古い時代の神々のとらえ方、祭りの姿を知るには、民俗学とは異なる方法で研究を行わなければなりません。そこでは、なぜ人間は目に見えない神・霊を感じ信じるのか、というメカニズムを明らかにする必要があります。「人間なら生存のため、こう直観する」という、人間の脳の認知機能にもとづく「認知宗教学」の視点は重要な手掛かりを与えてくれました。
認知宗教学に関しては、すでに多くの知見が示されています。代表的な例としてパスカル・ボイヤー氏の研究を参照してみましょう。
人間は、特定の現象の背後に、それを起こし司る「行為者」を直観し、心をもつとイメージする。ボイヤー氏は、こう指摘します。例えば、太陽は輝き、山・泉・川は貴重な水を供給し人々の生活を維持し、山・海の環境は多くの幸を恵む。また、海上の島は、豊かな漁場や航海の目印となる。一方で火山噴火や旱魃・大雨・洪水は人々に混乱と死をもたらす自然災害でもあります。これらは、いずれも自然の特定の現象です。その背後の行為者こそ、人間と同じ心をもつ太陽・山・海などの神となるわけです。これが自然の働きに神を直観する自然崇拝のメカニズムです。
詳しくはインタビュー後編でも触れますが、10世紀の大きな変動の後に成立した神・霊魂観を、10世紀以前にまで遡及させるのではなく、あくまで人間が生存のために持っていた、普遍的な脳の認知機能を手がかりに古代の文献と考古学資料を素直に読みなおしてみよう。そこに、私が認知宗教学を援用した狙いがあるのです。

大場磐雄著「まつりー考古学から探る日本古代の祭(新装版)」(学生社、1996年)
実は本書を執筆するなかで意識していたのは、我々の大先輩である大場磐雄先生の著作『まつり』(学生社)です。昭和42(1967)年に刊行され、平成8(1996)年にも新装版が出されるなど、現在に至るまで名著とされている一冊です。神社・まつりの実態を、考古学の立場で、原始・古代から中世までを見通そうと大場先生は試みておられます。一方で、大場先生は折口信夫の五博士と呼ばれるほど折口から薫陶を受けた弟子した。ですから、大場先生の古代のまつりや神の解釈は、折口から多分に影響を受けたものでした。
その大場先生からの学統を継ぐ私が、『まつり』のテーマを、半世紀以上の時間を経た現在、最新の研究成果とともに考えてみよう。『まつりと神々の古代』とは、そのようなねらいで著した一冊です。インタビュー後編では、本書を執筆しながら改めて見えてきた国際的な論点などについて、より突っ込んだ議論をご紹介したいと思います。
後編は「「起請文木札」から日本の神・霊魂観にまつわる、大きな社会的変動の痕跡を読む」>>
| 1 | 2 |
笹生 衛
研究分野
日本考古学、日本宗教史
論文
古代の水の祭祀-祭祀遺跡と文献史料から考える―(2025/03/27)
10世紀の気候変動がもたらしたもの―東国の集落と水田の景観変化から―(2024/08/01)