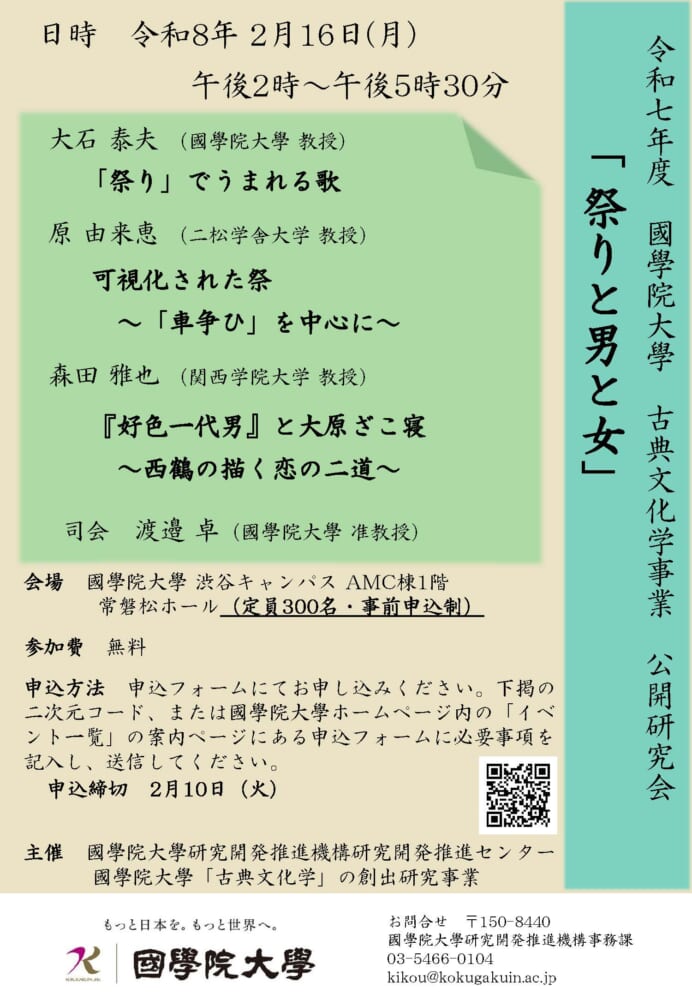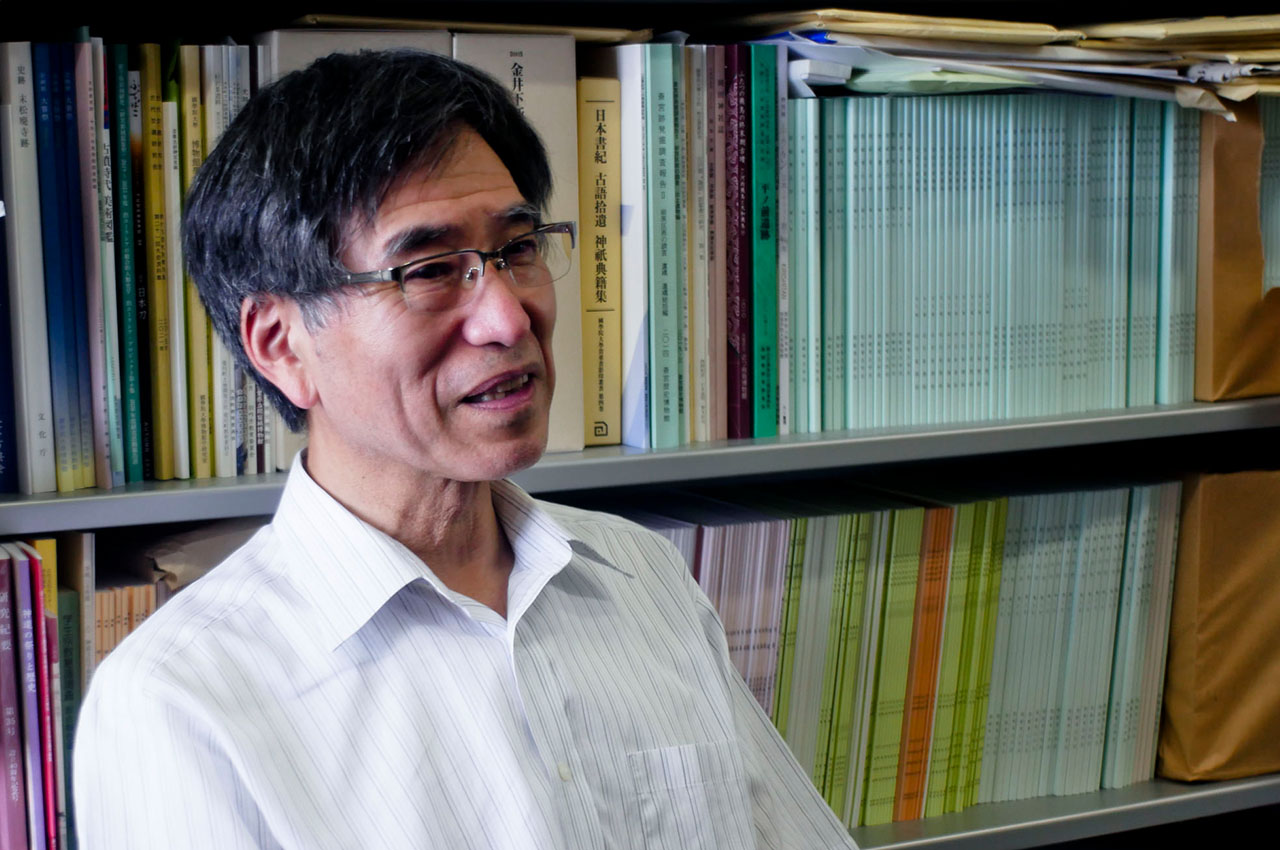
商売上の自らの誠実さを示すため、神々への誓約を書いた「起請文木札(きしょうもんきふだ)」。その文言からは、古代末期に日本の神・霊魂観が変化する様子が浮かび上がってくる──。
笹生衛・神道文化学部教授(國學院大學博物館館長)の新刊、『まつりと神々の古代』(吉川弘文館、2023)にかんする著者インタビュー。その後編で語られるのは、最新の知見を過去の歴史に重ねることで、正確に当時の社会の姿を照射しようとする、慎重かつ大胆な研究の一端だ。そんな笹生教授の見解が束ねられた本書には、来たる国際的な議論へ向けた、ある願いも込められている。
10世紀の自然環境の変化とともに、社会のありよう、そして神のとらえ方「神観」が変わっていったことは、インタビュー前編で触れました。特定の現象と結びついた場所に、その現象の行為者「神」は居られるという、古代の「坐す(居られる)神」という神観は、そのベースとなっていた自然環境そのものが変質したことで神観まで変容を遂げたと、私は考えています。
たとえば世界遺産となった「神宿る島」宗像・沖ノ島と関連遺産群の宗像の神々への信仰も10世紀以降に大きく変容しました。やはり、10世紀以降、港湾に適した宗像の海岸の地形が大きく変化し、それに伴い、神観や神まつりのありようが、仏教の影響をうけながら変容していった状況が確認できました。詳しくは、世界遺産「神宿る島」宗像・沖ノ島と関連遺産群、特別研究事業成果報告書を御参照ください。『まつりと神々の古代』の第5章「塩津の神と神社──変化する古代の神社」は、そうした自然環境と共に変質する神社の一例です。
塩津港遺跡は滋賀県長浜市、琵琶湖北端の塩津湾に面しており、琵琶湖の水運で賑わった古代末期の大規模な港の跡です。港の跡に隣接して、境内全体の様子がわかる神社の遺構も残されていました。神社の遺構は、これまでの発掘調査で、平安時代の後半、11世紀から12世紀にかけての神社本殿、付属する建物群も含め、どのように境内の景観が変遷したのかが明らかとなっています。
発掘調査の成果として興味深いのは、下層にある8・9世紀の神社が、9世紀後半頃、琵琶湖の水位上昇で一度水没、11世紀後半に再び陸化して神社が再興されていた点です。その直後の11世紀末期には港湾部分で埋め立て造成がはじまり、12世紀には船を接舷できる大規模な港湾が成立しました。
実はこの過程で、神や神社のありようもまた、大きな変化を遂げていました。変化がうかがえるのが、塩津港遺跡の神社遺構から出土した「起請文木札」です。年紀を確認できる木札は保延3(1137)年から建久3(1192)年のあいだのものでした。これらは水運を担う運送業者の誓約を墨書した木札で、預かった物資を盗んだり、失くしたりしないと書いています。彼らは、誠実に運送の仕事をすることを、神々に誓約しているのです。
起請文木札の冒頭には、誓約する神々の名を連ねる神文が書かれています。面白いのは、まず梵天・帝釈天など仏教系の神々「天部」から書き始め、続いて日本の神々が名を連ねるという神文の構成です。
そもそもなぜ、起請文が必要なのか。11世紀末期には、塩津港の北、日本海の港である敦賀には中国・北宋の商人が来着しており、交易の範囲は東アジア規模で拡大していました。交易範囲が拡大するなかで、場合によっては、国や出身地が異なる、初対面の相手と取引をしたり、大事な荷物を託したりする機会が生じ、そこでは「信用」が問題になります。その「信用」を担保するものとして、「起請文木札」が極めて有効に働きます。なぜならば、人々の行為を監視できる仏教の天部に誓約をして、誓約を破れば厳しい罰が下されることを明記しているからです。そして、そこに日本のローカルな神々も参加することになります。
古代日本の神々、例えば、住吉に坐す住吉大社に祀る住吉三神は、『日本書紀』で「港に出入りする船を見守る」とあるように、安全に船を停泊でき、瀬戸内海の水運から大和への内陸交通に接続できる住吉の地形・環境の働きに行為者「神」を直観した存在と考えられます。住吉の地形・環境のような特別な働き・現象が現れる自然環境・場に神は居られると認識される。特定の環境・場所に「坐す神」であり、その意味で特定の環境と直結した、ローカルな神なわけですね。
しかし流通が活発となり、交易の地理的な範囲や、関係する人々が拡大し、広範なネットワークを成立させるには、ローカルな神々に誓うのでは「信用」を裏づける精神的な土台とはなりえない。そこで、「信用」を獲得するために梵天・帝釈天などの仏教の天部が必要となったのです。仮にローカルな神々のことを知らない取引相手であっても、アジアに広く浸透していた仏教の天部であれば「その神々なら私たちも信仰している」となり、「その神々に誠実な仕事を誓い、もし破れば厳しい神罰を受けると約束する。そうならば信用できる」と受けとられ、アジア基準で「信用」を築くことができるわけですね。
次に仏教の神々である天部と日本の神々との関係が問題となります。9世紀初頭、空海は、唐の高僧である不空が改めて訳し直した最新の鎮護国家の経典『仁王経』を唐から持ち帰ります。10世紀には旱魃・疫病蔓延に際して、朝廷は、この『仁王経』を神社の神々に読み聞かせ、同経が説くとおり、日本の神々に国土守護の役割を期待するようになります。そして11世紀初頭には賀茂の神、石清水の八幡神などは、王城鎮守の神として法会の場に「勧請」される存在として登場します。11世紀の末期には、塩津港では物流の活発化を反映して港湾施設が拡大し始め、「起請文木札」が作られるようになったのです。
すでにふれたとおり「起請文木札」の神文には日本の神々の名も書かれており、それは天部と同様に日本の神々も神名を唱え神霊を招く「勧請」できる存在として認識されるようになったことを示しています。勧請とは、本来、仏教の考え方です。日本の神々が仏教の天部と同じく扱われるようになり、仏教の考え方で理解されるようになったからでしょう。その一方で、神霊を招くという勧請の神観は、折口信夫による「依代に神霊を招く」という神観と重なります。おそらく折口は、こうした十世紀以降に変質していった神観をもとに議論を組み立て、それを十世紀以前の古代社会にも当てはめてしまったのではないか……。拙速な結論は避けなければなりませんが、私はこうした問題意識のもとに、日本古代のまつりや神々のとらえかたをアップデートできれば、と考えているのです。
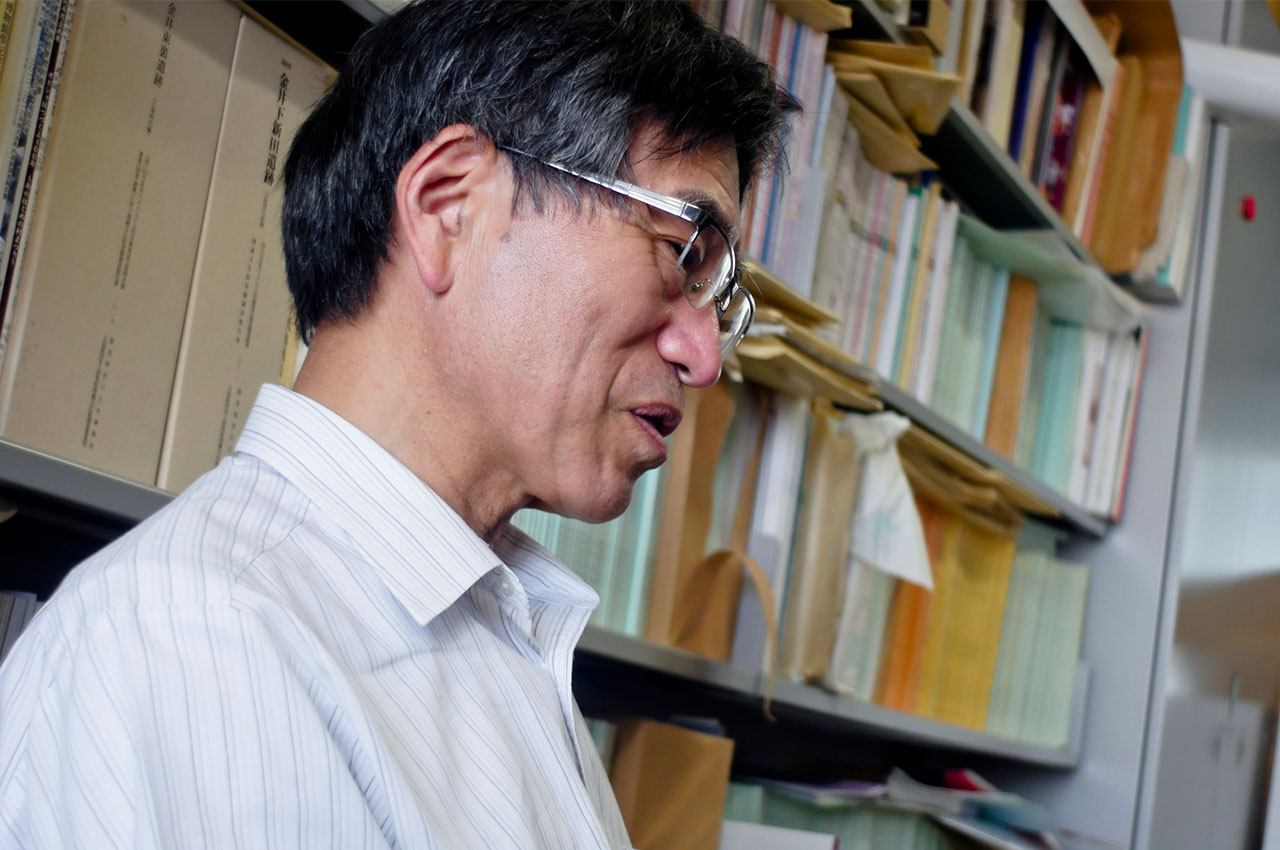
さて、このような観点で実証的に考えていきますと、日本のまつりや神々にかんしても、東アジアという広範な地域を視野に入れて考えなければならないことに気づきます。そして、認知宗教学や気候変動の復元研究といった知見を参照するのも、私としては、日本のまつりや神々をめぐる議論を世界的な人類史のなかに位置づけられれば、との思いがあるからです。
そもそも原始以来、地球上の各地に広がった人類は、それぞれの自然環境と自らの認知機能とでキャッチボールを重ね、結果として、各々の環境に適応した多様な文化・社会を創造してきたという側面があります。宗教文化は、その代表的な例といえるでしょう。ですから、それらをめぐる議論もまた、お互いの文化理解に寄与できる視点にもとづくものでありたい。そうすれば、「わたしたちの地域ではこんな例や議論があるのだけれど、あなたの所はどうですか?」「なるほど、こちらでは……」と、知の交換ができますよね。それは、世界の人々の宗教文化に対する相互理解にまで発展できる。そうした未来の議論につながればと思いながら書いたのが、『まつりと神々の古代』なのです。
<<前編は「気候変動・環境変化とともに社会のありよう、神・霊魂観は変った」
| 1 | 2 |
笹生 衛
研究分野
日本考古学、日本宗教史
論文
古代の水の祭祀-祭祀遺跡と文献史料から考える―(2025/03/27)
10世紀の気候変動がもたらしたもの―東国の集落と水田の景観変化から―(2024/08/01)