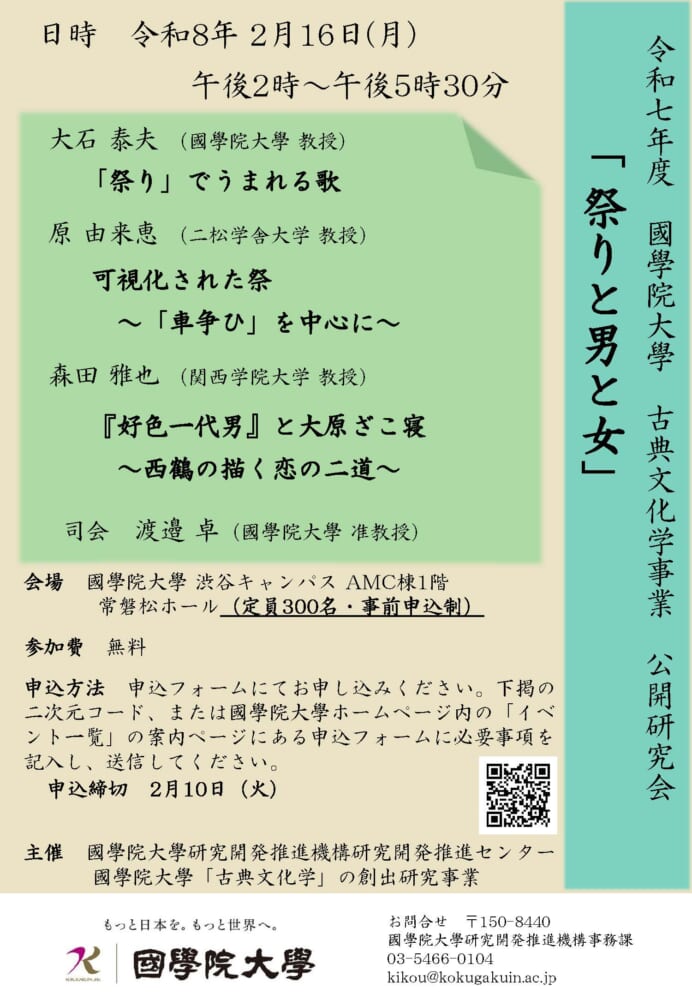| 言葉は、誰かとの共通理解のために用いられる。それが当然のことだと、私たちはいつの間にか信じてしまっている。しかし、言葉を使うことによって、むしろ理解できない何かと出会うことにこそ豊かさがあるのだといわれたら、どのように感じるだろうか。共通理解を目指して言葉が尽くされるからこそ、私たちはその言葉の余白のなかで出会い直す。その名状しがたい領域に「人文知」の存在意義もあるのだ、といわれたとしたら。 近年注目が集まる「人文知」の可能性を、國學院の学内から再発見していく企画、人文知探究室。ジャンルを横断しつつ、多様な専門家に問いを投げかけるインタビューシリーズの6人目としてこの度、石川則夫・文学部教授に話を聞いた。日本近代文学を専門とする石川教授だからこそ語りうる、常に言葉と共にある人間がもつ独特の揺らぎ。傍らにAIを携えつつ、私たちはいましばらく、言葉の不思議が満ちたこの世界を生きていくのだろう。 |
| ▼もくじ |
再現も反復もできない変化する側面を扱う
探究室 石川教授には以前、ご自身の専門分野である日本近代文学についてインタビューさせていただきましたが、今回はより広く、人文知というテーマでお話をうかがえればと思います。人文知という知のありようは、ご自身の目にどのように映っているでしょうか。
石川 ひとまず対置されるものとしての自然科学は、研究する対象に関して数値化などを施しながら検証していくものですよね。そこで目指されるのは、不都合なく再現・反復・観察可能な結論に至る、ということだと思います。こうしたいわゆるサイエンスの姿勢に対して、人文知は異なる側面をもつのだと私は考えます。思い切って言ってしまえば、人文知において導き出されるものは、再現も反復もできないものなのではないか、と感じているのです。
探究室 再現も反復もできない知、ですか?
石川 そうですね。研究対象を把握する人、認識する人によって各々異なる結論に達するでしょうし、同じ人であっても機会が異なれば、また別の結論に至るということが往々にしてあり得る──それが人文知というものだと、私は思います。
探究室 なるほど……。納得できる人もいるだろう一方で、かなり衝撃的な意見だと思う方もいるように想像します。
石川 私たちは、言葉を用いて議論をしますよね。知は共有化できるものだと捉えているからこそ、言葉を用いて他者へ自らの考えを差し出すのだと思います。文学研究の領域で行われている研究会や学会でも、私たちは絶えず学知の蓄積とその共有化を図っている。ただそれが、誰もが同じ結論に達するという意味での共有化とは違う、ということなのです。たとえば明治時代に書かれた森鴎外や夏目漱石らの小説は、既に100年以上研究されてきていますが、そこで前提とされているのは、既存の研究の流れを踏まえながら新しい知見を提出していくというスタイルです。私自身も、こうした研究の世界に生きています。しかし実態をよく見てみれば、本当に私たちは、何か累積的なかたちで議論のゴールへと進んでいるのでしょうか?

探究室 知は積み重ねられつつも、しかしそれがある結論へ向かって集約されていくわけではない、ということでしょうか。
石川 はい。もちろん研究者一人ひとりは、自分のなかに何かしらの目標はあり、そのゴールを見据えながら研究という行為・作業を繰り返しているはずです。ただ、それが集合的な営みとなったときに、反復可能な結論というひとつのゴールに収束していくのかどうかという観点は、実はかなり曖昧にしたまま議論をしているのですね。私はむしろ、反復不可能だと言い切ってしまってよいように感じます。各人の研究の成果は、その人の個性や物事の捉え方が浮き彫りになるようなもの、研究者の固有性が大きくかかわってくるのではないか、と考えているわけなのです。時代を経るごとに議論が進んでいくように一見思われながら、むしろその人の個性が輝いているところにこそ真の重みが見いだされる、それが人文知の姿なのではないか、と。
探究室 人文知がおっしゃるようなものだとすれば、まちまちの見解しか導き出されないにもかかわらず、それらを持ち寄って議論していて、しかも共通の見解を導き出そうとしているのではない、ということになりますよね。
石川 先ほども鴎外や漱石に触れましたが、ここでもひとまず、私が専門にしている文学表現を踏まえてお話ししてみます。私たちは、言語表現にかんする研究成果を、言語表現として形にしています。数式を用いて他者に伝達するという人は多くありません。漱石自身が『文学論』において文学の経験とは〈F+f〉という数式で表されると述べていますし、近年であればテクストのデータ解析によって研究を進める人もいるわけですが、文学という言語表現の研究が、同じ言語表現というアウトプットを基本としているということは、疑いようのない事実だと思います。そしてそこにはたしかに、各々が論理的だと感じ、他者にとってもロジカルだと考えている研究の方法や手順があるわけで、一つひとつ段階を踏んで、結論めいたものに達していくわけです。
探究室 その営みは一見、知が集約されていくものであるようにも見えますが……。
石川 もちろん、客観的な表現を用いて、ひとまず知の共有を目指しているわけです。しかし、その言葉を解する人であってなお、表現されたものを通して同じ意味合いを受信することができるとは限らない。こうした事態は、言葉を用いる際には常に起こりうることであって、研究者もまた逃れることはできません。言語表現がもつ本質にかかわることなんですね。そうした言葉によって知を共有しようとする人文知は、厳密にいってしまえば、ひとつの共有された知には達しえない、という逆説があるということなのです。
探究室 そうした人文知が、それでもある種の説得力をもちうるのはなぜなのでしょうか。世の中を見渡しても、人文知に対する一定の期待感があるように思われます。
石川 世の人文知に対する期待ですか、何が託されているんでしょうね……。ふと頭に浮かぶのは、自分の考え方とはまったく異なる物の見え方に気づいたり、自分とはまったく関係ないと思っていたこととの強いつながりを見つけたり、ということが人文知の世界では当たり前に起こる、ということです。たとえば大学のゼミで、卒論の中間報告会を開くとします。もちろん先ほど申し上げたような研究方法の指導もしていまして、過去に積み重ねられてきた研究成果を踏まえつつ、そのうえにひとつ、自分の読み方を積むように進めようとは伝えているんですね。そうした方法に則りつつ、決して短くはない月日を共に過ごしている仲間の発表を聞く。しかしそれでもなお、自分と隣り合う人が選んだテーマや、そこで発表されている物の捉え方というものが、あまり理解できないということはよくあるのです。そこにいる人間の数だけの発見がある──これは文学をはじめとした言語表現においては常態といっていいと思います。

思わず書かされてしまったような一文に出会う喜び
探究室 自分の足もとに揺さぶりをかけ、他なる物の見方に目を開かせてくれる状態こそが常、ということですね。
石川 そうした発見が、自分にとって本当に納得されるように感じられるのは、何もその場でのことだとも限らない。場合によっては何年もかかるでしょう。大学を卒業してから、ある瞬間にハッと、そうか、あの友人が語っていたことはそういうことだったのか、と腑に落ちるようなことさえ起こりえる(笑)。瞬間的な知ではない、ともいえるかもしれません。
探究室 ご自身にとっても、たとえば学生さんと文学の議論をするなかで、新たな発見に至ることはありますか。
石川 たくさんありますよ。たとえば、ある学生が卒業論文で、伊藤計劃という作家を扱いたいといってきたんです。私はまったく読んだことのない現代作家でした。
探究室 『虐殺器官』や『ハーモニー』といった小説で、2000年代後半から大変な人気を博してきたSF作家ですね。残念ながらデビュー間もなく三十代の若さでなくなられてしまいましたが、映像化も含めてその作品群は、いまなお大きな影響を読者に与え続けています。
石川 何も前提知識がない領域ではあったのですが、読んでみようかと手を伸ばしてみると、これがまた面白いわけです。そして読んでいくうちに、単純なSFではないことにも気づかされていく。ひょっとしたら神話的な構造があるんじゃないかとか、いろいろと考えさせられるところがあるんですね。私にとっても大変有意義な経験でした。またそうした気づきは、新たな作家や文学作品を読む場合にだけあるわけではありません。たとえば、誰もが知るような芥川龍之介『羅生門』でも、改めて読んでいるとハッとすることがあるわけです。
探究室 国語の教科書にも掲載されてきて、多くの人にとってなじみがある作品ですね。
石川 みんなで読んで、読んで、ある意味では読みぬかれてしまっているような作品であるはずですよね。「ある日の暮方の事である。一人の下人が、羅生門の下で雨やみを待っていた」という書き出しから、「下人の行方は、誰も知らない」という末尾まで、私たちはまるで羅生門のことを知悉しているようなつもりになっている。しかし再びひもといてみると、ああ、こんなことが書かれていたのか……と、驚くのです。たとえば、小説が始まって間もなく、こんなフレーズが書かれていることに、私は大変な新鮮さを覚えます。
雨は、羅生門をつつんで、遠くから、ざあっと云う音をあつめて来る。
石川 どうでしょう、すごい一文だと思いませんか?(笑) なかなか書ける文章ではないですよ。

探究室 たしかに……。目の前の羅生門への視点が、遠方への視点と同時に存在していますね。加えて雨の音に取り囲まれることによって、現代的な表現を用いるのならばイマーシブ(没入的)な感覚さえ抱きます。
石川 『羅生門』は下人の物語だと、誰もが了解しているわけです。しかしこの文章は、そうした共通理解の外にある。まるで世界の一瞬が活写されたショットといいましょうか、小説のなかからまるで浮き上がって見えるような、詩的な一文だということができるように思います。考えて書こうとした一文ではないといいましょうか、思わず書かれてしまった一文だと表現していいものかもしれません。そして実はこの感覚が、人文知においても大事なものかもしれないとも感じます。
探究室 思わず書かれてしまった一文の、人文知的な重要性ですか。どういうことでしょう。
石川 学生たちが卒業論文を書く場合、4年間の集大成として2万字以上の文章を書くことになります。自分で問いを立て、物事を調べて、考え、仮初めのものであれ結論を出していくというプロセスはもちろん重要です。そのうえで私が最も期待するのは、どういえばいいのでしょうか、その学生が考えてもいないようなことがパッと零(こぼ)れ落ちる瞬間なんですね。
探究室 自分で書いているのに、自分が書いたようではない一文、ということですね。
石川 卒論というのは議論を整理し、文章の意図を明確にしながら書いていくわけですが、そのうちに自分でも思いもしなかったことが書けちゃう、という瞬間が訪れることがある。その一文は、こちらから指摘しない限り気づかないものなんですが、読んでいるとわかるものなんですよ。そうした文章は、平たくいってしまえば、文学の表現に近いのです。先ほどの『羅生門』の一文のような、本人にも思いがけないフレーズが出現する。まさにそのようなフレーズが書き込まれた文学表現を読みながら、まとまった文章を書いていく過程のなかで触発され、言葉として書きつけられる。それは非常に重要なことなのだと、私は考えます。
探究室 そのお話は、昨今のAIにかんする議論にも接続できるものであるような気がします。自らならざる文章を誘発するという意味では、生成AIを相手にしつつの文章術が巷間で用いられつつありますが、仰っている“自分が書いているけれども自分のものではない文章”は、またすこし違うものですよね。
石川 そこで重要になるのは、AIは個性に基づく問いを立てられるのか、そのうえで文章を紡ぐことができるのかどうか、ということだと思います。人から問われたことにはたくさん応えることができますよね。では、たとえば夏目漱石の全集のデータをすべて飲み込んだうえで、漱石にかんする論文を書いてみてくれといたときに、どういう問いを立てるのか。それはおそらく、既存の問いを組み合わせたものにならざるをえないと思いますし、紡がれる文章も、そうした組み合わせのもとになされるでしょう。人が論文をしたためる場合も、たしかに歴史的に積み上げられてきた成果の先で書くことになるわけですが、既に申し上げたように、そこにはいかんともしがたい個性が入り込んでいきますから、文章を書くうえでの問いも、そのうえで書き進めていく文体も、やはりどうしたって個性的なものになっていく。文章表現の向こうに、書き手のイメージが湧くかどうか、というところにもかかわることかもしれません。
時間の経過と個々人の綻び
探究室 ある意味では、人間一人ひとりの歪(いびつ)なありようが反映されていく、ということですね。
石川 ある書道の先生にうかがった、面白い話があります。古書店にいって古い写本をめくっていると、どの時代のどんな人物が書いたものか、おおよそは当たりがつくというのですね。文学研究者でも、そういう感覚をもつ人はいるかもしれません。私はそこまでの自信はないですが、有名作家の全集や選集からパッと1ページくらい提示されたら、おおよそどの作家がどの時期に書いたものか察しがつくという方は、数十年文学を研究している人のなかにはいるのではないでしょうか。

探究室 近年はAIを用いて、くずし字を認識・解読するサービスも出てきていますが、そうした普遍的な可読性とはまた異なる、一つひとつの文章に滲む個人というものがある、と。
石川 時間という要素も見逃せないものだと思います。このインタビューの前半で卒論の中間報告の話をした際、理解できない友人の言葉が数年たって飲み込める場合がある、ということに触れました。それは、そのときには分からない言葉であっても、時空を超えて多様な局面の中で引用してみたら、ある意味が浮かび上がるという事態なのだと思います。同じように時間の経過を生きている相手同士だからこそ、言語表現のディスコミュニケーションというものが、逆に有意義に働くということがあるのではないでしょうか。AIの場合は、「その回答をしているお前は誰だ」と問われたら、何かしらの答えは返すでしょうが、それは時間の経過を生きている人間主体とはまた異なる存在だろうと思うのです。人の場合は、当然ながら、たしかにそこに生きているひとりの人間がいる。もちろん、「その回答をしているお前は誰だ」と問われても、ときに口ごもってしまうような主体でもあるわけですが。
探究室 AIもまたデータの学習によって変化はすると思いますが、それが人間の時間経過による変化とは、また異なるものだということでしょうか。
石川 AIの場合は、ユーザーが質問と回答の往復をした後に中断を挟んだとしても、その続きからすんなりと再開できますよね。人間の場合、そうはすんなりと継続的な問答ができないのではないかと感じます。たとえば私はいま、さまざまな質問を投げかけていただいて、それに対して当座の回答をしていますが、2週間後に同じインタビュー内容で続きを収録しようとしても、まったく異なることを口にしてしまう可能性はある。いや、いまから自宅に帰って夕食を食べたら、もうモードが違ってしまうかもしれません(笑)。それでもひとりの個人であり、局面が変わっていけばまた異なる自分というものを積み重ねていく。決して直線的に進んでいくのではないその人生の先に自分ならではの問いがあり、そこで文章を書いてみたとしたら、自らならざるものがほころび出る。これが私のいま考えている、それこそ仮の結論と申しましょうか、現時点での人文知の姿なのです。
|
人文知探究室後記 インタビューの現場となった石川教授の研究室には、古い蓄音機が置かれていた。いま若い世代で人気が再興しているレコードプレーヤーともまた違い、自分でハンドルをぐるぐると回すことで、レコードが再生される。そんな蓄音機という存在を横に石川教授の話を聞いていると、不思議とシンクロするようなものを感じたのだった。 レコードは、複製技術だといわれる。それは、何度再生しても、同じ音が流れるということを意味する。だが、本当だろうか? 再生する度にレコードは針と接触して、ごく僅かではあるが、削れていく。同じ盤であっても、昨日かけた音と、今日かけた音は、厳密にいえば違うはずなのだ。 それは、人間という存在の不思議さを中心においた、石川教授の人文知のビジョンと、どこか重なり合う。同じ人物が、同じ文学作品について考え、意見を表明するとしても、昨日と今日では実は出力が微妙に異なってくる。同一性を担保しきれないレコードとしての人間、そして人文知。そうやって絶えず生成される差異のなかに、未知への跳躍は潜んでいるのかもしれない。 人文知探究室 宮田文久 |
人文知探究シリーズ 第1回は「人文知とはデータを実感できる想像力」>>
\LINEでコンテンツの公開をお知らせしています/