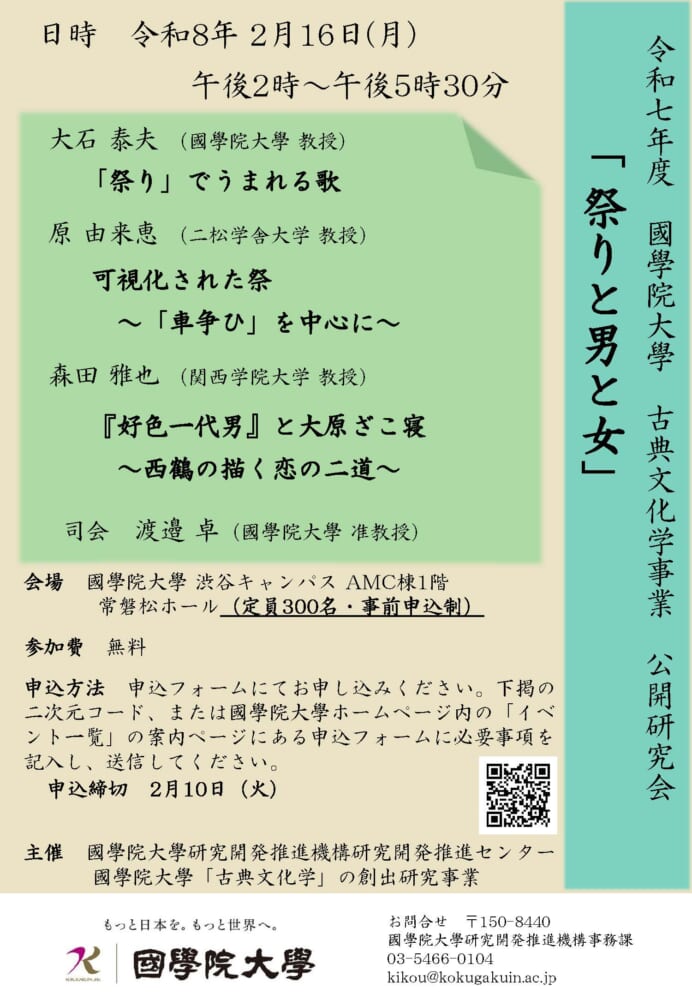十代の頃はほとんど文学を読んでいなくても、文学研究者になるということはある。石川則夫・文学部教授はまるで偶然に導かれるように、日本近代文学の専門家となったようだ。優れた小説が生き生きと描き出す、決してひとつの流れにまとまることのない人々の人生のように。
前後編にわたっておおくりするインタビュー。この前編では、考え、迷って、読んでは書くうちに文学の深淵をのぞき込んでいるような、そんな石川教授の軌跡を一緒にたどってみよう。
実は、日本近代文学を本格的に読みはじめたのは、大学に入ってからなんです。かつて私は工業高校に通って建築を学んでいたものですから、普段は設計の基礎やコンクリートといった材料の知識を学んだり、工作を繰り返したりといった日々をおくっていました。
ほとんど文学なんて関係のない高校生活でした。その頃は太宰治も夏目漱石も読んだことがない。国語の授業なんて、はっきり言って生徒はみんな、睡眠の時間にあてていたものです(笑)。
それでもいつの間にか、文学に魅かれるようになっていったというのは不思議なことですね。これは自分でもうまく言語化できないのですが、多感な頃ですから、もしかしたら毎日建築を学びに高校へ通う日々に、嫌気がさしていたのかもしれません。その頃には非常勤で教えにきている国語教員の方もいらして、おそらくどこかの大学院生だっただろうと思うのですが、萩原朔太郎の詩や与謝野晶子の短歌といったような自分の好きな詩歌をプリントで配って教えてくれる先生もいて、何かしらのきっかけになっている気もしています。その頃からわからないなりに近代文学、それこそ今回のインタビューで幾度か登場するような小林秀雄の文章、国語の教科書にあった「無私の精神」、これはなぜかはっきり覚えています。そうした作品に触れていった記憶がありますね。
大学に入るために浪人をして、そのなかで勉強もかねて、積極的に文学を読むようになっていきました。最初に好きになったのは、古典でした。『万葉集』や『古事記』といった上代文学を読んでいくようになり、大学でもそれらを学ぼうと思って進学したのです。入学時のアンケートには、将来の進路にかんして「大学院進学」と記入した覚えがありますので、この頃にはだいぶ進路にかんして意識的だったのだろうと思います。一年生の頃から、上代文学を専門にしている先生の授業をとったり、その先生の研究室で開いている勉強会にお邪魔したりしていました。

このままだと上代文学の道に進むような気もしますよね。ただこれも思わぬことで、仲間内で好きな本や論文を読んだりするような読書会を開催していくうちに、夏目漱石を読むことがあり、仲間や先輩たちと漱石研究会を作りました。そこからだんだんと近代文学に心が向いていったんですね。ほかにも同時代の作家として、柴田翔、安部公房、大江健三郎といった現代文学を読むようになっていきました。小説家であり劇作家でもあった安部公房は、自身の演劇集団「安部公房スタジオ」の拠点を渋谷のパルコのそばに置いていたのですが、そのファンクラブに入っていた友人と一緒に、パルコ劇場へ「壁」を観に連れていってもらったこともありましたね。その時に、「壁」の文庫本に安部公房のサインをもらいました。
そんな生活をおくっていると、今度はいつの間にか、大学院に進学する気がなくなっていた(笑)。大学を卒業して2、3年ぐらいは高校の非常勤講師をして食いつなぎつつ、大学にも聴講生のようなかたちでしばしば足を運びながら、これからどうしようかと、ぼんやりと考えていました。
大学2年生の頃には小林秀雄をよく読んでいましたから、彼のように文芸批評をはじめとした文章を書いて生きていくことはできないだろうか、と考えるようになりました。周囲に物を書くのが好きな人間はいましたが、本格的に文壇にデビューしているような仲間はいなかった。すると、物を書くという点で私にとって最も身近な環境といえば、やはり大学院であり、研究のなかで論文を書く、ということだということに思い至ったのです。指導教員の先生に相談して受験し、ようやく大学院で研究者への道を歩みはじめることになったのでした。専門とする内容や方向性も、そこから徐々に定まっていきましたね。

私は、言語の本質はコミュニケーションよりもディスコミュニケーションにあり、文学というものもそうしたものに根差していると考えています。そうした文学観は、もちろん学術的な検討を踏まえたものではあるのですが、実際に研究者として体感してきたものでもあります。たとえば、川端康成の文学作品を大学院の演習で読んで解釈を話しあったり、学会のシンポジウムで同じテーマをめぐって発表しあったりするとしましょう。そうした場合、みんなの話がまとまった試しはないのです(笑)。同じ結論になんてたどり着くことがない。学会であれば、発表者それぞれが腑に落ちず、わだかまりのようなものを自分自身のなかに沈めて、そのまま持ち帰ることになる。
しかし、そういうものだ、と私は思います。みんなが文学の言葉について、多くの時間をかけて調べ、論文を読み、疑問点を洗い出し、エビデンスも提出しながら論じるわけですが、ひとつの正解に着地することはない。さらにいえば、文学研究というものは、結局は自分自身に帰ってくる、自分を問うということに落ち着くことになる。そのことについて自分の言葉で書く、ということに行き着くのだと考えているんです。
では、そのような帰結へと至らせる文学とは、具体的にどのようなものなのか。インタビューの後編では、川端や小林についてもうすこし言及してみようと思います。そこで詳しくお話しするように、半世紀近く向き合っていても、まったく結論は出ていないのですが。
後編は「文学表現には、日常的なコミュニケーションから逸脱している側面がある」>>
| 1 | 2 |