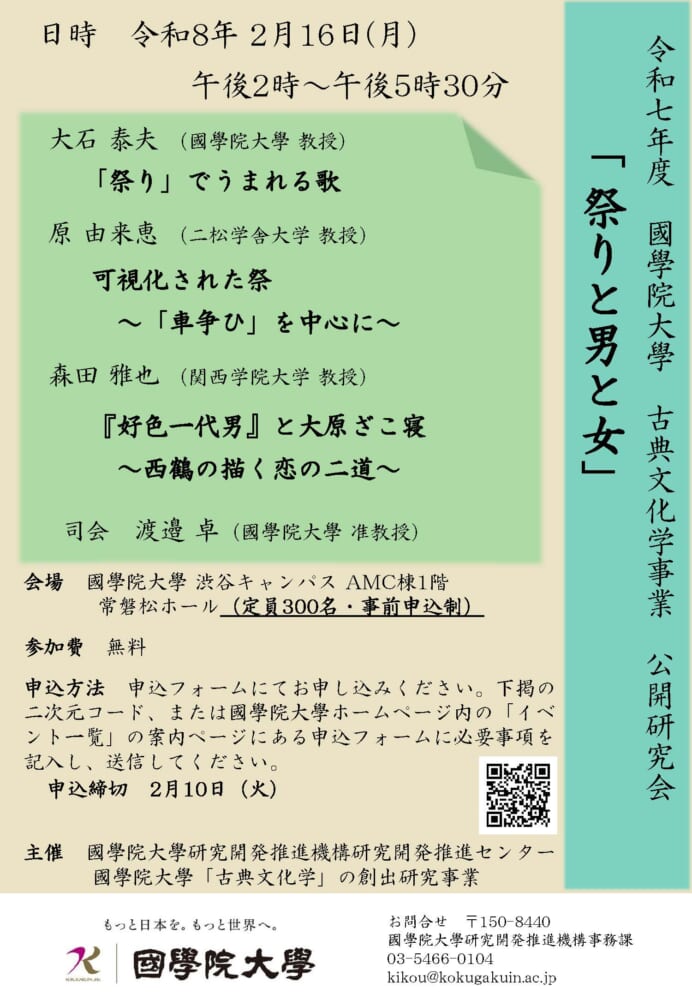「国境の長いトンネルを抜けると雪国であった」──という書き出しで有名な、川端康成の『雪国』。しかし実際に読んでみると、そんなにすんなりと納得できる「物語」にはなっていないと、石川則夫・文学部教授はいう。そしてそこにこそ、文学表現の面白さの一端も潜んでいるのだ。
奥深さとつかめなさに魅惑される、文学言語の地平。石川教授の歩みを振り返ったインタビュー前編を踏まえながら後編で踏み込むのは、川端や小林秀雄といった日本近代文学の巨匠たちの世界だ。読んでも、読んでも深まる謎。今日の流行りに則れば、“文学沼”ともいえる深みが、私たちを呼んでいる。
専門の研究者たちがそれぞれにエビデンスを持ち寄りながら議論しても、なかなか共通した解にたどり着くことがない。そんな文学の姿について、インタビューの前編ではお話ししました。ではそうした性質は、私が専門にしている日本近代文学のなかではどのように表れているものなのか、すこし見てみましょう。
そもそも人が展開する文章のひとつのパターンとして、「物語」というものがあります。基本的には時系列にそって、物事の順番を並べ、その「物語」を見聞きした人は、出来事のひとつのまとまりとして了承できるものです。「小説」という文学の一形態も、おおよそはこの「物語」のパターンに寄り添って展開していきます。

しかし、それがどこかで崩れていき、読み終わった読者が釈然としない「小説」というものがある。この人物がこうした境遇にあるのならば、こういうようなドラマになっていくのではないか……という地点にはいかない(笑)。たとえば日本近代文学の作家のひとり、川端康成の作品の面白さは、そんなところにあります。
『雪国』にかんして以前、アメリカから本学の大学院に留学していた女性に指摘されたことがあります。『雪国』では東京出身の島村という男性の主人公と、駒子という芸者が深い関係になっていくのですが、最後は島村が東京に帰るということも特になく、ある意味で途中の段階で終わってしまうわけです。すると、その留学生はこういったんですね。「どうして駒子は、東京にいる島村の妻と決着をつけないのか」と(笑)。
いわれてみればもっともといいますか、要するに物語としては『雪国』は綺麗に結末を迎えていないのです。人間関係や恋愛関係の展開というものを我々が物語として解釈するならば、当然こう展開するだろう、という方向にはいかない。こうした特徴は、たとえば夏目漱石などにも見ることができます。日本近代文学の一端は、こうした小説で構成されているわけですね。しかも川端の場合はそうした小説を、言語に依拠しながらもその言語自体を変形していくような独特の文体で書いている、というのも興味深いところです。
文芸評論家の小林秀雄もまた、言語に対するある種の疑問を常に胸のなかに抱いていた人でした。彼は当初、フランスの象徴派詩人であるボードレールやアルチュール・ランボーにのめりこんだことをきっかけに物を書いていった人です。そんな小林は、言葉というものを、記号的なものとしてはとらえず、あくまで象徴的なものとして考えています。インタビューの前編でお話したような、ディスコミュニケーションを基底とした私の言語観や文学観といったものは、こうした小林らの文章に繰り返し触れるなかで培われてきたのでしょう。
もちろんそうした文学表現のなかにも、たとえば中学校や高校の国語の授業で日本近代文学を扱うときのように、それが共通カリキュラムとして成立し、みんなで理解することができるような、日常的なコミュニケーションの地平で機能する側面というものはあります。私自身もかつて高校の教壇に立ったり、教科書の編纂にあたったりしたこともありますから、そうした側面はよく理解しているつもりです。しかし同時に文学表現には、コミュニケーションの回路にうまくのらない、いわば逸脱している側面というものがある。明治維新以降の近代化のなかで、人間の生き方自体が大きく変わっていくなかで、文学表現というものが担ってきたものも、当然大きいと思います。私が研究として着目しているのは、そうした文学のありようなのです。

ちょうどいま読んでいる、小林秀雄の『本居宣長』(新潮社、1977〔昭和52〕年)という作品があります。これは既に100回くらいは読んできたと思うのですが、いまだによくわからないところがあります(笑)。
奥付を見ると「昭和五十二年十月三十日 発行」「昭和五十二年十二月十五日 四刷」とあって、私も自分の手で「昭和五十二年師走 則夫」と記銘していますね。私がちょうど大学に入った年であり、古典文学を好んで読んでいた頃です。当時の小林秀雄といえば文芸批評の大家であったわけですが、そんな彼が出した新刊が、江戸期の国学者として『古事記伝』などを著した本居宣長についての本だった。当時は『古事記』など読んでいましたから「これなら読みやすい」と思って手にとったのでしょう。刊行されて二カ月のうちに四刷まで増刷されているわけですから、当時の読者の注目といったものも感じられますね。定価が4000円とありますが、当時の学生アルバイトが1時間働いて300円ほどだった記憶がありますので、大枚をはたいて買ったことがおわかりいただけるかと思います。
それから半世紀近く、『本居宣長』を読んでいるのですが、まだ全体像がつかめない。そもそもこの作品は論理的に書かれておらず、こちらも読んでいる端から忘れていくのです(笑)。小林については研究論文以外にも、小林秀雄に学ぶ人々が集うWeb同人誌「好*信*楽」といった場所で、もう6年くらい、すこしずつ自分の考えを書き継いでいるのですが、みんなで不思議だよねといいながら読んでいます。研究者であっても誰もが、こんなふうに対象とする書物を付箋だらけにして読んでいるのではないでしょうか。
こうして研究を重ねてきてつくづく思うのは、作品に没入し、そこに拡がっている言葉の群れへ、自分を解放しながら読み書く、ということの難しさです。卒論に取り組む学生にもよくいうんですよ、「何を書いたらいいかわからなくなってしまったのなら、作品に戻って、何遍でも読もう。それからキッチンにいって茶碗でも洗っているうちに、ふと何かが浮かぶものだ」と。つまり、散々読んで考えた末、何かの拍子に頭を空っぽにしたときにこそ、自分の言葉が訪れてくるのではないかと思うのです。
<<前編は「文学研究は、結局は自分自身に帰ってくる、自分を問うことに落ち着く」
| 1 | 2 |