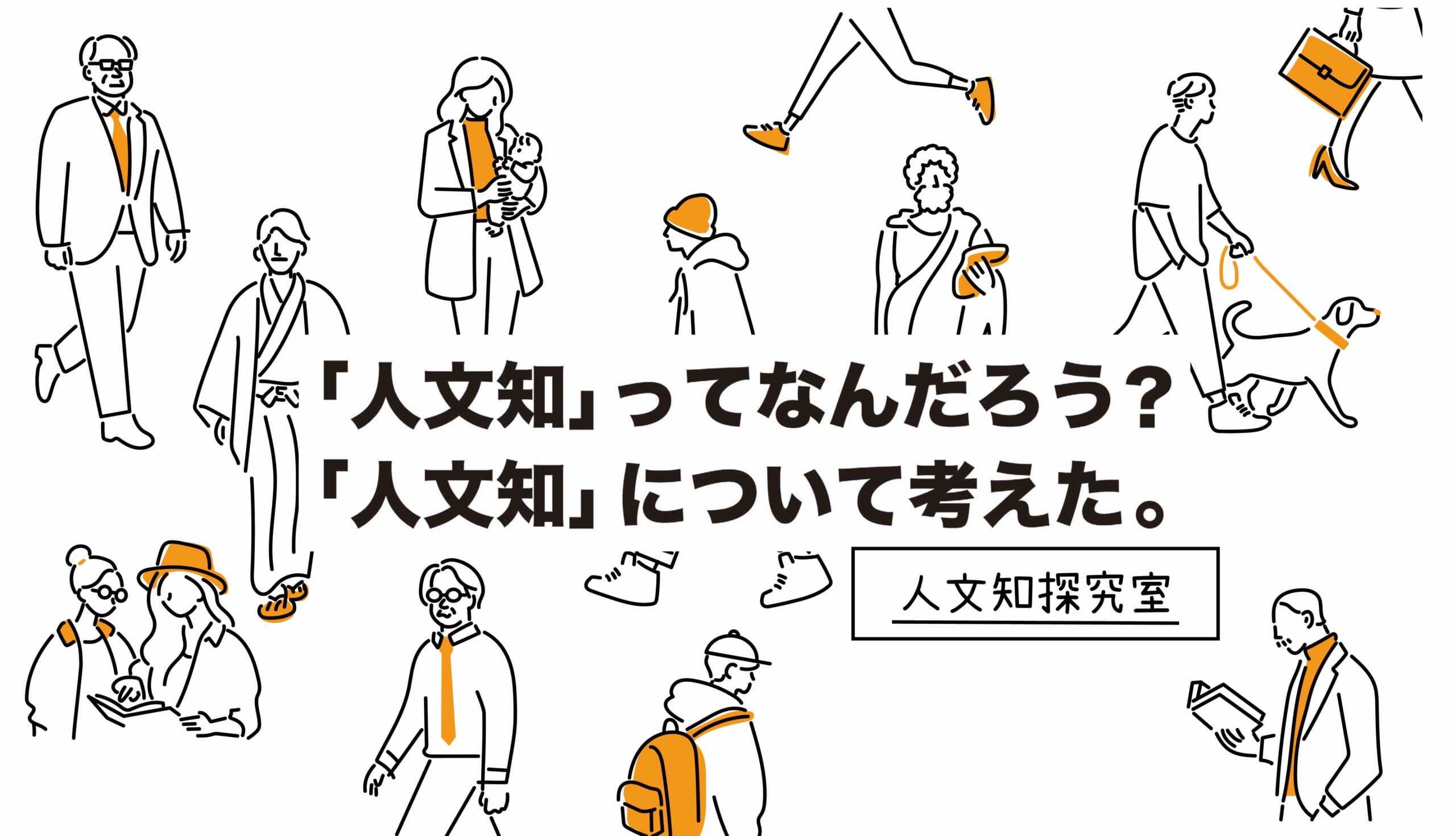ますます明日をも知れぬ世界となってきたかのような実社会。その只中にあって、すこしずつでも新たな一歩を踏み出すための手がかりを与えてくれる知的な枠組みとして「人文知」が注目されている。その可能性を見つめ、國學院大學に息づく人文知を追い求める人文知探究室では、多様な専門をもつ研究者たちと共に、日常生活からビジネスシーンまで役立つような視座を模索するインタビューシリーズを展開している。
シリーズ4人目は、池田榮史・研究開発推進機構教授のもとを訪ねた。モンゴル襲来(元寇)で沈没した元軍船の発掘調査で、大きな注目を集めつつあることは以前にも本メディアで取材した。その際も話題に上がったのは、水中考古学の最新の知見。沈没船の保存処理をめぐって進みつつある研究は、むしろ自然科学の領域のようにさえ見える。そんな池田教授と人文知──? インタビューを通じて見えてきたのは、まさに思わぬ遺物が姿を現すように、現在という水面を波立たせる歴史の意義だった。
| ▼もくじ |
沖縄の言葉「じんぶん」が開く世界観
探究室 水中考古学のプロフェッショナルである池田先生と、人文知。意外な組み合わせにも見えますが、どういった結びつきがあり、普遍的な議論につながりうるものなのか、じっくりうかがっていければと思います。
池田 なかなか広いテーマですので、どこからお話ししたものかと思いますが、まずはざっくばらんにはじめてみましょうか。私がかつて38年ほど赴任していた沖縄の地の言葉、うちなーぐちで使われる表現に、「じんぶん」がある、というフレーズが存在するんですよ。

探究室 「じんぶん」がある?
池田 辞書的には、いわゆる「知恵(智慧)」という意味なのだろうと思います。相手を褒める言葉で、主に目上・年上の人が、子どもたちのことを褒めてあげるときに使われる表現ですね。賢いね、ちゃんと勉強をしているね、努力しているね、というような意味合いで、しかもそうしたありようを可能にしている優れた人格も含めて他人を褒めるときに、「あんた、じんぶんがあるねえ」というような表現をする。そのことを大事にしなさいね、今後も育んでいきなさいね、という意味合いも滲みます。
探究室 味わい深い言葉ですね。
池田 真逆の場面でも「じんぶん」という言葉は使われます。たとえば何か物事に失敗したり、うまくいかなかったりした人を目の当たりにして、その人自身の資質も含めて非難めいたことをいうときに、あの人には「じんぶん」がないからね……というように用いられることもある(笑)。
探究室 「じんぶん」がない、とは言われないように生きたいものです(笑)。
池田 言語学などの専門的な観点からすれば、もうすこし細かい話にはなるだろうとは思うのですが、沖縄生まれではない私が受け取っていたのは、ここまでお伝えしたようなニュアンスです。ある理想的な、生きた知恵のようなものを「じんぶん」という言葉で呼んでいて、それがあると言ってもらえた側は、今度は「迂闊なことはできないな……」と気を引き締めることになる。
探究室 なるほど。いずれにしても「じんぶん」という言葉には、とても肯定的な意味が付与されているのですね。
池田 私自身、とても素敵な言葉だなあと感じてきました。沖縄の方々の、ひとつの世界観というものも表現されているような気がします。人はひとりでは生きられない。それぞれが、いろんなかたちで知や人格を磨き、自分なりの教養を築き、行動を支える理念を身につけて、社会のなかで共に生きていく。そんなビジョンが見えるような気がしています。そして、こうした「じんぶん」の意味合いには、学問の場での「人文知」を広く解き放ってくれるようなところがあると思うのですね。
探究室 「じんぶん」が「人文知」を開く、と。
池田 私たち歴史学、ひいてはそのなかにおける考古学の研究者は、人文科学という学問分野のなかで活動していることは事実です。人文科学、社会科学、自然科学……と分類される学問分野のなかで、人文科学とされるもののひとつとして歴史学や考古学があることは間違いない。そうした側面と、先ほどの「じんぶんがあるね」という沖縄の言葉を合わせて私が考えるのは、人文学とは人が物を思うこと自体について思考をめぐらせ、さらには自分がどうあるべきか、人は如何に生きるべきかという問いを追究する学問なのだろう、ということなんです。そのための手がかりや素材を見つける研究方法が、たとえば文学、哲学、歴史学というように異なるだけなのではないか、と。
考古学は人文科学か自然科学か
探究室 とはいえ、池田教授はモンゴル襲来(元寇)の際の沈没船をめぐる、保存方法の模索と研究を続けていて、そこではトレハロースという天然糖質(現在は人工甘味料として工業化)の保存処理剤の効果を探っています。これは自然科学の領域に踏み込んでいるといえます。歴史学ないし考古学が、このように学際的な側面をもつことについて、どう考えていらっしゃいますか。
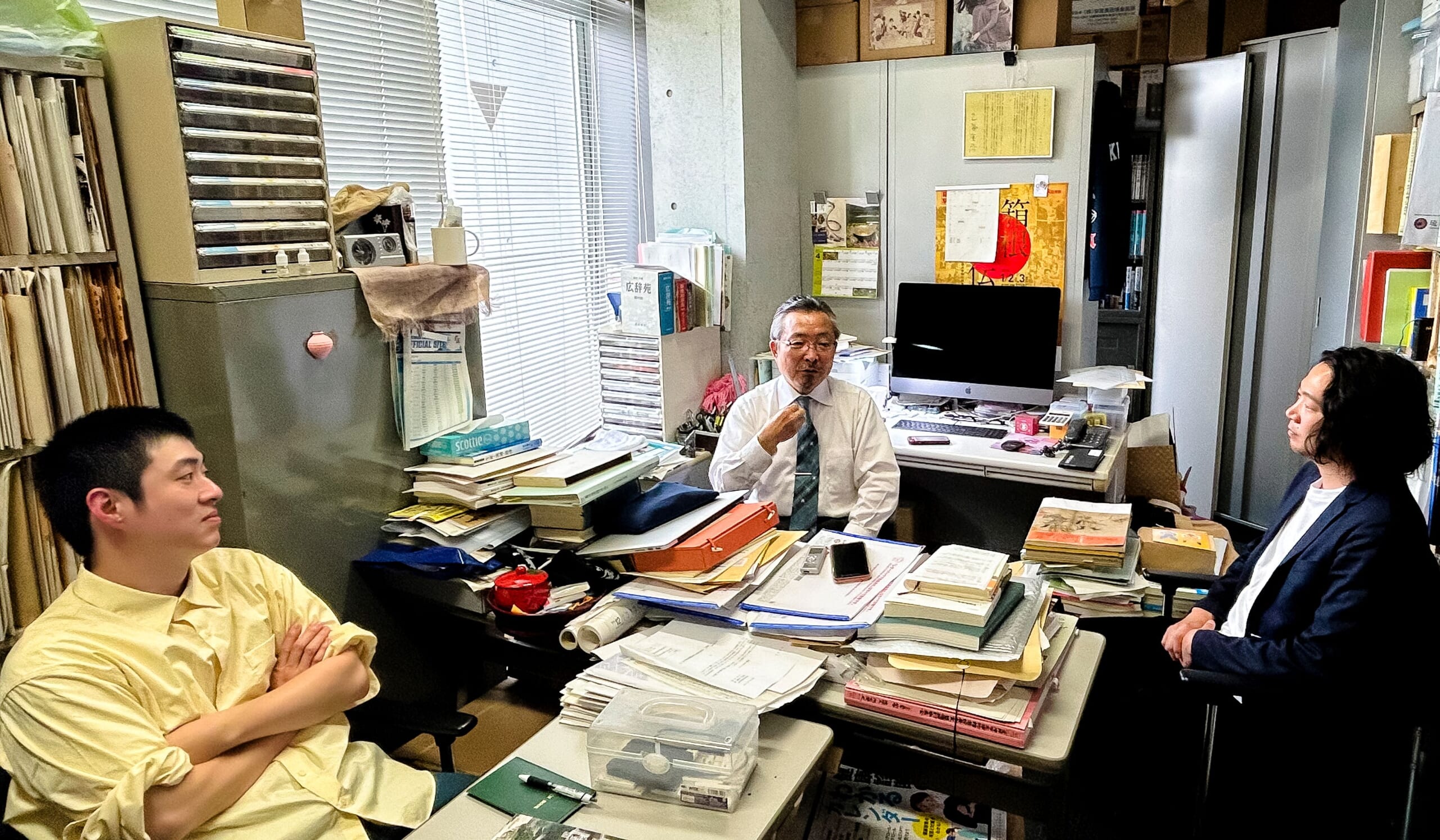
池田 歴史学と考古学については先ほどもすこし触れましたが、考古学という学問は歴史学の補助学としてはじまったという側面をもちます。歴史学の研究対象は文字資料、つまり文字による記録が中心です。しかし現在から時間を遡っていくにつれ、文字が残っている例は少なくなっていくのは道理ですよね。文字にかわる何らかの資料をもとにしながら、文字を使っていなかった頃も含めた今日までの歴史、人の営みなどを復元していかなければならないとき、遺物や遺跡といった物としての資料を研究する方法が必要になってくる。そうした必要が、考古学という学問を形づくっていったところがあるわけです。
探究室 歴史学と考古学の間での、大きな違いですね。
池田 考古学は、物としての資料の取り扱い方法を確立していく必要に駆られました。そのなかでは当然、動物学や植物学、物理学や化学といった自然科学的な知識を援用していかねばならないわけですね。いってみれば、人文科学の一端をなしている考古学が、総合科学化していくということです。人類の歴史的な営みの復元という点においては人文科学の領域ではあるのですが、そこで取り扱う資料は、自然科学の対象を含む。自分とは異なる専門家の方々に教えていただき、学び、協働しながら、研究を進めていくのですね。
探究室 実際に水中考古学では、物を相手にしていらっしゃいます。
池田 海底から出てきた遺物、特に木材は、地上に引き上げた瞬間から空気やらバクテリアやら、大量に溢れる劣化要因のなかで保存状態が悪化していってしまいます。一方で海のなかならばいいのかといえば、海底に露出しているだけでフナクイムシが蚕食してしまいます。かといって、引き揚げた遺物を素早く保存処理する技術や施設がない段階では、見つけた沈没船をすぐに引き揚げるわけにはない。それならば、むしろ発掘しないで海底の土のなかに埋まっていたほうが、ひとまずの保存の観点からはベターです。我々は海底に埋もれていた遺物を分析し、理解するために見つけたわけで、壊すために発見したのではないわけですから。
探究室 しかしそのままでは、研究は進めづらいですね。
池田 分析・理解のためには引き揚げたい。ではどうすればいいのか、という試行錯誤のなかでトレハロースに行き着きました。もちろん保存科学の専門家の方々に実際の処理はお願いするのですが、メカニズムは我々自身も理解していなければならない。海底から取り出した瞬間から劣化は進むので、きちんとした保存に向けた適切な手順や知識を、ファーストタッチに携わる私たちが身に着けていなければならないのです。トレハロース以前の、水中考古学における保存処理の試行錯誤の歩みも踏まえながら、自然科学の専門家にすべてを託すのではなく、我々なりにちゃんと学び、よりよい方法を共同作業で築いていかねばならないのですね。
探究室 それでもご自身としては、あくまで考古学に立脚している、ということですか。
池田 そうですね。たとえば保存科学の専門家の方であれば、保存処理の理論や手法についての関心が主でいらっしゃる。一方で私は、そうして保存処理した物がいかなる存在であり、人間にとってどのような役割を果たしたのかといったようなこと──物自体の理解と、その物がもつ機能や社会的な意義、特定の場所から発見されたことに対する歴史的な評価などに興味がある。総じて言えば、やはり人間の営みの復元ということなのですが、いずれにせよ考古学の専門家でなければ引き出せない歴史的な情報というものもまた、存在するだろうと考えています。

探究室 ここまでお話しされてきたような、人の営みを根本から見つめる人文知、とでもいうようなビジョンは、ご自身としてはどのように培ってこられたのでしょうか。
池田 私の人生に即してお話しするならば、世代的な要因は大きいように思います。昭和30(1955)年生まれの人間として、高校入学の時期に70年安保を経験している。青春時代を過ごしたのは1970年代です。世間一般としては、その前の〈政治の季節〉と呼ばれる1960年代からしてみれば若者たちの政治的な意識はトーンダウンしていった時期と見られているのだと思いますが、少なくとも熊本で生まれ育った私の周囲では、たとえば高校生は高校生なりに身の回りで起こる社会的物事を自分の頭で考えていました。
探究室 池田教授は、いわゆる「しらけ世代」に属していらっしゃると思いますが、一括りにはできないものでもあるのでしょうね。
池田 周囲の多くの人間は、「社会のなかで自分たちは何をしていかなきゃいけないのか」ということを考えていましたし、実際に友人同士で「お前はこれから何がやりたいんだ」というようなことを議論する場が、日常的にあったんです。誰かが本を読んでいたら、「おい、何読んでるんだ」「カフカだよ」みたいな会話も珍しくない。カフカと言われたほうは、「なんだ、かっこつけやがって」と、内心思っているのですが(笑)。その傍らで、女の子がサリンジャーの『ライ麦畑でつかまえて』を読んでいる──このように、それこそ「じんぶん」的な探究をそれぞれにおこなっている時代だったんです。大学に入ってサークル活動をするにしても、なんでそんなことをやっているのか、説明しようと思えばできたし、問われ、語ることもあった。なんとなく、と答えることはあまりなかったように記憶しています。
探究室 同じ世代でも人によって体験は大きく異なるでしょうが、興味深いお話です。
池田 意外なトピックも、こうした人文知をめぐる問いにつながっているんですよ。いま、私の研究室にポスターが貼ってある昭和のアイドル・南沙織がデビューしたのは、昭和46(1971)年のこと。私は熱烈なファンでして、高校生の頃にはファンクラブの会員にもなっていました。
探究室 南沙織は昭和29(1954)年生まれで、池田教授とほぼ同世代。「17才」というデビュー曲がヒットし、現在まで続くアイドルという存在の先駆けともいわれる人ですね。
池田 よく知られている話でもありますが、彼女の昭和46年のデビューは、翌昭和47(1972)年、5月15日の沖縄返還を見越してのもの。沖縄出身の、いまでいうところのアイドルが必要とされた、という側面があります。本土と沖縄の関係性を考えるとき、求められたのが南沙織という存在であることには、私自身は後ほど気づいていったわけです。さらにはやがて考古学の道に入った自分が沖縄の大学に赴任することになるとは、夢にも思っていませんでしたけれども。先ほどの「じんぶん」という言葉とは、こうした過程の先で出会ったのです。
探究室 偶然に継ぐ偶然が、まさに人文知の探究とも重なっているのですね。
発掘現場で出会った葛藤と考古学に進む決意
池田 時間は再び遡るのですが、高校では考古学クラブに所属していまして、暇を見つけては自転車で熊本県内各地の発掘調査のお手伝いに赴いていました。そのなかで出会った、県の職員の方のことが忘れられません。本学で考古学を学んだ卒業生で、まだ若い男性でした。仲良くなるうち、現場が終わった後の自宅に遊びにいくようになり、本棚の専門書などを見せてもらっていました。彼はひとりで酒を飲んでいるのですが、そのうちに酔っぱらっていく。すると、「なんでお前はこの発掘現場にくるんだ!」と怒り出すんです(笑)。

探究室 ……? なぜでしょうか。
池田 いや、私もそう思って言ったんですよ。現場では「おう、よく来た」だなんて言って私を迎えてくれて、手伝わせてくれたじゃないか、と。でも、彼は収まらない。やがて、泣きながら怒りの感情を叩きつけるのです。なぜかと思い、よくよく話を聞くと、わかってくるものがありました。彼が手がけていたのは、九州縦貫自動車道の建設にともなう発掘調査だったのです。
探究室 九州縦貫自動車道は、1971年から部分的に開通していきますね。九州歴史資料館のウェブサイトにまとめられている調査報告書を読むと、1960年代後半から発掘調査が進められていったことがわかります。
池田 「発掘したら、この遺跡は壊さなきゃいけないんだ」と彼は訴えるのです。「自分は歴史が好きだから考古学の道に入ったのに、職業として発掘をするとなれば、遺跡を壊すための調査なんだ」と。この遺跡がどんなものなのかは、一生懸命に調べてまとめる。でも、それをやった結果として、遺跡が壊れていく。そうした自己矛盾を抱えながら日々四苦八苦しているところに、お前のような能天気な高校生が現れて面白がっているのは何なのだ、という怒りだったわけですね。
探究室 なるほど、筋の通った怒りですね。
池田 その次の日に発掘現場で会うと、また「よう来た」なんて言ってケロリとしていて、これだから酔っぱらいは嫌だと高校生ながらに思いもしましたが(笑)、とはいえ人はここまで一生懸命になれるのか、という不思議な感慨を抱いたんです。考古学という学問を学び、好きなことの一環として遺跡を発掘しているが、その発掘が辛いという。しかし、泣きながらでも汗水垂らして発掘する場からは離れられない、そういう不思議な人たちがいるのだ、と。
探究室 矛盾だらけの現代のなかで、人の営みを復元する考古学に邁進する人たちがいることに気づいた、と。
池田 これもまた偶然ではあるのですが、その発掘調査を進めていた遺跡は膨大な古墳群になりました。保存運動が盛り上がって──私も高校生としてその一端にかかわったのですが──現在まで残されることになった熊本市城南町の国史跡「塚原古墳群」であるわけですが、人が本気になっていろんなことに取り組んでいくと、物事はこのように展開していくのだ、と新鮮な感覚を抱きました。やがて私はその人に、「僕も将来、考古学の道に進みたいです」と伝え、「だったら國學院に行け」と勧められ、いまに至るのです。
「人文知」がつなぐアジアの未来
探究室 お話をうかがっていると、歴史を遡ればやがて現在のことを考えるという、人文知の一側面が見えてきます。
池田 考古学を含めた人文知というものは、逆説的な物言いになるかもしれませんが、現代人のためにあるものだと私は思います。繰り返すように、自分たちがどんな行動をとっていくべきなのか考える心の動きがあり、それがたまたま過去を向いているのが、歴史学や考古学という学問なのでしょう。その向かう方向が文学だという人もいれば、哲学だという人もいる。私たちがどう生きるべきか、なぜ存在するのかといった根本的な問いかけをし、その謎を解明していくための素材を提供してくれるのが、私にとってはたまたま考古学なんです。
探究室 モンゴル襲来(元寇)が今後、文字資料ではなく、物から語られていくことになるということにも、さまざまに現代的な可能性がありそうですね。
池田 日本に住む者からすれば文字通り「モンゴル襲来」なのですが、実はこの歴史的な出来事にかんしては、軍事的な観点や勝ち負けのレベルの話からは離れて、アジアの研究者たちの国際的な関心が集まるようになってきています。ちょうどこのインタビューの後、 私はモンゴルに行くのですが、実は我々の調査にモンゴルの人たちが強い興味を抱いているんです。もっとも海底から発見されつつある物は当時の元に服属し、弘安の役に同行させられた南宋の人たちの品が多いのですが、やはりモンゴル人も軍団を構成していたのは確かであり、このことの繋がりから関心が寄せられている。当然、南宋のことですから中国の研究者の人たちも興味を抱いているし、文永の役・弘安の役ともに高麗も軍団を構成していたことから、韓国の研究者の人たちも面白いと言ってくれる。
探究室 引き揚げようとしている沈没船が、アジアの歴史的な関心の焦点になりつつある、と。人文知がつなげうるものがありそうです。
池田 アジアの多くの国々がかかわって、こうした歴史的な事象をみんなで研究しようという空気になることは、いままであまりなかったことなんです。特に近現代の歴史にかんしては、私自身も経験があるのですが、こうした国際的な試みに踏み出したとしても、それぞれの国の歴史観の問題があり、成果が結実するところまではなかなか到達することができませんでした。今回は、もしかしたらみんなで足並みを揃えていけるかもしれない。嵐という天候が為した出来事だからこそ可能だという側面は大きいでしょうが、戦争の痕跡でありながらも、関係したすべての国の研究者が共有化しながら研究する素材となりうる。
探究室 沖縄の人々が「じんぶんがあるねえ」と声をかけあうように、いま私たちが日常において人文知を考えるということは、もちろん教養的な楽しさやビジネスにおける有用性といった側面を持ちつつ、アジアに暮らす人間としての「じんぶん」を身に着け、連携していく未来も示唆しているように感じます。インバウンド需要も含め、アジアとの関係を捉え直す時代に、重要な問いをもたらしてくれるのが人文知なのかもしれません。
池田 本当に、そうですね。ここまでお話ししてきたように、人文知の営みのひとつとして、わたしたちは一緒に歴史を掘り下げていくわけです。そして過去の出来事を共に考えるという作業を通じて、現在という時点において、アジアの人々が関係を紡いでいくという積極的な動きにつながっていく。人文知にはそうした可能性があると思いますし、近現代において大きな断絶を抱えてしまった アジアの関係性、その困難を踏まえてなお、大きな希望を感じさせてくれるところがあるのです。
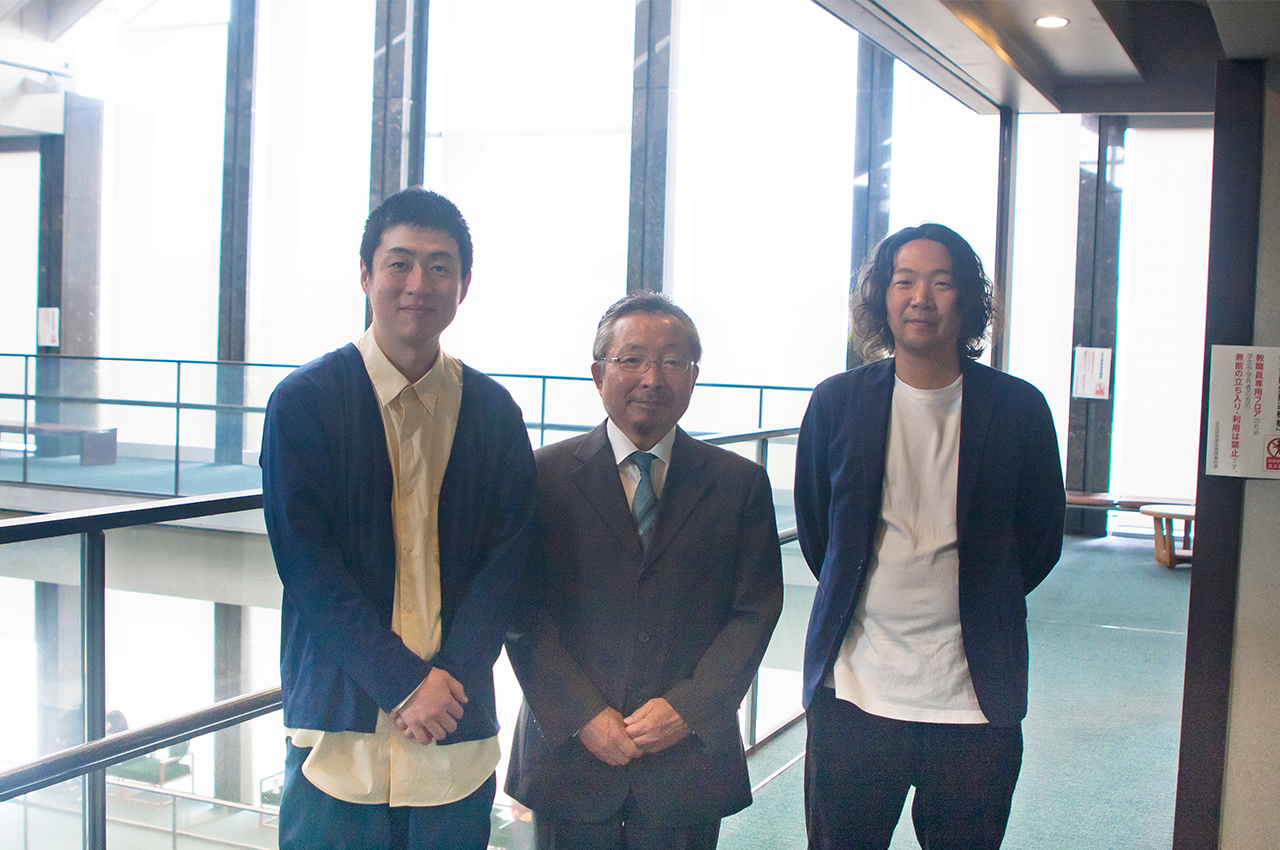
| 人文知探究室後記
以前に池田教授にインタビューしたときのこと。発掘調査を進める「鷹島海底遺跡」にはじめて潜った際の第一印象を語る言葉が強烈だった。「びっくりしました。自分の目の前もほとんど見えない、まるで味噌汁のなかにいるような状態。海中に張ってあるロープを辿りながら発掘地点までたどり着くのですが、慣れるまでは怖かったですねえ」 (人文知探究室 宮田文久) |
人文知探究シリーズ 第5回は「人文知とは、人間にとって価値のあるものを考えること」>>