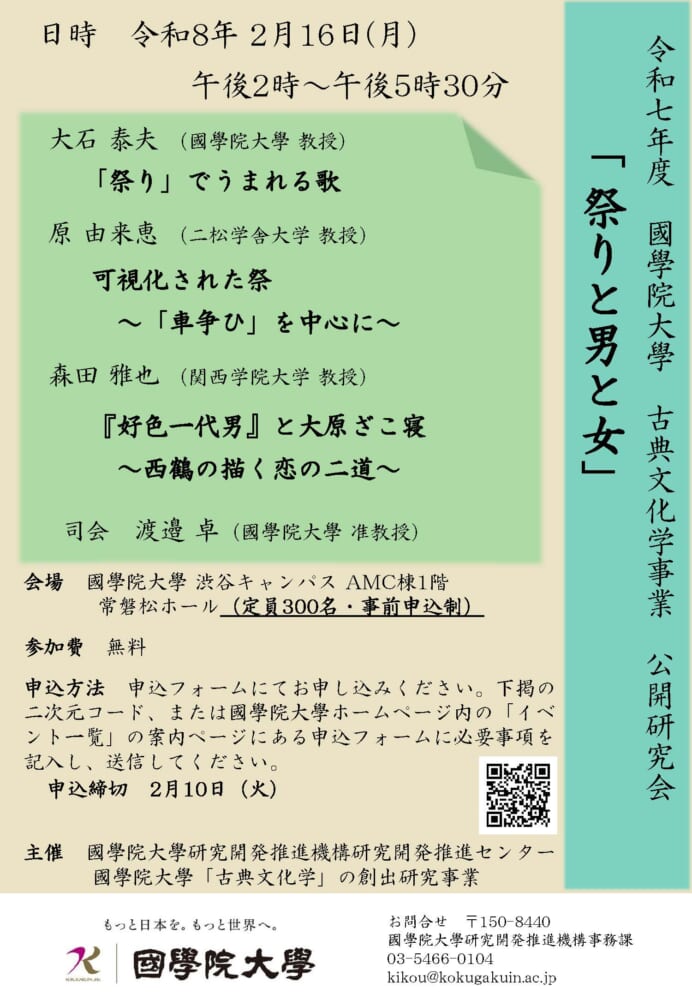言語をベースにした力を育む教室自体を、多様な社会のありようをできるだけ反映したものにする。そうすることで、学習者の力はもっと花開く――。リテラシー教育とバイリンガル教育の双方を専門とする加納なおみ・教育開発推進機構准教授が、現在のような発想に至った背景には、シンガポールやニューヨークで通算15年余り生活した経験が大きいという。
“現代的な教育”の最前線を尋ねたインタビュー前編に続き、この後編では過去の経緯について訊く。そこから見えてきたのは、未来の学生にとって必須となる“問う”力だ。答えのない世界を進む、その礎となる力の育成は、どうすればいいのだろう。
今でこそ大学でリテラシー教育とバイリンガル教育の研究・実践を行っている私ですが、最初からこうした専門分野に通じていたわけではありません。そもそも研究者でもなかったのです。大学卒業後は一般企業への就職を経て、興味のあった外国人向けの、第二外国語としての日本語を指導する日本語教師養成課程を修了し、日本語教育の道に入りました。
その直後、家族の転勤でシンガポールに行くことになりました。シンガポールはマルチリンガルな多文化社会で、コミュニケーション自体がマルチリンガルであることがノーマルな状態でした。みんな自然かつ自由にコミュニケーションをとっていて、初めは衝撃を受けました。そしてことばを使ううえで自分がいかに規範意識に縛られていたかに気づきました。その中で日常生活をおくっていたことは、インタビュー前編でお話した「人工的な空間である教室と、その外との断絶をつくらない」という意識に、強く結びついています。

教師としては、インターナショナル・スクールで国際バカロレア日本語コースを教えることになりました。そこで痛感したのが、ライティングの大切さです。これがリテラシー教育を研究するようになる第一歩でしたね。帰国の際にシカゴ大学日本校という、当時東京で一時開かれていたプログラムで、トゥールミンモデルをベースとしたロジカル・ライティングに初めて出会いました。そこで読み手と書き手のコミュニケーションとしてのライティング、思考力を伸ばすライティング教育の奥深さを学びながら、修士(哲学・人文学)を取得しました。
その後、家族が今度はニューヨークに転勤になり、コロンビア大学教育学大学院でふたつめの修士(教育学)をとりました。そのまま博士(教育学)の取得を目指すときに、新たに研究しはじめたのが、バイリンガル教育です。アメリカで研究するにあたって、それまでの日本語のライティングだけでなく、バイリンガルのライティングまで広げて考えるようになったんですね。これを機に、コミュニケーションの礎をなす「対話(ダイアローグ)」の本質、さらに言えば言語と思考の関係について一層掘り下げて考えるようになりました。
ここで関係してくるのが、インタビュー前編で触れた“問う”力です。國學院大學が令和3(2021)年度から行う「アカデミック・リテラシーズ」という授業でも「発問力」を育成するとお伝えしましたが、自分自身がシカゴ大学やコロンビア大学で痛感した、あるいは周囲の日本から来た学生たちを見てわかったのは、ライティングの前提となる「発問力」「問答力」を、あるいは何を問われているのかを理解する能力の重要性でした。
英語の意味は表面上なんとか理解できても、結局質問の意図自体がわからない、つまりどのようなこたえが期待されているのか全くわからない、ということが、とても多かったのです。でも、たとえば授業の課題としてある本を読むようにいわれて、次の授業でディスカッションする際に先生が「どうだった?」と漠然とした質問を投げかけても、現地の学生はみんなポイントを突いた回答をするんです。なぜだろうと考えると、小さい頃からずっと様々な問答のやりとりをしながら育っているからなんですね。つまり、“問い”を知っている。どのような問いが重要なのか判断でき、問われた際には問いのポイントを捉えることができる――そうした力の大切さに気づいていきました。
國學院大學の「アカデミック・リテラシーズ」の授業でも、問答作成の指導を行っていきます。これは「アカデミック・リテラシーズ」の前身である「基礎日本語」の授業でも行っていたものです。

私は教育学者ベンジャミン・ブルームによる思考の6段階モデル(改訂版)に沿いながら、問いと答えをセットにして学生に考えてもらうようにしています。基礎的な問いというのは、相手の記憶や、理解を問うようなものです。それを発展させていくにつれ段々と、単純な答えのない、オープンな問いになっていく。
プレゼンテーションをする際にも質疑応答をあわせて行うのですが、本当にその人の力量が試されるのは、何が問われるのかわからない状況での問いに答える、という難しい場面です。それは同時に、問う側の力も試される。
学生も最初はなかなか、問い自体が出てきません。そこから問いの立て方を学び、答え方を学ぶ。そうすると徐々に、問いに対する価値づけが行われていきます。どういうことかというと、「問答するということはすごく意義があることなんだ」というように、クラスの文化が少しずつ変わっていくのです。
世界全体が前例のない、つまり単純な正解がない状況にある中、この「発問力」の重要性を、より強く感じるようになっています。すぐに正解は出ずとも、よりよい答えにたどり着くための問いを立てる、そのことの重要さも考えていかなければいけません。
よく学生に話すのは、「自分の視点がどこにあるのかを認識しよう」ということ。そして、「その立場から発せられる問いや、求められる答えが、誰にメリットがあるのか、誰に還元されていくのかを考えよう」ということです。
その問答が自分だけではなく、自分とは異なる立場の人々をも益するものである――。こうした複数の視点を持つためにこそ討論といった協働学習がありますし、そのプロセスが行われる教室の環境自体を、できるだけ社会と断絶がないものにしたいのです。
加納 なおみ
研究分野
リテラシー・ライティング教育、バイリンガル/マルチリンガル/マルチリテラシーズ教育、トランスランゲージング教育論、協働学習、アクティブ・ラーニング、教師教育
論文
「継承語教室のカリキュラムとトランスランゲージング教育論 - 考える力とことばの力を伸ばし,多言語話者の健全なアイデンティティを育むために-」(2025/11/01)
「トランスランゲージングと複言語主義-両者の接点から新たな教育実践を切り開く-」(第27回ヨーロッパ日本語教育シンポジウム 基調講演)(2025/06/30)