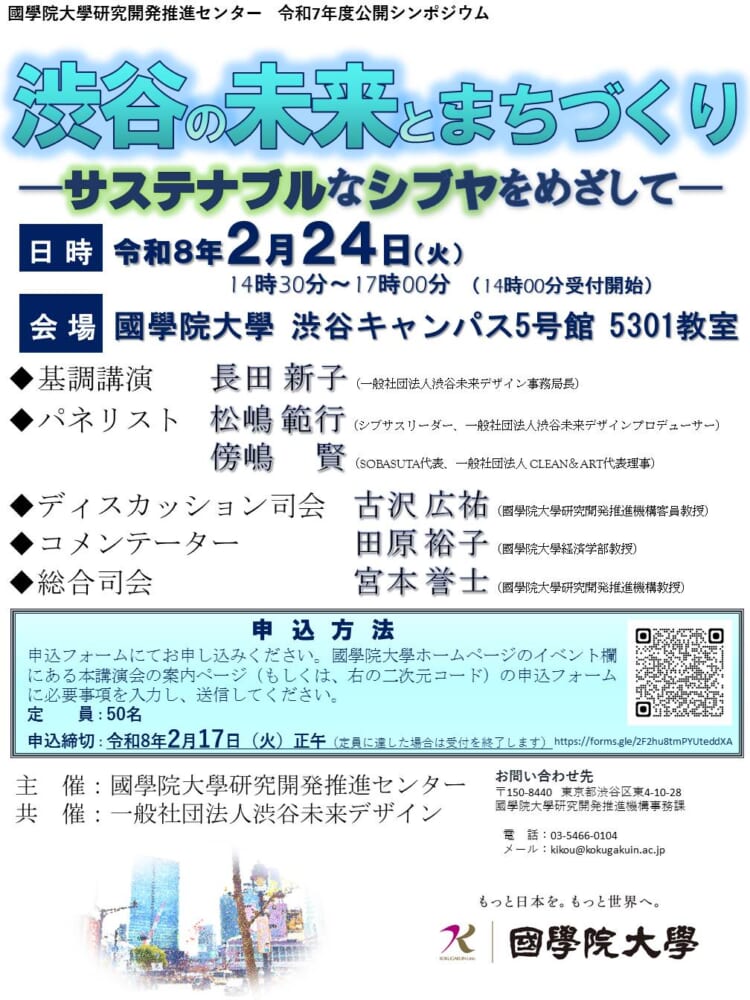手がかりがないときに古(いにしえ)の知恵を頼るのは、人の常だ。黒澤直道・文学部外国語文化学科教授が研究する中国の少数民族・ナシ族の信仰であるトンバ教では、自然神にして債権者である「シュ」という神と、負債者である人間の関係性が描かれる。その神話は、現代の私たちの姿をも、鮮やかに照らすだろう。と同時に、安易に現代に適用しようとすれば、文化本来の豊かさを捨象することにもなりかねない。アカデミックな手つきだからこそ見えてくる“知”の倫理が、前後編のインタビューから見えてくる。
雲南省麗江市を中心に居住する、人口約32万人の少数民族・ナシ族。彼ら独自の宗教に、トンバ教というものがあります。トンバと呼ばれる祭司が、様々な儀礼を執り行うというもので、その経典には「シュ」という神が登場します。
多神教であるトンバ教の中にはさまざまな神が存在します。万物に精霊が宿るとされ、神から悪霊まで、名前を挙げると1500を超える。その中でも「シュ」は自然界の主宰者であり、日本における八百万の神のように、あらゆる場所にシュが宿っているとされます。イメージとしては、人間の体と蛇の尾を持つ神です。頭が蛙や馬、虎、牛、ヤク、水怪、象、鹿のものなども存在します。
そうしたシュが、至るところにいる。たとえば、天には99のシュがおり、地には77のシュがいる。山には55のシュ、谷には33のシュ、村には11のシュ……他にも海(湖)のシュ、崖のシュ、雲のシュ、風のシュ、川のシュ、泉のシュ、坂のシュ、草原のシュ、石のシュ、木のシュなど、枚挙にいとまがありません。
興味深いのは、もともとシュと人の祖先は異母兄弟姉弟である、とされていることです。やがて人がシュの領域を侵したため、シュが報復し、人とシュの争いが始まって……と展開していくのですが、基本的に人とシュの関係は、負債者と債権者のようなものとして描かれるのもまた、面白いところです。
人間という存在の大前提として、自然に対して借りがある、ということですね。
今、「共存」ということを考えるにあたって非常に示唆的なものを含んでいるわけですが、こうした物語を、あるいは語りをめぐる社会的な状況をどう捉えるべきなのか。それをじっくり考えていく中で、私たちの現在をも捉え返すことができればと思います。

シュの宿る澄んだ泉には、線香の煙が絶えることがない。廸慶チベット族自治州内のナシ族居住地にて。(平成31(2019)年8月)
ナシ族といっても馴染みのない方も多いでしょうから、改めて、大まかに概要から紹介させていただければと思います。
ナシ族が話すナシ語という言語は、チベット・ビルマ語群に分類されまる系統です。つまり漢民族が話す扱う中国語とは本来異なるものなのですが、現在はナシ族のほとんどの人が中国語も喋るので、ほぼいわばバイリンガルの状態になっています。また、ナシ語を書き記すためのローマ字はいまだに普及しておらず、彼らは書き言葉としては漢民族の中国語を用います。経典に用いられる絵文字は、もともとトンバだけが使っていたもので、かつ難解であるため、一般のナシ族がこれを使って話し言葉のナシ語を記したり、読んだりすることはありません。
かつてナシ族がつくった麗江旧市街は、平成9(1997)年に世界文化遺産に登録されました。私が麗江に滞在し始めたのがちょうど同年。そこから3年間にわたる滞在で目の当たりにしたのは、急激に観光地化していく土地の姿でした。
旧市街の街並み住居は、12世紀の宋の時代につくられたとされていますが、実はその後、清代以降にナシ族が漢民族の文化から大きく影響を受ける中で変節しています。つまり、もともと旧市街の住居は、漢民族の文化を取り入れた“中国の古い街”であり、その懐かしいイメージから、観光客のほとんども中国国内からの人々です。そして急速な観光開発に伴い、ナシ族の多くは郊外へ転居。ネオン煌めく旧市街は、テーマパーク化していきました。
こうしてナシ族本来の文化が一気に奪われていく中、90年代末から、自民族文化の伝承活動が始まっていきました。そこで注目されてきたのが、トンバ教を中心にしたトンバ文化なのです。
そもそもナシ族のルーツを辿ると、中国西北部に住んでいた羌(きょう)人という遊牧民族が、秦の圧迫から逃れて南下してきたものがルーツのひとつ、とされています。今も麗江の北部にはチベット人のエリア自治区が広がっているわけですが、そうした地理的条件もあってか、トンバ教においては、固有の素朴な自然信仰と、チベットなどからの外来信仰が折り重なっているんですね。
たとえば、トンバの開祖であるトンバ・シャラ(トンバの開祖)という至志尊の神がいるのですが、この神にかんするストーリーは、チベットの民俗宗教・ボン教の始祖であるシェンラプ・ミボに出てくる類似の名称を持つ神のストーリーと、ほぼ重なります。また、イグオカとイグティナと呼ばれる善悪の二神なども、遥か遠くから伝承してきたと思しき、ゾロアスター教の影響をうかがわせるところがあるのです。
さて、ここで共存の神話に戻ります。人間と長く争った自然神・シュと人間の間には、トンバ・シャラが調停に入ったとされます。トンバ・シャラが遣わせたシャチュ(大鵬、語源はチベット語)が、両者に協定を結ばせた。耕地、家畜、家といった文化の世界は人間に、山林や泉、野生動物などの自然の世界はシュに帰し、人とシュが共有していた宝冠はシャチュに帰すことになりました。

テーマパーク化し、観光客で溢れる麗江旧市街。もはやナシ族の住民はほとんどいない。(平成28(2016)年8月)
ここから、トンバ教における儀礼の必要性が説かれます。あらゆる人間の活動は自然界の基礎に依拠しており、何らかの活動を行えば自然を侵害することから、儀礼によって生計活動で得られた供物をシュに捧げることになった、というのです。
人とシュの関係は、負債者と債権者のようなものである。人間が活動をすれば、必ずや自然神=シュに借りを負う。
シュの報復は災害、病となって現れるため、定期的・不定期的に、儀礼を行って供物を捧げるのだ、ということなのですね。
こうした人間と自然の関係性は、非常に示唆的です。しかし同時に、これを共存の神話として単に享受していいのかどうか、という問題もあります。なぜならば、トンバ文化を考えるにあたっては、トンバ教の経典に書かれた一見目を引く象形文字(絵文字)ばかりが注目されがちで、音声言語が後回しにされてきた歴史があるからです。そしてそもそも、シュと人間の関係を説く経典には、調停に至るものだけでなく、ずっと争いが続くようなものも別にある。また、トンバ文化を考えるにあたっては、トンバ教の経典に書かれた一見目を引く象形文字(絵文字)ばかりが注目されがちで、音声言語が後回しにされてきた歴史もあります。この一筋縄ではいかないところがまた興味深いのですが、それは後編に譲りましょう。