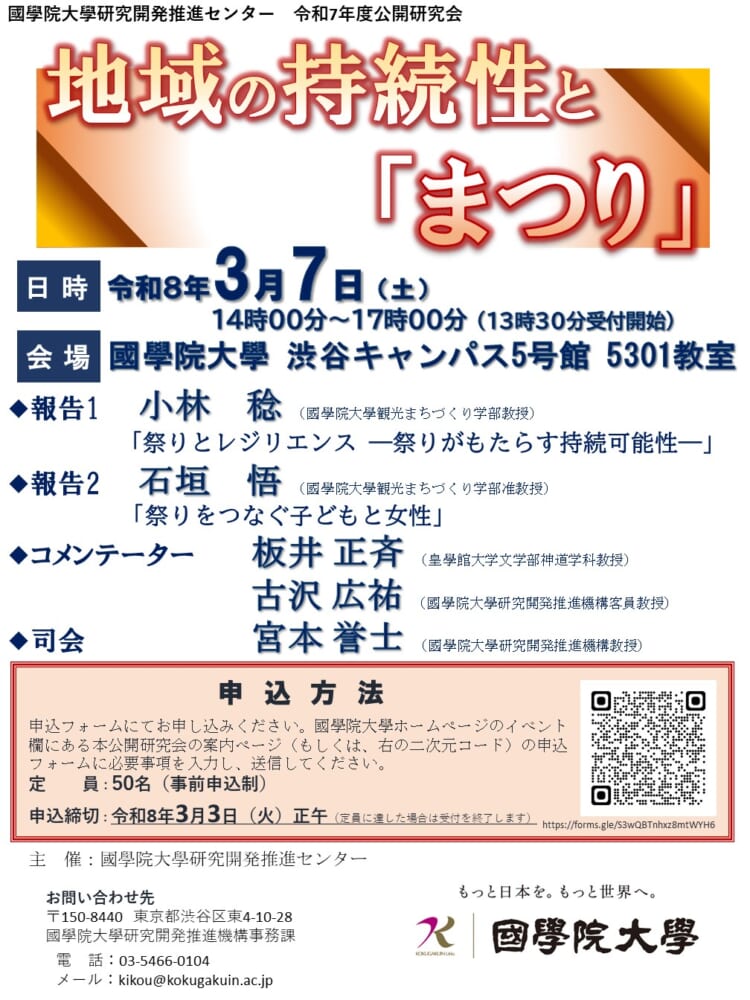佐久間長敬著『刑罪詳説』より「追放者廓外門前払ノ図」。「公事方御定書」以前に行われていた「追放刑」は江戸の町の治安維持を狙ったものだが、矛盾や弊害も抱えていた。 (写真:国立国会図書館)
江戸時代の8代将軍、徳川吉宗によってつくられた「公事方御定書」。編纂開始からおよそ10年の歳月を費やして成立したこの法典は、若い頃より無類の法律好きだった吉宗が、中国の「明律」(みんりつ)をはじめとする律令法を研究し、それを日本の社会に適するようにアレンジして作った、当時としては画期的なものだったという。
前回の記事:「暴れん坊将軍の作った法律はこんなに画期的だった!」
「『公事方御定書』において重要なのは、それまでの考え方から大きく転換して『更生』を目指す刑罰を定めていることです。当時はまだ希薄だった、『犯罪者がもう一度社会に戻れるように配慮した刑罰』が採用されているのです」
そう解説するのは、法律の歴史を研究する法学部の高塩博(たかしお・ひろし)教授。吉宗がこの法典に「更生」の要素を入れたことについて、「明律との関係性」を紐解きながら解説してもらった。ここでは、吉宗がなぜ更生にこだわったのか、詳しく聞いていきたい。

中国法に示唆を得ながら考え出した「懲して善に進む」の概念
――「公事方御定書」は、それまでの刑罰に加えて、犯罪者の社会復帰を意味する「更生」にこだわった刑罰を取り入れたと伺いました。どういうことでしょうか。
高塩 博 教授(以下、高塩) 「公事方御定書」ができる前、江戸時代前半の刑罰は、罪を犯したものの多くが「死刑」か「追放刑」に処されました。それが意味するのは、「共同体にとって不都合な存在、危険な存在を排除する」ということです。
「死刑」というのは、命を絶つことであり、その瞬間に共同体から排除されます。対する「追放刑」は、当時の“江戸払い”“江戸十里四方追放”などに代表される刑罰です。たとえば江戸十里四方追放なら、江戸の日本橋から半径五里(約20km)の範囲を立入禁止区域として、その外に放逐する刑罰です。
ポイントとなるのは、江戸払いや江戸十里四方追放のような追放刑は、原則として生涯刑だったことです。つまり、追放刑を受けると立入禁止区域に一生入ることができません。加えて、追放刑に処された者は戸籍から外されてしまいました。
ですから、江戸時代前半の刑罰は、罪を犯した者の命を絶ったり、生涯その立入禁止区域に足を踏み入れられないようにして、共同体から排除してしまうのです。そういった考え方でした。
――それが、「公事方御定書」で更生の要素が含まれてくるのですね。
高塩 はい。従来通りの死刑や追放刑も定めてはいますが、吉宗は追放刑の適用を極力控えるように指示しています。それと同時に、犯罪者がもう一度社会に戻れるよう配慮した刑罰も採用しています。そしてこの場合、吉宗が若いときから勉強した「明律」の刑罰にその形式を借りていることが分かります。
――どういうことでしょうか。
高塩 前回の記事で、吉宗は将軍となる前、和歌山藩主の頃から中国の「明律」を研究してきたことを紹介しました。明律研究は将軍になった後もますます盛んに行い、学者に注釈書や翻訳書を作らせたのです。
そして、上下巻に分かれる「公事方御定書」の構成は、中国の律令法典の性格と類似していると指摘しました。それは、明律などの律令法典を「公事方御定書」の作成に生かしていることを意味します。
そんな中、吉宗が明律研究の一環として学者につくらせた「大明律例譯義」(だいみんりつれいやくぎ、14巻14冊)は、明律の各条文を分かりやすい日本語に翻訳したものです。この書物の巻頭には「律大意」といって、刑法の運用や刑罰の適用について、心がけるべき重要な事柄を39箇条にわたって述べた箇所があります。著者の高瀬喜朴は、その第2条の中で次のように述べています。
「律令は天下を治る法なり。其内(そのうち)令は前方に教えて善に至らしめ、律は後に懲して善にすすむ」
律令法典の「令」は「このようにしなさい」とか「こうしてはいけない」という命令や禁止を定めた教令法、「律」はその違反を罰する制裁法(懲罰法)となっています。これは、「公事方御定書」の上下巻にも見られる構成なのですが、先の一文で大切なのは、「令は前方に教えて善に至らしめ、律は後に懲して善に進む」という部分です。
「前方」は「あらかじめ」という意味で、「後」は「罪を犯した後」ということです。“あらかじめ善に至らしめること”はもちろん大切なのですが、罪を犯してしまった後は、刑罰によって“懲らしめて善に進ませよう”という訳で、ここに更生の考えが強く表現されています。
「犯罪を再生産」する現実。庶民に寄り添った吉宗

徳川吉宗(とくがわ・よしむね):1684〜1751年。江戸幕府の第8代将軍。和歌山藩徳川家の第2代藩主光貞の四男。1705〜1716年まで和歌山藩の藩主を務めた後、1716〜1745年まで江戸幕府の将軍となる。享保の改革を推し進め、財政を復興。また、新田開発の推進や目安箱の設置といった政策も行った。
――しかしなぜ、吉宗はそこまで「更生」にこだわったのでしょうか。
高塩 幕府としては、江戸払いのような追放刑を実施する方が、本当は楽なはずです。手間としては、常盤橋門の外(今の日本銀行の裏側)まで連れて行って「ここから出ていきなさい」と、立入禁止の地域を記した書面を罪人に渡すくらいです。ですから、刑を執行するのにほとんど費用はかかりません。それでいて、罪人がその地域から立ち去ったなら、表面的にはその地域も安全になります。
しかしながら、こういった追放刑は「犯罪を再生産している」という矛盾があったのです。なぜなら、追放刑を受けた罪人は戸籍から外されて、「無宿」となってしまいます。江戸時代であっても、まともな仕事をするためには、現在と同じように保証人が必要でした。戸籍のない無宿はそこをクリアできず、真っ当な仕事に就けません。
その結果、日々の食べ物や冬の寒さに困り、結局は盗みなどの犯罪に走るという矛盾が生じる訳です。そうして、追放先の治安も悪化するという弊害も生じることになります。つまり「追放」という刑罰は、犯罪人をA区域からB区域に移動させているに過ぎないのです。
――それだと、本当の意味で社会が良くなっていきませんね。
高塩 さらにいえば、追放という刑罰は「懲戒」、つまり犯罪者を「懲らしめる」という意味合いが薄かったんですね。「ここから出ていきなさい」と言われるだけですから、役人に見つからないように江戸にとどまったり、立ち戻った追放刑者もいました。江戸の外に立ち退けば生活ができないからです。
でも、もしそれが見つかれば、次はより重い刑罰になり、最悪は死刑になります。追放刑は、こういった不具合に満ちていたんですね。
江戸払いのような追放刑は、為政者にとって簡便な刑罰ですが、吉宗は違う形を追い求めました。それは、彼が庶民のことを考えていたからだといえます。前回、彼が乳牛を飼って酪農を始めたり、飢饉に備えるために、さつまいもを関東で作れるように研究させたりしたエピソードを紹介しましたが、それらと同じことですよね。
吉宗は、税金を厳しく取り立てるといった面もあったようですが(笑)、しかし更生に力を入れたのは、彼が庶民のことを真剣に考えていたからこそだったのではないでしょうか。
窃盗の刑罰に見られる、更生するための工夫
――吉宗の「更生」への思いが分かりました。では、彼は法典においてどのようにその思いを具現化したのでしょうか。
高塩 分かりやすいのが「盗み」、すなわち窃盗犯罪に対する刑罰です。窃盗は、「犯罪の王様」と言われています。それは、犯罪の中で一番多く発生することとともに、犯罪を重ねる傾向があるからです。
そういった窃盗犯罪に適用する刑罰として、「公事方御定書」では、初犯に「敲」(たたき)の刑、再犯に「入墨」(いれずみ)の刑、三犯には「死罪」という名の死刑を科す原則を作りました。このような「窃盗三犯は死刑」という原則は、前回も紹介したように、やはり明律と共通しています。
このうちの入墨については、中国では入墨のことを「刺字」(しじ)と称し、初犯だと右腕の手首と肘の間に「窃盗」の漢字を彫り込み、再犯では左腕に同じものを彫りました。そして三犯には、死刑を科したのです。
「公事方御定書」では、それをアレンジして、初犯は敲、再犯で入墨としました。入墨の入れ方についても、漢字を彫るのではなく、図案化したものを入れるように決めました。
――窃盗の犯罪者に対して、すぐに追放刑や死刑という形で「排除」するのではなく、初犯、再犯で猶予を与えながら、敲や入墨によって更生を図ったということですね。
高塩 加えて、入墨には別の意味もあります。まず、入墨は「死刑の前段階にあること」を示す印になります。さらに、入墨という形で「前科者の烙印」を押すことで、周りの人たちは「入墨の人がいたら気をつけましょう」と、盗み犯罪から身を守るように警戒させる役目がありました。「入墨」の刑には社会防衛としての役割もあったと考えられます。
――死刑や追放刑もありましたが、一方でこのような更生を考えた刑罰を取り入れたんですね。
高塩 そうですね。ちなみに吉宗の孫であり、老中を務めた松平定信は、こういった考えを引き継いで、人足寄場(にんそくよせば)という収容所を設けます。これは無宿や、刑罰を終えた罪人が社会復帰できるよう、教育的な処遇を施す施設でした。
当時、盗みの罪などで、敲や入墨の刑を受けた無宿が、この人足寄場に収容されました。これは吉宗が亡くなった後の話ですが、そういった形で「更生」の思いは受け継がれていくのです。
この「人足寄場」については、また別の回できちんとお話しすることにしますが、いずれにせよ、吉宗は「敲」や「入墨」といった刑罰によって、犯罪者の更生に力を入れていきました。
――そうだったんですね。ちなみに、「敲」という刑罰が江戸時代に存在していたことは知っていましたが、それが更生と深く関わっているのは意外でした。
高塩 実はこの「敲」こそ、吉宗の更生に対する思いが強く現れた刑罰といえます。現代では“野蛮な刑罰”というイメージが強すぎるのかもしれません。しかし、当時の時代背景を照らし合わせると、「敲」の本当の姿と、そこに込められた心遣いが見えてきます。
「敲」という刑罰と、更生との関係については、次回詳しくお話ししましょう。