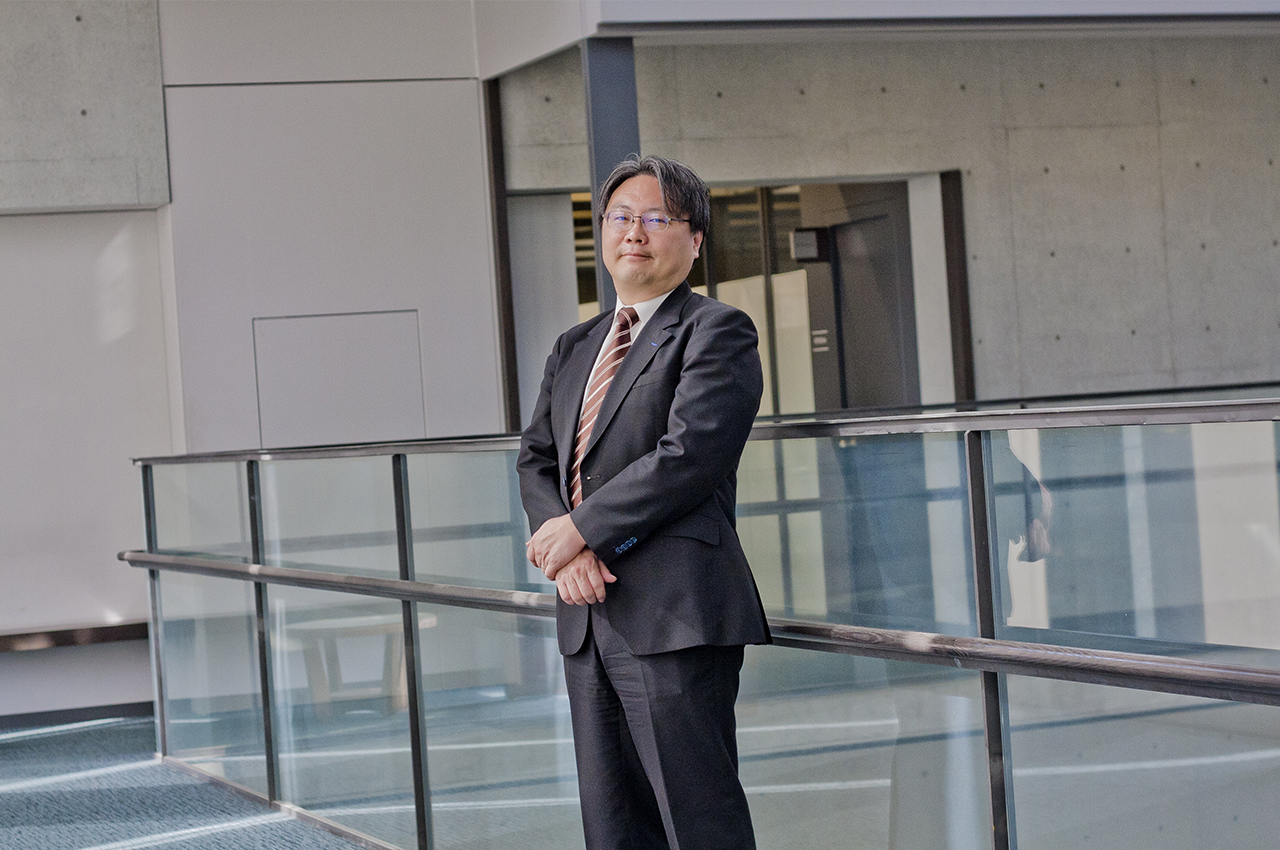
現在、私たちがおおよそ考えるような「宗教」という概念が未だ判然としていなかった時代。明治期に生きた宗教者たち、たとえばキリスト教者や仏教者の知識人たちは、自らの宗教こそが正しい「宗教」であると、激しく舌戦を繰り広げていたのだという。
星野靖二・研究開発推進機構教授へのインタビュー。この後編では、自身が宗教学へと足を踏み入れた経緯を語ったうえで、明治期の宗教者たち、特に知識人たちの活動へとフォーカスしていく。まるで現代のラッパーたちのような、宗教者たちのディスり合いの面白さ、そしてその先に見える「宗教」研究の醍醐味に触れてみよう。
宗教の研究をしようと考えた要因のひとつとしては、「いま自分がなぜ、このようなものの考え方をしているのか知りたい」と思ったからです。といっても、私はなにかしらの宗教の自覚的な信者ではありませんし、また倫理学や思想史学でも「ものの考え方」を研究することはできたのかもしれません。色々なご縁や出会いがあって、宗教に焦点を合わせて研究するようになり、宗教学にたどり着きました。
ふりかえれば、学部生の頃に漠然とそのように考えるようになっていたかと思います。この問いに答えようとするならば、仏教や神道あるいは民俗宗教など、日本においてよりメジャーな考え方や宗教、思想などを掘り下げて、自分の考え方の淵源へ遡っていくやり方もあったかもしれません。しかし、自分はそう考えなかったのです。
近代以降、日本が西洋から絶大な影響を受けてきたことは疑いようのないことですが、他方で日本にもたらされたキリスト教が主流の宗教になったとはいえません。それでは、キリスト教という宗教が日本においてどのように提示され、またそれを受け入れた日本人はどのようにキリスト教を捉えていたのか、という視点から、逆に日本における宗教のあり方を照らし返すことができるのではないか、と思うようになったのでした。キリスト教や教会との縁はまったくなかったのですが、アメリカのキリスト教系の大学に交換留学して、実際に信者の生活やものの考え方に触れることができたのは良い経験でした。

当時の自分の中には、キリスト教こそ宗教を代表するような宗教、いわばザ・宗教だというイメージが漠然とあったのだと思いますが、インタビュー前編での「宗教」という概念の歴史的な展開をめぐる議論を踏まえれば、まさにそうした「宗教」概念を自分の中に取り込んでいた結果だったのだな、と。
その後、宗教学の大学院に進み、「宗教」概念をめぐる議論にも触れ、宗教についての自分のものの考え方をも解きほぐすような形で、研究を進めてきました。人との出会いに恵まれ、関心の幅を広げてもらったり、共同研究に誘ってもらったりしてきたので、自分が受けた恩を若い研究者に返すことができればと思っています。
具体的な研究について、主な手がかりとしたのは、宗教者でありかつ知識人である人々が残した文字資料です。
これもインタビュー前編で触れたことですが、明治期の宗教者たちは、他の宗教者たちや、より広く社会一般に対して、自分たちの宗教が良いもの、正しいものであると弁明する議論、広い意味での「弁証論」を行いました。そこで、より良い、より正しい「宗教」であると論じる際に、西洋における「宗教」をめぐる議論が参照され、またそのような議論が積み重ねられていくことを通じて、当時の日本における「宗教」という概念が組み上げられていくことになります。
たとえばキリスト教は江戸時代に禁じられていたわけですので、いくら文明開化の時代だといっても、キリスト教者たちは「我々は怪しいものではない」と社会に対してわかりやすい言葉で説明する必要がありました。そのように自分たちの正統性を強調する議論のなかに、従来の日本の宗教、たとえば仏教への批判や非難が含まれることがあったのです。

それに対して仏教者たちのなかから、いや我々はそんな言われ方をするようなおかしな宗教ではない、むしろキリスト教より優れているのだといった反論が出てくることになります。こうして、弁証論の応酬というものが見られるようになるわけです。現代的な表現を用いれば、お互いにディスり合っているわけですね(笑)。
明治中期頃の弁証論の応酬は、演説という形で、信者に限定されない広い聴衆に対する語りかけとしても行われました。また演説筆記や論説が新聞や雑誌に掲載される場合もありました。そこでキリスト教あるいは仏教の立場に立つ知識人たちは、お互いにディスり合う一方で、何が良い宗教であるのかという枠組、つまり議論の土俵については、ある意味で共有していくことになるのです。
たとえば、キリスト教の神学に自然的宗教と啓示宗教という考え方があります。これは全ての宗教に人間の本性に基づく自然的宗教の側面を認める一方で、キリスト教のみが神の啓示を受けた啓示宗教であり、より優れた宗教であるという主張を可能にする分類法で、実際に明治時代のキリスト教弁証論にも使われました。これに対して、キリスト教への対抗を念頭に置いて仏教を擁護しようとした中西牛郎という人物は、全ての宗教に、すなわち仏教にも啓示的な面があると主張しました。キリスト教についての知識を持っていた中西は、このように論じることで、キリスト教が他の宗教に対してマウントをとるためのロジックを突き崩そうとしたと一方ではいえます。他方で、およそ宗教というものは啓示的な面、すなわち何らか超越性との関わりを持つ、という形で宗教一般を論じるための土俵を共有し、設定したともいえるのです。
中西のこうした議論は、例えば明治22(1889)年に出された『宗教革命論』という著作に書かれていますし、また当時中西は『経世博議』という雑誌で主筆を務めたり、あるいは他の仏教系の新聞や雑誌に多く論説を寄せたりしていました。この時期に中西が唱導した「新仏教」という考え方が、その後の議論に影響を与えたことが明らかになっていますが、こうした文字資料に注目して、私は研究を進めてきた次第です。
面白いことに、私の著作である『近代日本の宗教概念 宗教者の言葉と近代』(有志社、平成24〔2012〕年)にかんして韓国語版を出していただく機会に恵まれ(만들어진 종교:메이지 초기 일본을 관통한 종교라는 물음、2020年)、また中西の『宗教革命論』の一部に解題を付けて英訳したものが、東北大学で日本の宗教を研究しておられるオリオン・クラウタウ(Orion Klautau)先生らによる令和3(2021)年の共編著Buddhism and Modernity: Sources from Nineteenth-Century(University of Hawaii Press)に収録されるといった出来事が続いています。
さらに、昭和30(1955)年に創立された本学の日本文化研究所は、研究開発推進機構・日本文化研究所としてこの令和7(2025年)で70周年を迎え、私はこの4月に所長を拝命しました。日本文化研究所は、創立当初から国際的な学術交流と発信を重視し、現在に至ります。日本の宗教の研究は、もちろん日本の宗教を研究するものですが、同時に日本の宗教だけに限定されたものでもありません。また、「宗教」概念の普遍性が問い直されるようになっても、時代や地域によって、どのように異なっているのか、あるいは同じであるのかといったことは、比較研究をしなければわからないことでもあります。自分としても、また日本文化研究所としても、開かれた形で研究を進めていきたいと、あらためて考えているところです。
<<前編は「わたしたちがもつ「無宗教」という誤解」
| 1 | 2 |
星野 靖二
研究分野
宗教学、近代日本宗教史
論文
「明治初期における世界の「諸宗教」像――黒田行元による著作の検討」(2022/10/25)
「合理的宗教論」と「実存的宗教論」―井上円了と清沢満之を取り巻く同時代的な文脈(2020/12/01)


