
日本社会は無宗教だから──至るところで耳にするフレーズだ。しかしこうした宗教の捉え方は、明治期以降、「宗教」概念が醸成されていくなかで形成されたものではないかと、宗教学を専門とする星野靖二・研究開発推進機構教授は語る。私たちの「宗教」をめぐる思考のありようは、あるいは時代の流れと共に形成されてきたものなのではないか、と。
歴史を紐解くなかで見えてくるのは、明治期のキリスト者や仏教者たちを中心に、西洋的な「宗教」の概念を踏まえながら、考えを巡らせ、発言していった宗教者たちの姿。インタビューの前後編を通じて、そうした思想の流れをたどりつつ、現在の私たちの足元を見つめ直してみよう。
「宗教」という言葉から、どんなイメージを抱くでしょうか。さまざまな宗教を包括できるような概念のことを考える方もいれば、個別具体的な宗教を思い浮かべる方もいることでしょう。
私が専門としている宗教学においても、宗教とは何かについて、いまだに誰もが納得するようなはっきりとした答えはでていません。とはいえ、宗教学の歴史を振り返ってみると、宗教は普遍的に存在するという考え方が、議論の前提とされていた面があります。つまり、古代から現代まで、どんな時代でも、どんな国・地域であろうとも、共通の普遍的な性質をもった宗教というものが存在する、という考え方ですね。
対して、近年では、そうした時代や国・地域を超えて普遍的に存在する宗教というようなイメージを、簡単に前提にしてしまってはよくないのではないか、という考え方が出てきています。たとえば、私たちが今生きている日本の社会に焦点を合わせ、現代日本語における「宗教」という言葉が西洋のreligionの訳語としてつくられていった過程や、そのreligionをめぐる考え方自体を日本の社会がどのように受け入れていったのか、その試行錯誤に目が向けられるようになってきているわけです。
私は宗教学のなかでも近代の日本、特に明治から戦前にかけての時代をメインに取り組みつつ、戦後も視野に入れながら研究を進めているのですが、いま述べたような「宗教」をめぐる再考という流れのなかに、自分の研究も位置づけることができると思います。具体的な研究対象として、近代日本におけるキリスト者や、その言説に影響を受けながら自らの考えを深め、発言していった仏教者などを取り上げて論じてきました。

先程「宗教」という語が訳語として成立したといいましたが、これについて、もとからあった日本的な宗教性のようなものが、近代になって日本にもたらされた西洋的・キリスト教な「宗教」に塗り替えられてしまったという考え方をされる方もおります。ただ私としては、同時代的にも、そしておそらくは今でも、そこまで白黒がはっきりしていたわけではなく、いろいろと混ざり合ってきていると考えています。私の研究についていえば、キリスト者や仏教者といった当時の宗教者たちが新たな「宗教」という概念に触れ、これについて思考し、その考えを公表するということが行われ、それらがお互いに影響を与えながら、折り重なり、積み上がっていくことで再帰的に「宗教」という概念が構成されていったプロセスに注目してきたといえるでしょうか。
これを受けて、明治の世になってから現在までの150年以上のあいだ、外からもちこまれた「宗教」という考え方がどう捉え直されながら現在に至っているのか、何がどう変わってきたのか、ということを考えることができればと思っています。戦後のことも視野に入れているのは、変遷を遂げた明治期の宗教者たちの言説が、その後、現在に至るまで、どう捉え直されてきたのかを見ることで、日本における「宗教」のあり方とその変化を観察することができるだろうと踏んでいるからなのです。近代の研究でやらなければならないことが非常に多く、なかなか手が回らずにきてしまったというところは正直あるのですが……(笑)。それでもなんとか戦後まで含めて考えてみたいと、目下研究を進めているところです。
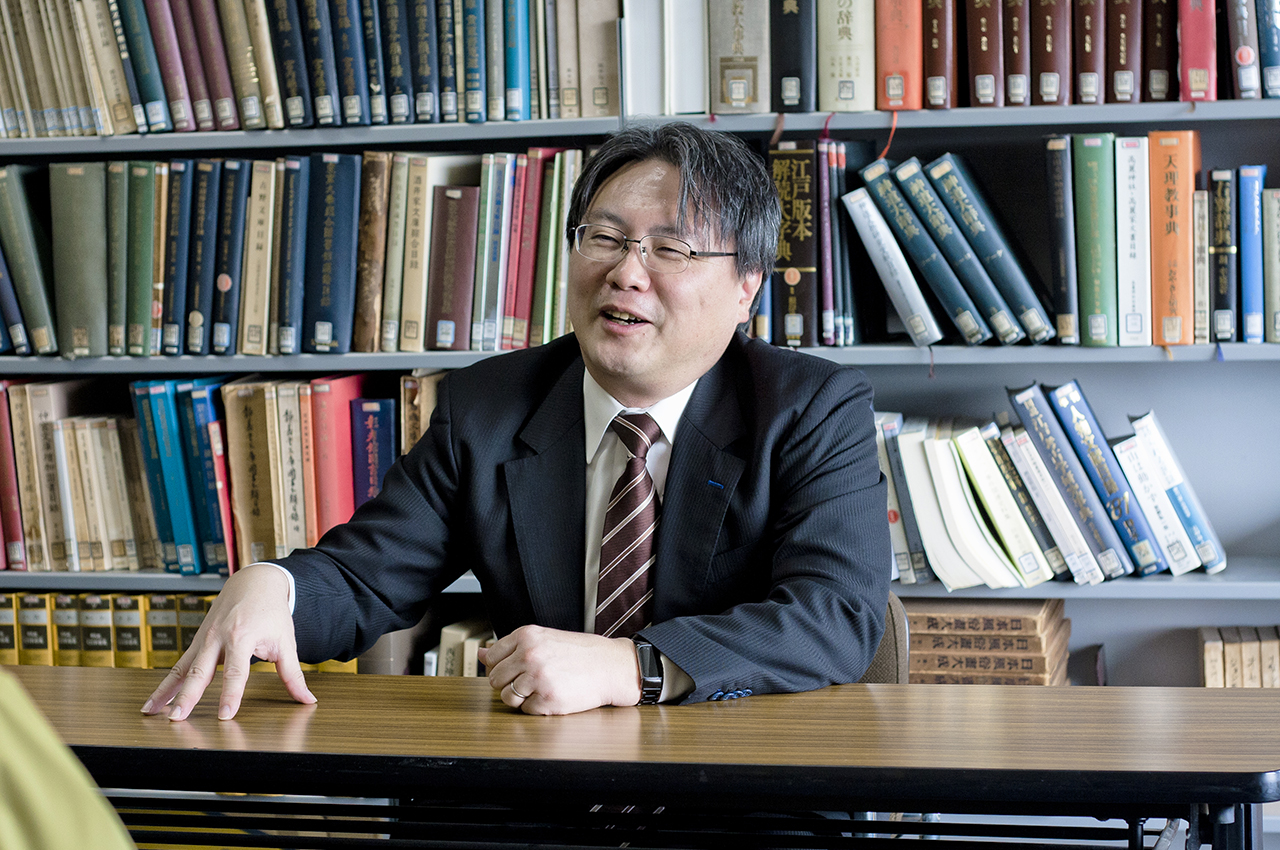
こうした議論のひとつとして、もう一点、読者の皆さんにお尋ねするとすれば、「宗教とは、その教えを信じるものである」というイメージを抱いていませんでしょうか。日本社会においてはそこまで教えや教義を信じる人がいないから無宗教的だ、というような考え方にも結びつく宗教イメージですね。
しかし、「宗教といえば教えを信じるものである」というセオリー自体がプロテスタント・キリスト教的ではないかということが、近年の宗教学の研究でいわれています。聖書を読み、その教義を自分で咀嚼して理解し、実践していくというプロテスタント・キリスト教の理念が、ある意味宗教のモデルとして設定され、それが他に投影されていったという歴史上の出来事がありました。これが近代の日本でも生じ、日本の「宗教」の見方に影響を与えたのです。
しかも実際のプロテスタント・キリスト教においては、教えや教義を信じるかどうかとは別の次元で、例えば教会に足を運ぶことによって宗教の共同体に包摂されるといった、弾力性のある宗教実践の様相が見て取れます。しかし、日本に「宗教」概念がもたらされた時に、そうした共同体的な要素にはあまり目が向けられず、純粋に、あるいは過剰に「教えを信じる」ことが強調されていった面があると考えています。その影響は今でもあって、それゆえに「教えを信じる」ことをしていなければ宗教者ではないといった考え方や、「日本社会は無宗教だ」というような物言いが出てくるようにまでなっている、といえるのではないでしょうか。
初詣やお墓参りといった日本に住む私たちにとって身近な儀礼的行為が、宗教的な側面をまったくもたないとは到底いえません。かといって先ほど申し上げたように、日本には、外から持ち込まれた「宗教」ではない、日本的な宗教性がもともとあるのだと開き直ってしまうのも、近代以降の概念の変遷を捨象してしまうことになってしまいます。宗教という概念をめぐるさまざまな絡み合いがあり、普段はなかなか自覚しないようなズレやギャップというものが、明治以降に大きく広がってきたのではないかということを、冷静に見ていくことができれば──と、私としては考えているのです。
このような観点において私が宗教に関心を抱くようになったのには、それこそなかなか一言ではいえない経緯があるのですが、インタビューの後編ではそのあたりにも触れつつ、明治以降における宗教者たちの「弁証論」などについて考えてみたいと思います。「宗教」という概念が醸成されていく時代において、キリスト者たちは、あるいは仏教者たちは、どのように相手を非難し、自らを擁護したのか。いまの物言いでいえば、ディスり合いですね(笑)。そのありようの一幕も合わせて、お伝えしたいと思います。
後編は「「宗教」概念の形成と明治期の激しい議論」>>
| 1 | 2 |
星野 靖二
研究分野
宗教学、近代日本宗教史
論文
「明治初期における世界の「諸宗教」像――黒田行元による著作の検討」(2022/10/25)
「合理的宗教論」と「実存的宗教論」―井上円了と清沢満之を取り巻く同時代的な文脈(2020/12/01)


