
ゲームばっかりしてないで、体を動かして遊んできなさい──運動不足の子どもに対して、大人がこう口にするのは簡単だ。しかし子どもが実際、自律的にスポーツや外遊びに取り組むということは、なかなか難しくもある。そうしたなか、いまでは日本の子どもたちのうち、小学校高学年であれば、およそ10人に1人は「肥満傾向児」であるという統計が出ているという。
そうした現状に対して、なんとか手立てを考えようと模索を続けているのが、川田裕樹・人間開発学部健康体育学科教授だ。幼少期から成人後まで、人が生涯にわたって健康的に暮らすということは、どのようにして可能なのか。そのための知見を、インタビュー前後編で訊ねていく。
スポーツ科学や運動生理学といった分野のなかでも、子どもの発育や発達にかかわるところ、特に子どもの肥満やメタボリックシンドロームといった健康問題に対応し、健康増進に寄与するための研究を進めています。
実測体重が標準体重よりも何%上回っているかの指標である「肥満度」が20%以上の子どもを「肥満傾向児」と呼びます。令和4年度学校保健統計(学校保健統計調査の結果)によれば、肥満傾向児の割合は、男女ともに小学校高学年が最も高く、10歳男子における肥満傾向児の割合は約15%、10歳女子では約10%という結果になっています。いずれにしても、小学校高学年の子どもたちにおいては、おおよそ10人に1人以上は肥満傾向児である、という状況になっているのです。
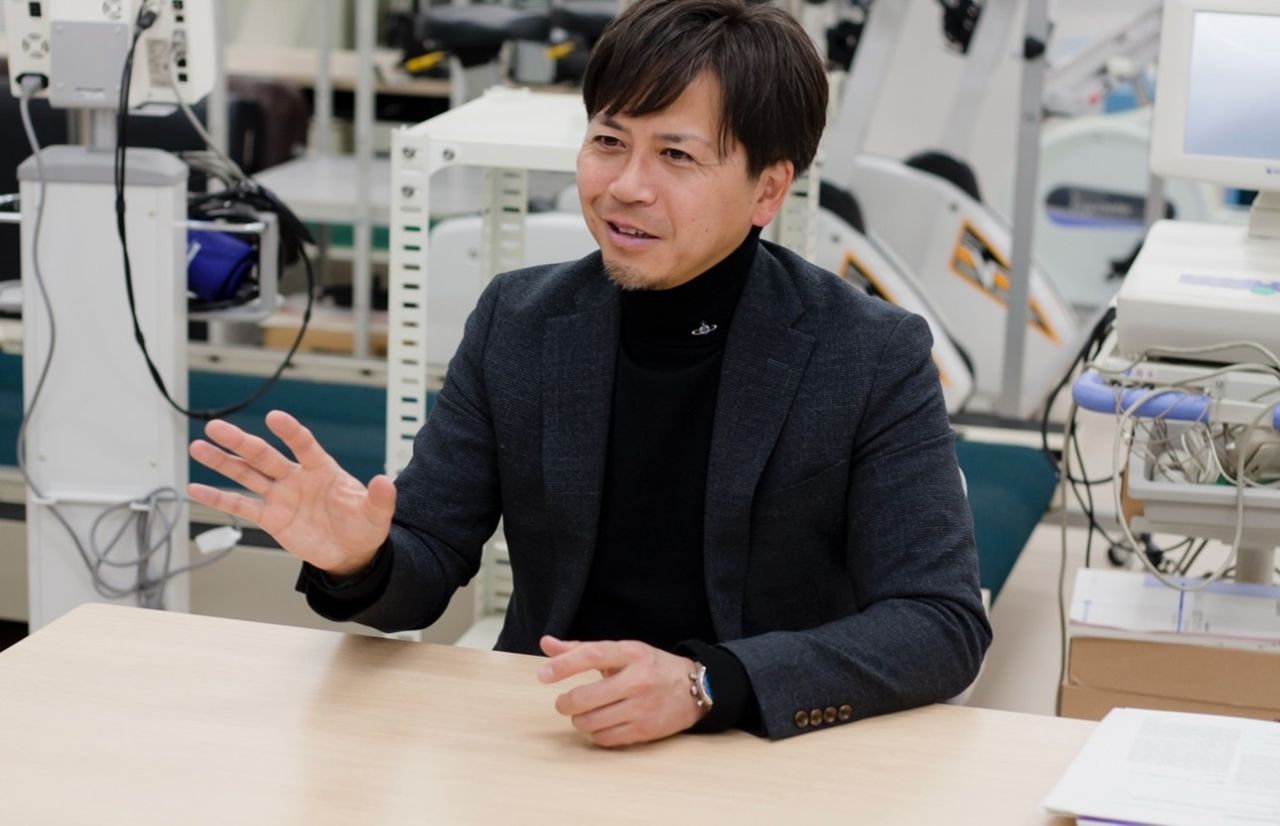
仮に30人の学級であれば、そのうち3~4人は肥満傾向児ということになります。子どもの肥満を放置していても成長するにつれて勝手に解消してくれるのであればそれで良いのですが、残念ながらそのように都合よくはいきません。日本人の肥満小児を対象に長期追跡調査を行った疫学研究によると、小児期の肥満を放置してしまうと、そのまま成人肥満に移行するリスクがかなり高くなることが報告されています。したがって、肥満傾向児は、やがて成人肥満へ、そして高血圧症や脂質異常症、糖尿病といった生活習慣病へとつながっていってしまう恐れがある。これは見過ごせる問題ではありません。
成人の生活習慣病については多くの大人が問題認識をもっているでしょう。たとえばダイエットといった営みは──そのうち過度な取り組みがもつ問題点などをひとまず置いておくとすれば──私たちの社会において、日常的なものとなりました。
しかし、そうした問題意識から、子どもという対象は抜け落ちてしまうことも少なくないのです。しかも子どもたちが自ら対策しようという意識をもつことは、なかなかない。だからこそ、社会で子どもの健康について考え、必要に応じて支援していかなければならないのです。
もちろん、子どもたちにおいて過度なダイエットが課される、というような事態は厳重に避けなければいけません。大人においてさえ、適度な運動を伴わない、食事のみによる減量はなかなか推奨できるものではありませんが、子どもに対しては厳禁です。なぜなら、成長期である子どもに対する急激な食事制限は、その後の成長に著しい悪影響を及ぼしてしまうからです。
子どもの肥満対策というものは、大人以上に、食事のコントロールだけではなく、スポーツや外遊びなどの身体活動を大きく取り入れていくことが重要になってきます。栄養バランスや間食の量などを見直しながら運動習慣を身につけていくことでエネルギー消費を増やし、肥満度がそれ以上増加しないよう食い止める。身長がどんどん伸びていくなかで、結果的に肥満度のパーセンテージが減少していくのが望ましいと考えます。

ここですこし、私のバックグラウンドについてお話しさせてください。30年近く前のことになりますが、大学で体育学部に在籍していた私は、子どもの健康というよりは、主に高齢者の体力や健康増進について研究するゼミに属していました。体育学部の学生というと、アスリートのパフォーマンスに興味をもつ人が多いわけですが、私はその頃から「人々の健康に貢献したい」という方向性が、ぼんやりと自分のなかにありました。ただ、それでも自分の視界に、子どもという対象は当初入っていませんでした。
そんな学生時代にゼミの一環でたまたま読んだ、小児肥満に対する運動療法の研究論文に興味を抱いたのが、現在に至る専門分野へと足を踏み入れる、そして大学院進学の大きなきっかけでした。その論文を執筆された先生のもとへと進学し、子どもの肥満問題へと──大人になる前の早い段階でのアプローチの必要性について、考えていくようになったのです。
生涯にわたる健康維持・増進を考えた場合には、やはりできるだけ早い段階でのアプローチが必要です。成人肥満に対する対処は叫ばれてはいたものの、子どもの肥満については、現在ほど注目されておらず、研究も盛んではない時代でした。
大学院で師事した先生は、そのなかでも先駆的に子どもの健康増進に──特に子どもの肥満に対する運動療法についての研究に取り組んでいる方のひとりでした。だからこそ、その方の論文を読んだ私は驚きましたし、子どもの肥満への対処という取り組みに、新鮮な魅力を感じたのでした。実際に大学院に進学すると、病院の小児科と協力し合って、高度肥満の子どもに対して医学・生理学的な知見を踏まえながら食事・運動・行動療法を行うとともに、その効果についての研究が積み重ねられていました。
そのような取り組みに参加しながら私は、研究のノウハウのみならず、子どもの頃からの運動の習慣づけの大切さも学んでいったのです。「三つ子の魂百まで」ということわざもあるように、やはり幼少期のうちにきちんと食習慣・運動習慣を身につけることが、生涯にわたる健康の維持増進につながっていくものと考えています。
とはいえ、肥満の子どもが自分自身に運動を課す、ということはなかなか難しい。やはりそこでは、周囲にいる大人の存在が鍵になります。インタビューの後編では、子どもの健康増進と大人の深い関係性について、お話ししてみたいと思います。
後編は「子どもの健康は周囲の大人たちと共にある」>>
| 1 | 2 |
川田 裕樹
研究分野
発育発達、運動生理・生化学、栄養学、運動処方、健康教育学
論文
GPS測定による移動軌跡から得られる幼稚園児の活動の特徴(2022/02/01)
The Association of Body Image Self-Discrepancy With Female Gender, Calorie-Restricted Diet, and Psychological Symptoms Among Healthy Junior High School Students in Japan(2021/10/05)


