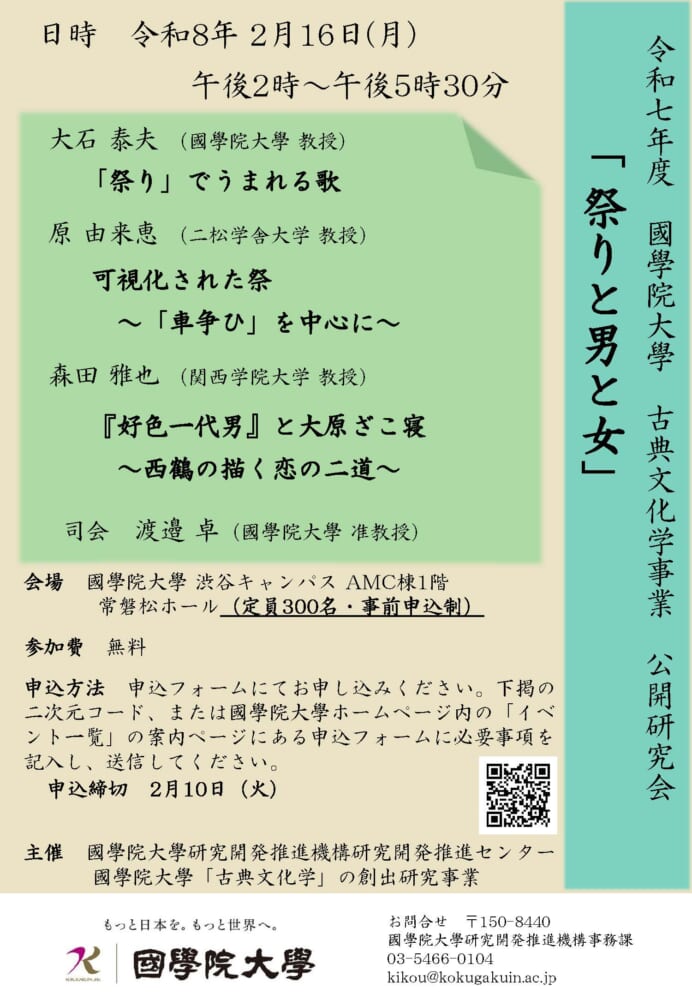令和6(2024)年に無罪が確定した冤罪事件、「袴田事件」にかんして、多くの報道がなされている。しかしそうしたなかでも、なかなか取り上げられない問題があることが、中川孝博・法学部法律学科教授の話からは見えてくる。
これほどまでに冤罪が幾度も発生してしまう、問題の淵源は何なのだろうか。刑事訴訟法を専門とし、そのなかでも「訴訟関与者のコミュニケーションの適正化」をテーマに研究を続ける中川教授へのインタビューは、実際の公判を踏まえながら問いを深めていくことになる。私たちの社会のなかで紛れもなく起きている出来事の細部を、専門家の目を借りながら共に見てみたい。
インタビュー前編の最後に、私が大学3年生のときに考えることになった「甲山事件」について触れました。詳細はそちらの記事に譲りますが、殺人容疑にかんして被告人を無罪とした一審に対し、審議が足りないと二審が差し戻しを決定したということに大きな構造的な問題がある、と当時の私は感じたのでした。
私は一審の判決が妥当なものだと考えましたが、かといって二審がまだ審議する余地があるはずだと言われれば、そのような気がするものです。つまりは本来、一審と二審のあいだで、真理をめぐる論理的な決着はつかない。にもかかわらず、二審の判断が優先されるわけです。
刑事裁判には「疑わしきは被告人の利益に」という大原則があることを、読者の皆さんもご存じでしょう。決定的な判断ができないなら、その時点では無罪になるはず。しかし、最終的に平成11(1999)年に無罪が確定するまで、昭和49(1974)年の事件発生から被告人は人生のうち、ほぼ四半世紀の時間を費やす結果となってしまった。そこにはまるでルールに抜け道があるように、私の目には映りました。

私が「訴訟関与者のコミュニケーションの適正化」という現在の研究テーマに至るうえで、この甲山事件は原点となりました。二審は決して、一審の無罪判決の論理を完膚なきまでに突き崩したわけではありません。つまりそこでは論理で優劣が決まっていったのではなく、構造的なコミュニケーションの上下関係のなかで差し戻しが決まっていったのです。その間に被告人が過ごさざるを得ない時間は、あまりにも長い。
時期は前後しますが他にも、近年多くの報道がなされており、ここでも後述する「袴田事件」や、昭和42年に発生した強盗殺人事件である「布川事件」といった有名な冤罪事件がいくつもあります。布川事件は被告人に無期懲役判決が出た後、平成21年に再審が開始され、地裁で無罪判決が出たのは平成23年のことでした。この中でも再審開始決定書の厚さは特筆もので、なんと300ページもある。有罪判決を出す場合はたいてい薄いのですが、有罪を無罪へひっくり返す場合には、有罪と考えうる可能性をすべて潰していかなければいけない。そこで膨大なページ数となってしまう。「疑わしきは被告人の利益に」という原則があるにもかかわらず、逆転現象が起きている。このコミュニケーションの手間が、無罪判決を出しにくくしていることもありうるでしょう。
刑事訴訟法の範疇における、コミュニケーションの構造的な不全のなかで、それほどまでに被告人に犠牲を強いていいのか──そうした疑問が、甲山事件のことを考えていた学生時代の私の頭からどうしてもぬぐえなかったし、その後もこの問いがずっと私の根っこにあります。「訴訟関与者のコミュニケーションの適正化」への研究へ進んでいった背景としては、このような大きな経験があったのでした。

ディスコミュニケーションは、起訴前の捜査段階にも、公判のなかにも、至るところで見受けられます。たとえば、供述の信用性を吟味するうえで重要な心理学鑑定は、裁判官によって大きく扱いが異なります。先述した袴田事件は、昭和41年に発生した強盗放火・殺人事件にかんして袴田さんに死刑判決がくだり、後の再審で令和6年に無罪が確定しました。この第一次再審請求時、供述に対する意見書を提出したのは、発達心理学者である浜田寿美男氏でした。
しかしこの浜田意見書に対して、東京高裁の裁判官は激しい拒否反応を示しました。「裁判官の自由な判断に委ねられるべき領域」に、このような心理学鑑定の意見書が立ち入るべきではないとまで述べたのです。
一方で、こうした心理学鑑定を柔軟に受け入れる裁判官も存在します。浜田氏はあの甲山事件の際には特別弁護人を務め、目撃者の証言を分析したのですが、被告人に対して無罪を言い渡した第一審判決では、ほとんど「コピペ」と表現していいほどに、浜田意見書が取り入れられている。
このように、心理学鑑定ひとつとっても、コミュニケーションが上手くいっているとは到底言えない。私は袴田事件の再審において無罪判決が出たこと自体は大変すばらしいものだと考える人間のひとりですが、しかし実はこの無罪判決においても、心理学鑑定はあまり参考にならないと、ほぼ加味されていないということは看過できません。ここまで述べたような心理学鑑定の扱いをめぐる問題は、残されたままなのです。「供述の信用性評価に関する公共的基準の構築」は、私が目下取り組んでいるテーマのひとつです。
全体的な「訴訟関与者のコミュニケーションの適正化」にかんして、もうひとつ、近年私が着目しているのはAI(人工知能)です。ディスコミュニケーションから冤罪が生まれてしまうという仮説を立てるとすれば、その穴を埋めていくものとして、AIが使えるのではないか、ということですね。裁判官がすべての証拠の評価を漏れなく行うということは、非常に大変なことです。あるいは検察はそうした証拠評価に際して、被告人を有罪にするのに利するような言及に偏るという問題がある。それらのなかで取りこぼされてしまうポイントを、AIならば拾い上げることが可能かもしれない。刑事訴訟法の専門家として、新たな技術も取り入れながら、コミュニケーションが十全に行われる未来を目指したいと考えています。
<<前編は「冤罪と刑事訴訟法 法の現場で直面する課題」
| 1 | 2 |