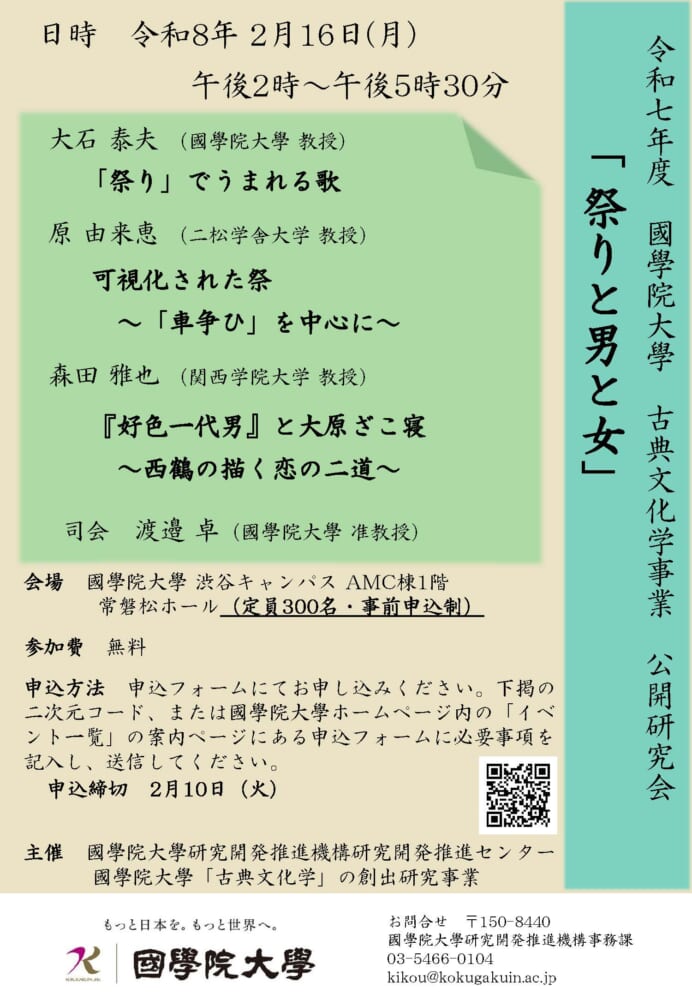刑事訴訟法の専門家である中川孝博・法学部法律学科教授の語り口は、驚くほどにフレンドリーだ。捜査や公判といった手続にかんする法律という、一見ドライなイメージをひっくり返してくれるのは、中川教授がそもそも刑事訴訟法を研究するに至ったきっかけに「コミュニケーション」への興味があったからなのかもしれない。
私たちも一喜一憂を繰り返している、日々のコミュニケーション。そうした日常的なやりとりと、刑事訴訟法が抱える問題は、実は隣り合っているようなのだ。どういうことなのか、自身の歩みと共に、前後編のインタビューで訊ねてみた。
刑事法のなかでも、特に刑事訴訟法という法律を専門としています。犯罪・犯人・刑罰を確定させる手続を規定する法律なのですが、起訴前手続である捜査や公訴を経ての公判、そして場合によっては上訴など、その範囲は広いものです。
そうした刑事訴訟法において私は、「訴訟関与者のコミュニケーションの適正化」を、長年研究しています。詳細は後ほどお伝えするとしても、刑事訴訟法という堅苦しいイメージのある法律の研究において、生々しいコミュニケーションをめぐる議論が存在するということ自体、意外に思われるかもしれません。私がずっと刑事訴訟法のことが好きなのは、まさにこのコミュニケーションの奥深さが存在するからなのです。

いや、むしろ、実はかつては刑事訴訟法ないし刑事法に興味があったわけではないというのが正直なところなのです(笑)。本来はコミュニケーションに興味があって、そのうち偶然にも刑事訴訟法の道に深く分け入っていった、と表現したほうが正確でしょう。
読者の皆さんも身に覚えがあると思うのですが、たとえば思春期の頃というのは、他人とのコミュニケーションがうまくいかないことがありますよね。友人と雑談をしていたときに、自分の言葉がちょっと間違って受け止められてしまったり、話題を提供したのにスルーされてしまったり、ということが起こりえる。あるいは保護者と喧嘩していて、自分が絶対に正しいと思っていても、年長者のほうが語彙も豊富であるなどして言い負かされてしまって悔しい、なんてこともあるでしょう。
こうしたコミュニケーションをめぐるズレというものは、大人になっても、日常でいくらでも体験することだと思います。そして私は子どもの頃から、このコミュニケーションの上手くいかなさ、ズレというものにずっと興味があったのでした。
ディスコミュニケーションの果てに、ドラマや事件というものが発生してしまうことがあるわけですが、中学生から高校生にかけての私はそうした世界を、ミステリ小説、特にアガサ・クリスティの作品で読んで理解することにのめりこんでいきました。
ミステリにもさまざまなジャンルがありますが、いわゆる「フーダニット(誰がその犯罪に手を染めたのかという点に焦点を当てて展開する作品)」というものがあります。たとえば何気ない会話のなかに、犯人しか知りえないようなことをサラッと言ってのけている登場人物がいて、犯人がわかってから注意深く読み返すとたしかに書いてある、というような驚きがミステリの愉しみのひとつです。クリスティなんかは、まさにこうしたコミュニケーションの観点をうまく利用している人なのですね。
当時文庫化されていたクリスティ作品をほとんど読み通すうちに、イギリスの刑事法や刑事訴訟法に慣れ親しんでいくようになりました。たとえばスコットランドヤード(ロンドン警視庁)の管轄で、変死体が発見されたとする。こうした場合、クリスティが生きていた当時は、検死をめぐる判断──つまりは自然死などであるか、あるいは誰か犯人による他殺なのかを、本来は素人である陪審員が決めていたのです。クリスティの作品を読んでいて、そうした制度をいちいち調べていくうちに、日本の刑事訴訟法よりもイギリスの刑事訴訟法に詳しくなってしまったぐらいでした。

そうこうしているうちに大学受験が迫り、いろいろと進路を取捨選択し、残ったのが法学でした。もし当時、たとえば会話分析といった社会学的な方法・研究が存在し、人々のディスコミュニケーションについて考えることができると知っていたのなら、そちらに進んでいた可能性もあります。これから大学を受験したり、入学したりする人には申し訳ないところはあるのですが、まあ、人によってはこういう生き方もあるのだと思ってください……(笑)。
さて、大学3年生のときに入った刑事訴訟法のゼミで、人生を変えるような出来事を体験します。それは、かつて昭和49(1974)年に発生し、私がゼミ生だった当時まだ無罪か有罪か確定していなかった「甲山事件」を検討する、という機会でした。知的障害者施設で園児2名が死亡し、施設職員が殺人容疑で逮捕・起訴された事件です。
公判の焦点のひとつは、遺体が発見された浄化槽を閉じていた、重いマンホールの蓋です。園児のひとりが、自分たちが遊んでいたときにマンホールの蓋を開閉したと証言しました。いわば、これは事故だということを意味する証言ですね。
昭和60年の一審は無罪判決が出たのですが、検察が控訴し、高裁では無罪判決を棄却し、地裁へ差し戻し。被告は上告したのですが、平成4(1992)年に最高裁がこの上告を棄却し、地裁への差し戻しが確定した──というタイミングで、私たち学生はゼミでこの事件を検討することになりました。
そのときに、刑事手続をめぐる、非常に大きなディスコミュニケーションを感じ取りました。私にとって一審の判決は説得力をもつものだったのですが、その後の二審は、一審で審理が尽くされていないとしている。しかし、それぞれの裁判官が予断や偏見にまみれているわけではないのです。一方で、市民やメディアは捜査や裁判をめぐって誰かを悪者にするようなバッシングを続ける……。
結論から申し上げれば、この事件は平成11年に無罪が確定するのですが、被告人にとっては四半世紀の時間が流れてしまったのですが、ここに明確な悪者はいない。問題は、こうした訴訟関与者たちのコミュニケーションが上手くいかない“構造”にあるのではないか? このような疑問を起点に進めていった研究について、インタビュー後編ではお話ししようと思います。
後編は「冤罪を生まないための司法の対話 中川教授が語る課題と未来」>>
| 1 | 2 |