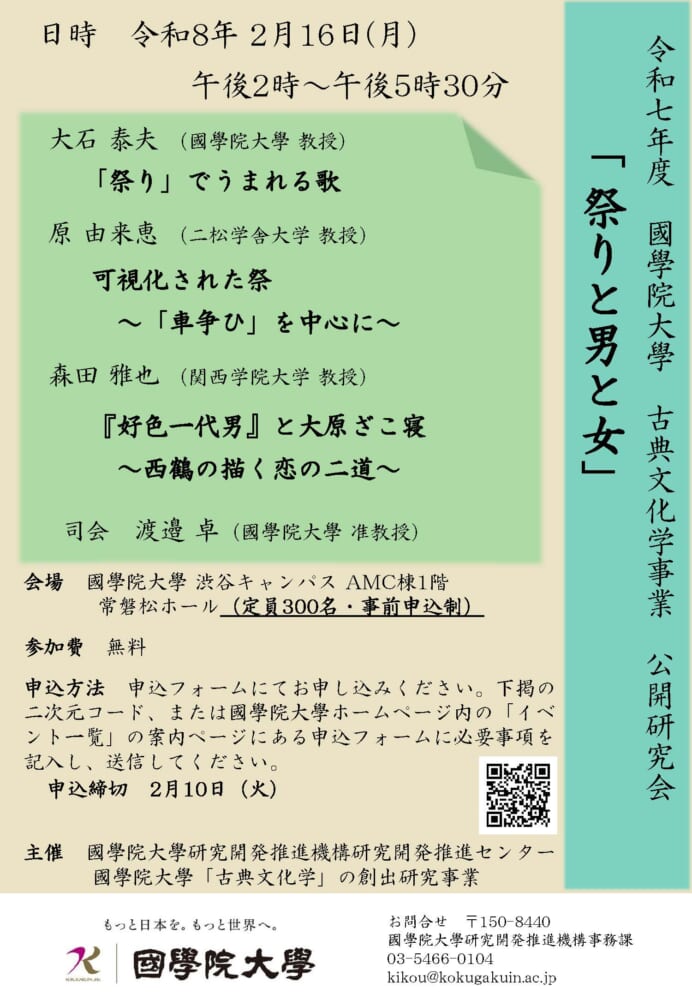身ひとつで飛び込んだ、神宮の世界。そこには、人生を賭けて、そして悠久の歴史を背負いながら祭儀に奉仕している“生粋の神職”たちがいた。そう、山口祐樹・神道文化学部助教は熱を込めて語る。
神職として奉職するに至る、大学院までの日々について語ったインタビュー前編を経て、この後編では、伊勢の神宮での貴重な経験について話してもらった。そこで見聞きし、学んだものがあるからこそ、いま、学生たちに伝えられることがあるはず──“現場肌の教員”を自認する山口助教は、そう信じながら、未来を担う若人の前に今日も立つ。
大学院を修了した私は、神職として伊勢の神宮に奉職し、同時に教学課研究員も拝命したことで、それまでに学んできたことも活かしつつ研究活動にも取り組みながら、幅を広げていけるのではないかと考えていました。
偶然のタイミングではあったのですが、私が神宮にて御奉仕するようになった平成17(2005)年というのは、そこから9年かけて行われていく第62回式年遷宮のはじまりの年でありました。
20年に一度行われる、式年遷宮という歴史の蓄積そのもののような祭儀を、その最初から経験することができる。新たに神職に就くものとして、これ以上の幸運はないといっていいくらいの巡り合わせでした。
とはいえ、インタビューの前編でお伝えした通り、神職として奉仕する道を選ぶまでに、かなり右往左往してもおりました。そんな私が伊勢の神宮で目の当たりにしたのが、文字通りの“生粋の神職”の方々だったのです。
大神様の祭儀に奉仕するということに人生を賭している神職の先輩たちが、右を見ても左を見ても、そこら中、本当にたくさんおられる。それが、神宮という環境でした。
そしてそこには、大学院で学んだ後に奉職された先輩神職も多くいらっしゃり、それこそ私が籍を置いた教学課や、神宮に伝えられた古文書などを保管する神宮文庫で、御遷宮や日々の奉仕の糧とするためにしっかりとご自身の研究も続けておられました。
一命を賭すようにして奉仕しておられる“生粋の神職”の方々がいて、そのなかでも研究を続けているという方々がいた。つまりは、これから私自身が目指すべきモデルとでもいうような先輩たちが、目の前にいるという大変刺激的な状況に身を置くことになったということを意味しました。これもまた、本当にありがたいことでしたし、ここではじめて神明奉仕と研究とが一本の糸で繋がったように感じました。

新米神職として神宮のさまざまな祭儀に奉仕する生活というのは、決して楽なものではありませんでした。たとえば、「三節祭」とも呼ばれる、6月、12月の「月次祭(つきなみさい)」や、10月の「神嘗祭(かんなめさい)」は、神宮にとって非常に重要な祭儀です。特に深夜に執り行われる宵暁の御饌祭は、浄闇の中、参拝者が一切いないところで、大神様と奉仕する神職だけの、極めて特殊な空間での祭儀です。
奉職して2か月ほど、私は神職として最初に就く職階である「出仕」として初めて月次祭に奉仕しておりました。薦(こも)という敷物の位置ひとつをとっても、非常に細かく定められており、その他にも覚えなければならないことばかりで本当に大変でした。しかも、神宮の祭儀は外で行われますから、雨が降ってきたときには雨天時のために定められた対応が求められ、雨がやんだらやんだで、即座に復旧しなければならず、天候が目まぐるしく変わる状況の中で十分な奉仕ができませんでした。
後年、伊勢の風にも慣れた頃、親しくさせていただいていた先輩に冗談まじりで、あの時の状況は奉職2か月目の新米に判断させるには、あまりにも荷が重かったのではありませんか、といったことを訊ねたことがありました。先輩は笑いながら、そうかもしれないが、あれで神職としての覚悟が決まっただろう、といったことをおっしゃっていました。
祭儀に奉仕するということは、雨が降ろうが風が吹こうが、ときに人がひとり欠けようが、いつ何時、どんな不測の事態があろうとも、目の前の状況に臨機応変に対応しながら、祭儀の次第を滞りなく進めることこそが肝要である。大神様の前で決して滞りや礼を失することがあってはならない、その為に万全の準備をしなければならないし学び続けなければならないということなのです。
そして先輩方は、悠久の歴史の中で連綿と紡がれてきたこうした祭儀に奉仕することに、人生を賭している方々ばかりでした。
私は伊勢神宮に計10年間──うち3年は宮内庁掌典職に出向させていただきましたから、実質的には7年間、伊勢の神職として奉仕する日々をおくらせていただきました。そのときに周囲にいた方々は、祭儀を前に自らの心身を徹底的に研ぎ澄ませ、先人らの足跡を貪欲に学び、一切の妥協なく大神様に奉仕している“生粋の神職”の皆さんだったのです。

もちろん、こうしたありようだけが神職のすべてだとは申しません。それぞれの地域のなかに有機的に根をおろし、周囲の人々と密に関わりながら神様とお参りにこられた方々のご縁をつないでいく、そのような神職の存在も、とても重要なものです。私自身、現在は妻の実家である都内の神社にて奉仕しておりますし、さまざまな神社や神職のありようのことも、もちろん踏まえたうえでお話ししている次第です。
だからこそ、心も体も無駄なものを徹底的に削ぎ落としながら、圧倒されるような歴史を背負いつつ目の前の祭儀に一心に奉仕している、あの神宮の神職たちの姿は、常に頭の片隅に置いておく必要があるのではないかとも思うのです。私自身、大学で教壇に立つようになったのも、そうした経験をした人間だからこそ学生たちに伝えられることがあるのではないか、それこそが貴方の役目ではないかと、恩師の岡田莊司先生(本学名誉教授)をはじめお世話になった方々からのお声を頂戴したからでした。
いま、実際の奉仕経験をもとに学生の皆さんと相対しているなかで、心と体のみならず、やはり知識もきちんと伝えなければならないと強く感じています。祭儀のなかで頭をさげる作法ひとつとっても、それは歴史のなかで積み上げられてきた、きちんとした背景のある所作であるわけです。
現在私は、古代の神宮において、朝廷から派遣された大神宮司や、伊勢の神職層である禰宜、大内人といった人々が、どのように祭儀に奉仕していたのかということについて研究論文を書き継いでいっています。それもまた、長い歴史の中で数多の神職らがどのように感じ、考え、奉仕してきたのかということを、神職を志す学生たちにも伝えていければと思うからでもあります。
歴史を知っていれば、迷わない。神明奉仕の経験を重ねてきた教員として、そして歴史を遡りながら伝えていく立場の人間として、これからも神職を志す学生たちの背中を押していければと考えています。
<<前編は「学びと奉仕の橋を渡す 伊勢神宮で得た教訓と学生への伝承」
| 1 | 2 |
山口 祐樹
論文
中世移行期神宮祭祀の基礎的研究『皇大神宮年中行事』にみえる祭儀次第の検討ー正宮への参入・退出経路を中心にー(2025/02/15)
古代伊勢神宮における祭祀所役について ー禰宜職の増員と所役の変化ー(2022/12/15)