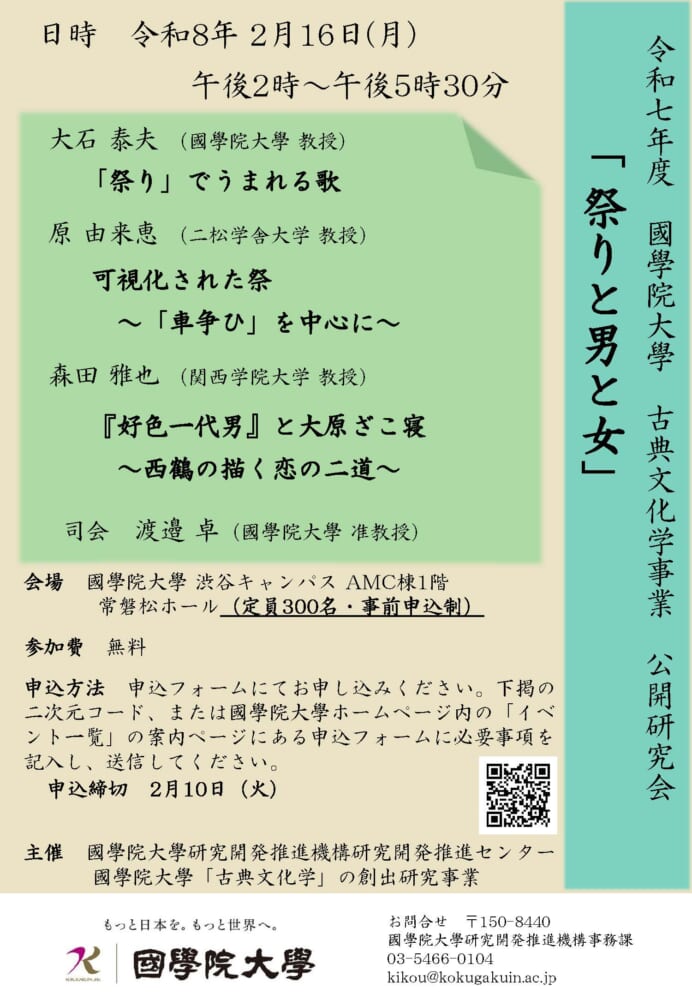神職として奉職する人間だからこそ、教えられることがある──かつて伊勢の神宮で祭儀に奉仕する日々をおくり、現在は東京都内の神社で奉仕する山口祐樹・神道文化学部助教は、そう信じながら学生たちとの日々をおくっている。
しかし、はじめから思いが定まっていたわけではない。かつて、神社や祭礼に興味を抱きながらも、なかなか進むべき道が見えなかった頃があるからこそ、現在にたどり着いている。迷いが感じられないほどにスッと通った、その真っ直ぐな背筋を支えているのは、迷いを重ねた日々なのだ。インタビューの前後編で、神職として学生を教える、その熱意の所以を訊ねた。
私は現在の自分のことを、純粋な研究者というよりは、いわゆる実務家教員に近い存在だと思っています。たとえば大学院において公認会計士や公務員の方など実務をなされている方が教壇に立ち、それまでの経験やスキルを学生へ教えるといった先生方ですね。
神職においても同様なのではないでしょうか。私自身が神職として奉職してきた、その奉仕経験から得た知見を、将来神職になることを希望する学生たちへと伝えていく……そうした役目をなんとか果たしていきたい、と考えているんです。
こういった思いや姿勢についてご理解いただくためにも、伊勢の神宮で奉職していた時期も含め、これまでの私の歩みのことをすこしお伝えできればと思います。
振り返ってみますと、気づけば少年時代にいつの間にか、神社やそこで行われるお祭り、いわゆる祭礼事に興味を抱くようになっていました。親類が神職ではありましたが、父は一般企業に勤めていましたので、神社や神職のすぐ隣にいるということが日常であったというわけでもなく、本当に自然と、地域の祭礼などを中心として神社を歴史的な観点から──いつ頃から、どのように執り行われてきたのだろうかと考えることに、関心を抱くようになっていたのでした。
そんな日々をおくっていた中学生時代、お世話になった恩師が、偶然にも本学の出身者でした。高校に入ってからも、それこそいまに至るまで親しくさせていただいている方なのですが、進路を考えるようになった頃に「後輩になってみるか」といわれたことが、私の進む道へ大きな影響を与えました。
実をいうと本学の文学部神道学科(現神道文化学部)に入学した折には、神職になるということについて確固たる信念があったわけではありませんでした。その時期は、神社や祭礼を文化的、歴史的に考えるということに、シンプルに興味を抱いていたのだと思います。

ただ、これも正直なことを申し上げれば、学部時代にそこまで学業に注力したということでもありませんでした。神道史を学ぶ研究会には所属していましたが、むしろ学部時代の4年間は神社でのお手伝いや合気道部の活動に力を入れていたと思います。たとえば、渡邉卓先生(研究開発推進機構准教授)はその頃からの先輩でして、あの頃先輩や同級生らと部活動に打ち込んだ日々というのは、いまでも私にとって大切な記憶となっています。その一方で、なかなかしっかりと勉強しきれなかったな、という思いも残りまして、大学院へと進学することにしました。
しかしその後、ストレートに研究職の道を進むことはありませんでした。といいますのも、研究者としてその道を全うするということは本当に大変なことであり、その難しさも大学院での研究を通じて痛感したからです。
あくまできっかけのひとつではあるのですが、こんなエピソードがあります。当時師事していたのは、現在も本学の名誉教授でおられる岡田莊司先生です。あるとき、確か忘年会か何かだったと思うのですが、食事をしながら日頃の疲れを労うような場がもたれました。
会話が進むなかで、私はふとなにげなく、岡田先生にこんな質問をしたのです。「先生は普段から調査や研究などに多くの時間を費やしていらっしゃいますが、気分転換はどのようにされているのですか。他に趣味などをおもちなのですか?」と。
岡田先生は海沿いにお住まいでしたから、私はてっきり、海岸を散歩などしているといったようなお返事があるのかなと思っていました。ところが、先生は笑いながらこうおっしゃったんですね。「趣味かあ…、やはり史料や本を読むことかな」と。
研究の気晴らしに古文書を読む……すごいお話ですよね(笑)。これが一流の研究者というもののレベルなのか、と愕然としました。笑っていらっしゃいましたが、とにかくもう、その研究への姿勢と熱意に衝撃を受けたんです。私なんて、とうてい先生のような研究者にはなれないと強く感じました。

それと前後するように、将来的に神職として奉職するということも、具体的に考えるようになっていました。学部を卒業して以降、周囲の友人や先輩の中にも既に神職として奉仕している人がたくさんいて、顔を合わせた時には色々な話も聞くようにもなっていました。
興味深かったのは、日々熱心にご奉仕されている宮司さんのもとで、友人らが神様と地域の皆さんの間をとりもつ存在としてとても充実した日々を過ごしているという話でした。神道において神職が果たしうる役割というものに、徐々に魅かれていったのですね。
当時は就職氷河期の真っ只中でもありましたから、職に就くということ自体が大変な困難を伴っていた時代です。自分がこれまで学んできた神道文化というものを、仕事に活かすことができる道として、神職として奉職するということが、私のなかで大きなリアリティをもつようになっていきました。
一方で、大学院でもなお学びきれなかったものを細々とでも続けて考えていければ…、とも感じていました。今考えてみれば、この時は神明奉仕と研究活動というものが自分の中ではまだ直接結びついていなかったのでしょうね。そんな折、岡田先生や椙山林継先生(本学名誉教授)にアドバイスをいただき、奉職しながら研究も続けられる環境というものがいくつかあるから、そこで奉仕してみたらどうかとおっしゃっていただきました。本当にありがたいことで、そこから視野が広がり、神宮に奉職しながら、教学課研究員としても研究活動に取り組むことになったのです。
とはいえ、ここまでお読みいただければわかる通り、神職としての確固たる覚悟というようなものが十分でなかったことは確かです。そうした私の精神を鍛え育ててくれた神宮での貴重な経験などについても、インタビューの後編でお話しできればと思います。
後編は「祭儀の重みと奉仕の中で育まれた覚悟」>>
| 1 | 2 |
山口 祐樹
論文
中世移行期神宮祭祀の基礎的研究『皇大神宮年中行事』にみえる祭儀次第の検討ー正宮への参入・退出経路を中心にー(2025/02/15)
古代伊勢神宮における祭祀所役について ー禰宜職の増員と所役の変化ー(2022/12/15)