
日本と韓国の歴史とその認識をめぐっては、激しい議論が繰り広げられてきた。そうしたなかで、日韓両国で共通の歴史認識というものを模索できるのではないかと考えてきた研究者のひとりが、山﨑雅稔・文学部史学科准教授である。
山﨑准教授の専門は、近代や現代の歴史ではなく、日本と韓国の古代史である。日々の研究や実践には、どんな思いが込められているのだろうか。前後編にわたるインタビューで、胸の内を尋ねた。
私が専門としているのは、日本古代史、そして韓国(朝鮮)の古代史です。歴史教育を通した日本と韓国における“歴史対話”にも、20代の頃から取り組んできました。まずは、日韓の歴史教育のことからお話ししてみようと思います。
日本の韓国併合にいたる過程や植民地支配の実態、その記憶と語り、清算のあり方とともに、日韓関係に関する歴史教科書の叙述については、現在でもさまざまな意見があります。そうしたなかで、1970年代から今日にいたるまで、およそ半世紀にわたって、両国の歴史研究者が“対話”のためのテーブルについて、議論を重ねてきたことはあまり知られていません。
私は、1998年以来、東京学芸大学とソウル市立大学校の歴史対話プロジェクトに参加して、両国の歴史学・教育学の研究者や、中学校や高校で生徒に歴史を教えている先生方と一緒に、歴史教科書の叙述の分析、各時代・分野の研究成果と課題の整理を行いつつ、日韓共通の歴史教材づくりを進めてきました。当初は、学術的な交流もまだ少ない時代ですし、両国の歴史に対するアプローチも大きく違っていましたから、激しい議論が交わされることもありましたが、史資料を手がかりにして共通理解を模索していくなかで、歴史認識の共有に近づけるのではないかという思いがありましたし、駆け出しの同世代の研究者と意見を交わすのも刺激的でした。

私たちは10年をかけて、歴史教育研究会(日本)・歴史教科書研究会(韓国)編『日韓歴史共通教材 日韓交流の歴史―先史から現代まで―』を日韓両国で出版しました(同書日本語版 明石書店、2007年)。
この時期には、日韓、日中韓で一緒に歴史を考えようという同じような試みがいくつか行われました。自分の国を中心に一国史的に語られてきた歴史を、国境を越えてアジアのなかで考えて、私たちの財産にしようという動きは、歴史教育にも影響を及ぼします。例えば、2012年度には、韓国の高等学校歴史科目として新しく「東アジア史」という選択科目が誕生しました。私たちの取り組みも教科書に紹介されています。その点では、有意義な取り組みだったと思います。
その後、『調べ・考え・歩く 日韓交流の歴史』(同研究会編、明石書店、2020年)を出版しました。韓国で「東アジア史」の科目設計に関わった研究者や同科目の教科書執筆者にご協力いただきながら、日本の研究者・高校教員とともに行った研究成果の一部です。2022年度から日本の高等学校で授業がはじまった「世界史探究」「日本史探究」を念頭に、教育現場で実際に使うことを前提にしたテキストです。
じつは、2024年度から新たなプロジェクトをスタートさせています。韓国では「東アジア史」の後継科目として、2026年度から「東アジア歴史紀行」が開設されます。語弊があるかもしれませんが、昨今の状況をみると、日本の歴史教育は韓国に遅れを取っているようにも思います。そこで、若い研究者や高校教員を巻き込みながら、韓国にも学んで、歴史学と歴史教育の新たな可能性を探りたいと考えています。
この半世紀のあいだ、多くの研究者が日韓の歴史認識をめぐる葛藤に真摯に向き合い、信頼関係を築いてきました。そうした先達の努力の先に私たちの取り組みがあります。私自身も、日韓の共通教材づくりに関わる機会に恵まれたことで、日本史、韓国史(朝鮮史)という枠組みを越えて、日韓にまたがる研究をはじめることができた、と思います。
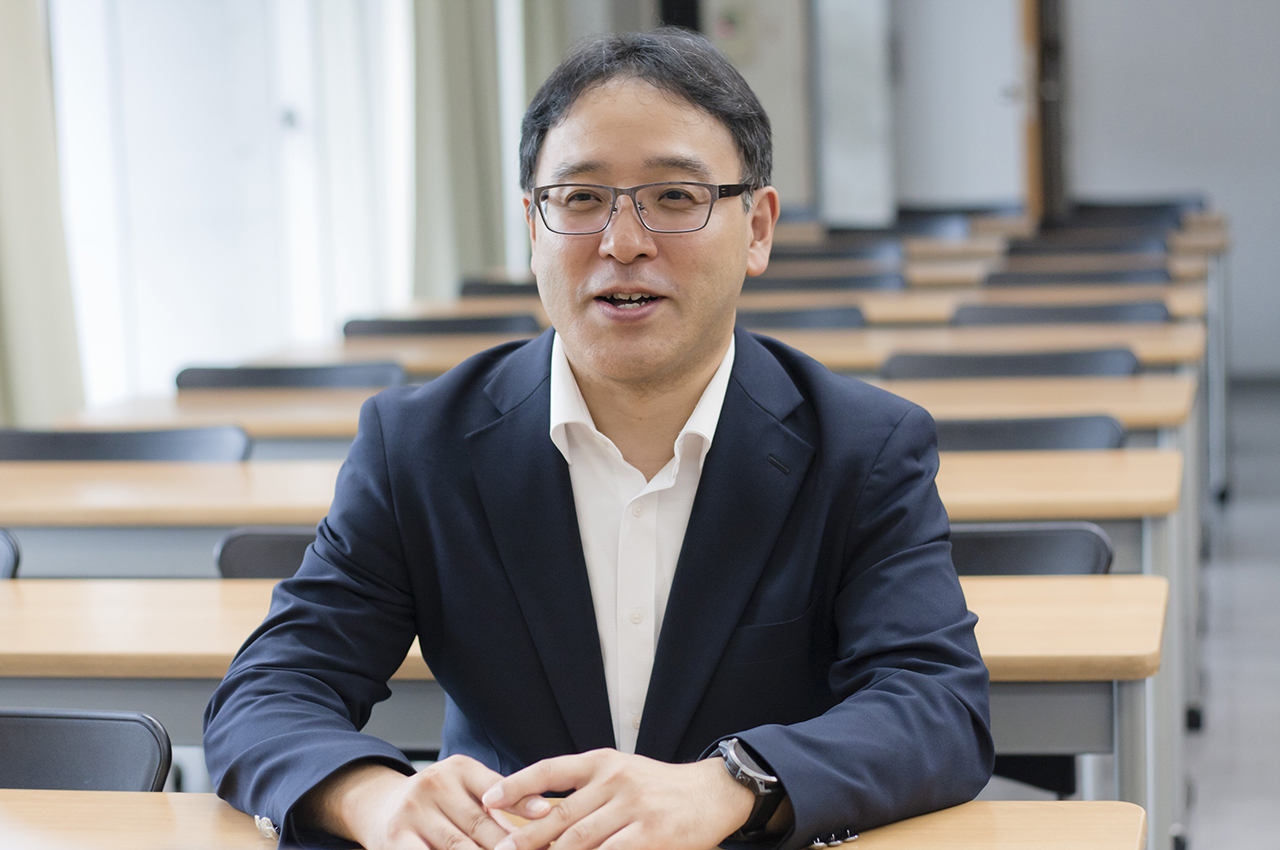
現在、私がおもに扱っているのは4世紀後半から10世紀までの古代史です。日本ではおよそ古墳時代から摂関政治の時期まで、韓国・朝鮮においては高句麗・百済・新羅の三国時代から、高麗が建国された頃までを研究対象としています。「王政復古」をスローガンとした明治政府は、朝鮮との関係を古代に遡らせて理想とします。『古事記』や『日本書紀』には倭(日本)が朝鮮の勢力を服属させ、半島南部を支配していたように書かれていますから、先ほどお話した“歴史対話”においても、古代史の理解は、日韓関係史の根幹に関わる重大な問題をふくんでいました。
しかしながら、最初からいまのような関心を抱いていたわけではありません。歴史は好きなほうでしたが、高校での授業は覚えることばかりで、さほど興味を持てずにいました。ただ、進学した大学は、史学科がないにもかかわらず、歴史学を勉強するための学生主体の自主ゼミが数多く開かれていました。そこでとりあえず、という軽い気持ちで日本古代史のゼミに顔を出すようになったのが、研究の道に進むきっかけになりました。
大学2年生の時には、リバイバルされた日本史研究の名著、石母田正『日本の古代国家』(岩波書店、1971年)に出会いました。苦戦しながらもこの難読書を読み進めていくうちに、古代国家の形成や天皇を中心とした社会構造の歴史に興味を持つようになりました。
3年生の時には、財政史の研究に取り組むつもりでいましたが、卒業論文では9世紀の日本と新羅の関係を研究しました。朝鮮・韓国の歴史に興味を持ったのは、ゼミの先生に誘われて韓国を訪れたのが1つのきっかけです。初めての旅は大学2年の冬でした。ソウルを出て江華島や北朝鮮との国境付近まで行きました。砲弾を運搬する軍事車両が走行していて、検問所でも遠くから銃を向けられるなど、物々しい雰囲気が漂っていました。北朝鮮の核開発疑惑によって、半島情勢が緊迫するなか北朝鮮との国境に向かっていたことを、あとになって知りました。翌年には、解体準備が進んでいた旧朝鮮総督府建物(当時は国立中央博物館)にも足を運びました。
実際に訪れて、その歴史にふれたことで、韓国が身近になったこともありますが、当時から歴史問題を抱えてモヤモヤしていた日韓関係について、歴史学の立場から自分なりにみつめてみたい、韓国・朝鮮に向き合う日本(人)の意識構造について掘り下げて考えてみたいと思うようになったのが、いまにいたる研究のきっかけでもあり、問題関心の根っこにある何かだといえます。
大学院に入ってからは、日本史と韓国史をまたぐような研究を目指すようになります。インタビューの後編では、その流れをもう少しお話ししつつ、具体的な研究内容もご紹介しましょう。
後編は「日本と朝鮮の交流史からみえてくる、古代史の真実」>>
| 1 | 2 |


