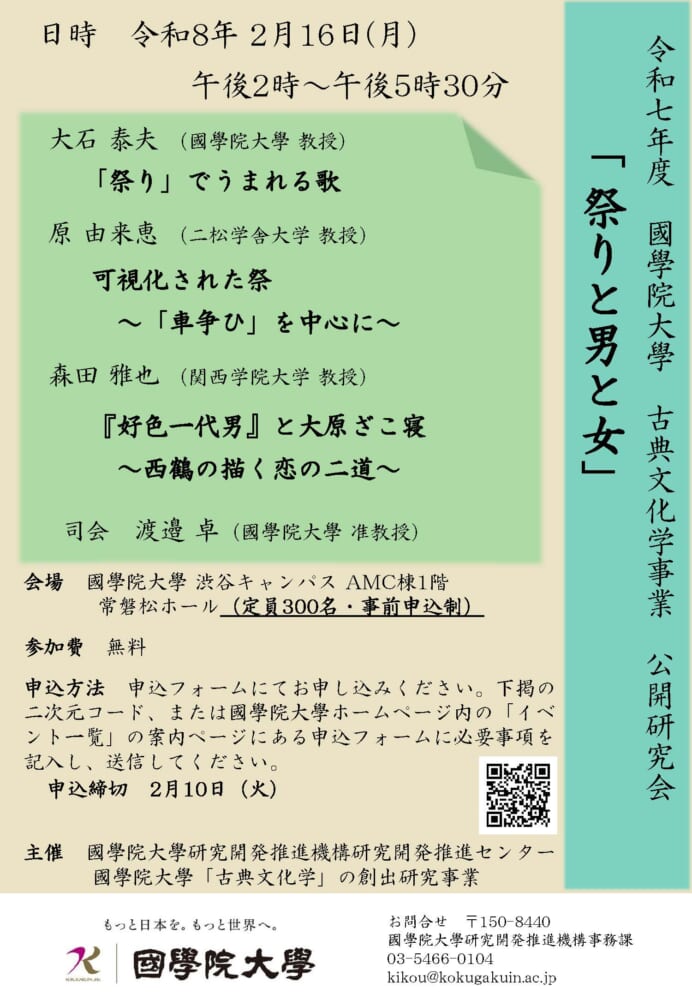近くて遠い? 遠くて近い? そんな親の気持ちや大学生の子どもの気持ちを考えます。
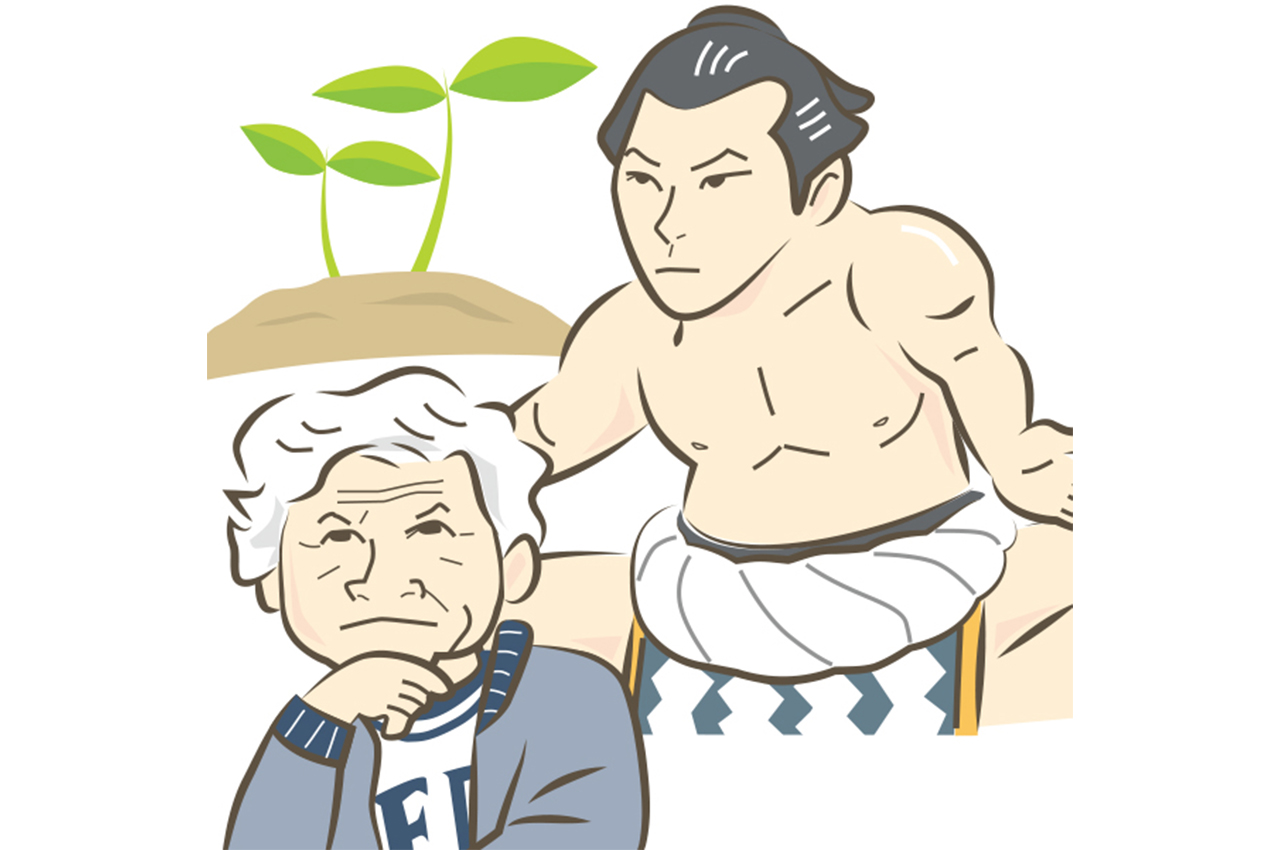
「強いから横綱ではなく、横綱だから強いのです」
「強いから横綱なのではなく、横綱だから強いのです」。これが、ウルフと称された小さな大横綱千代の富士のNHK記者インタビューの「どうして横綱は強いのですか?」への返答でした。
記者は意味が呑み込めず、「えっ、強いから横綱なのでしょう」。それに対し千代の富士は同じ言葉を繰り返し、ただ満面の笑みでした。
「横綱だからこそ、横綱という持ち場=ポジションを汚さぬよう(頑張って)強くなっているのだ」。そのテレビ画面を見たとき、大横綱のオーラを感じたものでした。
「場を得て、子どもは光る」
今年の出雲駅伝、全日本大学駅伝での平林清澄選手の快走は記憶に新しいところです。前田康弘・國學院大學陸上競技部監督に同じ質問をすれば、おそらく次のように回答するでしょう。
「速いからエースなのではなく、エースだから速いのです」、と。総じて言えば、「場を得て、子どもは光る」なのです。
昨年度より、國學院大學の「本(モト)ヲ立ツル」人育てとは、をテーマに挙げ、前回は「期待される厳しさを」でした。今回は、その方策の一つについてです。
もう一つ、エピソードを取り上げましょう。
蔦(つた)野球「全員野球」「ニコニコ野球」の人育て
徳島県立池田高校は、昭和49(1974)年の甲子園春の選抜野球で準優勝でしたが、優勝校報徳学園高校よりも「全員野球」「さわやかイレブン」「ニコニコ野球」などと称され、池田高校蔦文也監督の野球はその年、紙面をにぎわせました。巨人軍長嶋茂雄監督にして、「高校野球の原点」とまで言わしめましたが、その根拠も、「場を得て、子どもは光る」でした。
「勝つ野球の監督である前に、自分は教育者である」と自負した蔦監督の指導方針が、「さわやかイレブン」と「全員交換ポジション制」でした。
「さやかやイレブン」
「さわやかイレブン」について言えば、14人のベンチ入り選手枠(当時)に対し、彼は11人で臨みました。
それは、一人でも手を抜けば試合が成立しない人数に絞り込み、「自分は掛け替えのない大切な存在なのだ」という意識をつくること、すなわち筆者のいう「尊在感」づくりでした。
蔦文也監督に依れば、昭和49(1974)年当時、子どもたちがそれ以前と大きく変わったと言う。「嘗ては、子どもたちは、弾けるような元気があり、生徒指導はある意味、このエネルギーをいかに抑えるかであった。野球の試合で言えば以前は、俺を俺をと、目の前をうろうろして監督にアピールしていたものだったが、今は(当時は)、調子は大丈夫かと4番バッターの顔色をうかがうようになった」、と。
スポーツを指導している者は、こうした子どもたちの変化は、如実にわかるのです。
「全員交換ポジション制」
後者の「全員交換ポジション制」は、他のポジションも全員に経験させることで、「自分は大切な存在だが、他者もまた大切な存在である」ことを意識づけることでした。
「一人一人を大切にと先生方は言うけれど、それにどう具体的に取り組んでいるのか」。そう言い放った時の蔦監督の教師の顔が忘れられません。
今日の学校現場にはびこる「いじめ」の社会的背景も、学術的には「自尊感情の喪失」と「他者理解の喪失」、と言われています。これを「蔦野球」に当てはめれば、前者は「さわやかイレブン」、後者は「全員交換ポジション制」に対応しています。
勝つ野球監督として講話招聘に来た筆者に対して、「私は、勝つ野球の監督の前に教師である」と豪語した、蔦文也先生の面目躍如と言ったところでした。
今回も、家庭教育(庭の訓(ヲシヘ))の大切さを詠った「明治天皇御製」を掲載しましょう。
「たらちねの親の心はたれもみな 年ふるまゝに思ひ知るらむ」(親の愛情というものは、誰もが年を取るにつれて次第に思い知るものだよ)
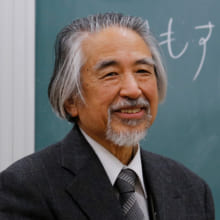 |
新富 康央(しんとみ やすひさ) 國學院大學名誉教授/法人参与・法人特別参事 |
学報掲載コラム「おやごころ このおもい」第24回