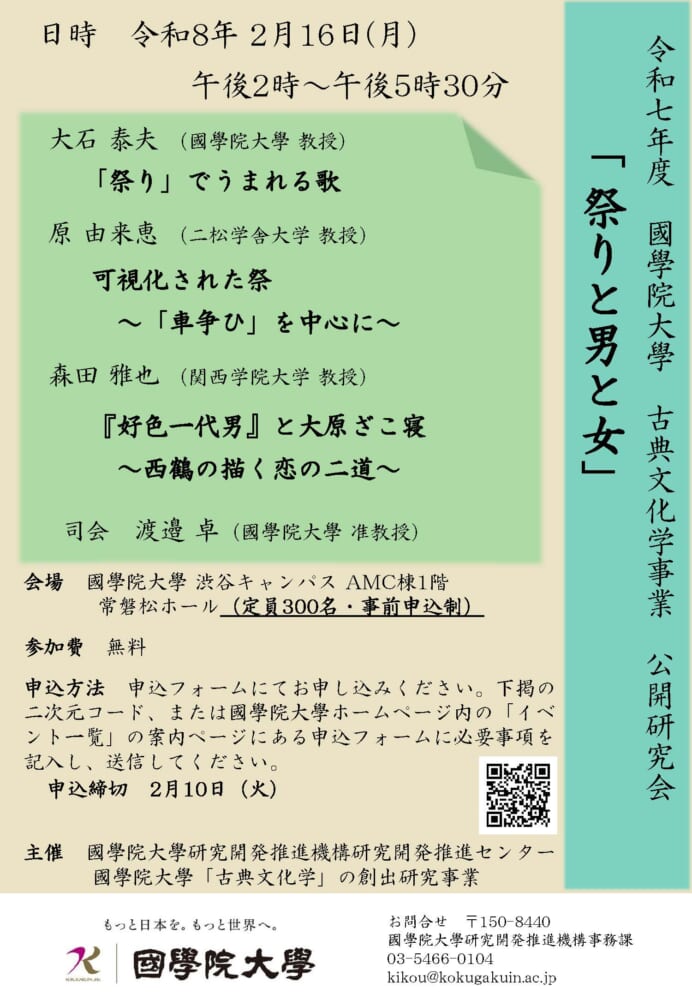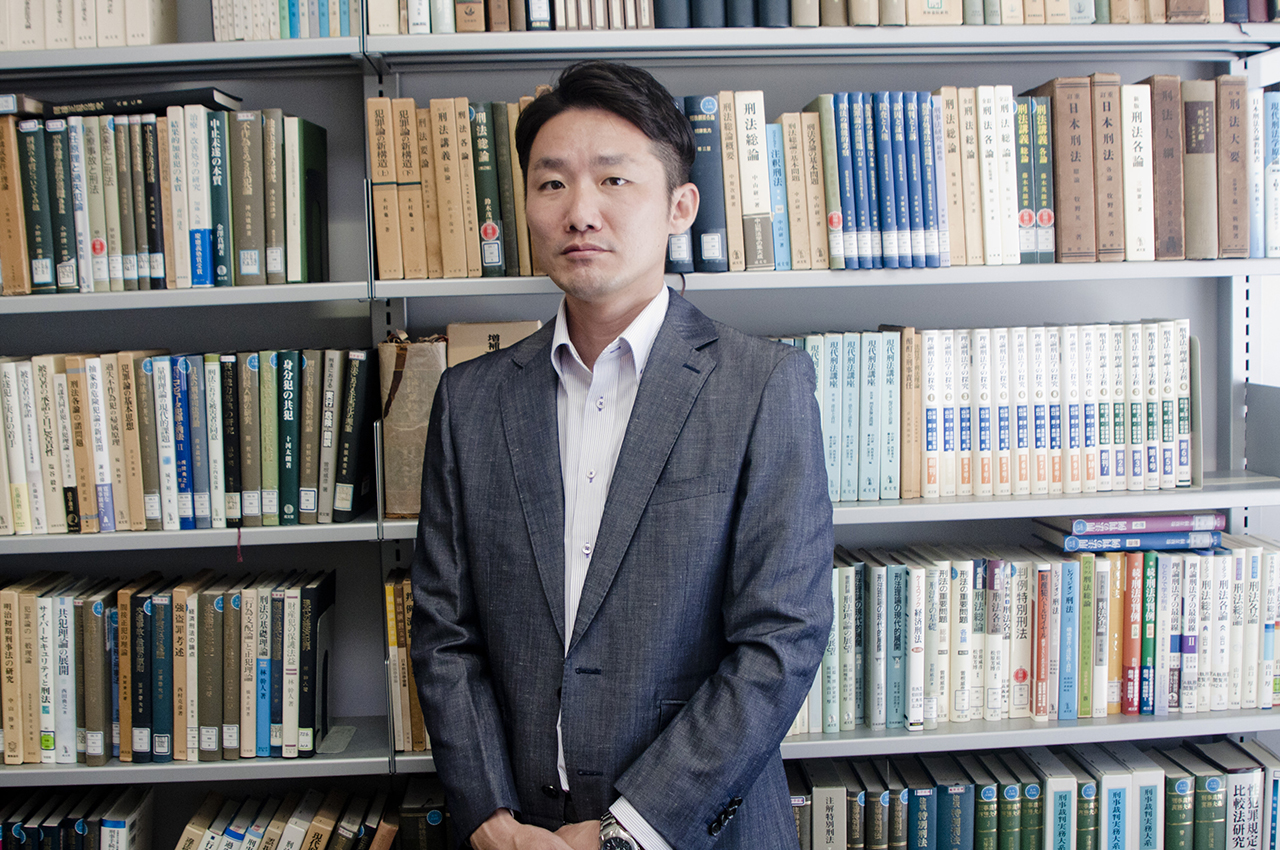
複雑な議論を展開する法学の研究者。そのキャリアのスタート、法学の世界へと足を踏み入れることになるきっかけは、意外にもトレンディドラマへの憧れだったという。紆余曲折を経ながらも、やがてドイツ法学界の刺激的な学説をもとに、オルタナティブな議論を展開するように──。
山下裕樹・法学部准教授へのインタビュー前後編。「不作為犯」と呼ばれる問題領域はたしかに難しく、インタビュー冒頭でも山下准教授は「あんな大変な論文を読んできたんですか……」と零していたが、しかし思い切って飛び込んでしまえば、とても面白いテーマだということがわかる。刑法を研究することの醍醐味を、一緒に味わってみてほしい。
刑法には「不作為犯」という問題領域があります。もしかしたら読者の方のなかには、犯罪は「~する」というかたちで実現されるものだというイメージをお持ちの方もいるかもしれません。たしかに刑法においては、「物を盗む」「人を欺く」など、「~する」ということ=「作為」というかたちで実現された、作為犯という犯罪が基本です。しかし一方で、「~しない」ということ=「不作為」というかたちで実現された、不作為犯と呼ばれる犯罪もあるのです。

何もしていないのに犯罪になるというと、不思議なことのように思われるかもしれません。しかし、何もしていなくても、ときには共犯になりえさえします。たとえばですが、薬物売買をおこなっている人間が横にいるのに止めなかったというとき、場合によってはその売買を心理的に促進していたと見なして罪に問う、というようなことがありうるのですね。後にお話しすることになる遺棄罪といった犯罪も含めて、不作為犯という領域は、とても広いものなんです。
刑法に総論と各論があるということは、聞いたことがある方も多いと思います。犯罪や刑罰をめぐる基礎的な議論や、犯罪が成立する一般的な条件などを扱うのが総論であり、個々の刑罰にかんする法規を解釈していくのが各論だとおおよそ整理できるわけですが、不作為犯という問題領域はこのうち総論に含まれます。それが、たとえば遺棄罪にかんする解釈となると、各論の領域にもまたがっていくということになります。
私が不作為犯という問題領域に関心をもつようになったのは、大学の学部生の頃でした。実はもっと時間を遡ると、大学入学時は法曹志望でした。きっかけはテレビドラマだったのです。木村拓哉さんが検察官役で主演していた『HERO』(第1期は平成13(2001)年)や、ミムラさんやオダギリジョーさんが司法修習生たちを演じていた『ビギナー』(平成15年)を見て、「かっこいいなあ」と憧れました(笑)。検察官を目指して、ロースクールに進学するつもりだったんです。
ただ実際に裁判の傍聴に出かけたところ、検察官の方々のお仕事が、自分で勝手にイメージしていた検察官像とは異なることにも気づいていき……刑法の勉強自体は好きでしたので、指導教授の先生とも相談し、大学院に進むことを決めました。並行して、卒業論文で取り組むテーマとして絞り込んでいったのが不作為犯だったのですが、卒論はまったく満足いく結果とならず、院でも引き続き不作為犯に取り組み続けることになります。

そんななか、指導教授に勧めていただいたのが、保護責任者というトピックでした。刑法218条には保護責任者遺棄罪が定められており、ここを深掘りしていけば、総論から各論までを含めた、広がりのある議論を展開できるのではないか、ということでした。各論であるはずの遺棄罪の話が、どのように総論の領域にも及んでいくのか、すこしご説明したいと思います。
遺棄罪の規定は非常に複雑で、議論が尽きないところでもあります。それはなぜかといえば、条文自体が非常に込み入っているからなのですね。単純遺棄罪を規定する刑法第217条、そして保護責任者遺棄罪を規定する第218条を見てみましょう。
第217条 老年、幼年、身体障害又は疾病のために扶助を必要とする者を遺棄した者は、一年以下の懲役に処する。
第218条 老年者、幼年者、身体障害者又は病者を保護する責任のある者がこれらの者を遺棄し、又はその生存に必要な保護をしなかったときは、三月以上五年以下の懲役に処する。
第217条では、誰が犯罪を為すことができるのかという主体が限定されていません。処罰される行為は、「遺棄する」ということのみです。一方で第218条では、保護責任者という主体の限定がある。さらに「遺棄する」だけではなく、「生存に必要な保護をしなかった」ことも処罰されています。さらに刑罰にかんしては、保護責任者による犯罪のほうが重い。このふたつの条文の関係性を、どのように説明したらよいのかという各論的な論点だけでも、非常に議論が複雑になるであろうことはご想像いただけるかと思います。
他方で、このような不作為犯一般にかんする総論の論点も存在します。日本の通説として、不作為犯を実現できる人は、作為義務を負う(あるいは保障人的地位にある)人だけであるというものがあります。人を殺す、暴行するといった作為の犯罪は誰でも為しうるわけですが、作為義務を負う者しか不作為犯の主体にはなれない、という考え方です。そこで、「生存に必要な保護をしなかった」という不作為を処罰する第218条の主体である保護責任者は、不作為犯の主体である作為義務者と同じだと考えていいのか、それともそれとは異なる特別な立場の人間だと見るべきなのか、という議論が発生するわけですね。
第217条と第218条をめぐる刑法各論の問題領域が、総論の議論と重なっていく。院生から現在に至るまで、こうした広がりをうまく捉えられないかと研究を進めています。インタビューの後編では、近年お誘いいただいて参加している自動運転自動車にかんする研究、そして人のつながりがもたらしてくれる議論の人間臭さや生々しさについて、よりお伝えできたらと思います。
後編は「法学者の刺激的な日常ドイツ法学から学ぶ革新的な議論」>>
| 1 | 2 |
山下 裕樹
研究分野
刑法
論文
不作為による名誉毀損・侮辱罪に関する予備的考察(2025/12/31)
【判例研究】邸宅侵入、現住建造物等放火被告事件1件を含む複数の被告事件が併合審理された裁判員裁判において、建造物等以外放火被告事件では公共の危険の発生の有無が争われたのに対し、犯行現場の客観的状況や被告人の行為態様から公共の危険の発生が推認される上、燃焼実験結果に基づいて複数の延焼可能性が存在すると指摘する専門家証言は客観的な裏付けを伴う合理的な判断であるとして公共の危険の発生を認めた第一審の認定判断が、控訴審において是認された事例(2024/02/20)