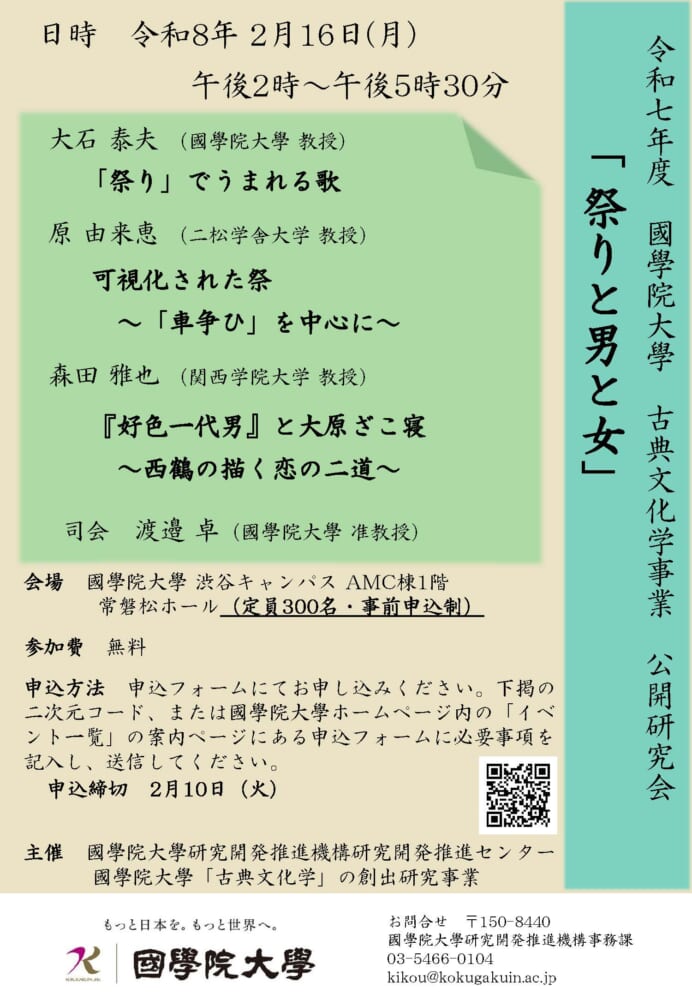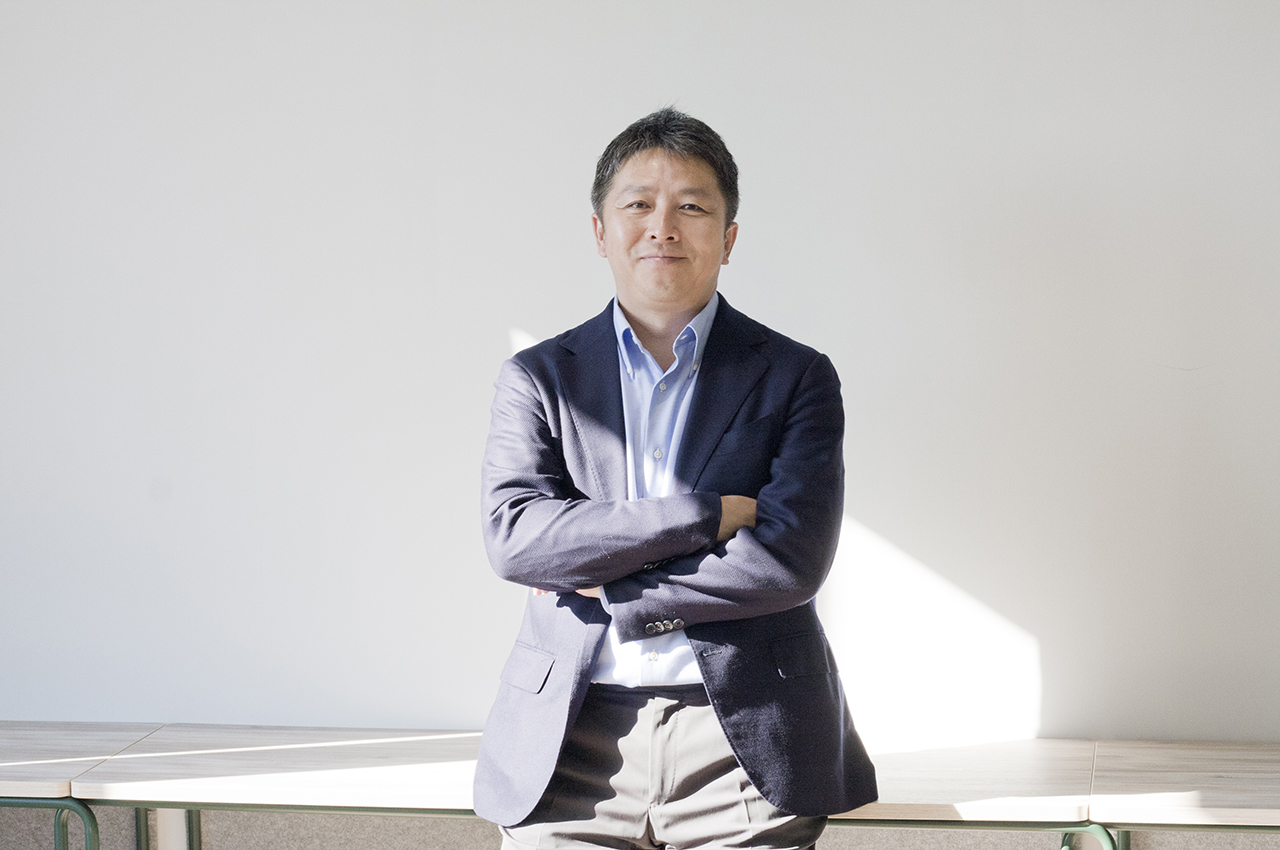
地域が、専門家の理論や理想に基づいて設計されることは果たして正しいのだろうか。清野隆・観光まちづくり学部准教授は、あるとき、そう感じたという。多少不便な環境であっても、目の前にある資源やネットワークを見つめ、自らの手を動かして暮らしを成り立たせていくことがコミュニティのあるべき姿であり、人間にとって幸福な生活なのではないか、と。人々の無数の実践のもとに生まれる地域のダイナミズムが、ここにはある。
コミュニティ・デザインを専門とする清野准教授へのインタビュー前後編。まず尋ねるのは、現在の視座を獲得するに至る、自身の歩み。山梨県の緑豊かな地域で生まれ育ちながらも東京に憧れていた准教授が、そうした地域の豊かさに気づくようになるまでには、さまざまな変遷があったという。
コミュニティ・デザインを主な研究テーマに掲げていて、そのなかでも特に興味を抱いているのが、歴史をもつ地域のデザインです。
たとえば、私が長年かかわらせていただいている場所のひとつが、新潟県長岡市山古志地域です。棚田や、錦鯉を養殖するための棚池が斜面地に広がっていて、もとから豊かな自然はもちろん、そのなかで人々が営んできた生活、築いてきた歴史や文化そのものが風景となっています。
時代やライフスタイルの移り変わりのなかで、こうした地域の姿はどうしても変わっていきがちなものではありますし、変化すべき点はする必要があるかもしれません。しかしやはり、コミュニティの根幹にある歴史性を大切にしていくことは、地域の未来へとつながっていくものです。どうすれば、受け継がれてきたものを大切にしつつ、住民の方々が現在から未来へと暮らしを紡いでいけるのか、微力ながらお手伝いしながら研究を進めています。

とはいえ私自身、田舎で育ったにもかかわらず、その地域の価値というものに長らく気づいていませんでした。生まれ育ったのは、現在の山梨県南アルプス市。果樹園が広がる風景が、幼い頃から当たり前のものとして周囲にありました。
しかし、特に思春期においては、東京をはじめとした都会への憧れもあり、自分が暮らす地域のことをまるで時代遅れであるかのように感じていたことは事実です。やがて大学入学に伴って上京し、東京のさまざまな側面を目の当たりにするにつれ、自分が生まれ育った地域にしかない歴史的な豊かさ、一度失われてしまっては取り戻せない環境の価値のようなものを、再発見していくようになりました。
東京にいると、いろいろな物事が自動的に動いていき、そのシステムに自身も乗っかっていきながら生きている、という感覚を抱くことはないでしょうか。その便利さ、快適さには目を見張るものがある一方で、豊かな日常がときに経験の貧しさへとつながる一面があることは、否定できません。
地方、特に不便な田舎に暮らすということは、さまざまな手間がかかるということを意味します。ただ、その面倒さが、ポジティブなものに転換することがある。地域で生きて来た人々の歴史に基づきながら、自分の手を動かして生活を成り立たせていくこと、そうした時間を過ごすということによって、満たされる感覚があるわけです。

大学に進学したときも、当初は都市計画について学びたいと思っていました。『シムシティ』という、一世を風靡した都市開発シミュレーションゲームをご記憶の方は多いかと存じます。住宅や商業施設などのさまざまな施設や都市インフラなどの機能をつくると街がオートで動いていくシステムになっていて、街をどう作るかによってどう発展していくのかが決まっていくという、まさに都市開発的な観点に基づいたゲームです。
そうしたただ一つの最適解を求め導く世界観にかつては憧れを抱いていましたし、実際に面白さもありました。ただ、そうした巨視的な観点からのみで人間の生活というものは本当に豊かになるのか、都市に暮らすということは単に画一的なライフスタイルに則っているだけなのではないかなどと、さまざまに疑問を抱くようになったのも事実だったのです。当時はまだ頭でっかちではありましたが、人が住む地域における社会問題といったものに、どうしたら向き合えるだろうかといったことにも考えが向くようになりました。地域の歴史とコミュニティ・デザイン、といったトピックへ関心が徐々に向いていくようになったのには、こうした背景があります。

決定的な契機は、20年ほど前にイタリアに留学したことでした。特に感嘆したのは、ウルビーノ歴史地区です。自分が訪れたのは平成10(1998)年に世界遺産に登録されてから5年ほどが経った時期だったのですが、都市部に残っている文化的な遺産と、住民たちの暮らしがバランスよく両立していることに驚いたのです。それは昭和39(1964)年に都市基本計画を作成して以来、歴史的な景観と住民たちの生活を上手に結びつける、いわばコミュニティ・デザイン的な観点を先取りするような取り組みが長らく行われてきた結果でもありました。
と同時に、さまざまな課題も見えてくる。たとえば平成11年から平成13 年にかけて、Data という歴史的建造物の再生プロジェクトをめぐって景観論争が起きました。Dataの歴史的文脈は保持しつつ再生させようという、建築家や当局が考案し、公共事業としての意思決定プロセスの透明性もきちんと確保されていたプロジェクトなのですが、いざ走り出すと美術界などから批判の声が上がりました。歴史的な文脈のデザインとコミュニティ・デザインという観点において、さまざまな意味で参考になる出来事だったと思います。
さて、イタリアから帰国した私は、博士論文を書き終えて、これからどうするか考えていたのですが、そんな折に人を介して偶然出会ったのが、新潟県長岡市山古志地域でした。幾度も足を運びながら見えてきたことについて、インタビューの後編でご紹介したいと思います。
後編は「山古志の挑戦と展望から考える地域の持続可能な暮らし」>>
| 1 | 2 |
清野 隆
論文
都市計画家G. De Carloによるテリトーリオ論に関する基礎的考察-論考「Reading and Design of the Territory」の要約と考察(2025/08/01)
山古志村 限界を越えて、つながる(2018/04/)