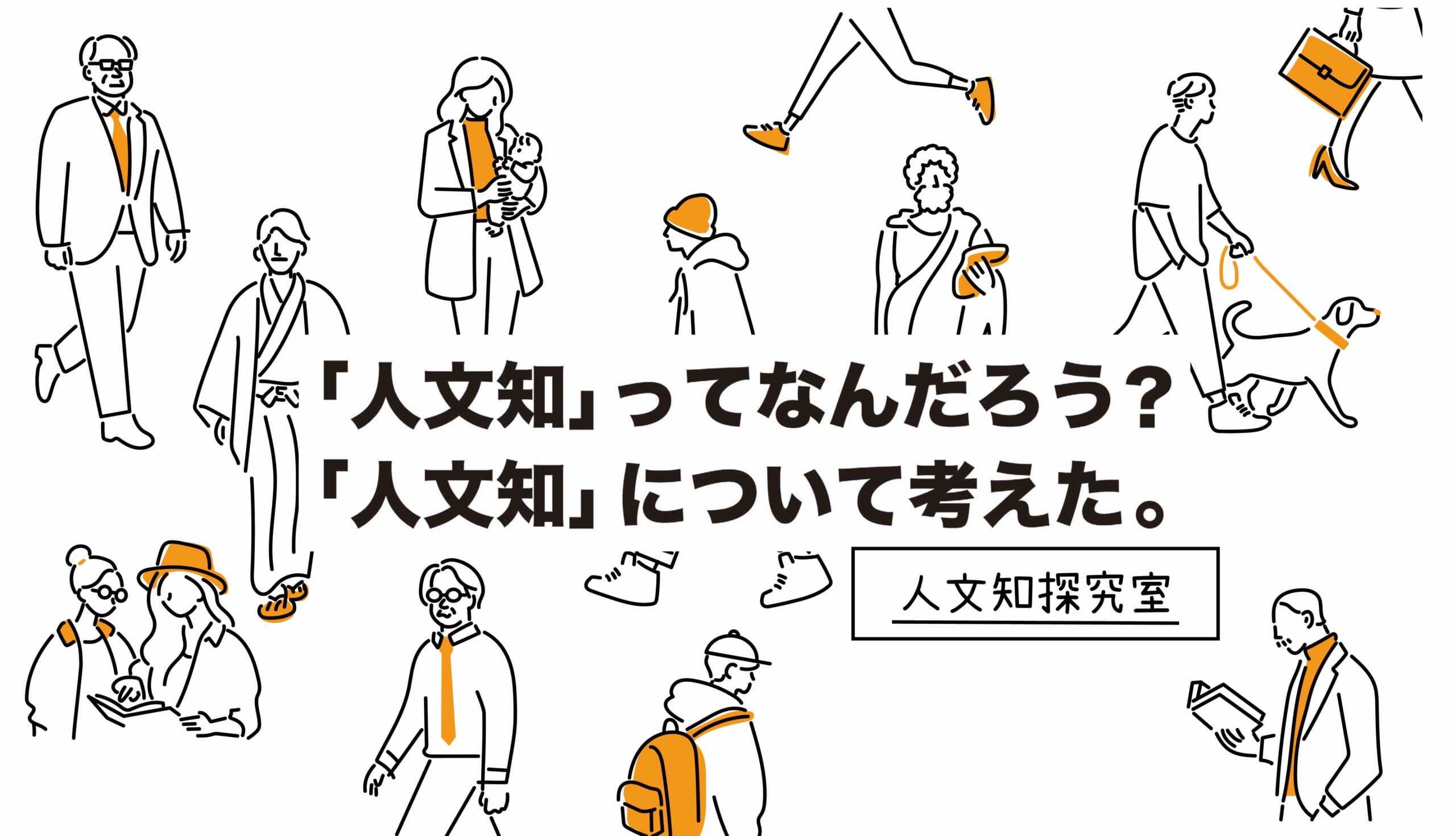いま、経営者やビジネスパーソンなど人々のあいだで、熱視線を浴びつつある「人文知」。答えなき現代の指標となりうるかもしれないその知のありようは、しかしいまだ言語化されきっていないようにも見える。いまの世の中で改めて考えるべき「人文知とは何か」という問い──その難問に対し、國學院に息づく人文知をさぐるために人文知探究室が立ち上がった。日本固有の文化を探究する国学や神道・伝統文化、文学・史学と様々な学問領域から人文知に長年向き合い、人文社会科学系のみで構成される大学として日本有数の規模を誇る國學院大學にて、研究者との対話を通して人文知を探究する。教員の多種多様な専門知を参照し、共に悩みながら、「人文知」の現在を照らし出すことで、AI時代にこそ不可欠となる人文知を探る。
初回に登場するのは、竹内正彦・文学部日本文学科教授。『源氏物語』を中心に中古文学を専門とする竹内教授は、文学という視座から古今の知の変遷を見つめてきたひとりだ。揺れ動く私たちの社会のなかで、人文知には何が可能なのだろうか。人文知探究室のメンバーと教員が膝をつき合わせての、道なき道をゆく質疑応答はやがて、「データを実感できる想像力」というキーワードへ辿り着く。
──「人文知とは何か」という、一概には答えていただきづらいであろうテーマを掲げた探究の、最初の対話となります。
第一回目ですか、緊張しますね……(笑)。そして本当に難しいテーマですね。どのようにアプローチをすればよいのか迷いますが、まずは私自身がどうしてこの道に進んだのかという“原点”をお話をするのがよいのではないかという気がしています。

──原点ですか。ぜひお願いいたします。
私は本学に入学して以来、古典文学研究の道を歩んできました。そうした意味では、私も「人文知」を求めてきたもののひとりといえますから、今回は個人的な体験を足がかりとしてみたらどうかと思ったのです。
振り返ってみますと、この道に進んだ私の原点には「私とは何か」という問いがあったように思います。どなたでも思い当たることがあるかと思いますが、青春時代は「自分という存在とは、いったい何なのだろうか」と考えたり、ときに悩んだりする年頃ですよね。ご多分に漏れず、私も高校時代、「私とは何か」という問いを前に、その答えを求めていました。私はなぜ生まれてきて、何をなすべき人間なのだろうか……などと、さまざまに思いをめぐらせていたんです。
──「私とは何か」ですか。アイデンティティというのは、青春期のひとつのテーマですね。
その答えに近づこうとする道筋は、いろいろとあると思いますが、私は、「私がいまここにあることの不可思議さ」ということに思い至りました。そして、私を包み込み、私の内面を形づくっているもののひとつに、日本の文化というものがあることを自覚しました。普段、日本語を用いて生活しているということにとどまらず、私のものの見方や考え方、いうなれば私という存在の根っこの部分に、日本文化というものが抜き差しがたいものとしてあると感じたのですね。では、日本文化とは何か。私はその答えを古典文学のなかに探ろうとし、古典文学研究の伝統を受け継ぐ本学の門戸を叩くことにつながっていきました。
──自身の内面がどのように形成されているのかの源流に日本の文化があるのではという問いですか。異なる文化で育った方とお話しすると自分を形成している文化が浮かび上がってくる感覚は記憶にあります。
「私とは何か」という問いは、「日本文化とは何か」という問いのほか、「他者とは何か」「人とは何か」「心とは何か」「世界とは何か」などといった問いにつながっていきます。もちろんすぐ答えが出るものではありません。しかし、そうした人が人として生きるうえで核になるべきことを考えようとすることこそ、人文知がもちうるひとつの力なのではないでしょうか。たしかに、それを考えることすべてがダイレクトに社会的な課題の解決などに結びつくのかどうかは、なんともわからないのですが……。けれども、根源的な問いに向き合う姿勢がやがて自分が暮らす国や社会について考えていくことにつながっていくことは疑いがないことだと思います。
──興味深いお話です。ただ、「私」という存在を掘り下げるにも、たとえば生物学的に構成要素を突き詰めていくなど、多様な観点がありえますよね。人文知、特に古典文学がもたらしてくれる視点には、どのようなものがあるのでしょうか。
これもまた、個人的な体験からお話をしてみたいと思います。本学に入学した私は、『源氏物語』を対象とした研究会に入りました。その研究会では夏合宿において自身で題材を選んでテーマ発表をすることになっていたのですが、その時に私が選んだのが源氏物語における「蛍」についてでした。大学からの帰途、夕暮れ時に河辺を歩いていて、「そういえば最近蛍を見ないな」という単純な感慨がきっかけですが、そこから源氏物語の時代の人びとは「蛍」をどのように見ていたのかということに興味を覚えたのです。
夏の闇夜に青白い光を明滅させながら飛んでいく「蛍」はとても神秘的なものです。それに対して、「蛍はなぜ光るのか」という問いを立てると理系の学問の問題になろうかと思いますが、私は「日本の人びとは蛍をどのように見てきたか」という問題に関心がありました。いまここに生きる私が蛍を見て抱く思いは、はたして源氏物語の時代の人びとと同じものなのだろうか。そこで、私は現在を出発点として時代を遡りながら古典文学のなかに蛍がどのように描かれているかを調べてみることにしました。
文学史を遡っていく方法は、折口信夫が『日本文学啓蒙』(全集 23)で行っています。現在、「蛍祭り」「蛍の夕べ」などといった催しものが各地で開催されていますが、昭和 30 年代の頃までは、蛍は夏の風物詩として一般的なものであったように思います。それは、明治でも同様で、蛍の名所に汽車を使って皆で見に行くというようなことがあったようです。また、江戸時代でも、「蛍見(ほたるみ)」といって、船を仕立て、三味線を奏でて酒や料理を楽しみながら皆で蛍を見るということをしており、松尾芭蕉はその様子を「蛍見や船頭酔うておぼつかな」と詠んでいます。船頭まで酔ってしまって手元が危ういというのですね。なんとも楽しげな「蛍見」です。

──現代を生きる私たちにも、通じる蛍の楽しみ方ですね。
「蛍見」ということば自体が示しているように、蛍見は、花見や月見、雪見などと同じ趣向のものでした。こうした民衆が景物を集団で見るという風習が広く行われるようになったのは江戸時代の頃からだとされています。しかし、なぜその対象が花や月や雪かといえば、平安時代において形成された美意識に基づいていると考えてよいでしょう。『古今和歌集』では、春といえば桜、秋ならば月、冬は雪といった季節ごとに代表的な景物が詠まれていますが、そうした美意識は日本の文化に深く根づいていきました。貴族から武家へ、そして庶民へと広く、深く浸透していったのですね。平安貴族たちは蛍も賞美していました。平安中期の清少納言『枕草子』の初段には、「夏は夜」としたうえで「闇もなほ、蛍の多く飛びちがひたる。また、 ただ一つ二つなど、ほのかにうち光りて行くもをかし」とされていますし、『源氏物語』には「蛍」巻という蛍が印象深く描かれる巻もあります。
──なるほど、今の私たちと同じ感覚で蛍を楽しむ文化が平安期には成立していたのですね。
けれども、さらに遡って平安時代より前、上代にいくと蛍の用例は極端に少なく、ほんの数例を数えるばかりとなってしまいます。約 4500 首の歌が収録されている『万葉集』のなかで、「蛍」を詠んだ歌はたった 1 首しかありません。しかも「蛍なす」という枕詞の用例ですから、蛍の実景を詠んだ歌は存在せず、蛍が和歌の対象ではなかったことがわかります。『日本書紀』神代巻では「多に蛍火なす光る神と蠅声なす邪神(あしきかみ)と有り」とあり、「蛍火」は「邪神」の形容として用いられています。つまり、上代ではどうやら蛍は邪悪なもの、畏怖の対象としてとらえられていたようなのです。
ただ、この感覚は現代に生きる私たちにも理解できるものではないでしょうか。科学的な知見では、蛍の光は「ルシフェリン」という物質と「ルシフェラーゼ」という酵素が反応したものとされていますが、闇夜にふっと光りながら飛んでいく蛍を見て、頭では光るのは化学的な反応の結果だと理解できても、やはり感覚的には人魂(ひとだま)のようなものを感じてしまう……。
──たしかに、ゆらゆらと飛び去る光は、ぞくぞくとさせるところもあります。蛍というものが風情のあるものと知ってわざわざ見に行くからこそ、恐れは感じず、ただただありがたく見ていますが、蛍を知らずに初めて闇夜の向こうに飛び光る様を見たら怖く感じるかもしれません。
上代では畏怖の対象とされていた蛍が平安朝では風情があるものとしてとらえれていく。そうした蛍のとらえ方の転機になるのが平安時代初期の漢詩文隆盛期です。とくに「蛍雪の功」の故事は官人たちにとても好まれました。平安期の人びとの蛍の見方はそうした漢籍にふれることによって、変化したものと思われます。平安時代の文化は、国風文化というイメージが強いのですが、漢詩文の影響を忘れてはならないように思います。蛍の見方も漢詩文によって大きく変わったのです。けれども、蛍の畏怖の念がまったく消え去ってしまったかというと、そうではありません。平安中期を生きた和泉式部は「物思へば沢の蛍も我が身よりあくがれ出づる魂(たま)かとぞ見る」と歌い、蛍の光に自分の魂を重ねて見ていますし、現在の小説や映画などでも蛍に人の魂を見るという描写は数多く見られます。つまり、私たちのなかには、優美な蛍と恐ろしい蛍というふたつの感覚が同居していると考えられるのです。
──日本文化がとらえてきた蛍への感覚が、知らぬうちに現代に生きる「私」の感覚を形づくっているものがある、ということですか。
現在、日本に生きる私たちが自分独自の感性でとらえていると考えているようなものも、古来の「文化」というものに縛られているということがあるのですね。蛍についても、おそらく外国ではまた見方が異なることでしょう。人文知は、そうした「私」の心のありようを明らかにするとともに、「歴史」や「文化」のあり方などまで解き明かしていくことにつながっていくのだと思います。
──あえて、ここまでのお話をまとめて考えてみると、竹内先生個人=「私」をめぐる問いが、やがて普遍的な私たちへの問いに接続していくところにも、人文知の面白さがあるような気もしてきました。
私は長野県の自然が豊かな土地で生まれ育ちましたから、少年時代、蛍はとても身近なものでした。古語に「すだく(集まる)」という語がありますが、河辺で蛍がたかるように「すだく」ありさまは、たんなる美しさとは異なる何か名状しがたいものを私に感じさせました。大学に入ったばかりの私が蛍を研究テーマに選んだのもそうした名状しがたい何かを明らかにしようと考えたのかもしれません。
本学の古典文学研究は、伝統的に「実感」と「実証」を重んじていますが、このふたつのことは人文知ということを考えるうえでも欠かせないのではないかと思います。対象が「私」のなかで「実感」され、「実証」されたとき、はじめて対象が生き生きとした姿を現してくるように思います。
── 一方で、近年は文学研究においても、膨大なテクストデータを解析するテクストマイニングといった、文理融合的な最先端の手法が注目されてきています。このような新たなアプローチによって、人文知の土台自体が変容を遂げてきているのではないでしょうか。
おっしゃる通り、いま文学研究は過渡期にあると思います。以前のインタビューでもすこし触れているのですが、特に 1980 年代にはテクスト論という、作品を作者から切り離し、読みの可能性を模索していくような読解の方法が示されました。
──テクストの表層を捉えることに傾注するような立場ですね。
『源氏物語』は作者の自筆本が残っていません。作者が書いたそのものの本文がないかぎりそこに作者の意図を求めるのには限界がありますから、テクスト論の考え方自体は有効です。しかし、「読みは人それぞれ」ということだけでは研究としては認められにくい。現在は、写本などの確かな「モノ」に基づいた研究が盛んになされるようになっているように感じます。もちろんそうした研究は極めて重要です。けれども、文学研究としては『源氏物語』の表現世界の解明といったものにも、もっと精力的に取り組んでいかなければならないと思います。では、どのように取り組めばよいか。いまは、その方法論的な試行錯誤がなされている時期であるように見ています。
──今が過渡期とおっしゃる所以ですね。
同時に、現在は研究をどのように進めるかということも課題になっているように思います。たとえば、私が学生のころなどは、作品の用例を整理することにとても多くの時間をかけていました。作品それぞれについて索引にあたり、ページを繰りながら用例をひとつずつカードにとって収集して行き、それらを整理したうえで分析をし、論理化していくという方法ですね。そのころは、論文なども自分で目録を作成してひとつひとつ読んでいきました。
しかし、いまでは多くの作品がデータ化され、検索システムも整備されて、用例は瞬時のうちに集まりますし、論文なども電子化されて、キーワードを検索すればすぐにヒットした論文を読むことができるようになってきました。すなわち、“整理の時代”がほとんど終わったのだと思います。
──“整理の時代”の終焉は、研究者の方のみならず、一般社会における肌感覚でも理解できるところがあります。今は、20 年前と比べても情報の取得コストが圧倒的に下がった時代を生きていますよね。
では、そのように進展する新しい技術をどのくらい自身の研究に取り入れるのか、取り入れれば何ができるのか。研究者一人ひとりが模索している時代だということができるでしょう。そうした新時代のありようを仮に“現代人文知”と呼ぶのだとすれば、それは、瞬時に集まる膨大な情報を用いて、そこに何を見るのかが鋭く問われる知の姿だということができます。多くの時間をかけていた従来の作業を経ないで、ビッグデータを足場として利用できるというメリットがある一方で、ではそこに何を見るかということの方に力を注がなくてはならないのです。
──現代人文知。ビッグデータ・ネイティブの時代だからこその人文知とも言えそうですね。人工知能(AI)をめぐる議論も含めて、所与の環境のなかでどうような問いを立てるのか、どう立ち回るのかの判断が問われます。
本当に難しい時代だと思います。先ほどビッグデータのメリットについて触れましたが、それがデフォルトである環境に生きるということは、作品の理解に時間をかけるというプロセスがスキップされがちな状況に身を置くということでもある。紙の書籍のページを繰りながら時間をかけて用例を調べていた時代は否応なしに作品の文脈を追わざるを得ませんでしたが、現在はすべてが情報の断片と化してしまいかねないという、知を育むうえでの危うさもまたあるわけですね。たとえば学生が何か用例を調べたいと思ったときに、検索すれば瞬時にそれを集めることができますが、それらからどのようなことを導き出すことができるのか。作品そのものはもちろん、その作品を生み出した文化的背景などへの理解がないと、その用例が意味していることがわからないということが容易に起こりえてしまう。個々の事例には簡単にアプローチできるのだけれども、それらを総合して見えてくるものをとらえるという点は、今後の人文知におけるひとつの課題だと感じますね。
──ビッグデータの全体像を把握することは根本的に困難ですが、とはいえ何かしらの全体像を把握しようとする姿勢は必要だ、と。また、全体像を把握せずに個別の答えをつかまえてしまうと、全体像とは外れた理解をしてしまうこともありそうですね。
ただ実は、そうした人文知の新たな困難を打開するきっかけを与えてくれるのも、これまでに培われてきた人文知だとも思うのです。たとえば、読んでいる古典文学作品の文中に、「蛍」という言葉が出てきたとしましょう。学生たちには、その「蛍」の一語を、単なるデータの断片として処理するだけではなく、想像力を用いながら、生き生きとした「読み」へと広げていってほしいと思っています。そして、それは「実感」と「実証」という人文知の訓練のもとで養われていくように思います。いわば、データから自分の「実感」にいかにつなげていくのか、ということです。加えて、いかにしてその「実感」を「実証」して他者と共有していくのか──。
──「私とは何か」という問いを抱えていた高校時代から、人文知への旅路は始まっていた
のかもしれませんね。
もしかしたら、そうなのかもしれません。「私」の世界と人文知の世界はつながっているはずなんです。いま人文知に注目が集まるのは、社会生活を営むうえで人文知の知見の必要性を感じておられる方が多くいらっしゃるからでしょう。とくにいまの日本は、一昔前のように、右方上がりで進んでいく社会状況にはありません。多様な価値観のなかで、一人ひとりがお仕着せではないものの見方や考え方をもって、自身の道を選び、自身の足で歩いていかなければなりません。そうした現代にあっては、人文知はささやかな、しかし確かな指針となるはずなのです。
──誰も先を見通せない時代だからこその人文知、ということですね。
もちろん、人文知に関心を持たなくても経済的には豊かな生活を送ることができるかもしれません。しかし、以前から経済界における巨人といわれる方々は、人文知に投資を惜しみませんでした。たとえば、私が古典文学を研究する際の足場のひとつとしている民俗学は、かつて実業家・渋沢敬三が全面的にバックアップしていました。企業の経営にあたったり、国や社会の中核を担ったりする方々こそ人文知が必要であるということを、さまざまな人びとが理論的・直感的に把握し、行動に結びつけてきた歴史があります。何より私たちが人としてよりよく生きるために最後の最後で必要なものは何だろうと胸に問うたとき、人文知が求められる時代に入っている。そういうことなのかもしれませんね。
| 人文知探究室後記 自分の周りに存在している、普段は意識的に捉えることのない世界。その膨大な領域を一つひとつ意識し、名前をつけていくことで、人々は後世へと知識を受け渡し、歴史を紡いできた。生成 AI の登場は、意識化された世界のすべてを瞬時に睥睨し、整理することが容易となる世界の始まりなのかもしれない。いままでは困難だった、こういってよければ全-世界的な認知(?)を補助する人工知能が登場したからこそ、われわれは、自分たちの周囲をぐるりと見渡し、いまだ把握しきれない世界の端緒をすこしずつ掴み取っていく力を鍛えないといけないのではないだろうか。古来より、人文知というものがどのように磨かれてきたのか。この問いを探ることは、これからの時代において不可欠な作業であると考え、学内外の有志が学問領域を横断し、ときに学問の外から素朴な疑問もまじえながら、新たな地平を探究する人文知探究室を立ち上げた。初回である今回は、図らずも話題が「ビッグデータ・ネイティブの時代だからこその人文知」へと発展した。漠然とした、しかし魅力的な人文知という営みの本質を、今後も探っていく。(人文知探究室:柳原暁) |
人文知探究シリーズ 第2回は「人文知とは生きていくための知恵」>>
竹内 正彦
研究分野
中古文学
論文
明石の鐘の声―明石一族物語の原風景―(2026/02/01)
指貫の裾を濡らす光源氏―『源氏物語』「蓬生」巻の常陸宮邸訪問をめぐって―(2025/12/20)