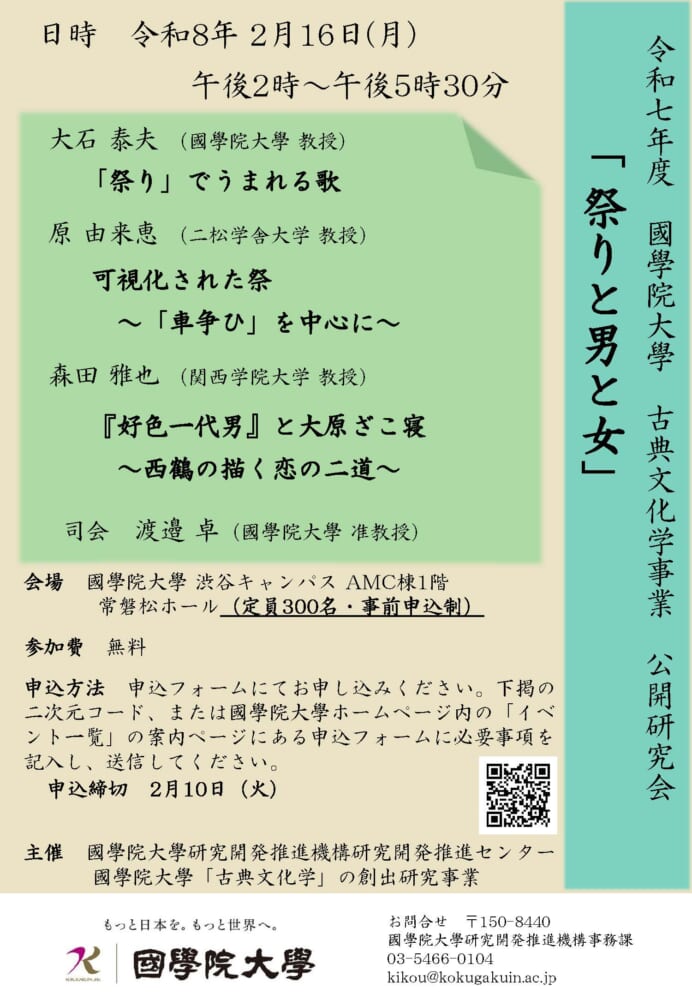清野隆・観光まちづくり学部准教授が2000年代後半に出会ったのは、地震からの復興へ向けて模索を続ける、新潟県長岡市山古志地域だった。まさに地に足のついた、かつ地域の外ともつながりコミュニケーションをとっていく復興のプロセスからは、何が見えてきたのか。
コミュニティ・デザインの可能性を考えるインタビュー、後編では、具体的な実践の数々を取り上げながら、現代人にとっての“地域の暮らし”を見つめ直す。グローバルな課題はローカルで解決するという、新たな時代の回路は、今日もこの世界のどこかで生み出されているのかもしれない。
新潟県長岡市山古志地域に出会ったのは、イタリアから帰国後しばらく経った、平成20(2008)年の秋頃かと思います。かつては山古志村だったこの地域は、ご存じのように平成16年10 月23 日の新潟中越地震で甚大な被害を受けました。平成17年、長岡市と合併し現在に至ります。
私は地震発生直後の大変な状況を体験しているわけではありません。ただ、その後のさまざまな復興プロジェクトに、調査をしていた研究者の方を介して、かかわる機会をいただいたのでした。私が現地に足を踏み入れた時期は、地震で一度離れた住民の方々の一部も戻って来て、これからこの地域をどうしていくべきかを議論していらした時期。私はそうした復興プロジェクトのための調査に携わりながら、山古志地域の豊かな環境、そして大切な暮らしというものを垣間見させていただくことになったのでした。
これまでに、多くの実践が生まれてきました。その基底にあるのは、平成17年の長岡市との合併時に設立された「山古志住民会議」。そしてその住民会議が策定した「やまこし夢プラン」であり、さまざまな取り組みがなされてきました。もう一点、同プランで重要なのは、「つなごう山古志の心」というスローガン。内のつながり、世代間のつながり、外とのつながりの3点を重視した地域を目指すことが明記されています。
実際に、外とのつながりでいえば令和4(2022)年に、デジタル住民票を発行するという先駆的な取り組みを行っています。他の地域に住んでいる人々も含めて、山古志地域を応援したいという人がオンラインでコミュニケーションをとり、交流から課題解決へと模索を続けています。
また内とのつながり・世代間のつながりにかんしては、令和2年に「小さな山古志楽舎」という、地域の若者たちを主体とした任意団体が立ち上げられました。伝統文化や、震災復興経験を伝承する活動を行ってきました。令和6年は新潟中越地震から20年という年であり、「山古志つながる大作戦」という、山古志へ向けたメッセージを集うプロジェクトも展開されています。

調査しながら私が改めて実感したのは、自分たちの地域の環境と暮らしは切り離せないものである、ということでした。その日々の生活をどう持続できるのかを、地域の内外の人たちが議論し続けている。そしてそのことは、こうした実践が山古志地域だけでなく、他の多くの地域にとっても普遍的な価値をもち、参考にできるものだということを示していると思います。現代人である私たちは、移動の自由をもつなかで、住む場所も各々の観点で決めることができる。そのなかで、これからはある場所に根差して暮らすということが重視されるようになると思います。まずは地方都市や農山村にみられる、根差した場所の暮らしが成り立つよう他の地域を応援して、場所に根差した暮らしの豊かさを理解する。そしてゆくゆくは大都市でも場所に根差した暮らしを構築するということもある。
いずれにしても人の生活というものは、それを支えている目の前の環境と向き合っていくことからはじまりますし、そこから社会や経済というものを形づくっていくものでもある。地域の歴史性を踏まえたコミュニティ・デザインは、改めて現代的に考えうると思いますし、その意味で山古志の試みは、広く参考にしてもらえるところがあると感じるのです。
より広い視点で捉えれば、SDGsや気候変動といった近年の議論にも通じるところがあります。際限なく資源を使える時代ではなく、一方で災害が多発する時代に私たちは生きている。そのなかで可能なコミュニティやライフスタイルのあり方はどういったものなのだろう、私たちはどのような転換を経なければならないのか、といったことを見つめる必要がある。そのときに、地域の限られた環境を持続させ、そのなかで生きるというテーマは、個別具体的でありながら普遍性をもつと思うのです。
グローバルな、地球規模の問題を解決することに、ローカルな、地域規模での課題に向き合うことが寄与するかもしれない、ということでもあります。もちろん、インタビューの前編でお話ししたように、私も最初からこうした観点を持ち合わせていたわけではありません。若い頃からの度々の発見や気づきがあり、特に近年、年をとってくるなかで、工学的な観点からだけではとらえきれない、地域性の大切さというものを実感することも増えてきました。自分たちの身の回りの環境でどうにかするしかない、ということは、制限されたものであるというよりは、D.I.Y的な豊かさにつながるものである、ということだと考えられるわけですね。本学で取り組んでいる「まちづくり」も、そうした観点で考えることができるでしょう。

私が最近関心を抱いている地域のひとつに、新潟県佐渡の宿根木という場所があります。廻船業で栄えた江戸期の町並みを上手に現代に伝えており、そこで人々の生活が営まれ続けている。そのなかで、たとえば地域の特産品である海苔に再び光を当てるような取り組みを、移住者の方がやっているというような例もあります。
いろいろな地域や場所で、土地の知恵やポテンシャルを見つめ直すことからはじめられることが、これからも多くある。そう感じています。
<<前編は「歴史と暮らしをデザインし、地域の価値を目覚めさせる」
| 1 | 2 |
清野 隆
論文
都市計画家G. De Carloによるテリトーリオ論に関する基礎的考察-論考「Reading and Design of the Territory」の要約と考察(2025/08/01)
山古志村 限界を越えて、つながる(2018/04/)