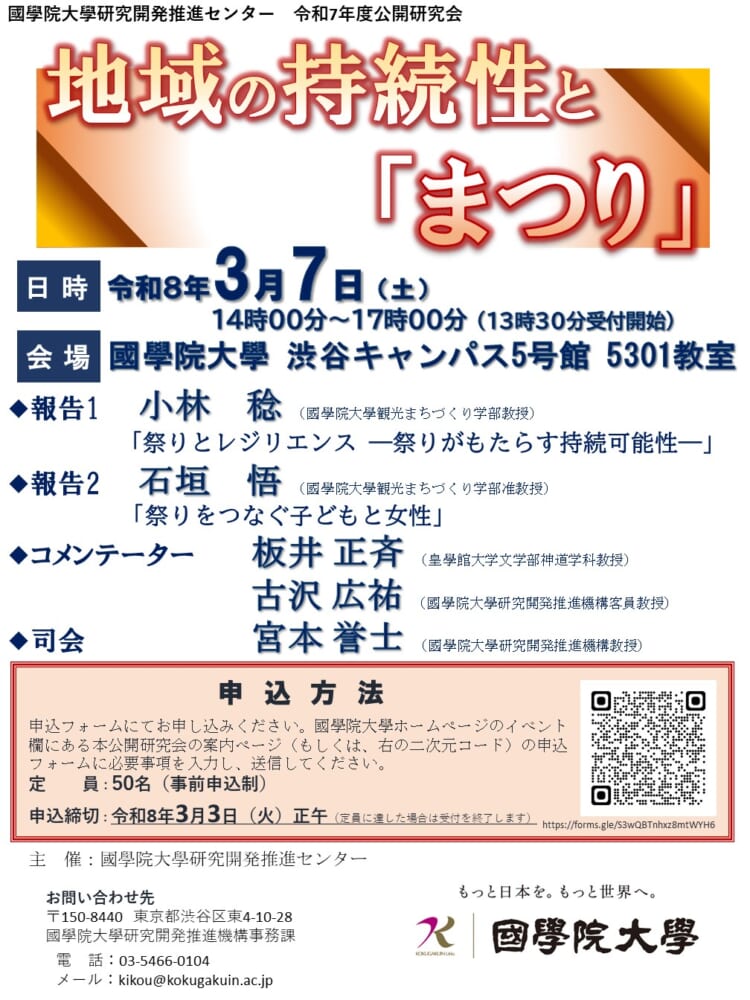高等学校時代の国語の時間には、どんな記憶があるだろうか?長い時間が経っても自分の心に刺さっている文章に出会ったという人もいれば、正直あまり面白いと思えなかったという人もいるかもしれない。
そんな教育現場のリアリティを引き受けながら、国語教育学の世界で研究を進めているのが、高山実佐・文学部日本文学科教授だ。長らく高校の教壇に立っていたという高山教授は、研究によって何を現場にフィードバックしうると考えているのだろう。自身の歩みを振り返りつつ、前後編のインタビューで語ってもらった。
中等教育段階における国語教育学を研究しています。30年近く東京都立の高等学校で教員をしていたこともあり、高校の国語科授業について考えることが多くあります。
かつての現場での国語科授業の実践は、現在のささやかな国語教育学研究のよりどころとしても、とても大きなものになっています。というのも、商業高校や普通科高校を経て3校目の赴任校となった工業高校で、まったく授業が成り立たなくなったという経験が、私の大きな転機になっているからです。
それまでも授業の上手な先生に憧れつつ、自分では、うまくいったような気がする、ほんの何回かの授業が支えでした。が、工業高校で、座学が嫌いで、卒業後は社会でものづくりに関わっていこうとしている生徒たちを前にして、国語の授業をうまく進めることはできませんでした。たとえば古典を教えていても、これが一体何の役に立つのかという雰囲気で、「そんなに言うなら、先生、古典語でしゃべってみろよ」と詰め寄られたこともあります(笑)。授業で古典を扱う意味は何か、そもそも国語を学習することの意味は何だろうかと、私自身が勉強するという感じでした。
うまくいかない50分の授業時間をどうしよう……と悩み、国語の授業をどうつくっていけばよいのか、本格的に学びたいと思いました。研究会などに出、明日の授業へのヒントを得ることはあったのですが、あちらこちら求めた挙げ句、大学院修士課程の門戸を叩くことにしました。教師としての生活が10年を超えていました。

初めて自覚的に学ぶことになった国語教育学は、学問として積み上げられてきた理論をさらに追究し続ける知の世界でした。一方で、私が経験してきた日常は、生徒たちとどう向き合っていくのか、どのような教材を使い、どのような活動をし、どうすれば最後に「なるほど」「わかった」「できた」と思ってもらえるのか、ひたすら悩みながら過ごす、実践のみの世界でした。
いま教室の中の目の前で起きていることや、実践のなかで何となく身についていたものを学問のなかでどのように語り直すことができるのか──理論と実践とを往還する国語教育学の研究は、とても楽しいものだと感じられました。
国語教育学の研究を始めてしばらく経ってからですが、さまざまな高校での経験を考慮に入れていただいたのか、学習指導要領の作成協力委員になる機会がありました。現在実施されているもののひとつ前、2009年3月に告示され、2013年から年次進行で実施された学習指導要領です。このときもまた、日々の授業を支える、国語科の教科構造、目標、指導内容、言語活動などについて、広い視野から改めて考える機会に恵まれました。
先ほど研究の世界に楽しさを覚えたという話をしましたが、たとえば、言語を扱う国語教育というものは何をする場なのだろう、という根本的な問いがあります。
いろいろな答え方があると思うのですが、恩師の一人である浜本純逸先生は、国語学研究者・岩淵悦太郎(1905年~1978年)の言う、言語の四つの機能を挙げながら、ことばの教育ということを話してくださいました。
「認識」「思考」「伝達」「想像/創造」が、その四機能です。人は言語を用いることで、認識することができます。「花」の中でこれがチューリップなのだという認識は、「チューリップ」という言語があることで可能になります。また、漠然とした思いを言語化することにより思考とすることができ、さらに、このインタビューの場のように言語によって他者に伝達できるということがあります。そして、言語によりさまざまなモノやこと・人、世界を想像できたり、言語により新たな世界を創造できたりという、イマジネーションやクリエイティビティにかかわる機能もあります。
言語があるからこの世界を認識することができ、思考、伝達、想像・創造することができるというのは、当たり前のことかもしれません。けれど、この四つの機能はとてもわかりやすく、私は、「ああ、これが国語科教育のなかで生徒たちにわかってほしい、身につけてほしいことばの姿、ことばの力なのだ」と感じました。

また、浜本先生は、学習者の言語活動──通常は、話す・聞く、書く、読む、の四つとされる活動の他に、もうひとつ「見る」ということをおっしゃっていました。
ことばの力というものは、学習者自身の言語活動を通じて、初めて身についていくものです。ですから、話す・聞く、書く、読むという活動は非常に重要であるわけです。しかし、今日、生徒たちを取り巻くメディア環境が大きく変わりつつあり、音声言語・文字言語のみではなく、画像・映像などとともに情報はもたらされます。ならばここに、「見る」も入ってくるだろう、というのが浜本先生のお考えでした。
国語教育学における議論の一端ではありますが、「言語にはどのような機能があるのか」「国語の力とは何か」などといった、現場の実践と学問の理論が交差する、とてもおもしろい論点だと感じました。
国語教育学の研究とは別に、実際の高校教員生活ではさまざまな業務に追われます。会議、部活や進路の指導もあり、黄昏の放課後、担任していた生徒と屋上で一緒に泣いたこともありました(笑)。修士課程を終え現場に戻った後しばらく経って、指導教授であった田近洵一先生に、指導主事となって学校現場を指導していくのか、管理職を目指すのか、国語教育学の研究を続けるのか、と尋ねていただいたことがありました。その時、国語教育学を考え続けていきたい、研究を続けることで国語科教育に何かできることがあるのではないかと思いました。そして、現在に至っています。
私自身の研究トピックはというとかなり広がっていて、一言で整理するのが難しい状況です。修士課程では、高校教科書の定番教材といえる、夏目漱石の「こころ」について昭和31年検定(清水書院)の「上」からのみが初採録であることなどについて、教材史を調査しました。そこから関心が広がり、今は、明治・大正・昭和戦前期の中等教育段階で使われていた教科書、読本や教育課程などの国語教育史にも興味をもっています。
高校の国語科教育は、2022(令和4)年度以降、大きな変化のただ中にあります。それは新たな学習指導要領が実施されていることによります。インタビューの後編では、どんな変化なのか、どういった教育実践がありうるのか、私なりの考えをお話ししてみたいと思います。
高校の国語科教育は変化のただ中にある後編「高等学校の国語科教育激動の一年でなにが起きたのか」はこちらをタップして進んで下さい
高山 実佐
研究分野
国語教育学
論文
「ことばの学び」を求めて―高等学校国語科授業を考える―(2024/03/30)
国語科教育における言語の機能―戦後学習指導要領、高等学校段階を中心に―(2024/02/20)