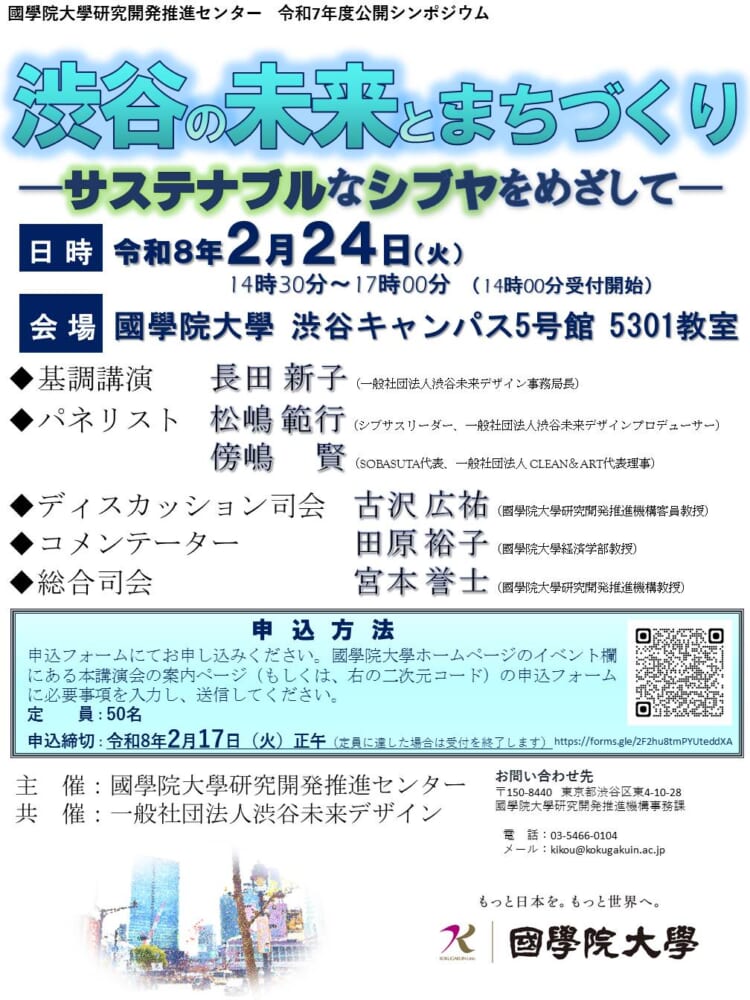「今、私は、私たちの常識に反して、見かけの障害にかかわらず、人はみな豊かな言葉の世界を持っており、沈黙の中で研ぎ澄まされた言葉は独自の輝きを持っているという考えに立つにいたりました」――。柴田保之・人間開発学部教授がかつて、『沈黙を越えて:知的障害と呼ばれる人々が内に秘めた言葉を紡ぎはじめた』(萬書房, 2015.5)という著作で記したフレーズだ。
障害者とのかかわりあい、その現場に立って約40年。介助つきコミュニケーションという方法を通じて、誰もが持っているはずの豊かな言葉が溢れる瞬間を見つめ続ける日々。その思いを、前後編のインタビューで訊ねた。
たとえば、知的障害があるとされる人のなかには、ペンを渡すとグルグルとまるを描く方がいらっしゃいます。体は動くのに、字が書けない。それはまるで、言葉を持っていないように見えてしまうかもしれません。あるいは、子どもが絵を上手に描けるようになる途中の段階のように見えるかもしれない。
しかし、そのグルグルという手の動きは当事者にとって、「運動のコントロールがきかない」ために起こっている動きである可能性があります。そこで私たちが当事者の方に寄り添って、力強くグルグル動いているその力をいったん抜いてもらう。すると、小さな力で、当事者の方が字を書きはじめる……。
これは、現場で実際に日々起こっていることです。横から人が手を添えると、コントロールできなかった力が抜けていって、自分の意に沿うような微かな動きが出てくる。グルグルという動きの向こう側に隠れていた、文字を書く動きが出てくるわけです。
みんな、言葉を持っている。私はこう考えて、実践と研究に取り組んでいます。
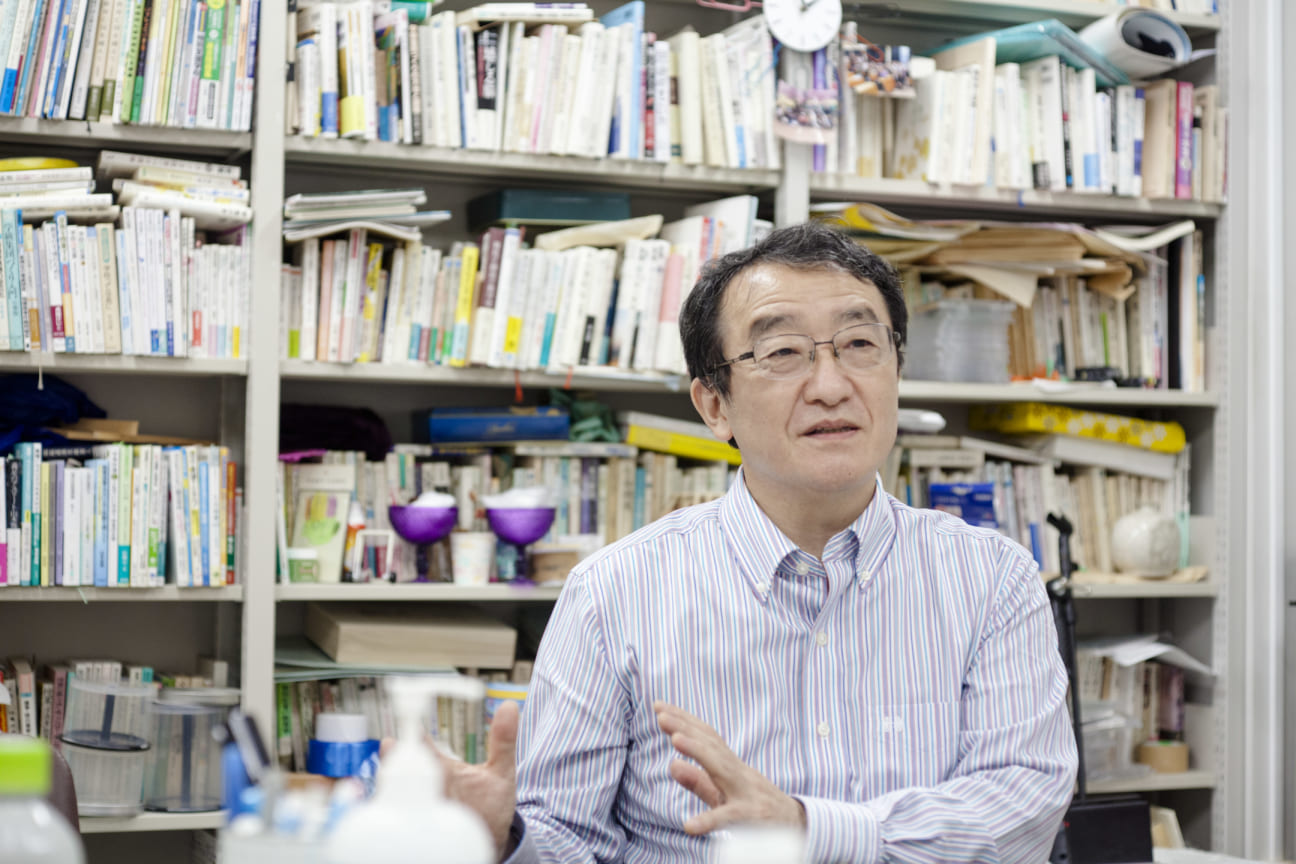
私が長年かかわっているのは、障害によって意思表出に困難を抱えている方々ですが、その状況はさまざまです。まったく喋れない人のうちにも、「体が動かないがゆえに意思表示の手段を持てずにきた」という人もいれば、「知的障害が重く、言語がなかなか表出できない」と見なされる人もいます。あるいは、日常生活をおくる上ではいろいろな動作ができても、喋ることには困難を抱えている、という人もいる。
しかし、どんなに言葉を持っていないように見える方であっても、必ずや言葉を持っている、そしてその当事者の言葉は「介助つきコミュニケーション」によって表出することができる。それが、今の私の考えです。
たとえば重度の身体障害があって体がほとんど動かない方でも、微かに動くことはできる。その微かな動きは、ハイテク機器で拾える場合もあるのですが、運動のタイミングの調整が、意外と難しい。
むしろその小さな動きは、人間なら拾えるということも多いのです。だから私たちは、簡単なスイッチ機器とパソコンのワープロソフトを組み合わせ、介助つきで操作していくという方法や、字を書こうとしている微かな指の動きを読み取っていく筆談といった方法を用いてきました。このような手段をとれば、当事者は言語での意思表出が可能になるという事例を積み重ねてきたのです。
先ほど、言語表出ができない人の内面が実際の年齢より低く見られてしまう、そうした見方について触れました。これは、「発達」という考え方と密接に結びついています。
心理学を中心とした「発達」という考え方は、たとえていえば一本の物差し=標準です。障害を持つ10歳の行動が、3歳の行動とそっくりな場合、その子どもの発達は3歳段階であるというふうに考える。しかしもし障害者の人が、10歳なら10歳の言葉の世界をこちらに伝えてきたとしたら、どうでしょう。
心理学のみならず、福祉や医療、教育の世界においても、「言葉を持たない障害者」という見方にかんして、当然だと思っている向きはあります。いや、かつて私自身がそうでした。言葉を持たない障害のある人たちがいることは前提で、むしろ非言語的な手段でどれだけ人は通じ合えるのかを探っていました。

それがだんだんと、誰もが言葉を持っていることに気づくようになりました。スイッチや筆談を用いることで、言葉を書く。見かけとは関係なく、豊かな心の世界を表現する。その事実を前に、私の考え方は変わっていったのです。誰もが言葉を持っている、そのことを見つめるためには、「発達」という見方を疑わなければいけないと考えるようになり、ひとりひとりと向き合っていきました。
あるとき、重度の自閉症の方が、たしかに文字を選択していくのを目の当たりにしました。普段はほとんど音声言語を発することはなく、椅子にじっと座っているのも困難で、自由に歩きまわり、時にはゆくえをくらませてしまうこともある方でした。
その人と私の間には信頼関係もありましたから、思わず聞いてしまったんです。「あなたが言葉を持つことはわかりました。でも、普段の行動はどう説明がつくのでしょうか。それを聞かなければ、今目の前で表現しているあなたと、いつものあなたの間での説明がつかないんです」と。
するとその人は、スイッチを用いてこんな言葉を綴りました。「かってにからだがうごいてしまうのでかなしい」――。この言葉を前にしたとき、自分のなかの疑問がスーッと解消していく感覚がありました。冒頭で申し上げたような、グルグルとペンを動かしてしまう人も、まさに「かってにからだがうごいてしまう」例ですね。介助つきコミュニケーションは、こうした方々の意思表出を可能にするのです。
思わぬ発見の連続。その過程で、私自身の認識が次々と塗り替えられ、現在に至ります。インタビュー後編では、当事者の人たちがどのような言語表現をしてきたのか、そしてその表現をめぐってどんな議論や展望があるのかを、お話しできればと思います。
柴田 保之
研究分野
重度・重複障害児の教育、知的障害者の社会教育
論文
津久井やまゆり園の事件と知的障害当事者の主張(2021/02/01)
「先天性盲聾児に対する点字や指文字による言語教育の可能性」(2018/02/28)