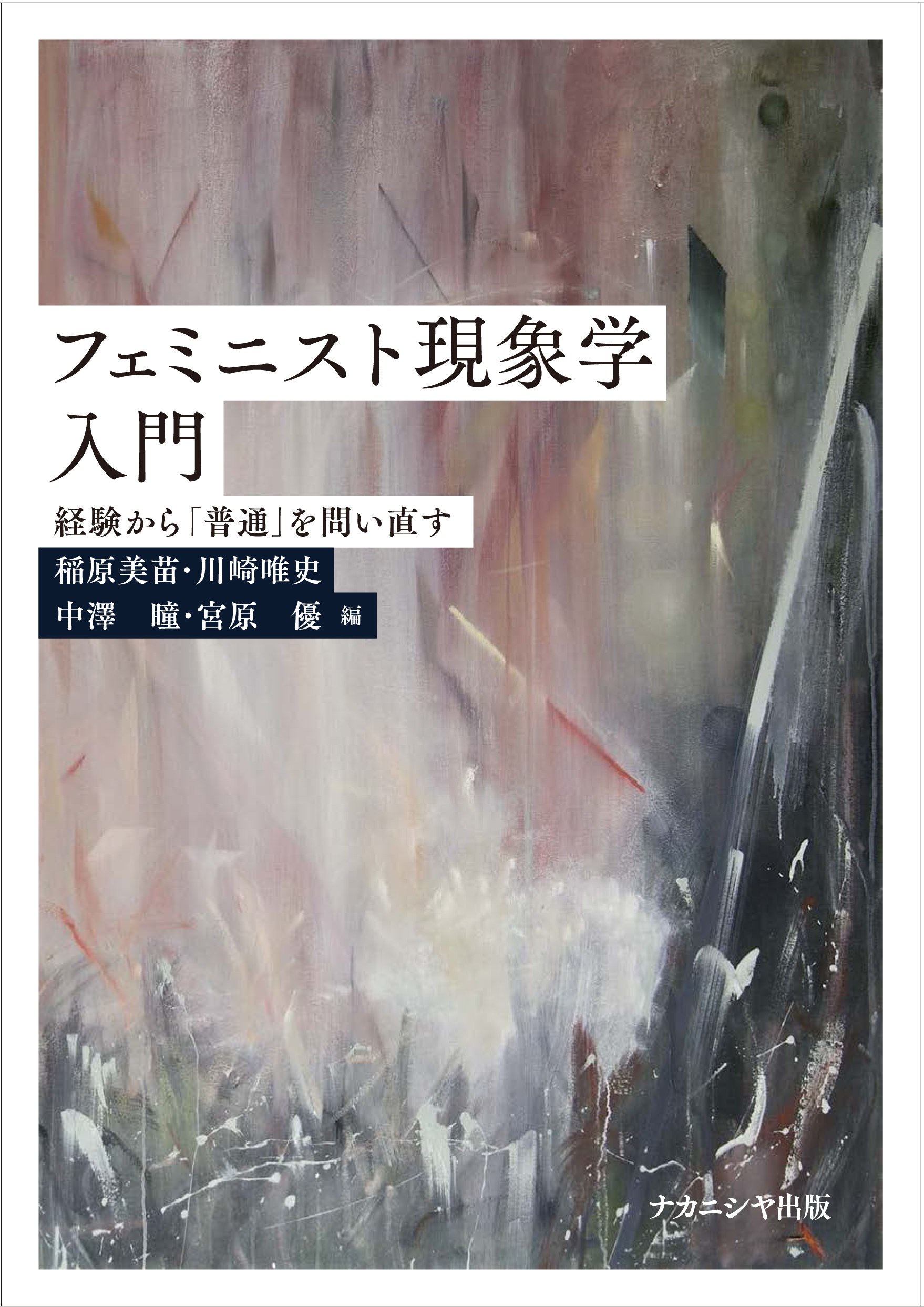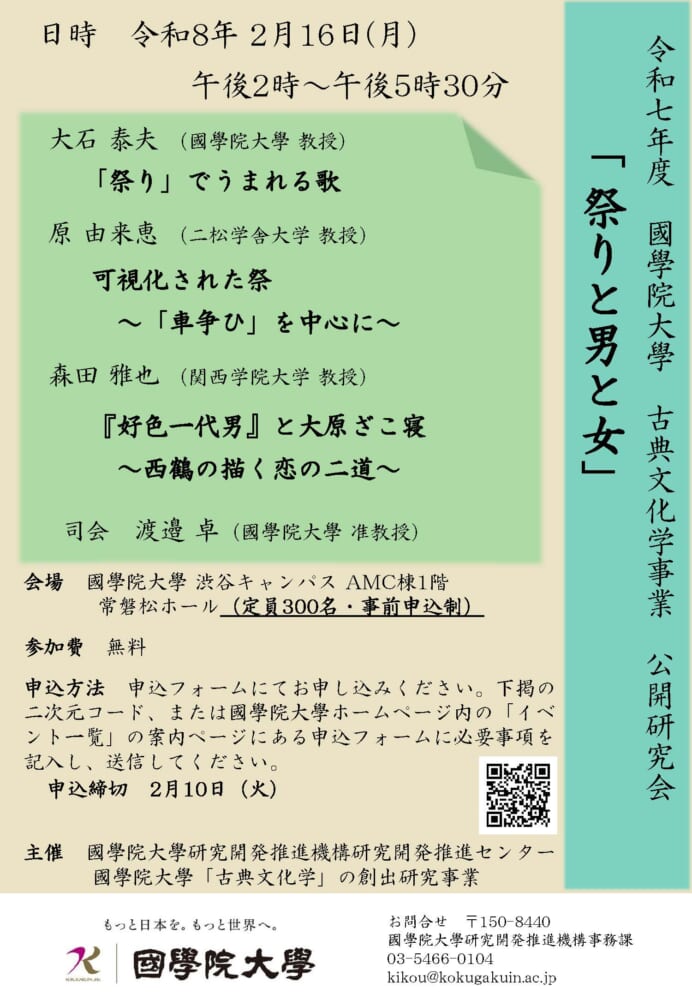「性差」を中心に、自身の「経験」に立ち戻る現象学の手法を説いてもらったインタビュー前編に引き続き、後編ではその学問的背景、そしてなぜ倫理的課題を考えるのかという「責任」について聞いた。
一人ひとりの「経験」に立ち戻って、現実の倫理的な問題を考えてみる。たとえば「性差」の問題であれば、誰しもが差別してしまったり、差別されたりした経験を持っている。それらがいったいどういう「経験」だったのか分析し直して、振り返ってもらう――。
現象学のこうした手法は、誰もが当事者として問題を考えることができる、有効な方法なのでないか、ということを、前編でお話ししました。
「性差」「人種」「親子」「難民」「動物の命」……近年私が考えているのはこうした5つの現実的な課題ですが、元からここまでそれぞれのテーマを深堀りしていたわけではありません。むしろ以前は、より理論的に、現象学にかんする過去の哲学者のテクストを厳密に読み、分析する、という研究を行ってきました。

特に注力していたのが、現象学の研究者のひとり、レヴィナスでした。2015年に刊行された私の最初の単著『甦るレヴィナス:『全体性と無限』読解』(水声社)も、レヴィナスの主著のひとつで論じられている理性論を丹念に読み直し、「他人」との関係という観点から積極的に解釈し直す、という本だったのです。
その一端として、レヴィナスが論じる「女性的なもの」といった概念や、「レヴィナス的倫理学」の可能性としての「動物」の問題、ということにも触れていました。レヴィナスの哲学が現代においてどのような価値を持つのか、実践的な問題に対してどういう示唆を投げかけてくれるのか、ということですね。
そんな折、前編で触れたような学生さんたちとのやりとりから、自分の取り組んできた現象学の方法を、より現実的な倫理的問題に当てはめて考えてみよう、と思うようになりました。先輩の現象学者のお二方と一緒に現象学的倫理学の可能性を考えてみたり、フェミニスト現象学のシンポジウムを聞きに行って衝撃を受けたり、といった中で、上記の5つのトピックを論じた『現実を解きほぐすための哲学』(トランスビュー)に至るような問題意識に至っています。
しかし、そもそもなぜ、私たちひとりひとりが「経験」にもとづき、こうした現実的な倫理の問題について考えなければならないのでしょうか。たとえば「難民」の問題ひとつとっても、「自分には関係ない」と考える方もいるかもしれません。それでも考えなければならないとすれば、そこにはいったい、どんな「責任」があるのでしょう。
私たちはよく、「責任を取る」「責任を負う」といった表現を用います。これらはいわば、「責任」を「負債」として捉える考え方です。

何かを壊してしまったから賠償責任を負う、あるいは私が教師という立場なのに何かをしてしまった/すべきなのにしなかった、というような意味での「責任」ですね。こうした「負債」としての「責任」という枠組みは、「難民」に直接私は関係がない、というような人に対して説得的ではないでしょう。
一方で、「責任」を自身の哲学の主題のひとつとして考えていたレヴィナスは、「責任」とはそうした狭い意味に収まらない、と考えます。
まず「負債」としての「責任」においては、「責任」を取る、あるいは取らない、ということがある種の交換関係のなかで考えられます。先ほど述べた、「難民」は自分と関係ない、という態度はここに由来します。私は「難民」に対して何もひどいことをしていない、だから「責任を取る」必要はない、というような交換関係の論理ですね。
しかしレヴィナスは、交換関係で倫理を捉えてしまっては、それは倫理とは似て非なるものになってしまうと考え、そうではない「責任」――いわば「責任を感じる」という表現が当てはまるような論理を模索します。
たとえば、世の中の性差別に対して何ら責任を負う必要はないと感じている人がいるとしましょう。それでも、誰かがセクシャル・ハラスメントを受けている現場に遭遇したにもかかわらず、周りでそれを見ているだけだったり、見過ごしてしまったり、という「経験」はあるのではないでしょうか。見て見ぬふり、という「経験」は、恥ずかしながら私も含めて、誰しもが身に覚えがあるはずだと思います。こうした経験に後ろめたさを感じるとしたら、自分がハラスメントをしたわけではないにもかかわらず、そこに何らかの責任を感じていたということではないでしょうか。
「責任を取る」「責任を負う」のではなく、「責任を感じる」――これこそが、レヴィナス的倫理学における「責任」の可能性です。
レヴィナスの論理に即していえば、自分が責任を感じる相手を選ぶことができないという責任の「受動性」、自分が生み出したり関与したりしたわけではない不正や苦難に対して生じる責任の「無起源性」、ということになります。こうした観点から見ていくと、「難民」に対する「責任」も、見え方が変わってくるのではないでしょうか。

もちろん、いきなりすべてに対して「責任を感じ」て、行動に移すことは難しいでしょう。ほとんどの場合、人間はつねに道徳的に振る舞うような「道徳的聖者」ではありません。
たとえば、「動物の命」にかんして言うと、肉食批判者であるシンガーの議論を踏まえてなお、私は肉食を止められていませんし、右往左往しています。むしろ、そこでシンガーの意見に一気に感化され、明日から肉食を止める、という極端な行動に走るほうが危険だとも感じます。
いっぺんに自分の考えを何らかの考えや理論と「取り替える」ということは、またすぐに別の意見に流されて無関心に戻ってしまう危うさをも抱えているからです。
むしろ自分の「経験」に立ち戻りながら、自分自身が少しずつ変わらざるをえないほどにまで考えていくなら、瞬間的なものではない、持続的な思考が可能になるのではないか、と私は思います。
たとえばこれらの問題にじっくりと取り組んだ学生が、卒業して就職したとする。1、2年は忙しくてそんなことは考えられないかもしれませんが、持続的な思考が培われていたならば、問題意識はやがてまたふっと、日常の中で回帰してくることでしょう。
私自身も、「性差」「人種」「親子」「難民」「動物の命」というトピックを、これからもっと深く考えていければと思っています。もちろんそれぞれのテーマについては既に、各専門の分野において、多くの議論の積み重ねがあります。その最中に、現象学という方法で参加していくのは、実は私自身にとっても相当なチャレンジでもあるのです。私自身も、常に「経験」へと立ち戻りながら――それこそ今は子どもの育児に取り組みながら――考えを深めていきたいと思っています。
小手川 正二郎
研究分野
フランス近現代哲学、現象学
論文
「フェミニズムの哲学」が可能だとしたら、それはどのようにしてか?(2021/05/01)
難民の哲学―定義や条文解釈をめぐる議論に何が欠けているのか(2021/03/01)