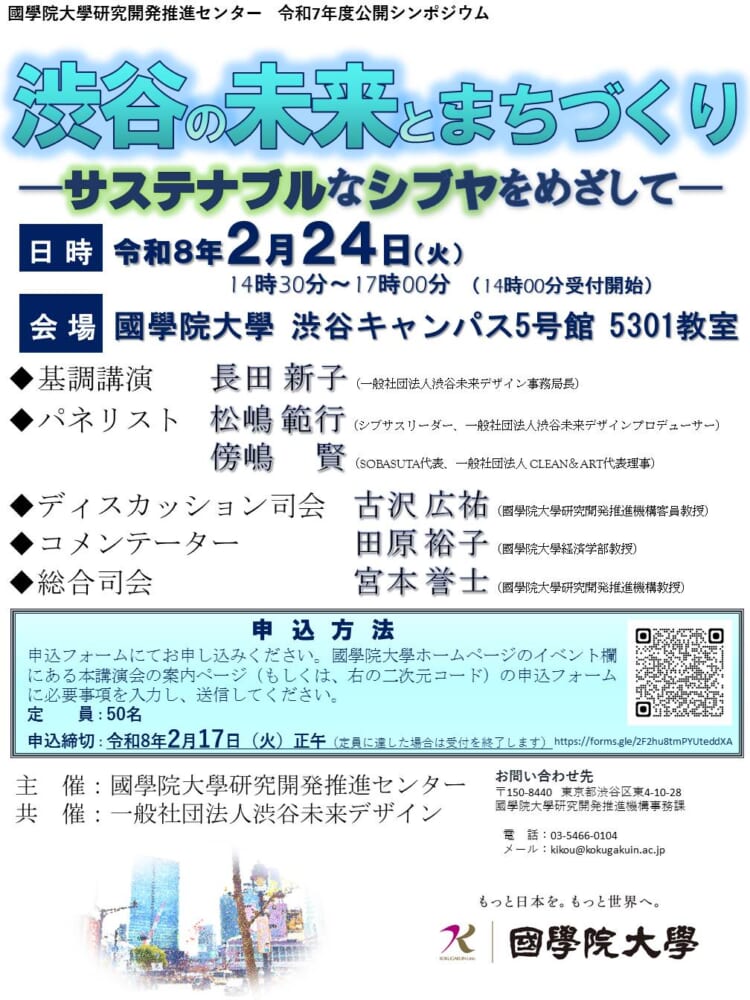哲学は「現実的」な学問なのだ、と彼は言う。決して机上の空論を振り回しているのではなく、自分自身の頭で考え、自分自身が変わっていく学問としての哲学――。
「性差」「人種」「親子」「難民」「動物の命」という5つのトピックが、新刊『現実を解きほぐすための哲学』(トランスビュー)で、小手川正二郎・文学部准教授が実際に取り組んでいる問題だ。「性差」については、近刊となる共著『フェミニスト現象学入門:経験から「普通」を問い直す』(ナカニシヤ出版、令和2(2020)年6月刊行)でも、さらに深く掘り下げている。
注目を集めつつある気鋭の哲学者へのインタビュー前編では、その探究の核に刻まれた「経験」の二文字が意味するところを、「性差」の問題を中心に尋ねた。
「性差」「人種」「親子」「難民」「動物の命」という5つのトピックが、新刊『現実を解きほぐすための哲学』(トランスビュー)で、小手川正二郎・文学部准教授が実際に取り組んでいる問題だ。「性差」については、近刊となる共著『フェミニスト現象学入門:経験から「普通」を問い直す』(ナカニシヤ出版、令和2(2020)年6月刊行)でも、さらに深く掘り下げている。
注目を集めつつある気鋭の哲学者へのインタビュー前編では、その探究の核に刻まれた「経験」の二文字が意味するところを、「性差」の問題を中心に尋ねた。
私が目下取り組んでいるテーマのひとつに、「性差」をフェミニスト現象学の立場から考える、というものがあります。
「フェミニスト現象学とは?」という疑問が皆さんの頭の中に浮かぶと思いますが、まずは、より一般的な観点から、徐々にお話しさせてください。
「フェミニスト現象学とは?」という疑問が皆さんの頭の中に浮かぶと思いますが、まずは、より一般的な観点から、徐々にお話しさせてください。

私は授業で、こんな自分自身の「経験」について、話をすることがあります。
たとえば、夫婦喧嘩。妻と言い争いをする中で、私は「稼いでいるのは俺じゃないか!」ということを口走ってしまったことがあります。
決して普段からそんなことを考えているわけではない(と自分では考えている)のですが、思わず零れ落ちてしまったこの言葉に滲んでいるのは、男性が仕事をして女性が家事をするという性別役割分業の価値観そのものですよね。ボーヴォワールが『第二の性』(1949年)の中で、男女平等を唱える男性でも妻と喧嘩するとこうしたことを口走る、といっているくだりそのままの「経験」です。
あるいは、私が大学の入試業務を担当したとき。一緒に担当した初対面の女性を、私は自分の補佐役だと思い込んでしまっていました。別の人が彼女に「先生」と声をかけて、同じ立場の方だったのだとハッと気づいた。「性差」について普段から教えている人間の、性差別的な「経験」でした。
たとえば、夫婦喧嘩。妻と言い争いをする中で、私は「稼いでいるのは俺じゃないか!」ということを口走ってしまったことがあります。
決して普段からそんなことを考えているわけではない(と自分では考えている)のですが、思わず零れ落ちてしまったこの言葉に滲んでいるのは、男性が仕事をして女性が家事をするという性別役割分業の価値観そのものですよね。ボーヴォワールが『第二の性』(1949年)の中で、男女平等を唱える男性でも妻と喧嘩するとこうしたことを口走る、といっているくだりそのままの「経験」です。
あるいは、私が大学の入試業務を担当したとき。一緒に担当した初対面の女性を、私は自分の補佐役だと思い込んでしまっていました。別の人が彼女に「先生」と声をかけて、同じ立場の方だったのだとハッと気づいた。「性差」について普段から教えている人間の、性差別的な「経験」でした。
こうした「経験」は、私個人に限らず、きっとそれぞれにあるはずです。その「経験」は、人が自分自身の物の見方を捉え直し、また他人の「経験」を理解するきっかけになるのではないか――。私は、そう考えています。
男子学生にフェミニズムの話をすると「今は女性のほうが生きやすい世の中じゃないか」という反応が返ってくることがあります。男女共同参画、そして女性活躍推進が謳われていて、むしろ男性より女性の方が得な面が多いのではないかという、バックラッシュ(揺り戻し)としての非難ですね。
世界経済フォーラムによる2019年度のジェンダーギャップ指数で、日本は153カ国中121位だったというデータからも、この批判はあたらないのですが、しかし頭ごなしに平等論を伝え、なぜわからないのかと迫るのでは、反発が強まることも少なくありません。
「性差」の問題に限らず、普段から学生相手に哲学や倫理学の授業をしている経験からいっても、これまでに研究者が論じてきた既存の議論——その多くが欧米から輸入された議論——を振りかざすだけでは、なかなか伝わらないものがあります。
男子学生にフェミニズムの話をすると「今は女性のほうが生きやすい世の中じゃないか」という反応が返ってくることがあります。男女共同参画、そして女性活躍推進が謳われていて、むしろ男性より女性の方が得な面が多いのではないかという、バックラッシュ(揺り戻し)としての非難ですね。
世界経済フォーラムによる2019年度のジェンダーギャップ指数で、日本は153カ国中121位だったというデータからも、この批判はあたらないのですが、しかし頭ごなしに平等論を伝え、なぜわからないのかと迫るのでは、反発が強まることも少なくありません。
「性差」の問題に限らず、普段から学生相手に哲学や倫理学の授業をしている経験からいっても、これまでに研究者が論じてきた既存の議論——その多くが欧米から輸入された議論——を振りかざすだけでは、なかなか伝わらないものがあります。

ひとつには、哲学の議論が現実の倫理的課題に対してどのように有効なのかがわかりにくい、という問題があります。同時に、それを説く教員自身も決して聖人ではないはずなのに、なぜそんなに正しい立場や中立的な立場を装えるのか、という疑念もある。私自身、そうした「上から」の議論が苦手だった学生でした。
「ひとりひとりが、自分事として考える」ということは、どのように可能なのか――。
社会を分断するこうした現実的な難題を解きほぐすために、私が有効だと考えている思考の出発点が、それぞれの「経験」です。
私が専門とする現象学という学問は、まずは私たち自身の「経験」に立ち戻って考えよう、という立場をとります。フッサールに始まり、ハイデガー、そして私が研究してきたレヴィナスなど、既に長い伝統のある学問です。
「性差」や「人種」といった問題でしたら、たとえば知らず知らずに男女や人種に相手を振り分けてしまっているとき、あるいはその人が男性的/女性的、あるいは●●人的だと感じてしまうときのような、自分自身の「経験」から物事を考えていく、ということですね。それによって、そうした経験に忍び込んでいる自分自身の偏見や見方の歪みを問題化していくことも可能になります。
フェミニスト現象学も、こうした立場のもとに発展してきた学問です。しかもそれは、現象学の代表的論者のひとりであるメルロ=ポンティの身体論に対しての、「経験」からの批判に端緒を発しています。
メルロ=ポンティの身体論では、月経や妊娠・出産といった女性の日常的な「経験」が例外的状況になってしまっていて、つまり扱われているのが男性的な身体であるにもかかわらず、それが中立的な身体として設定されている。ならば、女性たちが経験してきた身体経験(月経や妊娠出産)を現象学的に分析してみよう、ということでフェミニスト現象学は発展してきました。
「ひとりひとりが、自分事として考える」ということは、どのように可能なのか――。
社会を分断するこうした現実的な難題を解きほぐすために、私が有効だと考えている思考の出発点が、それぞれの「経験」です。
私が専門とする現象学という学問は、まずは私たち自身の「経験」に立ち戻って考えよう、という立場をとります。フッサールに始まり、ハイデガー、そして私が研究してきたレヴィナスなど、既に長い伝統のある学問です。
「性差」や「人種」といった問題でしたら、たとえば知らず知らずに男女や人種に相手を振り分けてしまっているとき、あるいはその人が男性的/女性的、あるいは●●人的だと感じてしまうときのような、自分自身の「経験」から物事を考えていく、ということですね。それによって、そうした経験に忍び込んでいる自分自身の偏見や見方の歪みを問題化していくことも可能になります。
フェミニスト現象学も、こうした立場のもとに発展してきた学問です。しかもそれは、現象学の代表的論者のひとりであるメルロ=ポンティの身体論に対しての、「経験」からの批判に端緒を発しています。
メルロ=ポンティの身体論では、月経や妊娠・出産といった女性の日常的な「経験」が例外的状況になってしまっていて、つまり扱われているのが男性的な身体であるにもかかわらず、それが中立的な身体として設定されている。ならば、女性たちが経験してきた身体経験(月経や妊娠出産)を現象学的に分析してみよう、ということでフェミニスト現象学は発展してきました。

私自身、フェミニスト現象学に感化され、そこからさらに男性たちの身体経験について考える、ということに取り組んでいるところです。たとえば「男らしさ」というものについて男性たち自身がどのように感じ、縛られているのか、という「経験」ですね。冒頭で述べた私の「経験」は、まさに「男らしさ」という価値観や規範に私自身が影響を受けていることを、考え直させてくれます。
こうした角度でしたら、授業における学生の目も変わってきます。単に哲学者たちの話をしているのではない。実際に学生たち、ひとりひとりの「私」の「経験」について分析していくということですから、伝わり方が違います。性に対する支配的な見方——男性と女性という二つだけで考えたり、異性愛を「普通」とみなしたり、生まれつき自分の性が生物学的に決められているとする見方——にこれまで疑問を抱いてこなかった学生も、逆に違和感を感じる学生も、そうした支配的な見方にどこまで自分の経験がひきずられているか、そしてそこから批判的な距離をとりうるかを考えてくれるようになります。
一方で私はかつて、こんなに現実的・倫理的な課題に取り組む人間ではありませんでした。それがなぜ、こうした実践的な研究にのめり込むようになったのか。そもそも、どうしてこのような問題について、私たちは考える「責任」があるのか……学問的な背景、そして「性差」以外のテーマも含めて、後編でお伝えしたいと思います。
こうした角度でしたら、授業における学生の目も変わってきます。単に哲学者たちの話をしているのではない。実際に学生たち、ひとりひとりの「私」の「経験」について分析していくということですから、伝わり方が違います。性に対する支配的な見方——男性と女性という二つだけで考えたり、異性愛を「普通」とみなしたり、生まれつき自分の性が生物学的に決められているとする見方——にこれまで疑問を抱いてこなかった学生も、逆に違和感を感じる学生も、そうした支配的な見方にどこまで自分の経験がひきずられているか、そしてそこから批判的な距離をとりうるかを考えてくれるようになります。
一方で私はかつて、こんなに現実的・倫理的な課題に取り組む人間ではありませんでした。それがなぜ、こうした実践的な研究にのめり込むようになったのか。そもそも、どうしてこのような問題について、私たちは考える「責任」があるのか……学問的な背景、そして「性差」以外のテーマも含めて、後編でお伝えしたいと思います。
小手川 正二郎
研究分野
フランス近現代哲学、現象学
論文
「フェミニズムの哲学」が可能だとしたら、それはどのようにしてか?(2021/05/01)
難民の哲学―定義や条文解釈をめぐる議論に何が欠けているのか(2021/03/01)