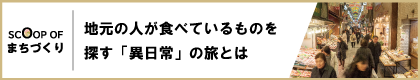- 國學院大學
- 教育
- 学部・学科
- 観光まちづくり学部
- 観光まちづくり学部について
- SCOOP OF まちづくり
- 食文化の本質とは何か 最新の取り組みとは
食文化の本質とは何か
最新の取り組みとは
2025年4月23日更新

観光に欠かせない重要な要素のひとつである「食」について、食文化の本質を押さえつつ、農業や漁業など第一次産業の実際も踏まえて「食の向こう側」を見る。観光における食の在り方について考えるのが「観光食マネジメント論」です。
観光食の価値を高める食材のストーリー

阿蘇の広大な草原の中で育つあか牛
地域の伝統食、B級グルメ、お土産など「食」は観光にとって重要な資源です。このような観光食について、食材はどこから調達しているのか、誰がどのような想いで料理をしているかなど、食の向こう側を知ることが「観光食マネジメント」では重要です。例えば、熊本県阿蘇で今話題となっている「あか牛」。阿蘇の広大な草原でのびのび放牧されているあか牛は、黒毛和牛と異なり、赤身が多いため旨味とやわらかさを兼ね備えた味わいが特徴です。長い年月をかけて改良を重ね、阿蘇の草原に適したあか牛が阿蘇の風景を構成する要素にもなっています。このような食材のストーリーを知ることで観光食としての価値は高まるのです。
食の向こう側を見る

食材、食器、サービスなども観光食マネジメントでは多角的に考察する
温泉地の旅館などの宴会料理では、よく固形燃料が使われています。これは、大人数の料理を用意し、その場で温めるために用いられた一つの発明でしたが、団体型旅行が華やかな頃の名残です。また、天ぷらは本来、目の前で揚げた熱々のものを冷たい天つゆにつける食べ物でしたが、いつしか、冷たい天ぷらを温める天つゆが必要となりました。
食文化の本質を押さえつつ、観光における最新の取り組みも学び、食の向こう側を見る。それが、観光食マネジメントを考える第一歩です。
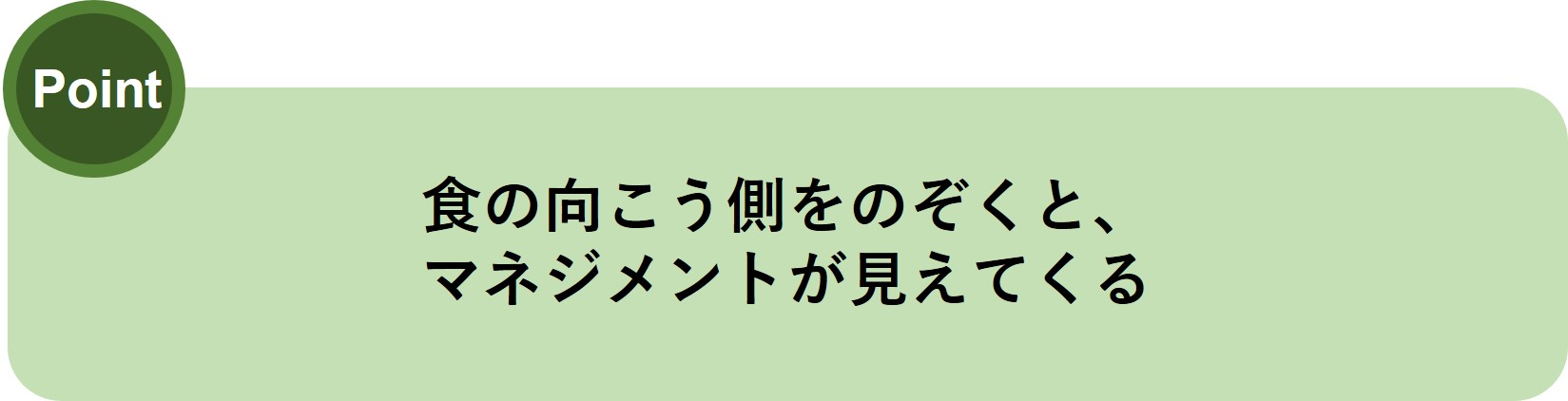
教員プロフィール
観光政策、観光まちづくり、観光産業、地域政策、移住政策
この教員の他のコラムを見る
このページに対するお問い合せ先: 観光まちづくり学部
RECOMMENDS
-
{{settings.title}}
{{settings.lead.title}}
{{{settings.lead.letter}}}
{{pages.title}}
{{articles.title}}
Language
SEARCH
{{section.title}}
-
{{item.tagline}}