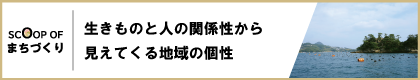- 國學院大學
- 教育
- 学部・学科
- 観光まちづくり学部
- 観光まちづくり学部について
- SCOOP OF まちづくり
- 希少な生物の野生復帰を支える地域の生態系と人々の営み
希少な生物の野生復帰を支える地域の生態系と人々の営み
2025年4月23日更新

地域の自然環境は人間の営みに影響を及ぼし、人間の営みは自然の姿を変えていきます。自然と文化が相互に作用していることを意識して地域を見つめると、その個性がいっそう際だって見えてきます。
相互に作用する自然と文化の多様性

トキで知られる新潟県佐渡島の水田。何気ない風景にも地域の人と自然の関わり方が表れる。
観光の魅力となる地域個性の側面から自然環境を捉えたとき、人為の影響が少ない原生的自然を保全することはもちろん大切ですが、人が手を加えることで維持されてきた二次的自然もまた、地域個性を伝える上で重要な要素です。中でも里地・里山と呼ばれる環境は水田をはじめとする農地周辺に薪炭林や溜め池・用水路など多様な空間が組み合わさり、生態系としても複雑な表情を見せます。どんな空間がどのように組み合わさっているかはその地域での暮らしぶりを反映したものであり、その多様性に富む姿は自然と文化が相互に作用した結果だと言えるでしょう。
特定の生物種の保護から生態系全体の維持管理へ

水鳥の保全のためにも生息環境そのものの維持管理が重要。(写真は葛西臨海水族園のクロツラヘラサギ)
かつては日本各地で普通に見られ、近年になって大きく個体数を減らした生きものたちがいます。トキなどの水鳥は代表的な例でしょう。日本国内では一度姿を消した後、佐渡島で人工繁殖させた個体の野生復帰の取り組みが進められ、現在は野外の環境下で一定の個体数が維持されています。こうした取り組みでは「個体数を増やすこと」はもちろんですが、同時にこれらの生きものが暮らせる環境(トキの例で言えば質の高い餌場となる水田や、安全なねぐらや営巣場所となる林地など)をトータルで維持することが重要です。この環境は地域の人々の暮らしぶりを反映したものであることから、トキという一つの生物種を守る取り組みの裾野がとても広く、生態系をはじめ歴史や文化、産業といった地域の個性につながる様々な要素を見つめ直すことにもつながることが理解できるでしょう。
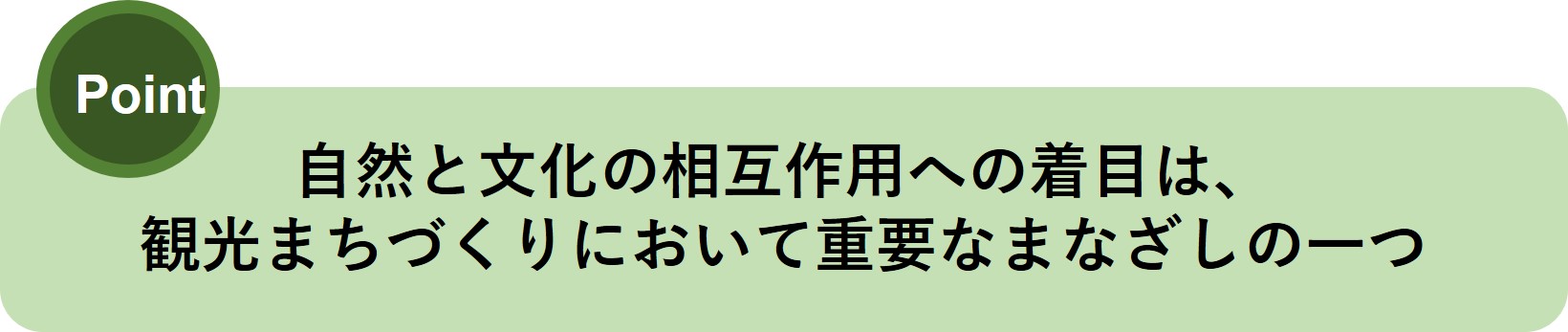
教員プロフィール
造園学、観光計画、観光行動、観光資源管理
この教員の他のコラムを見る
このページに対するお問い合せ先: 観光まちづくり学部
RECOMMENDS
-
{{settings.title}}
{{settings.lead.title}}
{{{settings.lead.letter}}}
{{pages.title}}
{{articles.title}}
Language
SEARCH
{{section.title}}
-
{{item.tagline}}