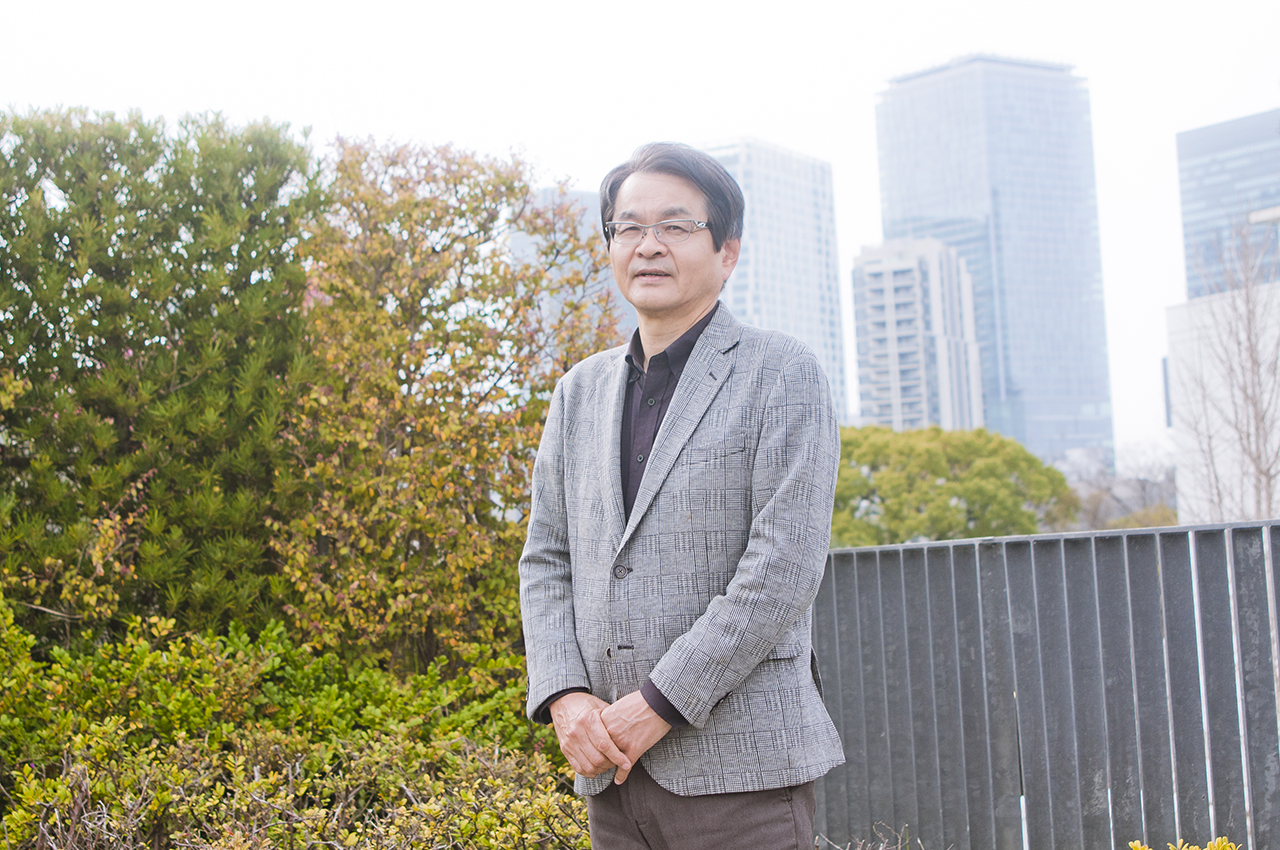
あの街からは、新たなビジネスが次から次へと生み出されている──そんな都市の姿を、ここ日本でも多くのビジネスパーソンが夢見ている。その夢を現実のものとする手がかりになりそうなのが、小野正人・経済学部教授のアプローチかもしれない。
新たな企業が続々と生まれていく背景には、そのエコシステム(=生態系)を成り立たせる歴史があり、社会構造が大きな役割を果たしているのではないかと小野教授は語る。大事なことは「温故知新」。小野教授へのインタビュー後編で、アメリカを中心に200年以上にわたるベンチャービジネスの歴史をひもときながら、未来へのヒントを探ってみよう。
私が特に力を注いでいるのは、「新企業を輩出するシステムはどのように形成・発展してきたのか」という研究です。新企業が続々と生み出されていくためには、それを可能にする社会構造が存在する。特にアメリカのベンチャービジネスにおける起業家と投資家の発展の軌跡を考察してきました。ここですこし、その歴史の一端をご紹介してみましょう。
新しく会社を興すには相当な資金が必要ですが、20世紀初頭までの起業をめぐる事情を調べてみると、リスクのあるビジネスに金を出すような人々はほとんどいなかったことがわかります。起業家が頼りにするのは自分自身か親戚や知人といったところであり、どこの国でもだれでも「個人の力とツテ」で事業を始めるしかなかったのです。

当時の「リスクのある大事業」というのは、たとえば自動車や映画といった産業が挙げられます。フォード(1903年創業)、ウォルト・ディズニー(1923年)といった企業がその代表的な存在ですね。ほかにも電機や航空機などが新たな産業として興りましたし、今日広く知られるIBM(1911年)やボーイング(1916年)もこうした流れのなかで生まれた会社です。
新しい事業においては、起業家に資金を提供し共に事業を立ち上げていく「リスクキャピタル」(=リスクを積極的に取る投資家)が必要です。特に多額の資金を要するハイテク事業は起業家だけで事業を行うことは不可能です。
このリスクキャピタルは20世紀初頭のアメリカで生まれました。中心となったのがロックフェラー家やホイットニー家などのアメリカ東部の富豪たちでした。航空機や映画産業を立ち上げるための資金、たとえば世界初飛行を実現したライト兄弟やハリウッド映画『風と共に去りぬ』の開発資金は彼ら富豪の個人投資によって支えられていました。
アメリカのリスクキャピタルの中心は、第二次大戦後から20世紀後半に東部から西海岸へと中心を移し発展していきました。多くの半導体メーカーが集ったことでシリコンバレーが形成されていった時期です。
リスクキャピタルの中心となったのがベンチャーキャピタルという専門の投資機関です。かつての富豪による個人支援ではなく、組織的にお金を出す仕組みと投資手法が進化していったわけですね。専門的にいえば、リミテッドパートナーシップという責任・利益分配を定めた組織設計やポートフォリオ長期分散投資といった新しい技術とノウハウが蓄積されていきました。シリコンバレーの発展はベンチャーキャピタルの発展なしには考えられなかったといっても言い過ぎではありません。
21世紀以降、世界各国でベンチャーキャピタルは大きく成長して巨大な投資組織となっており、2023年末の運用資産は約1兆8500億ドル(約270兆円)で、その7~8割はアメリカに集中しています。一方で欧州、中国やインドなどのハイテク産業地域でもベンチャーキャピタルが成長していますし、ここ日本でも1970年代にベンチャービジネスへの関心が生まれてから半世紀の時間を経てようやく環境が整ってきました。
20世紀半ばからアメリカにおいて、大規模かつハイリスクなベンチャー投資が、多様な金融手法の開発や改善によって可能となり、その結果、新企業を輩出するシステムが形成されてきたのは、ここまで見てきた通りです。「危険なスタートアップに合理的に対処できる」仕組み、すなわち「スタートアップ・エコシステム」は一朝一夕では成立せず、アメリカでも数十年にわたる長い時間をかけて形成され発展してきてきました。日本ではエコシステムのような考え方はなかなか取り上げられませんでしたが、最近10年で急速に広がって浸透しており、政府の文書でもエコシステムの役割を強調するようになっています。

駆け足ではありますが、アメリカを中心にベンチャービジネスとベンチャーキャピタルの歴史を振り返ってみました。新企業を輩出するシステムというものは、長い時間をかけて形づくられていくことが、皆さんも実感されたことと思います。
私が研究を続けるなかで長く仮説として想定してきたのも、こうした長い時間をめぐる考えなのです。すなわち、「新企業を輩出する要因とは、政策・金融・技術を短期間で整備すれば効果が表れるものではなく、地域の歴史的な時間軸のなかで形成されたものである」という考えですね。インタビューの前編から話してきた社会構造というのはそれぞれの地域の歴史的な時間軸にかかわるものであり、この仮説は現時点でもおおむね正しいのではないかと思っています。
私がこのようなテーマに関心を抱くようになったのは、1995年にたまたまシリコンバレーに位置するスタンフォード大学に留学することになったことがきっかけでした。そこでは、新たな事業を興す起業家たち、そして新企業を生み出す地域コミュニティというものが存在しており、私が体感したのはまさにエコシステムを有したコミュニティのありようでした。各地で開催される新技術やビジネスに関するミーティングにベンチャービジネスの起業家達が登壇し、会場のあちこちから質問を受けていました。GoogleやTwitterの創業者も聴衆の中にいたことを後で知りました。
忘れられないのは、当時メンローパークにある日本食レストランで食事をしたときのことですね。ふと目をやると、カウンターにスティーブ・ジョブズが寿司をつまんでいる(笑)。彼がAppleに復帰する直前の1996年のことです。こうした起業家、時代を画するパイオニアたちがごく近い距離で日々を過ごしているコミュニティこそが、新企業を生み出していくバックグラウンドとして重要なのではないかと、現地研究をするなかで仮説が確信に近づきました。もちろん現在では当時のシリコンバレー神話は半ば崩壊していますし、所得格差の拡大や地価・物価の高騰のような弊害も取りざたされるようにはなっていますが、新企業を輩出するシステムの形成・発展という点において地域コミュニティという視点は重要であり続けるでしょう。
國學院大學のキャンパスが位置する渋谷区も、ベンチャービジネスの拠点として注目を集めています。ベンチャーキャピタルも渋谷や近くの麻布台に集積しています。私は、「渋谷という多様で開放的なコミュニティ」という視点が、新ビジネスが数多く立ち上がり成功するためには欠かせないと思います。新しいことをしたいと思う若者が渋谷を目指して集まり、大学で学び、街で刺激を受け、新しい出会いが生まれるようなコミュニティになっていくことを期待したいと思います。
<<前編は「新企業創出における地域コミュニティの役割」
| 1 | 2 |
小野 正人
研究分野
アントレプレナーシップ、ベンチャーファイナンス、イノベーション教育、経営教育、企業分析
論文
再考 ベンチャービジネスの形成と発展 ー戦後から1970年代までー(2025/03/30)
(研究ノート)ドイツ実業教育の変化に関する一考察(2024/03/25)


