
新たに事業を立ち上げるということは、本来とても幅の広い営みだ。生き馬の目を抜くようなビジネスの世界のみに限った話ではなく、わたしたちの生活のなかにも、新事業の創造の種はあり、その芽を地面から覗かせている。
そのことが、「アントレプレナーシップ」を専門とする小野正人・経済学部教授の話を聞いているとよくわかる。最新のテクノロジーをもとに起業することも、課題を抱える地域のために奔走することも、同じ地平で眺めることによって、見えてくるものがあるのだ。前後編のインタビューでその可能性を一緒に探索してみよう。
私が専門的に研究しているのは、アントレプレナーシップというものです。これは文脈や人によってさまざまな意味合いをもつ言葉ですが、ここでは「新しい事業を創造する意志と諸活動」という意味で理解していただければと思います。このアントレプレナーシップは──たとえ耳馴染みがないという人であっても──現代社会に暮らす多くの方々にとって重要なものであるはずだと、私は考えているのです。
アントレプレナーシップという概念が含む活動は広範囲にわたります。わかりやすいところでいえば、スタートアップやベンチャー企業、あるいはベンチャービジネスと呼ばれている、起業者たちによる新しいハイテク企業の活動を挙げることができます。
現在広く知られている大企業も、もともとはスタートアップだったという例が多くあることはご存知の通りです。アメリカであればGAFAM(Google、Apple、Facebook、Amazon、Microsoft)、日本国内ならば楽天グループやディー・エヌ・エーですね。こうした企業は、第四次産業革命(インダストリー4.0)とも呼ばれる時代を象徴する存在です。世界各地でインターネット、ブロードバンド、モバイル、DXなどの新技術が生まれ、その領域で産声を上げた新しい企業が、革新的な製品サービスを市場に普及させて巨大企業に成長し、経済社会を牽引しています。今世界中で注目を浴びているAI(人工知能)には年間10兆円を超える資金がスタートアップに投資されていますから、これからも驚くような企業が生まれてくるでしょう。
一方で私は、こうしたハイテク企業を興すことのみが、アントレプレナーシップではないとも思います。もちろん最先端のテクノロジーを用いたビジネスは非常に意義深いものですが、それと同時に、アントレプレナーシップはより幅広い分野にひろがるべきであり、各所で新しい価値を創出する活動が重要になっていくと考えているのです。
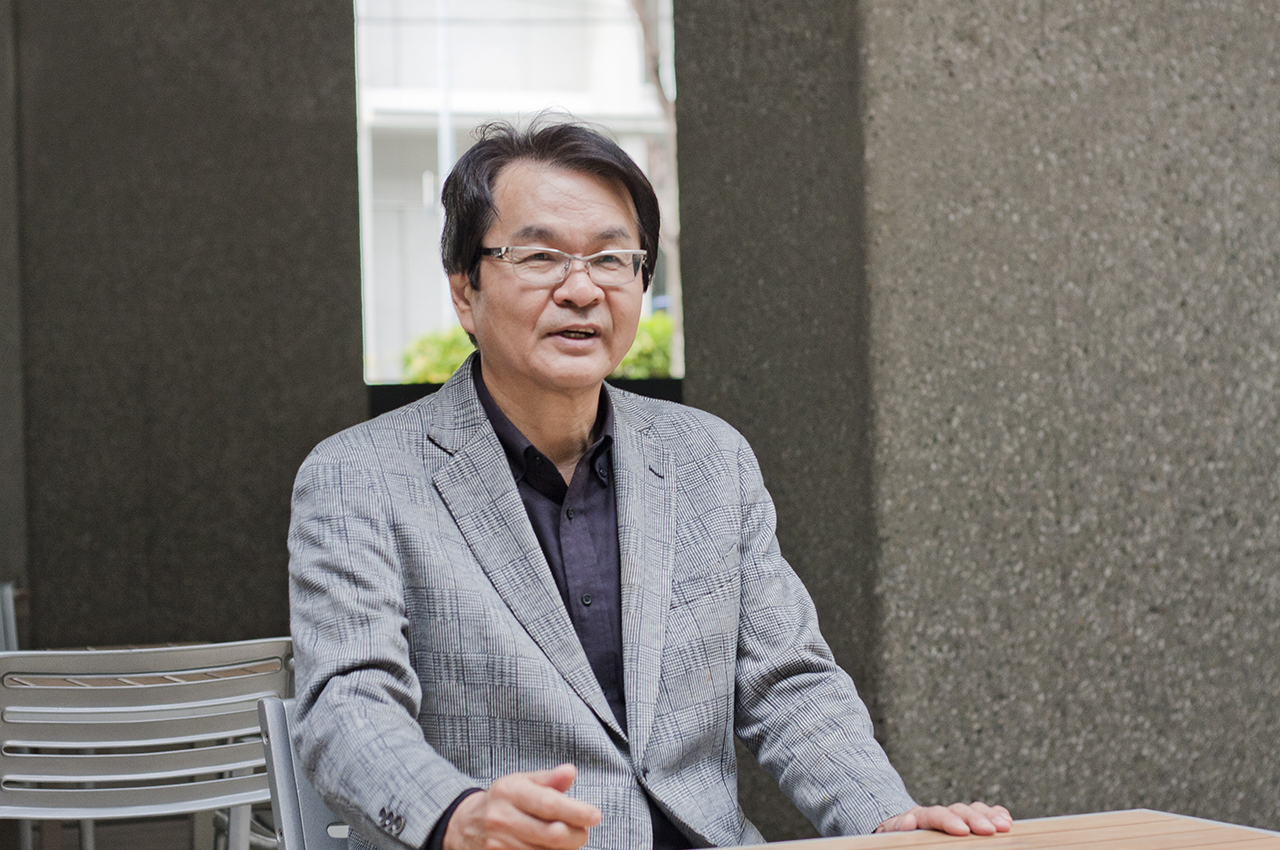
地方をはじめとした公的な組織においては、高齢化・人口減少社会・地方再生といった課題に対応した新しい仕組みや事業を創り出していく必要があります。たとえば、地方でシャッターが軒並み閉まっているアーケード商店街の再生といった事例もアントレプレナーシップの一環としてとらえることができる。あるいは、いま震災と豪雨の被害からの復興を目指す能登という地域に寄り添う、そして再生のための持続的な活動というものはどのようにして実現可能なのか。さらにいえば、大企業においてもベンチャービジネスを活用して新事業に取り組むコ-ポレート・ベンチャリングという手法が浸透しています。そうした各所で新しい課題に取り組む仕組みや事業を創り出していく行動もまた現代的なアントレプレナーシップだと私は考えています。
したがって、新しい事業を創造することについて来たる世代に伝え教えるアントレプレナー教育は、ハイテク企業で働くためだけではなく、広く大学生のキャリア教育と連関することが望ましいのです。大学生のみならず高校生であっても、自分で新たに事業を興したい、あるいは父親の会社を継ぐけれども何か新しいビジネスを起こしてみたい、という思いを抱く人の話は最近よく耳にするようになりました。私がアントレプレナー教育に携わる場合も、念頭にあるのはこうした若い世代の人々です。
そもそも、昭和の時代とは将来のキャリアに対する思いがまったく異なります。できるだけ大きな企業に就職して、それから定年まで勤めあげるというようなビジョンを描く人はどんどん少なくなっている。変動著しく将来を予知できない現代社会で数十年にわたるキャリアを構築していくことになる人たちにとって、アントレプレナーシップを学ぶことは、リスクを合理的にとらえて対処する重要性を理解し、その能力を習得する機会につながるものだと考えます。

さて、だいぶ話が先に進みましたが、ここでアントレプレナーシップの根本に、今一度立ち戻ってみたいと思います。
現代において重要性をもつアントレプレナーシップを探求するにあたっては、大きく分けて4つのアプローチがあるのではないかと思います。
まずは、経営学的なアプローチ。読んで字のごとく、スタートアップやベンチャーと呼ばれる企業の経営はどのようにすれば上手くいくのか、経営学の視点から考えていくというものです。従来の大企業の経営を分析するように、事業計画などを分析していくわけですが、たとえば経営組織論からみれば、既存の大規模な組織を分析するのと、少人数での起業を分析するのでは当然視点は異なってきます。また企業金融の側面からは、事業を発展させていくための資金調達というのも、スタートアップやベンチャーにとって重要なトピックです。
次に、広範囲のアントレプレナーシップの研究。先ほど述べた通り、既存の大企業や中小企業や地域において新しい事業創造のありようを探るものです。産業復興や地域再生にアントレプレナーシップの視点が必要になっているからです。
そして、人材教育です。新事業に取り組むためのアントレプレナー教育の価値が高まり、世界各地の大学やビジネススクールで講座が増えています。東大が70年ぶりに作る新学部「カレッジ・オブ・デザイン」も新たな価値の創出と社会課題解決をミッションにしており、起業家教育と同軸の発想と思います。
私はこれら3つの観点にも興味・関心を抱き、部分的に取り組んできているのですが、重点的に研究を進めているのは、もうひとつのアプローチです。
傾注してきたその問いを一言で表すならば、「新企業を輩出するシステムはどのように形成・発展してきたのか」というものになります。アントレプレナーシップの推進を可能にする社会構造を歴史的な観点から掘り下げていく-アメリカを中心に考えてきた研究-その詳細については、インタビューの後編で話を続けます。
後編は「新企業創出における地域コミュニティの役割」>>
| 1 | 2 |
小野 正人
研究分野
アントレプレナーシップ、ベンチャーファイナンス、イノベーション教育、経営教育、企業分析
論文
再考 ベンチャービジネスの形成と発展 ー戦後から1970年代までー(2025/03/30)
(研究ノート)ドイツ実業教育の変化に関する一考察(2024/03/25)


