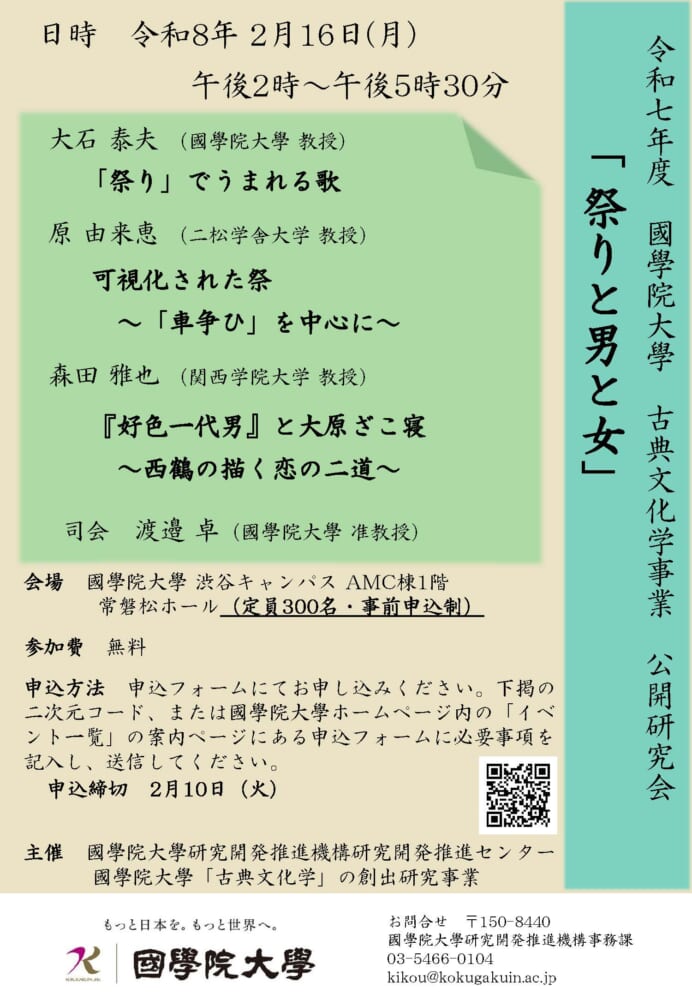レオナルド・ダ・ヴィンチをはじめとして、人々の創造性が開花した時代として、私たちはルネサンスのことを知っている……つもりだ。当時生み出された芸術作品の数々を、脳裏に思い浮かべることができる人もいるだろう。
しかし美学を専門として、ルネサンス時代のことを研究している岡本源太・文学部哲学科教授の話を聞いていると、既知のものであったはずのその時代が、改めて斬新なものとしてにわかに立ち上がってくる。岡本教授自身も驚嘆させられるという、当時の大胆な発想とは──。インタビューの前後編で繙(ひもと)いていく。
哲学のなかでも美学という学問を専門にしながら、おもに西洋ルネサンスと現代の事例を中心に研究を進めています。美学とは、さしあたっては芸術についての哲学でして、より専門的には「感性」の哲学的研究となります。では、なぜ芸術を哲学するのか、それによって何が分かるのか、これからその一端をお伝えしましょう。
ルネサンス時代にかんして、美術史の観点で芸術作品を研究する学者は日本にも多くいますし、美術史の研究に読者の皆さんも馴染みがあるかもしれません。一方で、哲学ないし美学を足場にしながらルネサンス時代を研究する学者は、さほど多くはありません。あとでまた触れますが、ルネサンス哲学には他の時代にはない独特の難しさがあります。ルネサンス時代とは、芸術家たちがただ作品を作るだけでなく、なぜどのように作るのかを理論的に、哲学的に、考えるようになった時代です。同時に哲学者たちも、思索するにあたってしばしば芸術の比喩を使用しました。いわば、芸術そのものが哲学化した時代なのです。

たとえば、ルネサンスに発明された絵画技法の一つに、いわゆる遠近法があります。正確には線遠近法と呼んだりしますが、これは、たんにリアルな見た目に描ける技法といったものではありません。遠近法の根本にある思想はもっと複雑です。
アルベルティは、『絵画論』(1435年)において初めて遠近法を理論化した万能人として知られています。彼はこの著作のなかで、遠近法によって描く絵画のことを「開かれた窓」と表現しています。この表現は、後世にはひとり歩きして、まるで窓から風景が見えるごとく絵画には自然そっくりの世界が描かれるのだといっているかのように理解されてしまってもいるのですが、それはアルベルティ自身の考えとは違います。
彼によれば、絵画という窓を通して見えるのは、自然ではなく物語です。絵画を窓になぞらえたのは、制作の最初に枠を決める必要性を説くためでした。窓のような有限の枠で画面を囲み、枠内に理論上は無限の奥行きをもつ空間を描きます。その空間が物語の舞台になります。遠近法による絵画は、そのようにして物語を見せるものなのです。

ルネサンス時代の線遠近法の例:ピエロ・デッラ・フランチェスカ《キリストの鞭打ち》(1453-1460年頃)[岡本源太撮影]
ここからはいくつもの興味深い美学的な問題が出てきます。思いつくままに挙げてみましょう。まず、なぜ物語を描くのに遠近法を使用するのでしょうか。なぜ遠近法を使用して描くものが物語なのでしょうか。それは、遠近法によらない絵画、中世のいわば記憶術的な絵画の物語と、どう違うのでしょうか。そして、有限の枠内にある無限の空間、というのは人間の視覚とも地球の形態とも一致しませんから、どうやってそのような非現実的な絵画を考案したのでしょうか。この時代の世界観はまだアリストテレス自然学が主流ですので、無限空間の概念が存在していません。それはアルベルティから百年以上も経って、ルネサンス最後の哲学者ジョルダーノ・ブルーノが初めて提起した考えです。
ほかにも、ルネサンス建築の窓やルネサンス演劇の物語との関わりなども問題にすべきでしょう。ともあれ、遠近法というルネサンス絵画を特徴づける技法ひとつとっても、美学において問うべきテーマが見いだされます。こうしたことを考えるには、もちろん美術史も勉強しなければいけないのですが、私は同じ芸術を探究しながらも、歴史面よりは思想面にいっそう興味を抱いて研究しているのですね。

ルネサンスの芸術には、今とは異なる、ときには突拍子もないほど新鮮な、世界や人間についての哲学が見いだせます。レオナルド・ダ・ヴィンチの万能ぶりはほとんどの皆さんがご存じだと思いますが、ルネサンス時代では芸術家と科学者が今日のように区別されはしませんし、現代とは思考の枠組みそのものが違うのですね。もちろん、現代の日本も明治以降の近代化のなかで西洋からの影響を大きく受けていますから、特に背景を知らずにその絵画を見ても、シンプルに「綺麗だな」と感じられるでしょう。しかし、背景となっている思想は、実はあまり馴染みがないものです。
またひとつ具体例を挙げるなら、レオナルドは、絵画の着想を得るためには壁の染みや燃え残った灰、雲、泥といったものを眺めるといい、と述べています。マンテーニャという画家の《美徳の庭から悪徳を追い払うミネルウァ》(1499-1502年)や《聖セバスティアヌス》(1456-59年)といった絵画では、背景の青空に浮かぶ雲が人間の顔や騎士の姿になっていたりもします。空を見上げて雲が何かの形に見えた経験は、皆さんもおもちでしょう。レオナルドやマンテーニャの念頭にあったのは、ひとまずは、今日の私たちには面白い錯覚だと思えるそうした事象です。

アンドレア・マンテーニャ《美徳の庭から悪徳を追い払うミネルウァ》(1499-1502年)から、背景の青空に浮かぶ雲[岡本源太撮影]
ところがこれは、ルネサンスの芸術家たちにとっては、自然と芸術の関係、さらには人間と神の関係を示すものだったのですね。自然がすでにさまざまな造形を生み出していて、そこに人間の芸術がいわばその跡を追って作品を作り出します。ルネサンス時代になると、この自然と芸術の関係が、模倣から競争へと変わり始めます。人間の顔をした雲を描くマンテーニャ、雲や泥や灰から次々と新しい着想を引き出すレオナルドには、そうした自然への競争意識が現れ始めています。
このような意識は、神がこの自然世界を創造したという、独特の神話をもつ西洋ならではのものでしょう。自然とは神による芸術作品であり、その自然と競争することによって人間は神に倣おうとするのです。神のごとき芸術家、創造者としての人間、という発想の登場です。

ルネサンス時代の絵画を哲学することには、こんな知的な楽しさがあります。インタビューの後編では、一般的に抱かれているルネサンス時代のイメージではなかなか捉えきれない、当時の発想の面白さについて、引き続きお話ししてみましょう。
後編は「再生としての、あるいは危機としてのルネサンス時代?」>>
| 1 | 2 |
岡本 源太
研究分野
美学、哲学、芸術学、西洋美術史
論文
パオロ・ウッチェッロを見るアンドレ・ブルトン――ルネサンスに照らされたシュルレアリスム絵画(2023/08/)
ルネサンスの宗教論と多様性の問題――マキアヴェッリ、ピーコ・デッラ・ミランドラ、ジョルダーノ・ブルーノ(2022/11/)