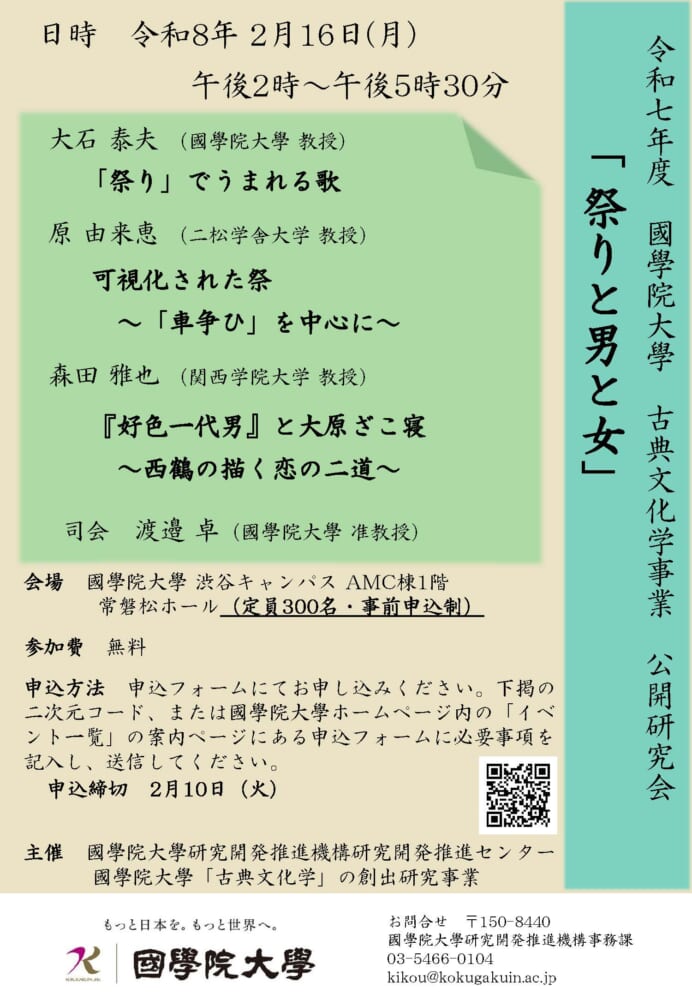かつて中学や高校の歴史の授業で習った、ルネサンス時代。その教科書的なイメージをとうてい収まりきらないような、当時の斬新な発想の数々に、岡本源太・文学部哲学科教授はいつも驚かされるという。
それまでの知の体系が通用しなくなった時代に、どんな思想が生まれたのか。新たな時代に向かうなかで古代ギリシア・ローマの文化を再生しようとしたルネサンス時代の人々の、アナクロニズム(時代錯誤)ともいうべき発想は、現代にどんな問いをもたらすのか。ハッとする瞬間に満ちた、いわば「ルネサンス時代(再)入門」といえるインタビューとなった。
ルネサンス時代のもっとも一般的な語られ方は、「近代の始まりの時代である」、というものかもしれません。古代ギリシア・ローマの文化を復興する人文主義運動のなかで、人間の尊厳、さらには個人の価値が見いだされていった──というイメージですね。
こうしたルネサンスのイメージは、19世紀の歴史家・美術史家のブルクハルトが提起して広まったものです。実は、今日では専門家ほどこのイメージに批判的だったりするのですが、それでも、人文主義者ヴァッラから芸術家ヴァザーリまでルネサンス時代の人々自身が「再生」を語ったことは事実です。そして、ブルクハルトのルネサンス理解もけっして単純なものではなく、彼はこの驚くべき「再生」の時代がまた同時にかつてない「危機」の時代でもあったと見ていました。
美学も含めた哲学の見地からルネサンス時代を眺めてみると、たしかにこの時代はこのうえない知的危機に直面していたでしょう。中世以来のキリスト教的な世界観では理解しがたいもので溢れかえったのが、この時代のヨーロッパでした。

人文主義運動によってキリスト教以前の異文明が発掘されましたし、また大航海時代でもありますから、安土桃山の日本も含めてヨーロッパの外部から異文化が流入してきます。さらにはレオナルドやコペルニクスやガリレイらによって数々の科学的発見が相次ぎ、その後の科学革命につながっていきました。ルターらによる宗教改革も起こり、ついには中世ヨーロッパの知的秩序の基礎であったキリスト教自体が分裂してしまいます。
世界も人間も、もはやこれまでの言葉や概念で説明できなくなってしまった――そのなかで、ルネサンス時代の人々は無数の試行錯誤を繰り返すことになります。それらがすべて新しい近代文明につながったわけではありません。それどころか言葉も概念も混乱していて、まったく支離滅裂に思えるものも少なくない。中世スコラ学の精緻な討論や近世デカルト主義の明晰な考察に慣れていると、ルネサンス時代の思想はまさに渾沌そのものです。ここに、ルネサンス哲学研究特有の難しさがあります。
しかしそれだけに、他の時代にはない、驚嘆すべき斬新な発想に満ちてもいます。「この世界は自分が思っていたようなものではなかった」と気づいたときにどれほど困惑するか、想像してみてください。そのとき、それでも世界をなんとか理解しようとしたルネサンス時代の知的努力を支離滅裂だと笑うことは、誰にもできないはずです。むしろ、この「危機」をかえって「再生」だと感じたルネサンス時代の知的な逞しさを思うべきでしょう。
ジョルダーノ・ブルーノは、こうしたルネサンス時代の思想的な試みを、もっとも徹底的に追求した哲学者のひとりといえます。彼はコペルニクスの地動説を大胆に発展させて、無限宇宙論と複数世界論を提唱した人物です。
ブルーノによると、宇宙は無限であり、世界は無数にあり、そのような無限のものを説明し尽くすことのできる完璧な言葉や絶対的な概念は何もありません。言葉も概念もすべて、時と場に応じた相対的なものでしかないからです。しかし、そうした相対的な言葉や概念が時と場に応じてのみ適切なものたりうるのなら、いかなる言葉も概念もそれ相応の仕方でなにがしかを理解させてくれるものでありうるでしょう。だから、無意味なものなど何ひとつない――。
いかにもブルーノらしい逆説に満ちた発想の転換ですが、読者の皆さんは話についてこられたでしょうか。世界を完全に理解することなどできないからこそ、あらゆる不完全な理解に意味がある、というのです。ブルーノはこれを肖像画に喩えています。全身を描かずとも、顔だけ描けば十分に肖像画になるのです。
ちなみにブルーノは、異端審問を受けて最後は火炙りにされた人物としても知られています。彼の哲学がキリスト教カトリックの正統信仰と相容れないとして、教会から弾圧されたのです。キリストの受肉やマリアの処女懐胎などの神秘を認めなかったことが直接的な理由になったとはいえ、たしかに、あらゆる言葉を相対化しながらそのすべてに意味を見いだすブルーノ哲学は、聖書の言葉を絶対視する教会の権威を突き崩してしまいうるものでした。教会からすれば、キリストの教えという中心がなくなると社会の秩序が壊れてしまう、と思われたことでしょう。危機をまえにして、精神の自由を求めるのか、社会の秩序を望むのか――ルネサンス時代の精神のドラマの一幕です。

ブルーノが火炙りになったローマの広場カンポ・デ・フィオーリは、現在は市場として賑わう。中央にはブルーノの銅像が建っている。[岡本源太撮影]
ルネサンス時代の渾沌とした思想に比べて、現代の私たちの思想は、専門分化のもとで精緻かつ正確になってはいるかもしれません。しかしどこか視野が狭く、発想も縮こまっているように感じられます。レオナルド・ダ・ヴィンチは、渾沌のなかでこそ才能は目覚めるのだ、といいましたが、彼やアルベルティほどの万能人は現代にはなかなか見当たりません。
もっとも、だから現代人はルネサンス人を見倣うべきだ、といいたいわけではありません。私はルネサンス美学とならんで現代美学の研究もしていますが、現代的意義云々というのはいわば他人を自分にとって役立つかどうかでしか見ないようなものでしょう。
それよりも私が興味を覚えるのは、「ルネサンス」が歴史上の一時代というにとどまらない、「再生」のイメージとしての神話性を帯びていることです。あらゆる時代にそれぞれのルネサンスがある、とは、ブルクハルトのあとルネサンス研究に多大な功績を残した美術史家ヴァールブルクの洞察です。ルネサンス時代の人々は、住み慣れたはずの世界が見知らぬものに変貌してしまったとき、古代ギリシア・ローマの古典を手本にすることでこの危機に向き合いました。古いものを甦らせることで新しいものを生みだそうというのは、ある意味ではアナクロニズム(時代錯誤)といえるでしょうが、現代を含めてどの時代の人々もしばしば危機のなかではそのように発想し行動します。ルネサンス時代のイメージはそのとき手本として、その神話的な原型として、働きます。ヴァールブルクのいう残存現象です。曰く言いがたいものに出会うたびに、ルネサンスはなおも繰り返されるのです。

ともあれ、危機にして再生の時代であったルネサンス時代の哲学と芸術は、驚くべき発想に充ち満ちています。哲学は驚きから始まる、とはプラトンの言葉ですが、驚きとは自分の理解を超えたもの、自身とは異質なものに出会う楽しみでもあるでしょう。
<<前編は「芸術はルネサンス時代に哲学となった?」
| 1 | 2 |
岡本 源太
研究分野
美学、哲学、芸術学、西洋美術史
論文
パオロ・ウッチェッロを見るアンドレ・ブルトン――ルネサンスに照らされたシュルレアリスム絵画(2023/08/)
ルネサンスの宗教論と多様性の問題――マキアヴェッリ、ピーコ・デッラ・ミランドラ、ジョルダーノ・ブルーノ(2022/11/)