
地域のまつりを担うのが、その村落や地域の人々だけではない時代が訪れている──石垣悟・観光まちづくり学部准教授は、そのように語る。いったい、どういうことだろうか。民俗学、博物学、そして文化財保護を股にかけて活動してきた石垣准教授の口から伝えられるのは、大きく変化を遂げつつある地域社会の現在地点だ。
地域のリアリティへと一気に突入していく、インタビュー後編。そこには、地域の変化を変化のまま共に生き、未来へつなげていこうとする、真摯な態度が垣間見える。
地域を人々の内側の目線で考える、ということについてインタビュー前編では触れたのですが、実は現在では、単に内側から考えるだけではその地域のことを捉えられないという状況になってきているのではないか、と思っています。いや、むしろ、「地域」という言葉が適切なのかどうかも含めて、私たちは再考すべき時代に入っているのではないか、とさえ感じているのです。
どういうことなのかと言いますと、私が民俗学の立場から村落や地域内部の視点で考える、というようなことに取り組み始めた平成の初めくらいまでは、まがりなりとも地域社会と呼ばれるものがギリギリ「伝統的」ともいえる形で残っているという実感がありました。インターネットが今日のように普及する前の時代のことです。比喩的に言うならば、「おらが村」と語るときの、その「おらが村」の範囲や構成員がある程度は見えている状態でした。住民もそうですし、私のような研究者も聞き取り調査を通じて、その内と外との区別が一定程度はできていたということです。だからこそ、私は内から見るという視座を獲得できていたともいえます。
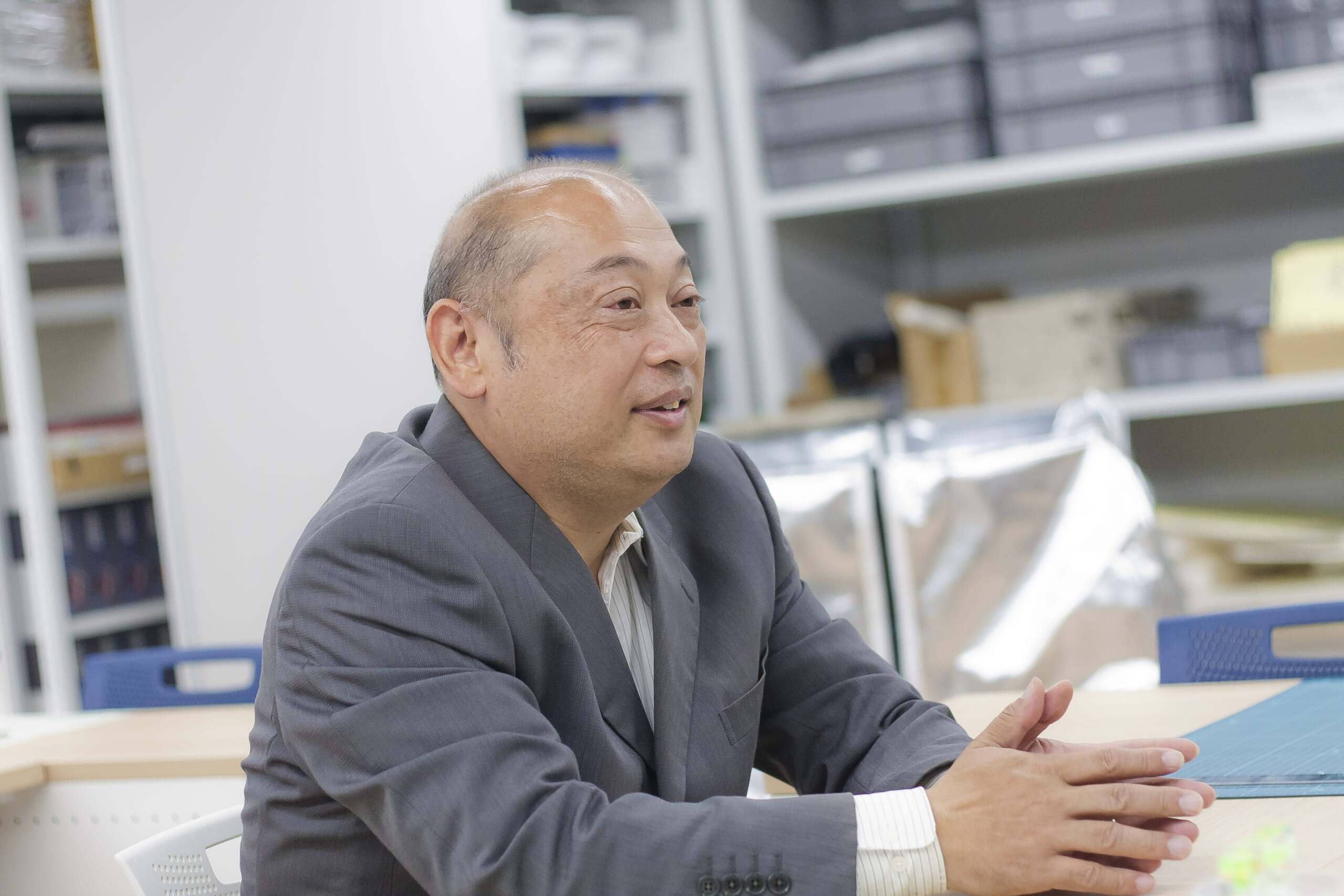
しかし現在では、ある意味で「地域」という言葉だけが独り歩きしていて、その「地域」が実際に何を指しているか、どのようなものを指しているのかというのは、かなり見えづらくなってきているのではないか。そう、私は考えるようになってきています。
それは単に人口が減ったとか、少子高齢化が進んだとかいうことだけではありません。日常的にさまざまな人々が出たり入ったりして地域を構成する人間が入れ替わっています。一時的にやってきて滞在する人や、二拠点生活を送っているというような人もいますし、さらにはインターネット上でつながった関係性もあります。驚かれるかもしれませんが、その地域に住んでいないのに町内会費を払っている、というような人まででてきています。物理的にその地域のなかにいるかいないか、その地域に関わっているかいないかということが、その地域社会の一員であるか否かという基準には全くならない、ということなんです。逆にいえば、人と人の繋がりにおいて土地はあまり意味を持たなくなっている、あるいは私たちと土地との結びつきが極めて希薄になってきているということだろうと思います。
そのときに、たとえば地域の──という表現が適切かどうか、いま問われているわけですが──まつりを続けていくといったとき、それを支えていく集団性といったものをどう考えるべきか、もはや従来の観点からでは捉えきれないところにきているのではないかと思うのです。人々の新しいかかわり方に対しては、当然新しい視点で考えていかなければならないのではないか。現在の実態をきちっと正面から取り上げていかないと、今世間でよく言われている「地域社会」というものが一向に見えてこないのではないかと、私は感じています。
たとえば、静岡県掛川市の横須賀という地区で行われている「三熊野神社大祭の袮里(ねり)行事」というまつりで、平成29(2017)年から平成31・令和元(2019)年にかけての青年(高校卒業から30歳頃まで)の参加者データを見てみます。すると、5割強から7割弱の割合がそもそも地域の外からの参加者になっており、地理的には相当広い範囲から参加者がいます。さらにいえば、まつりにお金を出す人や交通整理で雇われた人、沿道にお店を出す人、写真を撮りにくる人、動画配信する人など、まつりに関わる人々は他にもたくさんいます。私のように調査に訪れる人もいます。結局、関わり方の濃淡はあれ、こうした人々の存在によって、このまつりは成り立っています。このようなことは決して、このまつりに限ったことではありません。この現実を正面から捉えようとするならば、そこに住む直接的な担い手だけを相手にしていては不十分なことは明白です。
地域をその内部から見ることの重要性について私は考えてきた立場ですが、今やそのリアリティを踏まえるならば、地域を内と外という視点からではなく、内外という枠組みを超えたもっと多様な視点から考えなければならないのではないかと思います。私は、まつりに関していえば、こうした従来の枠組みを超えた「みんなのもの」というのがポイントになるのではないかと思っています。この考え方は、人類学などでいうコモンズとよく似ています。
コモンズとは、ある社会に共有された土地や財産とそれを利用する仕組みをいいます。その社会の人々は誰もが自由に共有された土地や財産にアクセスできるのですが、その自由とは身勝手という意味ではありません。身勝手にアクセスすればコモンズは消費され尽くしてしまいます。従って、共有された一定の慣習に基づいて「自由」に利用するわけです。まつりとの関わり方もこの考え方と同じなのではないかと思っており、1人1人がその自覚をもてるか否か、だと思うのです。そのように地域、そしてそこでのまつりのような民俗を捉えるとすれば、まつりを持続可能なものとして開く可能性も高まるのではないでしょうか。
ところで、現在のまつりをみると、そこでは継続を目指すまつりもあれば、積極的な意味において一度中断させるまつり、さらには中断後にそれを復活させるまつりもあるというようにその動向は実に多様です。まつりは生き物ですから、元気な時ばかりではありません。病気になって死ぬということがあっていい。そして生き返ることすらあり得ます。
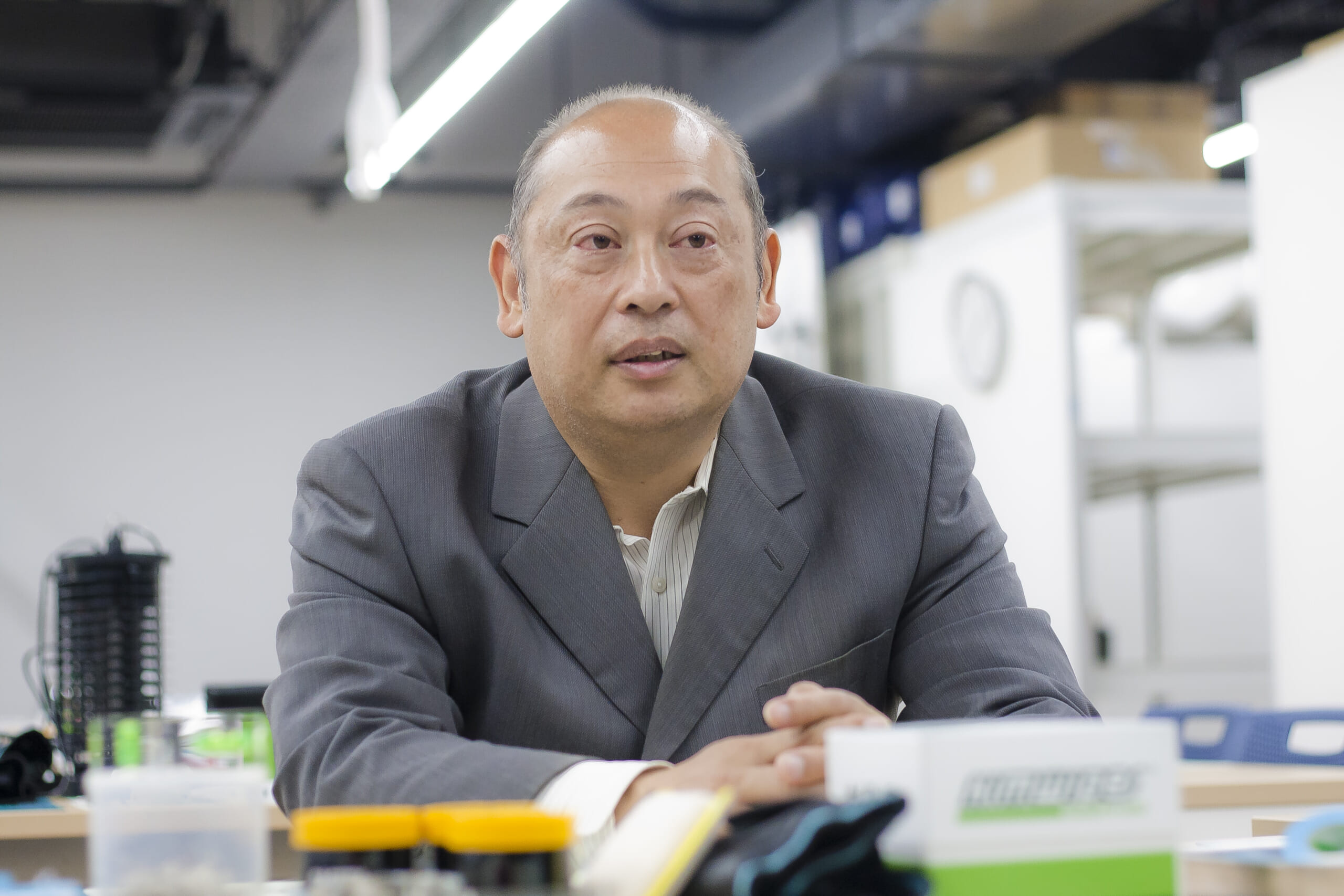
そこで今度は文化財保護という行政の判断も重要な意味を持ってくるわけですが、そのときに民俗学がなしうることは極めて大きいのではないか、と思っています。その地域にどんなまつりのどんな歴史があったのか、地域文化の一端を後世に伝える記録を作成するのです。特に一度中断していたまつりを復活させる場合、映像や文字で記録をとることが不可欠です。記録というと、私たちは映像記録を思い浮かべてしまいますが、映像記録だけでは足りません。なぜならばそのまつりに対して人々がどんな想いや意識を抱いていたのか、まつりをめぐる言い伝えや変遷といったことは映像では記録しきれません。従って聞き書きからそれを把握し文字で記録しておく必要もあるわけなのです。
もちろん、映像記録が捉え、再生しうるディティールの豊かさといったものは非常に重要です。文字で表現できない身体性や空間性のようなものも大きな意味を持つはずですから、映像記録はとても便利です。しかし一方で、映像はあくまで目で見るイメージであり、そこに人々が抱いていた気持ちまでは映り込まない ──それを映像に映り込ませようとするのが映像クリエーターでもあるのでしょうが──。また、映像だけではまつりに関する言い伝え、“起源”や“本質”──それはまつりを今日まで伝承させている原動力ともなる──がわからないのではないか、と思います。
そこにおいては、民俗学の聞き書き調査の力が発揮されうる。まつりに関わる多様な人々に聞き書きを行い、聞いたことを一字一句漏らさず文字化するわけです。そこで話された言い伝えや伝説、そして話してくれた人の心持ちも、話した人の側に立ってすくい取ろうとする。それは今まで誰も意識しなかったような地域の宝を発見する作業ともいえます。こうして映像だけでなく文字も併用した記録がきちんと残されていった先にこそ、地域社会が変容するなかで、まつりが継続・継承され、また復活する可能性も生まれ、地域の未来もひらけてくるのではないでしょうか。
現在、私が籍を置いているこの観光まちづくり学部で、私は主に博物館の学芸員を養成するための講義や実習などを担当しています。まさに、実践的な領域において活躍できる学生を育てるための場が、目の前にある。
そこでは、このインタビュー前後編を通してお話ししてきたように、地域を内側から、さらには多様な視点から考える民俗学に軸足を置きながら、博物館や文化財保護の領域で仕事をしてきた私の経験が、学生の皆さんにとってすこしでも活かしてもらえるものになるかもしれません。たとえば博物館で既存の資料や資源を単純に展示・紹介して満足するのではなく、資料・資源そのものを自身が地域に寄り添いながら調査して掘り出してくる、そのうえで掘り出した地域の宝の原石をまちづくりを念頭におきながら、整理、保管などの作業によって磨き上げ、宝として展示するというようなことですね。
そうした知見と技術を、自身がやりたいこととうまく融合し、昇華させていく学生が、これから多く巣立っていってくれれば──そんな期待感と責任感を抱きながら、この学部での日々を過ごしています。
<<前編は「石垣先生が語る民俗学と文化財保護の実践とは」
| 1 | 2 |


