
地域の文化財といったとき、何を思い浮かべるだろうか。地域で行われるまつり? それとも博物館で展示されている民具? 前者であれば「無形」であり、後者であれば「有形」の文化財とされる。それらを並行して考え、実践的に向き合ってきたのが、石垣悟・観光まちづくり学部准教授だ。
民俗学を起点に、地域の歴史博物館に勤務し、文化庁で文化財保護に従事し、やがて研究者へ。独特の歩みが築きあげたのは、地域の人々にできる限り寄り添う姿勢だ。まずはインタビュー前編で、石垣准教授のバックグラウンドに迫る。
民俗学、博物館学、文化財保護論──私がこのように、なんとも広い領域を専門とするようになったのには、民俗学を専攻していた大学院4年目のとき新潟県立歴史博物館学芸課の研究員になったこと、つまりは就職が決まったことなどが大きく影響しています。当時はいわゆる就職氷河期にあたる時期でしたからホッとしたことを覚えているのですが、後に文化庁文化財第一課(当時は伝統文化課)文化財調査官に転じたことも含めた人生のあらゆる経験が、現在の研究やその実践にまで影響を及ぼすようになるとは、まだ想像もできていませんでした。
新潟県立歴史博物館では4年ほど、文化庁では14年ほど働いていたのですが、いずれの職場も、基本的には実務・実践の場でものを考えながら、手を動かすことが重要でした。そうした経験すべてが、やがて研究者になったときの見地にも、大きく反映されていると実感しています。
どういうことか端的に述べますと、必然的に全国の「無形」と「有形」にまたがるさまざまな文化財に直接現場で触れることができた、ということが挙げられます。

民俗学の対象というのは、基本的には「無形」です。文化財的には無形の民俗文化財、というような表現を用います。たとえば私がかつて調査・研究の中心に据えていた村落のありようなどは、物体として明確な形をもっていませんから「無形」にあたります。
しかし、そうした民俗学が扱うような無形の対象は、歴史系博物館ではそのまま展示できません。それを展示するには、やはり「有形」であることが必要になってくる。たとえば民具といった、有形の文化財に目配りしながら展示を創り上げていくわけです。
私はこうした有形を扱う職場で働くことで、それらの知見や技術を学びながら、同時に民俗学を出自とするものとして無形についても並行して調査研究を進める、ということを日常的に続けていくようになりました。
有形と無形を並行して考えていくことによって、否が応でも視野が広がっていくことになり、文化庁に移ったあとも、こうした両輪での思考が大いに役に立ちました。文化庁はまさに有形も無形も、動産も不動産も手広く文化財として扱う行政機関です。自分の得意な分野だけを追い求めるわけにはいきません。常に視野を広げながら現場に行っては悩み考え実践的に仕事ができたことは、私にとってとても大きな経験だったのです。
ここですこしだけ時間の針を巻き戻して、そもそもなぜ民俗学に興味を抱いたのか、お話しできればと思います。先ほど村落のありようを調べていたという話をしたのですが、それには私の出自が関連しているのです。
生まれ育ったのは秋田県。と言うと、たとえば田んぼが広がる農村のような場所、なまはげのような伝統行事のある場所をイメージされるかもしれないのですが、実は秋田市内の、しかも戦後にできた新興住宅地に住んでいました。そうした場所では、たとえば長らく継承されてきた地域のまつりというようなものはほとんど存在しません。周辺の地域でみられた、毎年時季がやってくれば、伝統的なまつりを行う、またそれに参加するというような肌感覚は、幼心にとても不思議なものに思えました。
そうした興味関心が、やがて村落を内部の目線から考える、という私の民俗学的な研究へとつながっていきました。加えて、まつりひとつとっても、決してひとりでやるわけではなく、そこには村落の多くの人々が関係していて、何かしらの社会の意思のようなものが存在しています。そうした人々のつながりや、集団・組織、そしてその意思といったものを外からの目線で分析する研究は当時も比較的多くあったわけですが、聞き書きを踏まえてその村落の人々の視点で捉えてみたい、と思ったわけなんです。そうすれば、不思議に感じていたことの答えも見つかるのでは、と思いました。
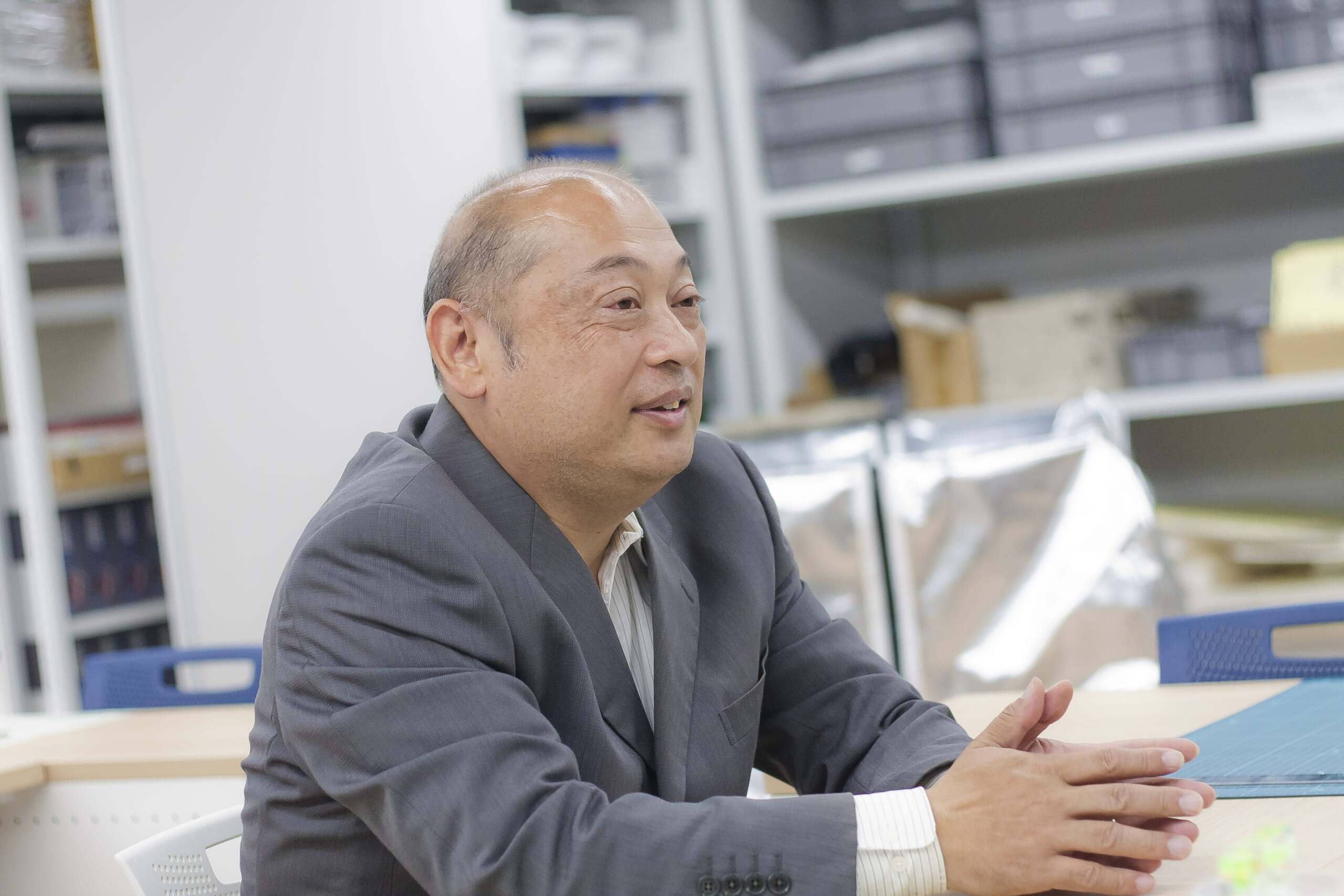
当初調査をしていたのは、私の父の生まれ故郷とその周辺地域、現在の秋田県雄勝郡羽後町のあたりの盆踊りでした。盆踊りを行う村落の人々の組織や関連する伝説や世間話、さらには彼らの歴史に対する意識といったようなものです。その地域には複数の盆踊りがみられたのですが、調査を進めていくと彼らなりの論理で伝統的な盆踊りを一生懸命続けているところもあれば、やめたところもあり、一度やめたけれども後に復活させたところまであることが明らかになってきました。私は、そこに組織がどう関わり、その内的な動機や意識がどのようなものなのかを、聞き書きによって得られたデータをもとにして村落どうしを比較しながら検討しました。
実はこのときの経験が、文化庁に入って以降も、大きく役に立ったということがあります。文化財を保護するということは、そこで明確に行政的な判断をくだす──つまりはある面で、現時点で残すべき文化財とそうでないものを分けるという大きな決断をすることを意味します。そのとき、その文化財に普段から携わってきた地域の人々の話を、相手の側、いわば内部の目線で出来る限り聞いて理解したうえで対応しなければたいへんなことになります。民俗学で培った姿勢が、文化財保護行政でも私を支えてくれたわけなのです。
もちろん、文化財保護という行政判断には、民俗学とは異なる点もあります。それは、文化財に対する評価を、その時点で客観的かつ固定的な結論として提示しなければいけないということです。学問であれば、より長期的なスパンで慎重かつ継続的に調査し、判断を保留したり、あるいはその判断を修正・更新したりすることができます。しかし、文化財保護行政においては年度ごとに明確に文化財の価値を判断しなければならない、そしてそれは以降、原則変更されません。そうした学術研究と行政行為との間にあるスピード感の違いという難しさも痛感しました。
ともあれ、そうした実践の場に立ちながら、民俗学的な知見もなんとかうまく取り入れようとする、そうした日々を、全国のいろいろな現場で文化財と人を直接相手にしながらおくることができたことは、私にとって非常に重要な経験だったのです。
さて先ほど、まつりを執り行う単位として村落について触れましたが、実は現代においては、ある村落や地域のまつりであっても、その域外の人々もいっしょに支えるという事例が増えてきています。そんな新たなまつりと村落や地域のあり方をヒントに、インタビュー後編では「地域」の現在を考えていきたいと思います。
後編は「「地域」の現在地点と地域社会の変容のなかでの文化財の未来」>>
| 1 | 2 |


