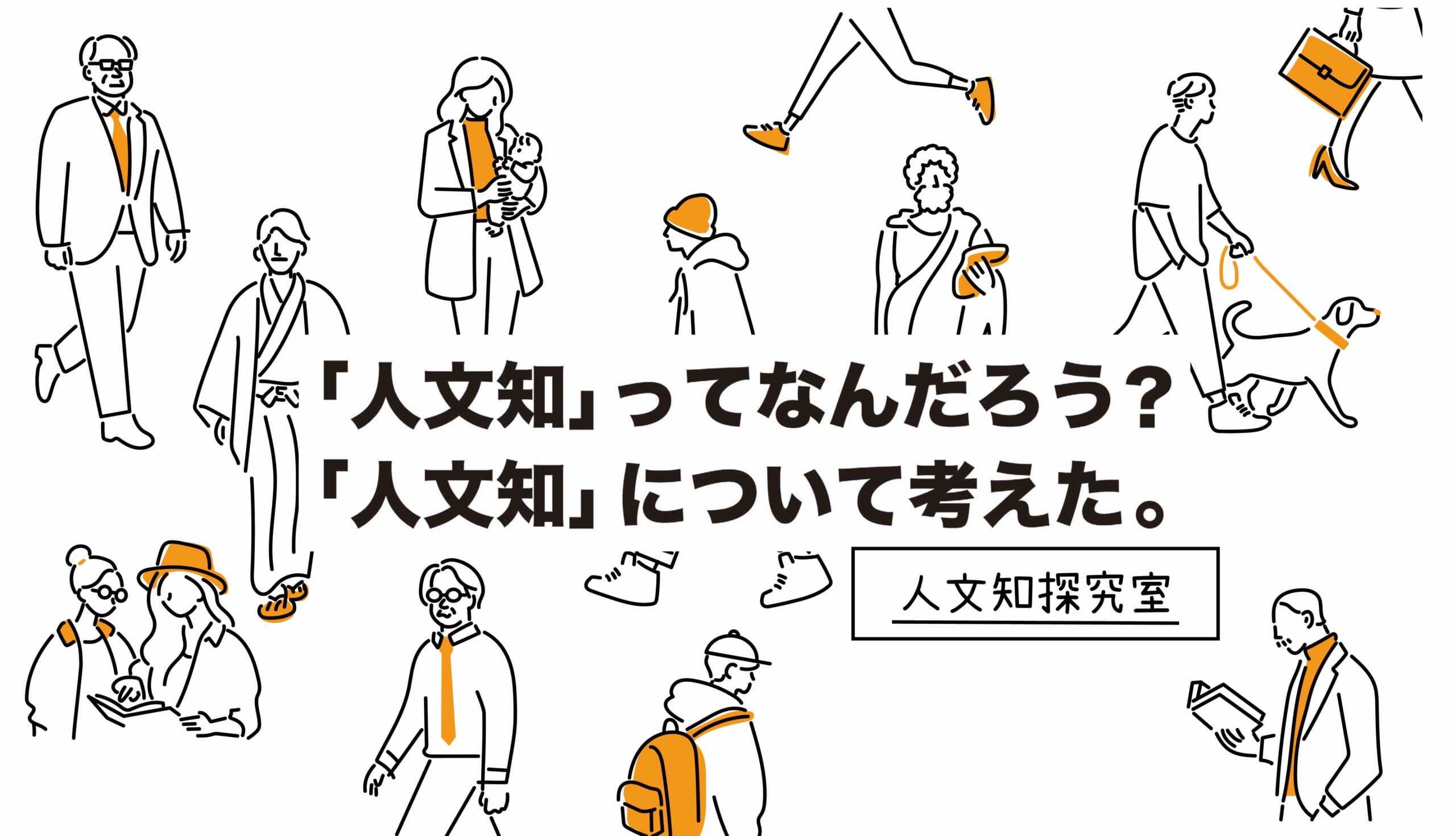人文知の豊かさを見つめると、幅の広い思考が生まれる
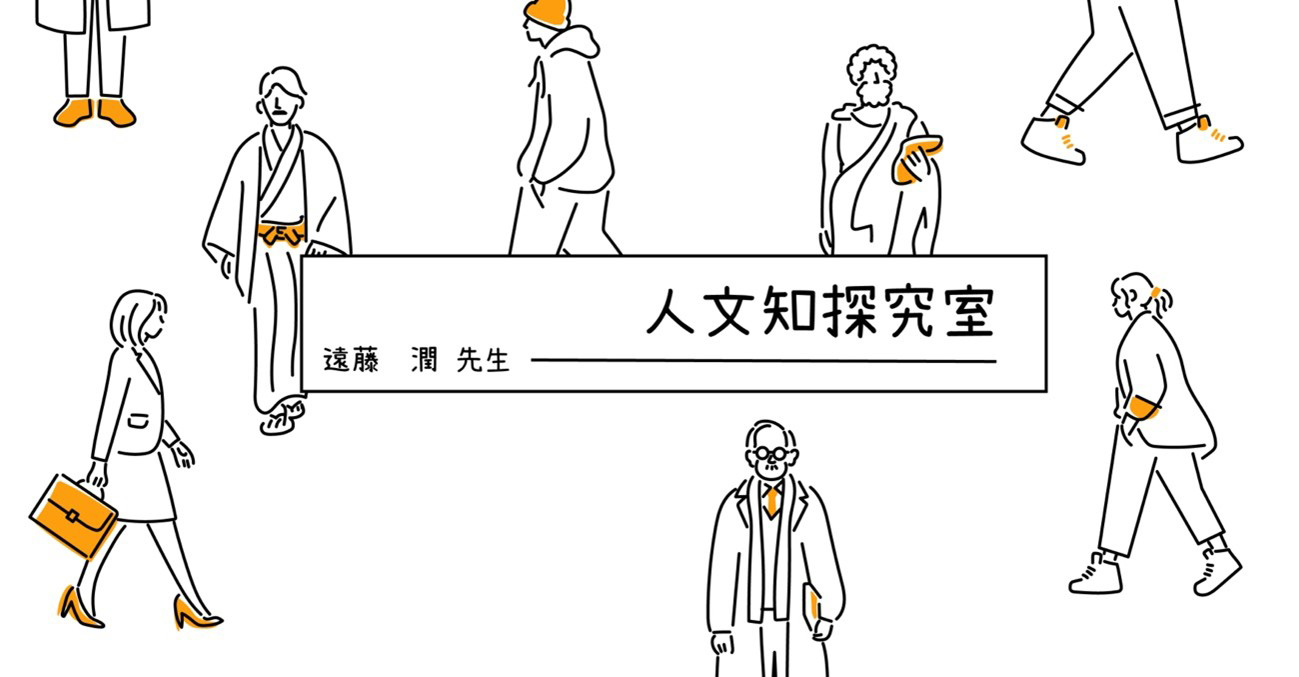
混迷を極める実社会において、何かしらの手がかりを与えてくれるかもしれない──いま、注目度を高めつつある「人文知」。その可能性を見つめ、國學院に息づく人文知を追い求めるのが、人文知探究室だ。さまざまな専門をもつ研究者のもとを訪ね、複数の分野の知見を横断しながら、日々の生活からビジネスにも響きうるような、新たな人文知の耳をそばだてるインタビューシリーズを開始している。
シリーズ3人目として話をきくのは、遠藤潤・神道文化学部教授だ。宗教学および日本宗教史を専門とし、神や霊魂といった目に見えないものを信じて生きる人々のありようを、特に国学者・平田篤胤の思想を中心に探ってきた遠藤教授。その目に、人文知の広がりはどのように映っているのだろうか。膝をつき合わせて語り合うなかで見えてきたのは、定まったかたちをとることのない、私たちの生き方をくみ取ろうとする人文知の姿だ。
──「人文知」というテーマに対して、まずはざっくりと、どんなことをお感じになりますか。
正直、自分がやっていることを「人文知」として認識したことは、あまりないんです。ただ今回、このようにインタビューの機会が設けられるなかで改めて考えてみると、「人間は合理性だけで生きていない」ということに向き合うのが人文知なのかなと、ぼんやりとではありますが再認識したんですね。例えば、科学的なだけの説明にはうまく乗り切らないものを扱おうとする、といいますか。
──人間は合理性だけで生きていない、ですか。
はい。この世界の中で生きながら、さまざまな物事や出来事に私たちは接していくわけですよね。そのとらえ方が、各自のいわば物語的な受け止め方をしていたり、あるいはより集合的なストーリーに則りながら考えたり、ということは往々にしてあります。つまり人間の営みというのは理屈だけではない道筋に拠るところも大きく、人文知というのはそうした科学的な証明がしづらい、合理的な説明の枠組みでは切り落とされてしまうところに手を伸ばし、きちんと迫ることができる学問なのかなと感じるんです。

──合理的ではない人の生き方、という点について、もうすこし詳しく伺えますか。
もちろんいろんな社会現象やニュースを見てもそのように感じられることは多いと思うのですが、より身近な例でいえば、恋愛といった人間の営みも、人文知が捉えうるような対象だと感じます。たとえば片想いをしていて、それが両想いにならなくてもいい、というようなときってありますよね。片方がもう片方のことを勝手に好いている状態で、ひとつのストーリーが完結していて、それだけで人生や毎日が楽しいというようなことがある。なんといえばいいのか、このように確固たるかたちをとらないような、いわば“ゆるい”人間の営みというものは実際に存在していますし、そうした“ゆるさ”に従いながら私たちも生きているところがある。
──たしかに、いわれてみればそうですね。
人間が生きているということ自体がある意味で“ゆるさ”があるから成り立っているといいます。私たちはそのゆるさの中を、平気で生きているところがあるわけです(笑)。ともすれば、思い込みをはじめ、妄想などといって切り捨ててしまわれかねない、そうした人間のありようを、きちんと掬い取るのが人文知だという気はするんですね。合理的にだけではうまく説明しきれない、明確なかたちをとらないものでいっぱい溢れている人の生というものの仕組みを、それでもなんとか説明するやり方を見つけ出そうとする、とでもいいますか。私が専門としている宗教学も、このような意味においては人文知の範疇にあるといえるのだろうと思います。
──目に見えないものも感じながら生きていく人間のあり方、そうした境地をきちんと考えようとする宗教学の見地などにかんしては、以前にもお話しいただいたことがありました。
宗教学において語られる神様や霊魂というようなものは、目に見えないし、合理的に語ることが難しい場合も多いし、どこか怪しげなものだと思われかねないところがありますよね。しかし、そうした説明しきれないものをくぐらせて自分の生を成り立たせている人は、私たちの世界にたくさん存在しているわけです。そのひとつが宗教でしょうし、先ほど触れた恋愛など、あるいはそれに限らずさまざまな人間の営みが、ことによっては怪しげだと考えられかねないものによって成立している。宗教学も人文知のひとつだと仮に括るのであれば、そうした人間の生き方をとらえる学問として考えられるわけですね。

──とはいえ冒頭でおっしゃったように、ご自身が専門とされてきた宗教学を、人文知的なものとしては、これまではあまり考えずにきたわけですよね?
そうですね……。これは非常に微妙な物言いになってしまうので、うまく言葉にしていきたいのですけれども、実は人文知的な学問の中心としておそらく皆さんがお考えになるような文学に対して私は、かつて心理的な距離があったんです。それは単に、私の若さといいますか、未熟さゆえなのですけれども……。
──文学に対して距離があったのですか? 以前に読書にかんするインタビューにお答えいただいた際は、愛読書の一冊であるという川上弘美さんの『真鶴』など、現代小説についても語っておられましたが……。
もちろん、文学を読むこと自体は好きなんです。友人に吉本ばななを勧められて読んだり、あるいは教養として夏目漱石をがんばって読んだり、人からおもしろいと聞いて、向田邦子の著作をコンプリートしようと取り揃えながらもその全部は読めていなかったり……(笑)。そうして文学に親しむということは、人並み以下ではありますが、これまでいろいろしてきました。ただ学問として取り組むにあたっては、あくまでかつての話ではあるのですが、すこし距離を感じていた。仮に人文知の領域をフィクションとノンフィクションに分けるとして、文学がフィクションなのだとすれば、私はもうすこし実際の人間の生、そのリアルな様相に迫る、ノンフィクション的な意味での宗教学に取り組みたいと、半ば勝手に思ってしまっていたんですね。宗教学も、文学よりは歴史学に近いものだと感じていましたし、歴史学の人に伝わるように研究するということも心がけていました。そうした文学と微妙に距離のある感覚が、自分が年を取るにつれて、だんだんと変わってきたんです。
──どのように変わってきたのでしょうか。
私の文学に対する理解の進みが遅かったのだろうと思うのですが……。もうすこしだけ、かつて文学研究に感じていた距離について説明すると、「テクストに対する自分の“読み”を他の人よりも優れたものとして提示するということは、とても自分にはできなさそうだ」と感じていたのでした。文学研究者の方は非常に繊細かつ緻密なタッチで“読み”を構築されていくわけですが、私の場合はその“読み”がどれだけ私自身の主観性を免れているかわからないと思いましたし、そのうえ自分の“読み”に自信をもつことはできなさそうだったんです。それは文学をめぐる問題というわけではなくて、私にとっての、自分の主観に終始しそうな内容を人に伝えることへの戸惑い、とでもいえばいいのかもしれません。ただ最近は、年を取ることで、だんだんと“主観”を伝えることへの自省が、それこそゆるんできたんですよね。
──そうなんですか?
いったん文学から離れてお話しするのですが、たとえば神道思想史にかんする授業のなかで、「心のなかに神がいる」という、中世から江戸中期頃まで多く見られた考え方について触れることがあります。たとえば朱子学においては、自分のなかに「理」が備わっている、というような考え方をするわけですね。このとき学生に、「どう思う?」と投げかけることがあるのですが、議論をするなかで、当時の文献には書いていないのだけれども、私としては発展的に議論ができるのではないかと思う“主観”を提示することがあります。ここから先の話は、神道学の先生方には、どうぞ広い心で読んでいただきたいのですが……(笑)。
──どうぞこの場においては、それこそゆるく語っていただければ(笑)。教室で、どんなお話をされるのでしょう。
「自分のなかに神がいる」と考えるということは、「自分のなかに自分以上の存在がいる」と考えることを意味します。それは単に世俗のレベルで、他人から「自分を大切にしなさい」といわれるのとは異なる。自分を超越したものを自身のなかに想定して、その存在に申しわけわけないから自分を大切にする、という回路が構築されるわけですね。すると、自分の体を傷つけないとか命を大事にするといったときに、単に日常的な感覚の範囲で自分の命が大切だから自分の裁量で守るという考え方ではなくなる。この体も命も自分のものではなく、なかに神が存在するから守る、という考え方になるのではないか──こんな話をすることがあるんです。

──なるほど、興味深いです。
繰り返すように、こんな考え方は当時の文献にはこういう形では出てきていませんし、その意味では私の“主観”に過ぎないのかもしれません。ただ、「自分のなかに神がいる」という信条において、自己をめぐる回路が小さく閉じずに、聖なるものの媒介によって反射したように自身に還ってくるように考える回路が築かれるということには、いろいろと可能性があるように感じるんですね。たとえば人間対人間の関係性においても、「自分のなかに神がいる」と考える者同士であれば、人間以上の存在でもある相手に対して敬意を示しあうなかでその関係が成立するし、ときには人権思想にも結びつくかもしれない。そうした発展的な議論の余地を感じるからこそ、思わず自分の“主観”を喋ってしまうんですね。そしてこうした話は、ときに説教くさくもなってしまうので、たまに喋ってしまったときには教室を去りながら「ああ、今日もまたやってしまった」と反省することしきりなのですけれど……(笑)。
──そうなんですね、そこまで反省されることもないように思いますが……(笑)。
ともあれ、こうして“主観”と改めて相対するようになってくるにつれ、文学との距離というものが縮まってくる感覚を抱くようになったんです。まず、自分のなかに人間を超えたものを想定するというのは、科学的・合理的な観点だけで見たら荒唐無稽なのかもしれないのですが、しかしそう考えるだけで生きていけるという境地があるわけですよね。ご飯を食べるから生きることができるとか、病気をしないから生きていけるというのとはまた異なる地平において、人が生きることを支える、何か意味をもつものがある。それはなかなか名指すことが難しく、まさに“主観”の領域に属すようなものでもあるわけですが、文学という分野はこの“何か”を浮かび上がらせることに長けているのでは、と感じるようになってきたんです。
──ある意味では、遠藤教授が宗教学において見つめてきたものに対して、文学もまたアプローチしているということでしょうか。
もしかしたら、そのようにもいえるかもしれません。たとえば先ほど名前のあがった『真鶴』という小説も、全編を通してそうした“何か” ──人の生を支える意味の輪郭を、そっと浮かび上がらせようとする作品だと表現することも可能かもしれない。こう考えると、かつてフィクションとして、つまりは人の実人生からは遠いものとして距離を感じていた文学の世界が、むしろリアルな次元で人間の生を支えるものを描いたり、そうした“主観”的な領域について精密な読解を通じて研究したりする分野として感じられてきたんです。
──そうしてゆっくりと、必要な迂回の経路もたどりながら理解に至っていくことができる点もまた、「人文知」の豊かさなのかもしれません。
とはいえ、研究を生業としている者としてはもうすこしスピーディーな理解ができないものかと、これもまた反省ばかりなのですが……(笑)。それでもやっぱり、神や死者も含めて人を底支えしているものを見つめていくという点においては、人文知とされる領域はいろいろと気になるものなんです。たとえば私が宗教学へと道を絞るようになる前、哲学も進路のひとつとして考えていた時期があるので、自分の興味関心に接するような領域の哲学の本は、素人ながらいまでもかじることはあるんです。人が世界をどう認識しているかといったような、物事の根本を考えるうえで、さまざまな前提を遡り、ときに覆しながら思考を深める哲学に学ぶことは多いですね。

──近年、マイブームになった哲学者などはいますか。
ええっ、それはまた、哲学ご専門の先生方からお叱りを受けないか、素人としてはただ恐縮するばかりの話になってしまいますが……(笑)。そのうえですこしお伝えするとすれば、ここ数年気になって読んできたものにアンリ・ベルクソンがいます。
──19世紀末から20世紀前半にかけて、まさに根源的な議論を進めたフランスの哲学者ですね。
私は宗教学の専門家ですので、「神や霊が存在していい世界観というのは、どういったものなのだろう」ということが気になるんです。ベルクソンに手を伸ばしたのは、そうした文脈においてなのですね。わからないなりに読んでいるだけなので、ここからは話半分で聞いていただければ幸いなのですが……。まず、ベルクソンは神秘主義的な側面をもっていたり、実際に「〈生きている人のまぼろし〉と〈心霊研究〉」という題の論文も書いていたりする人なんですね(『精神のエネルギー』所収、原章二訳、平凡社ライブラリー)。
──独特の立ち位置にあった人のようですね。
そうした側面が彼の思想のうちにあることを踏まえながら、たとえば主著のひとつである『物質と記憶』(杉山直樹訳、講談社学術文庫 2019年)などを読んでいると、「私の身体とは、物質界全体の中にあって、他のイマージュと同様に、運動を受け取ったり返したりしながら作用している一つのイマージュである」という一節が目にとまります。普通、私たちが苦痛快楽を感じ、確固たる存在と考えている身体をも「イマージュ」の一環として捉えてしまう世界観というのは、とても刺激的ですよね。
──曖昧な存在にも居場所があるような世界観ですね。哲学における専門的な議論はさまざまにあるとは思うのですが、すくなくとも宗教学のビジョンとどこか通じるところがありそうには感じます。
神や霊魂が存在できる世界観を考えるうえで、こうしたベルクソンの思想も含めて、哲学の議論も気になって読んでみてはきていますし、他の分野にもいろいろと経めぐってきています。こうして話してくるとなんだか、人文知とされるものの範囲において、いろんな知見をあちこちつまみ食いしてしまっているようで、なんだかお行儀が悪くて申しわけないのですけれども……(笑)。ただ、今回のインタビューを通じて改めて実感されてきたのは、人文知には人文知なりの“語り方”があるのだな、ということでした。
──語り方、ですか。
人間の生は、はっきりとこういうものだと明示的に説明してくださいといわれても、なかなか説明できるものではない。直接はいえないのだけれど、なんとか浮かび上がらせるように、そこに現れるように、間接的に表現し、描き出すという語り方をするわけですね。真正面から説明すればもしかしたらできるのかもしれないけれども、野暮になってしまう危うさがあるといいますか、そうやってダイレクトに名指すと、人間の生の大事な要素がこぼれ落ちてしまうのではないか、という気もします。そうならないように、意図された語りの余白において、状況を説明し、なんとか了解しあう方法を探しているという感じがしますね。こうした人文知の語り方自体を、私も十分に説明できませんし、それをさらに外の、広く社会の皆さんにご理解いただくということも、いろいろと難しいことかもしれませんが……。
──ただ、もし世において人文知への注目度もまた高まっているとすれば、そうした語り方でこそたどり着けるものに対する期待なのかもしれません。
なるほど。研究者として思うのは、学問の名が冠された瞬間に、私たち自身も気負ってしまうことがある、ということですね。なんでしょうか、たとえば宗教学の専門家として世に出るとすれば、どうしても宗教学者らしくというか、“いい子”にふるまってしまうところがある(笑)。人文知という枠組みがもし今後、さらに生きてくるとすれば、その豊かさを見つめながらも、枠には縛られないように議論ができたときにこそ、また多くのものが見えてくるのかもしれませんね。

|
人文知探究室後記 記事中のやりとりには含めていないが、遠藤教授の話を聞くなかでインタビュアーが話題に挙げたトピックがいくつかあった。そのひとつは、近年人気を博している人形文化のことだった。オタク文化圏において一世を風靡しているアクスタ(アクリルスタンド)や、「ぬい」などと呼ばれ、自作も流行しているぬいぐるみなど、人々の熱はとどまることをしらない。 ときに生身の人間、ときにキャラクターといったように、人形のかたちにされるものはさまざま。だが、そうした造形物と共に旅行にいき記念撮影をするといった行為は、まさに遠藤教授が語るように、名状しがたいものを感じる。何かの形をした無生物(いや、生きていないとどうしていえよう)に思慕の情を抱きながら生きることが何を意味するのか、その営みを楽しんでいる本人も含め、まだ私たちはうまく言葉にできていないのではないか。 もうひとつ挙げたトピックは、これも近年ホラーや怪談界隈で流行している、リミナルスペースやバックルームだ。これらは、延々と続くガランとした人工空間に恐怖を覚えるようなインターネットミームである。昔でいえば、スタンリー・キューブリック監督による映画『シャイニング』のあの有名な廊下の場面のような空間だ。人がつくったはずなのに、そしてそこに誰もいないのに、いやいないからこそ、なぜかわからないが恐怖を覚える……。 これらは、明快に論じた瞬間に霧散してしまうような性質を帯びており、遠藤教授の話を踏まえれば、まさに人文知的トピックであるといえるだろう。おそらく現代という時代は、その核心を名指すことが根本的に難しい。その最中における人文知の可能性を、今後とも探っていきたい。 人文知探究室 宮田文久 |
人文知探究シリーズ 第4回は「「じんぶんがあるねえ」と声をかけあえる世界を向いて」>>
遠藤 潤
研究分野
宗教学、日本宗教史
論文
日本社会における神と先祖 : 19世紀の国学を焦点として(2003/03/25)
平田篤胤『仙境異聞』の編成過程 : 〈語り〉と書物のあいだ(2019/07/)