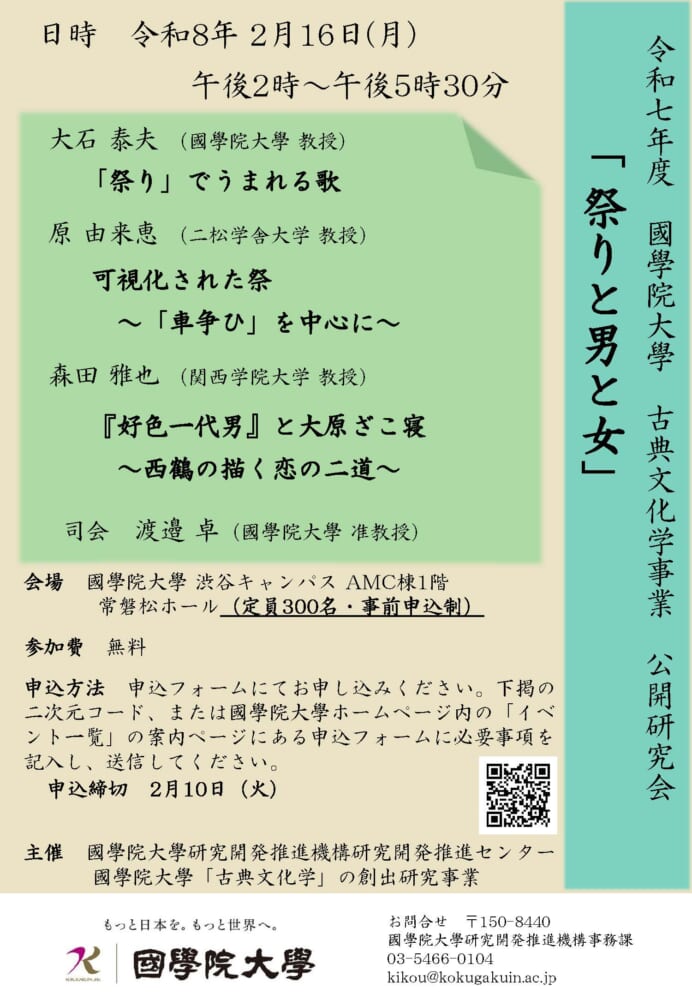国内旅行の旅先で、歴史的な町並みや建造物を楽しんだという経験をもつ人は、きっと多いだろう。そうした“生きた”観光資源として文化財を活用するというのは、地域にとって一挙手一投足で実現できるものではない。文化財保護の制度を理解し、さまざまなアプローチのもとに住民が納得できるかたちを模索してきた実践例が、日本社会の隅々に存在しているといえる。
下間久美子・観光まちづくり学部教授は、文化庁の職員としてその最前線に身を置いてきたプロフェッショナルだ。このインタビュー前編では、学生時代からの歩みを踏まえつつ、“理想の町並み”をめぐる歴史の一端を語ってもらった。
私の専門は、文化財保護です。建築や集落、町並み、文化的景観を守り、地域の発展に活かすことを主軸としているので、都市保全の側面もあります。この分野を選んだのは、建築学を学んでいた大学4年生の時でした。所属していた日本建築史研究室の大河直躬先生が長野県の調査を行っていたので、同行し、現場で図面をとる作業をさせていただきました。
歴史も好きでしたが、設計も好きだったので、大学4年生の時には前半で卒業研究を、後半で卒業設計をしました。日本の古建築も好きでしたが、この頃は、幾何学的な形と用途の合理性が結びついたルネサンス期の理想都市にも関心があったので、卒業研究ではユートピア文学における都市の形をテーマにしました。トマス・モア著、平井正穂訳『ユートピア』(岩波書店、1957年)、ウィリアム・モリス著、松村達雄訳『ユートピアだより』(岩波書店、1968年)等です。結果、ユートピアの実現は、都市の形よりもむしろ、格差を無くした公平で平等な社会の仕組みに希望を託しているという気づきを得ました。
一方、卒業設計は、1980年代後半のバブル経済期の風潮を捉え、卒業研究の成果とは真逆のコンセプトを置きました。個々人の幸せの集積が社会の幸福度を上げるという発想の基に、プライバシーが徹底的に保たれた団地設計を試みたのです。結果、先生方から異口同音に「むなしい」という感想をいただきました。私自身も同様にむなしさを感じ、調査で見た地方の地縁社会の良さに改めて関心が向きました。形と仕組みの関係が発端にあったので、今でも、文化財を見ることは人を見ること、文化財を伝えることは地域社会を伝えることだと思っています。
歴史にも計画にも携わりたかったので、大学院では都市工学に分野を移し、都市デザインとして町並み保存を学びました。指導教官は本学部の学部長である西村幸夫先生です。大学院では、先生にご紹介いただいて、新潟県村上市、岐阜県古川町(現・飛騨市)、長野県須坂市、新潟県相川町(現・佐渡市)、奈良県橿原市等、様々な場所で調査研究を行いました。沢山のご縁をいただき、沢山の方々に育てていただいたと思っています。

文化庁で働きたいと思ったのも、大学院時代に素晴らしい先輩方との出会いがあったからです。平成6(1994)年に文化庁に入庁しました。その2年前に日本はユネスコ世界遺産条約を批准していたので、文化庁からユネスコに職員派遣を行う検討がなされていました。運よく1995年から2年間、ユネスコに出向して世界遺産センターとバンコク地域事務所で世界遺産業務にあたることができました。この時に、途上国支援として文化財保護を女性の地位向上や貧困対策と一体的に考えながらプロジェクトの企画や実施を考える経験をしたことも、大きな糧となりました。このような20代の経験の中で、文化財との自分なりの向き合い方や、文化財保護において自分が目指したい方向が、自覚できるようになりました。
文化庁に28年間務める中で、最も長く、深く関わったのは防災や活用の促進です。若い頃の仕事で思い出に強く残っているものは、『文化庁月報』(WEB広報誌「ぶんかる」の前身)という機関誌に文化財建造物の火災予防(2000年1月)、保存修理(2000年6月)、環境保全(2005年7月)の考え方や、現状と課題を伝える特集を企画・担当したことです。
この頃はまだ、文化財所有者を始めとする様々な方から「文化財は釘1本も打てない」という苦言が聞かれました。文化財の現状変更規制が厳しく感じられる状況は否定できません。でも、制度とその運用の考え方が所有者や管理者の方々にもっと良く伝わっていたら、御苦労が少し軽減されるのではないかと感じられることもありました。
文化財の中や近くでは火を使っては危ないとして、火気厳禁としているところがあります。一方、囲炉裏や竈を使いながら今日に至っているものもあるわけですね。最も危ない状況の一つは、人々が火の管理の方法を忘れたり、怠ったりしてしまうことだと考えています。同様に、文化財を規制だけで守ろうとすると、人を建物から遠ざけ、必要な維持管理の慣習が失われてしまいます。施策としての活用の促進は、いわゆる「厳格な保護」を見直し、本来あるべき管理の目と手を時代に合った方法で取り戻すことです。その入り口として、文化財保護行政の仕組みや考え方をわかりやすいものにしたいという思いが常にありました。

私が関わってきたのは、「有形文化財」としての建築都市遺産です。歴史的な建物の多くは、建てられてから何度か改修されています。有形文化財では、その改変の経緯を解体調査で明らかにし、最も価値ある時代の姿を表わす「復原」が行われます。技術や材料、社会的・文化的背景等を知る上でも大切な行為です。明治初期にジョサイア・コンドルが工部大学校(現・東京大学工学部)に建築学の教師として来日し、西洋建築学を教えますが、この時に建築史という考え方も入ってきます。日本に建築史学を発展させる上で、解体調査と復原は重要でした。医学の発展に解剖学が不可欠であることと似ているかもしれません。
「有形文化財」においては、古社寺を中心に発展した解体調査が戦後に多くの民家にも行われるようになります。一方で、「民俗文化財」としての民家は、それが人々によって使われ続けてきた姿に価値があるとされるので、人が使わなくなっても現状の維持が基本とされ、復原は通例行われません。日常の生活文化を紐解く民俗学は、建築学を含む多様な分野と関係します。民家の保存活用の歴史には、大正期から昭和初期にかけての生活改善運動も含まれます。「復原」も大事な行為ですが、人の営みや、その跡を消さない有形文化財の保護のあり方を許容することも大事です。施策としての活用の促進は、対象に応じて保護方法の選択肢を増やすためのものであるとも考えています。
「伝統的建造物群保存地区」としての集落・町並み保存は、1970年代の草創期から、観光と一体的に捉えられてきました。長野県南木曽町の妻籠宿は、その代表的な事例です。過疎化が進み、新たな産業も起こしにくく、町並みを資本とする観光に大きな望みをかけたわけですね。「妻籠を守る住民憲章」は「売らない、貸さない、こわさない」という保存優先の原則だけが注目されがちですが、外部資本に荒らされることなく、良好で安全な生活環境を維持し、地域の住民が等しく町並みの恩恵を受けられるための様々な自主ルールを含んでいます。苦しかった頃の初心を忘れないようにしようということも書かれています。個人的には、町並みは大事な地域資源であることを思い起させるための一文と捉えています。
こうして考えてくると、先ほど触れたユートピア思想と実は近い、ということもまた興味深いと感じられないでしょうか。理想と現実を重ね合わせていく人々の営みについて、インタビュー後編ではもう少し語ってみたいと思います。
後編は「町並みをめぐる議論は人権と結びついている」>>
| 1 | 2 |
下間 久美子
論文
The Current Situation and Challenges of Cultural Propreties Protection in Japan(2024/05/14)
巻頭論文「国際専門家会合『文化遺産と災害に強い地域社会』の背景、目的、成果」(2016/03/31)