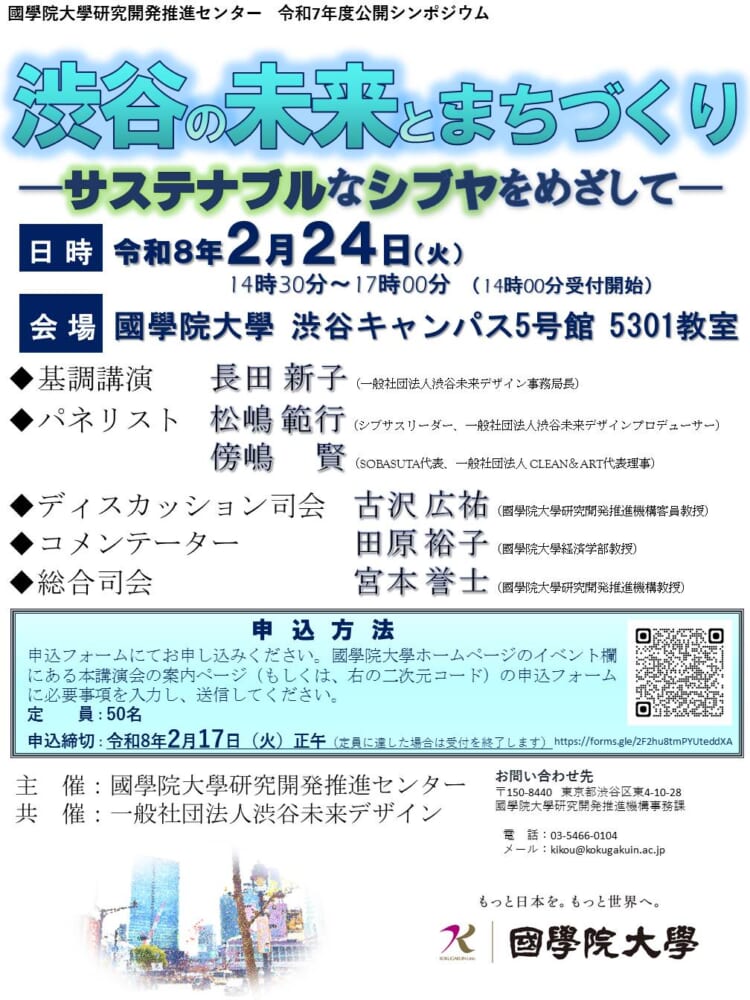新たな可能性が秘められた、未知の学問。国学を、そんな発想で捉え直そうとしているのが、松本久史・神道文化学部教授だ。既に定められた思想の解釈に終始するのではない道を模索する松本教授はいう、国学は“終わった”学問ではない、と。
総合知としてのポテンシャルを秘めた、いまだ完全には知られざる国学のありよう。そのダイナミズムについて、そして神道学との二本柱で研究を進める自身の歩みについて、前後編にわたるインタビューで訪ねた。
二足の草鞋ではないですが、二本の柱を立てて、同時に研究を進めています。ひとつは、国学という学問を、近世中期の発生以降、現代に至るまで通時的にとらえていく、ということ。もうひとつは、近世から近代へと流れていく神道史を考えること。この双方が、ときに密接に絡み合いながら、私の研究を構成しています。
特に国学にかんしては、“終わった”学問ではない、いまでも“ある”し、まだ多くの可能性を秘めているのだ、というスタンスをとっています。この見解について、徐々にお話ししてみたいと思います。

國學院大學日本文化研究所編『歴史で読む国学』(ぺりかん社、2022年)の冒頭で私は、「国学とは近世中期に発生した、後世の文献や外国の思想に依拠することなく、日本古典の文献実証を行い、それを通じて古代の文化を解明しようとする新たな研究方法による学問」だと書きました。
このインタビューをご覧くださっている方のなかでも、国学四大人(荷田春満・賀茂真淵・本居宣長・平田篤胤)、あるいは国学三哲(契沖・賀茂真淵・本居宣長)にかんして、ご関心を寄せておられる方は多いことと思います。もちろんこうした重要な国学者の思想について学ぶことには大きな意義があるのですが、しかし『歴史で読む国学』は、異なったアプローチをとっています。

左:國學院大學日本文化研究所編『歴史で読む国学』(ぺりかん社、2022年)
右:松本 久史著『荷田春満の国学と神道史』(弘文堂、2005年)
本書は私も責任者に名を連ねてきた同研究所「神道・国学研究部門」の研究プロジェクトの成果なのです。なかでも、国学にかんして各章を他の先生方にご執筆いただく際に、近現代にも多くの紙幅を割くような構成を心がけました。そもそも、各国学者の思想を章ごとに紹介・詳述するのではなく、国学をめぐる近世から現代までの歴史の流れを概観できるようなつくりにしています。書籍のおわりに、私はこのように記しました。
「従来の国学の歴史に関する叙述が、ややもすると主要な国学者の事績を年代順に並べるような、いわば『伝記体』的な国学史の記述が多く、通史的な国学を見通した本は必ずしも多くなかった。本書は、近世のはじまりから国学の展開を跡づけ、現代における『国学』に関する研究までを視野に入れ、日本史の展開に沿った『編年体』の国学史の構築を目指したものである」
こうしたことにかんする課題は従来、学生を相手に授業をしていても痛感していました。国学に興味を抱いている学生が、賀茂真淵や本居宣長といった主要な学者の思想について述べることはできても、それら国学全体の関係性や歴史といったこととなると、覚束ないところがあったのです。現代における最新の研究成果も含めて、国学を通史的に捉えるという視点を、学生はもちろん、広く社会に届けたい。それが『歴史で読む国学』のひとつの狙いでした。
これを私自身の研究に引き付けつつ、すこし別の角度からもお話ししてみましょう。私が修士から博士課程までの論文や学会発表などをもとにしながら上梓したのは、松本久史著『荷田春満の国学と神道史』(弘文堂、2005年)という本でした。荷田春満は先ほど触れた「国学四大人」の始祖と位置づけられてきた人ですが、京都の稲荷社(現在の伏見稲荷大社)の神職の家に生まれ、やがて『日本書紀』の注釈書などをものしていくようになったその歩み、学問としての実態は、実はあまり詳らかにされていなかったのです。

私の書籍は、荷田春満による国学の言説を、神道史と共に考えてみよう、という意図でした。実際、十七世紀の後半に最初期の神仏分離の動きが進むなかで、稲荷社家も自らの由緒から仏教を切り離していく必要があり、荷田春満はそうした神道史の流れのなかで学問形成をしていった、と見ることができます。
彼は『日本書紀』神代巻にかんする注釈や門人に対する講義を行っているわけですが、私がかつて前掲書所収の論文「荷田春満の神代巻解釈の形成過程 稲荷社祭神説と関連して」のなかで、「神代巻解釈中の各祭神を検討することから春満の神道思想と稲荷祭神説が密接に関連していることが明らかになったのではないだろうか」と述べたのは、国学と神道史を実証的に結び付けていこうとした研究方針によるところがあるわけです。
実は国学の研究というものは、各学者の思想的な主張、その内容ばかりを追うことになりがちである、という課題を抱えてきたと、私は認識しています。いえ、決してそうした思想面での研究を軽視してよい、というわけではなく、その重要性を踏まえたうえでいうわけですが、テクストに向き合うのみ、場合によっては部分と部分を切り取ってつなぎ合わせているだけでは、その背後にあるコンテクスト、すなわち社会的・歴史的な背景を取りこぼしてしまうのではないか、という懸念を覚えるのです。
たとえば荷田春満にしても、なぜこのような国学の思想家が生まれたのかということは、彼が稲荷社の神職の家に生まれているということ、そして稲荷社をめぐる当時の状況を踏まえない限り、わからないのではないでしょうか。
既に確定しているテクストをもとにだけではなく、きちんと、そして現代の最新の知見も踏まえながら幾度も、歴史の流れのなかに位置づけなおしていく。それが、国学が“終わった”学問ではないと私が述べるところの、ひとつの意味合いになります。
さて、国学は総合知であるということもお伝えしたいのですが、そのためにもインタビュー後編ではすこし、私自身の歩みについてもご紹介できればと思います。当初は史学を学び、一般就職もした後に学問の道に入るという、遠回りした人間として、お話しできることがあるかもしれません。
後編は「国学は人文知ではなく、総合知である」>>
| 1 | 2 |