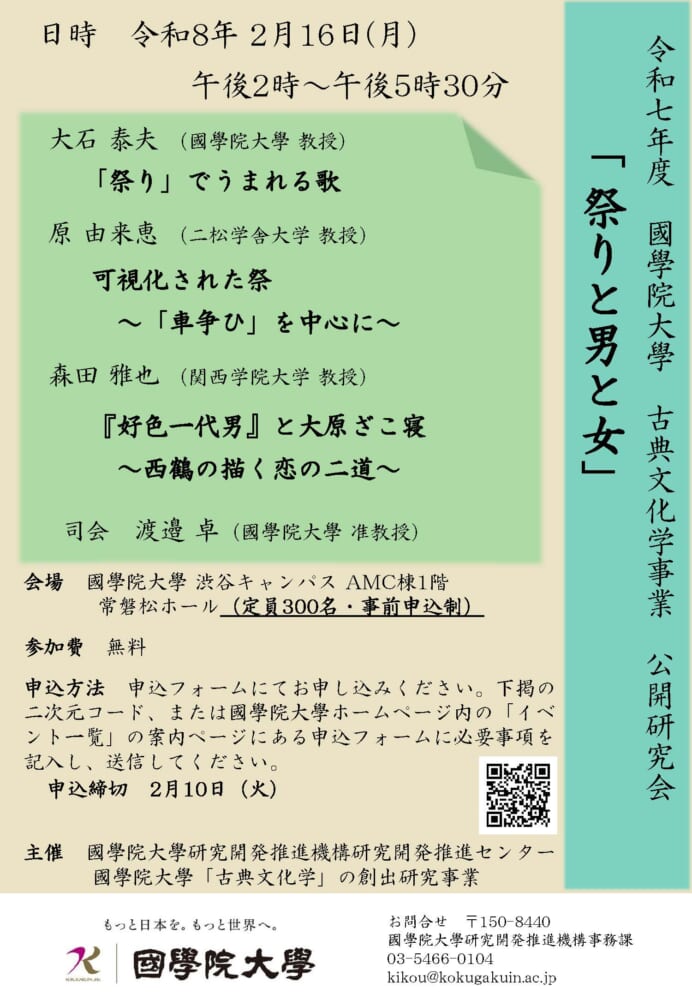スポーツ中継を見ていると、さまざまなデータが表示される。しかし一昔前まで、そんな状況は夢物語だったといっていいかもしれない。21世紀に入ろうとする時期にスポーツ情報戦略に目覚め、最前線で活躍してきた渡辺啓太・人間開発学部健康体育学科准教授は、その裾野を広げてきた第一人者だ。
バレーボール女子日本代表チームのアナリストとして平成22(2010)年に世界初となるiPadを用いた情報分析システムを考案・導入し、 32年ぶりの世界選手権でのメダル獲得に貢献。平成24年ロンドンオリンピックでは28年ぶりとなる銅メダル獲得をバックアップ──華々しいキャリアのなかで培ってきた知見を大学という場で共有している渡辺准教授に、スポーツ情報戦略の面白さについて訊ねた。
専門としているのはスポーツ情報戦略で、特に私が長年分析してきたバレーボールに軸足を置きながら、研究と教育にあたっています。スポーツにおいて、組織あるいは個人における目標達成や課題解決をするために、テクノロジーやデータを有効活用して意思決定に導く支援の一連のプロセスが、スポーツ情報戦略です。
スポーツには、感覚的な判断がつきものです。実際、そうした直感や主観、経験にもとづいた指導やコーチング、戦略の選択といったものも多くおこなわれてはいるのですが、選手の起用方法や試合中の戦術展開において、情報を有効に活用してより適切で、よりよい意思決定ができるように手助けしていく役割を担っています。
多くの方が、さまざまなスポーツで情報戦略が活用されている場面をご覧になったことがあるかと思いますが、私が高校生の頃にスポーツ情報戦略に興味を抱くようになったのがその黎明期だった、ということを思うと、活用のレベルも展開の幅も大きく変わってきたことを実感しています。

もうすこし具体的に、お話ししてみましょう。私が主に関わってきたのは、団体競技、特に球技におけるパフォーマンス分析で、バレーボールを中心としているわけですが、その周辺にはサッカーや野球、バスケットボールなど、他のスポーツも隣接しています。
それぞれに競技特性が異なりますので、スポーツ情報戦略の活かし方も、当然違います。分析が比較的しやすいといわれているのは、野球です。あらかじめ状況がセットされている場面が多い、というのがその理由ですね。ピッチャーとバッターが1対1で勝負するところから毎回プレーが始まりますし、意図せぬタイミングでいきなりピッチャーが投げてくるということもありません。一球投げるごとにカウントは変わっていきますが、都度プレーが止まって整理された状況からリスタートしていくため、分析する上での条件分岐、つまりは場合分けがしやすいといえます。日本のプロ野球をご覧いただければわかるように試合数もとても多く、集めることができる情報量が申し分ないということも大きいですね。
バレーボールも、野球に近いところがあります。サーブからはじまり、点が入った瞬間に一連のプレーがいったん止まる。そこで都度、区切れ目があるわけです。これはたとえば、卓球やテニス、バドミントンといった、コートの中心のネットを隔てて試合をするタイプのスポーツとも似ているところがある。
いま挙げた卓球・テニス・バドミントンなどには、ダブルスが存在しますから、集団競技としての側面が存在します。ただ、これらとバレーボールとのあいだでは、決定的な違いもあるんです。それは、バレーボールは自分たちのコートのなかでボールをつなぐことが許されている、という点です。
卓球やテニス、バドミントンにおいては、相手から来たボールやシャトルを自ペアのあいだでつなぐことは禁じられていて、一回で敵陣に返します。相手が強く打ってきていれば守備的なリターンに、ゆるい打ち方でしたらチャンスとみなして攻撃的に返していくわけですね。こうした頻繁な応酬の中で守備と攻撃の場面が切り分けにくいことが、分析するうえでは一定の難しさにつながるんです。

一方でバレーボールの場合は、相手からネットを隔てて飛んできたボールを、まずはレシーブし、その後につないでアタックにもっていきます。つまりは、守り、つなぎ、攻めるという3段階が基本的なワンセットになっていて、守備の場面と攻撃の場面が切り分けやすいという特性がある。ネット競技のなかでも、特徴的なところですね。
そのうえで、バレーボールの情報戦略と、実際の選手たちが魅せる創造的なプレーとのあいだの領域にある、面白さと難しさというものがあります。プレイヤーたちはネットを挟んで、常に駆け引きをおこなっています。相手の弱点のようなものは蓄積された過去のデータから分析できたとしても、次にこうしたプレーをするだろうという予測というものは、なかなか困難です。いまだったらAIに大量のデータを処理してもらえば予測ができるのでは、と思われがちかもしれませんが、コートの中では一定の駆け引き、もっといえば相手に対するごまかし合いや騙し合いというものが常に発生しています。
インタビューの後編では、こうしたバレーボールの複雑さとテクノロジーの関係、あるいはスポーツ情報戦略について大学という場で学生たちと学んでいくことの意義などについて、ご紹介してみたいと思います。
後編は「活用が進むスポーツ情報戦略の現状」>>
| 1 | 2 |
渡辺 啓太
論文
スポーツ現場における国内情報戦略専門スタッフの実態調査(2023/04/03)
サイドアウト率とブレイク率による勝率の予測 南部勝率:バレーボール版ピタゴラス勝率の導入の試み(2023/07/)