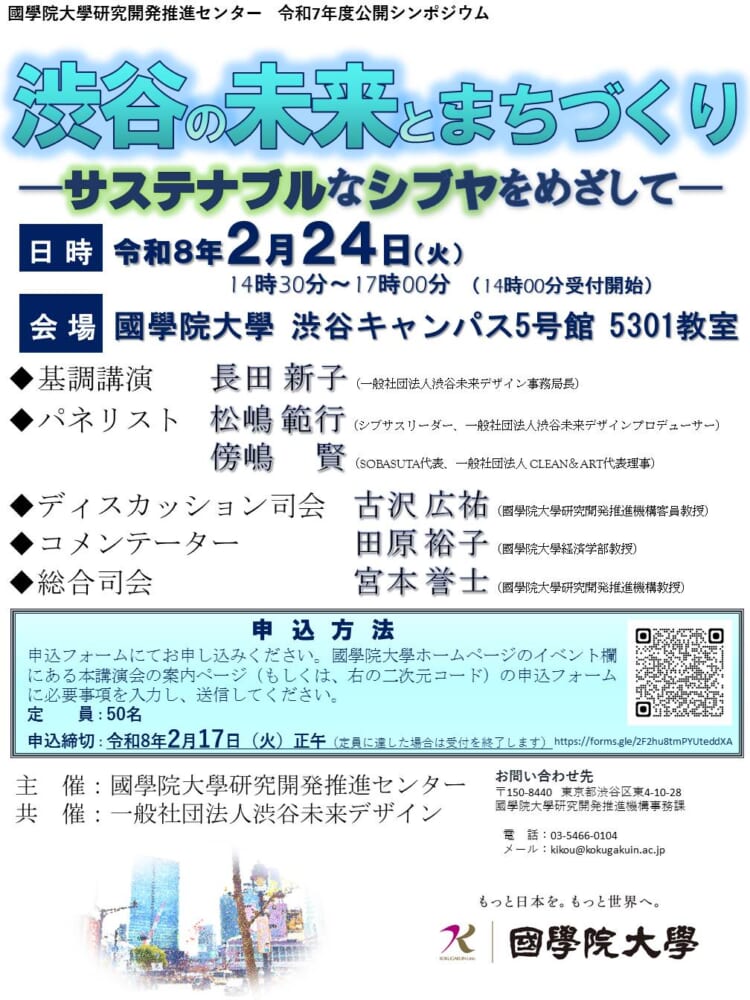地方の行政を考えるには、その制度上の“遊び”や”余地“をとらえなければいけないのではないか……と、稲垣浩・法学部法律学科教授は語る。人間くさい揺らぎを残している地方行政の姿をじっくりと見つめるからこそ、そのリアリティは浮かびあがってくる。
地方行政の実情に光を当ててきた稲垣教授だからこそ、その課題にも目を向けている。このインタビュー後編では、在日外国人への言語対応にかんして進めているという共同研究についても、熱をこめて語ってくれた。
研究テーマに悩んでいた大学院生の頃に耳にして面白いなと思ったのが、国家公務員と地方公務員のキャリアと、その制度上の関係性です。特に興味を惹かれたのが、出向をはじめとした人事交流でした。国の職員、つまりは官僚が都道府県にやってきて、仕事をするわけです。それを可能にしている制度というものがある。
実は地方自治体での職員採用は、学生などがイメージするような筆記試験を中心とする「採用のための競争試験(採用試験)」だけで成り立っているわけではありません。実はもうひとつ、書類選考や面接などを中心とする「選考」というルートも存在します。この「選考」では、複数の候補者から選ぶのではなく、予め特定された人のみを対象とする場合があります(地方公務員法第17条の2)。
なぜこの「選考」という制度が地方公務員法で採用されたのでしょうか。その理由にはいくつかあり、ひとつは国家公務員が地方へと出向する人事交流を円滑に行うためです。他にも、人事委員会を置かないような中小の自治体などで、多大な費用がかかる「採用試験」を行わなくても職員採用ができるようにするため、ということが理由として挙げられていました(当時このことは「試験経済」の問題と呼ばれていました)。また、自治体は、この地方公務員法の規定をもとに、先に述べた競争試験では求める人材が確保できない、応募者がいない場合などを念頭において、選考採用のルールを作成し、職員を採用してきました。公務員試験では、しばしば景気の良いときには民間に就職希望者が流れて、採用試験の応募が少なくなるといったことはよく聞きますよね。このように、職員採用を柔軟に行うために複数の採用ルートを作ったわけです。
ただし、これは結果的に、地方公務員の採用において、実質的な政治任用を行う余地を残すことにもなりました。実際にも、昭和40年代くらいまでは、自治体の首長が、自分の下で働く部長や課長などの幹部職員を「競争試験では確保できない人材」として役所の外部から連れてくることがしばしば見られました。
行政学というのは、こうしたブレのある領域とでもいえばいいのか、法律をそのまま解釈するような規範的・規律的な分析にはあまりなじまないような制度の生々しい実情について、考えていく学問だと思っています。そしてそうしたありようは、毎年発行される地方自治体の職員名簿にじっくりと相対して、「あれ、なぜこの人がこの年にいきなり課長に就任しているんだろう」というようなことをひとつひとつ見ていくことからわかってくることも多いわけです。インタビューの前編でお話ししたように、市役所の職員名簿を読んでいた幼少期から、基本的には変わっていないですね(笑)。
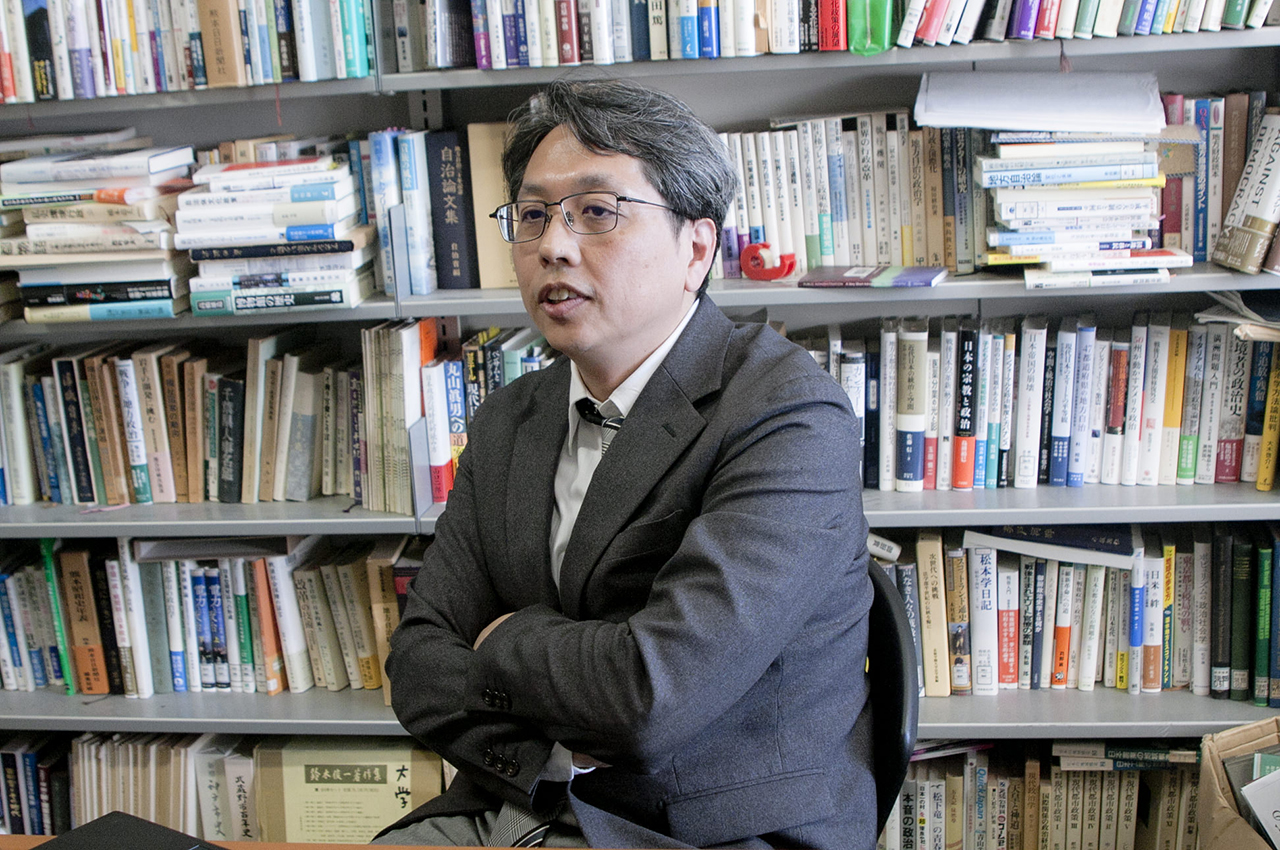
博士論文で扱った、戦後の地方自治体の局部組織制度についても同様です。地方自治法による規定や各省庁との関係性のもと、地方は国のいう通りに組織を編成しなければいけなかったというのが、それまでの通説でした。ところがよくよく当時の資料を検討していくと、そんなに一方向的に決まっていたわけでもないのではないか……ということが見えてくる。
つまりは、やはり遊びといいますか、相互的な関係性のもとに制度が変化していく余地のようなものがあるのではないか、ということが徐々にわかっていったのです。
こうしたことは現代の「改革」でも見られます。たとえば地方自治体で何か変革をもたらそうとするとき、組織の再編は手をつけやすいものではあるのです。役所の部局を新しい名前に変更するなんていうのはしばしば見られる手段です。こういうと元も子もないですが、変革がもたらされた気になるでしょう(笑)。しかも組織の中身が大して大きく変わったわけでもないので、行政活動に特段大きな問題も起きず、それによる責任問題にも発展しにくい。
では、組織再編は地方の側の独断によってのみなされていたのかというと、決してそうではない。まず、国との関係性があります。地方自治法による規定があり、各省庁との関係性がある。先ほど述べたように、戦後の省庁は人事交流で府県の関係部局に官僚を送り込んできましたから、出向ポストの削減につながるなど、省庁の反発を受けそうな改革は難しい。そこで、社会学的新制度論などで議論されるように、同様の変革を既に実行してきている他の地方自治体の例を、横目で見て、適当な改革の落としどころを探るということがあります。
合理的な選択をしているようで、その選択肢は予め、ある程度絞り込まれているわけです。この博士論文をもとに書籍『戦後地方自治と組織編成 「不確実」な制度と地方の「自己制約」』(吉田書店、2015年)をまとめた際は、局部組織の編成をめぐる「不確実性」を克服するため、「自己制約」をしながら改革を「正当化」するという表現をしました。
先ほど制度上の遊びや余地といった表現をしたのは、こうした領域の話です。ガチガチな制度で縛るのではなく、むしろ緩い枠組みにしておくことでまわっていくものがある。責任も分散されていきますし、だからこそ地方行政というものを持続させてくることができた、という側面はあるわけです。一方では、各地方で多少の変革がもたらされているように見えたとしても、全国的にもまた同じような組織や制度がつくりあげられてきた、という厳しい表現もできるでしょう。

とはいえ変革しているふりばかりでは、地方をはじめ日本社会が成り立たなくなりつつあるのもまた事実です。最近私が進めている研究のひとつに、武田珂代子先生(立教大学異文化コミュニケーション学部特別専任教授)という翻訳通訳研究を専門とする方との共同研究があります。地域に居住する外国人住民に、自治体はどのように言語面で対応するのか、通訳の専門性と自治体組織の構造という二つの視点から、自治体への調査などを通じて研究を進めています。
本来、住民であればアクセスや利用が可能なはずの行政サービスなどに、言語をめぐる障壁があることでたどりつくことができないという方々が増えつつあります。対応できている自治体であっても、多言語対応が可能な担当者の肩にすべてがのしかかっているような、いわば限られたマンパワーに頼り切っているというところも少なくないのです。同じ内容を伝えるのでも相手によって伝え方が異なるように、そうした行政の言語対応というものは、機械翻訳によっても、なかなか処理しきれるものでもありません。
住民が日本人あるいは日本語話者であることを前提としてきた日本の地方行政という制度は、そこに外国人が住んでいるという当たり前の状況に対して、まだきちんと認識や対応ができていないのではないか。言語の問題は、言語それのみにとどまるものではなく、住民の文化的社会的背景、国際関係や国家の在り方の問題にもつながっています。これまでのように、できるだけ混乱をもたらさないよう、小さな変革ばかりを積み重ねてきた地方行政の制度では、もはや立ち行かない事態が発生しているといっていいと思います。すでに、外国人住民の多い自治体などでは、国の対応を待たず、現場レベルで独自に工夫しながら対応するところも見られるようになってきました。
そうしたこれまでの状況を作り出した背景には何があったのか、いかにすればこうした状況を変えていくことができるのか。地方行政をめぐる制度は、今後も現実にきちんと対応することができるのか。私がこれから考えていきたい課題のひとつです。
<<前編は「地方行政の制度は、生々しい?行政の制度、組織や人間関係、働き方とは」
| 1 | 2 |
稲垣 浩
研究分野
行政学・地方自治論
論文
昇進試験制度下のキャリア初期条件の影響 札幌市役所を事例としたイベントヒストリー分析(2025/09/30)
自治体ライフヒストリー研究の方法と課題 ー研究者・職員協働型研究の経験から―(2024/12/01)