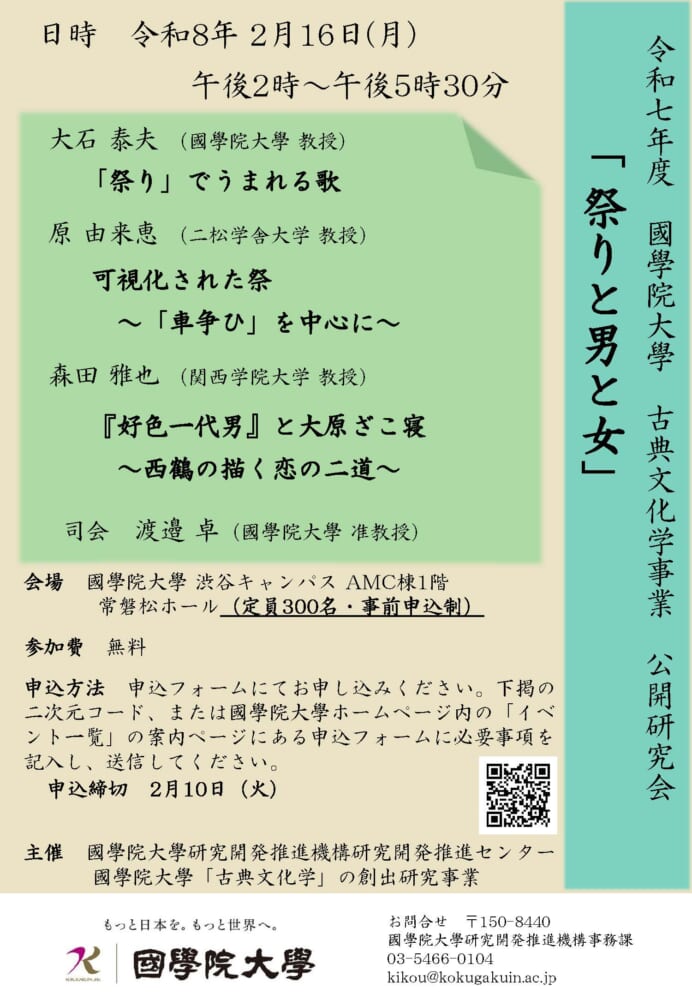何やら楽しげに歓声を上げ、あるいは秘密めいたやりとりをしながら、自分たち独自のやり方で遊びを構築していく子どもたち。その集団の傍らで観察を続けてきたのが、結城孝治・人間開発学部子ども支援学科教授だ。
その観察から導き出されてきた教訓は、子どもたちばかりでなく、私たち大人にも当てはまるものだという。集団において周囲を困らせてしまうような人物がいる場合、その人の個人的な責を問うのでは問題は解決しないというのだ。集団の問題は、集団の関係性のなかで解きほぐしていく──結城教授が子どもたちのやりとりに見出だしているのは、集団ごとに異なる、まさに千差万別の人間関係のなかに潜む問いだ。
幅広く調査や研究を行なってきていますが、その興味の中心にあるのは、子どもたちの遊びというものが組織されていく過程です。
複数の子どもたちが、ワイワイと何事かを話したり、道具を渡したり渡されたりしながら、その場での遊びというものは組織化されていきます。その遊びは、いったいどうやって成立しているのだろうということが、大学の学部生の頃からずっと気になっているんです。
実はこうした、複数名の人間がいる場での共同的な活動の組織化、あるいはその活動のクオリティというテーマは、この記事を読んでくださっている方々にとっても大きく関係していることなのではないかと思います。私自身も、子どもたちと向き合いながら、そうした広い意味合いでの興味関心というものを抱いています。
大人の読者の方であれば、日常的に仕事で会議をおこなう人も多いはずです。グダグダとした会議になってしまったり、別のメンバーとならばササッと物事が決まっていったりという経験は、身に覚えがあるのではないでしょうか。では、その過程というものは、どのように進展していっているでしょうか。
子供たちの遊んでいる様子を見ていると、リーダーシップを発揮するひとりの子が発言をし、他の子がそれを追認し……という活動の生成、その相互の影響が観察されます。しかもその過程、生成の様子は集団ごとに異なるわけです。
興味深いのは、その集団ごとの人間関係というものが、如実に反映されていくということです。その場での遊びや会議が成立していく手前に、既に構築されている人間関係をもとにして、共同的な活動が都度組織化されていくんですね。

これは、ある集団における共同的な活動が上手くいっていない場合、特にその責がひとりの人間にあるように見えるケースにおいて、その人ひとりに問題を集約しても事態は解決しない、ということを意味しています。
私は普段の仕事の一環として、保育の現場を指導するということが度々あります。たとえば、子どもたちの集団のなかにひとりの「気になる子ども」──保育者の目からは、子どもたちの集団のなかで問題を引き起こしているように見える子がいて、その子をどうにかしてほしいということで、私が現場に参加していくということがあるのです。
現場の方からすれば、その子自身の立ち居振る舞いというものに、専門家としての見地から、集団に馴染む行動へと変えていってほしいわけですね。
しかし既にその集団において、当のひとりの子どもと他の子どもたちの人間関係というものがつくられているとするならば、その子ひとりの行動が多少変わったとしても、集団の状況自体は変化していきません。ひとりの行動が変化しても、その行動は集団のなかでなされていく人間関係の再生産に収斂(しゅうれん)されていってしまい、状況は変わらずに循環していってしまうのです。
再び大人の私たちに引きつけてみれば、あいつが場を乱しているとか、あの人はリーダーシップを取れていない、というような非難めいた感情が集団のなかに生まれるということがあります。しかし私たちは既にその集団の人間関係のなかで適応的に生きてしまっていますから、お互いに微妙な距離感を保つことが優先されていく。すると、そこで起きている問題というものは、解決されなくなっていってしまうんですね。
集団みんなの人間関係を変えていかないと、その集団において発生している問題というものはほぐすことができない。これが、子どもたちの遊びの過程を観察するなかで、私が考えていることなんです。

ですから、先ほど触れたような「気になる子ども」、あるいは困った子、保育しづらい子という個人にフォーカスした目線自体が、集団で起きている問題の解決を妨げてしまっているといえます。
たとえば保育の現場に発達障害をもっているお子さんがいて、その子がいる集団では、子どもたちがうまく共同的な活動を展開できないとします。こうした場合、そのひとりの子の行動をどうにかするという対処療法に取り組んでも仕方がない。根本的に、その子を含めたみんなの関係を変えていかないといけないのです。
これは近年よく論じられるようになっている、障害の「個人モデル」と「社会モデル」にも近い話です。障害によって起きている問題について、その障害者自身にフォーカスするのが「個人モデル」であり、一方で社会的障壁との相互的な関係において考えるのが「社会モデル」です。たとえば私は地形のアップダウンが激しい地域に住んでいます。足腰の不自由な住民の方の移動が難しいという場合、仮に自治体が電動自転車の普及を支援してくれたとしたら、それは社会モデルによる問題の解決ということになります。
個人ではなく、集団を考える。子どもたちの様子から、私はこのような研究者としての視座をもつに至りました。では、子どもたちの様子というものは、そもそもどのようにして観察するのか。そのあたりをインタビュー後編ではお話ししたいと思います。
後編は「心理学から見る子どもとの関係性の築き方」>>
| 1 | 2 |
結城 孝治
研究分野
臨床発達心理学、発達心理学
論文
幼児期における教育相談の意義についての一考察(2018/02/28)
保育実習事後指導が保育者効力感及び実習に対する不安に及ぼす影響(2017/02/28)