
『源氏物語』の表現そのものに、真摯に向き合うことからはじめよう──。竹内正彦・文学部日本文学科教授のそうした研究スタンスは、さまざまな観点のもとで築き上げられてきたものだ。そのひとつは、インタビュー前編で触れた、『源氏物語』の研究史をふまえた判断。そしてこのインタビュー後編で語っていくのは、折口信夫らが、遠く時代を隔てた古典に触れてきた姿勢や方法である。
物語としてのありかたに向き合うと、『源氏物語』に登場する、ある歌をめぐる通説も新たな検証が可能になるという。なにより竹内教授自身の研究者としての歩みもまた、一歩一歩、物語の豊かさに魅了されていくプロセスだったようだ。
そもそも私が国文学研究の道に進んだ大きなきっかけは、高校生のときに受けた古典の授業での体験です。それまで古典の勉強といえば、重要古語や文法、古典常識などを暗記すればよいように思っていたのですが、ある授業で、教科書に載っていた和歌を一首ずつ担当して調べてきたものを発表するということがあったのです。私に割り当てられたのは、『新古今和歌集』の俊成女の歌でした。私は真面目な生徒でしたから(笑)、図書館に行って注釈書を比較するなどして調べたんですね。そうしたら、ひとつの歌でも現在に至るまでさまざまに解釈が分かれているということを知りました。
古典は、長い年月をかけて読み継がれてきているのに、いまでもそんなに解釈が分かれているのかと衝撃を受けました。そして、古典にも新たな発見の余地があるんだと思ったのですね。ならば、自分にできることもあるのではないかと考えて、古典研究の道に進むことにしました。
やがて本学の門を叩いたときには、一刻も早く、本格的に研究をはじめたいという心持ちでした。当時、毎月出ていた『国文学』(学燈社)という雑誌の彙報には、最新の論文目録が記載されていました。私は、高校の下校時に書店に寄るのを日課にしていましたので、それを目にして、本学には学生の論文集を出している研究会があることを知っていました。そこで、入学後、すぐにその研究会に入ったのです。
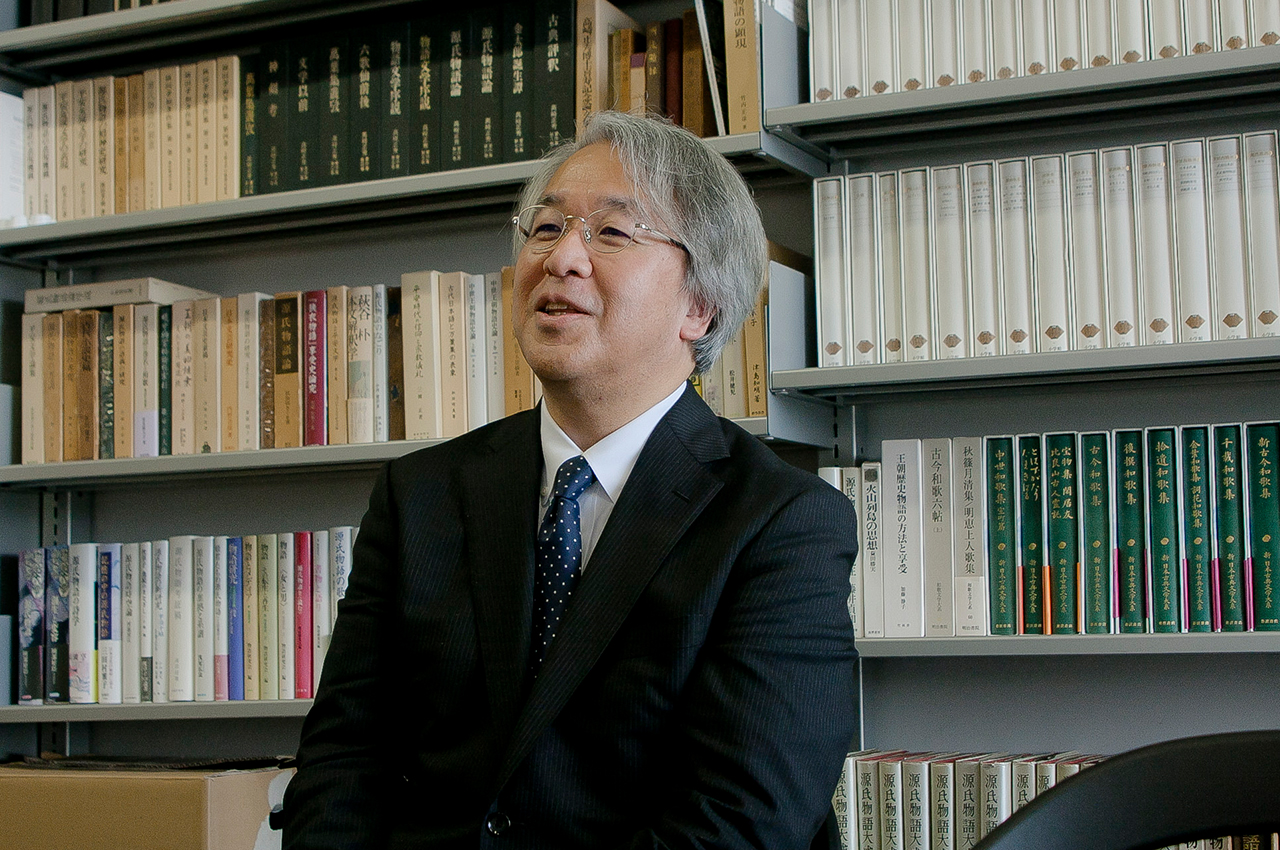
高校の先生からは、『源氏物語』の研究は面白いけれど、すでに多くの研究がなされているから、まだ研究があまり進んでいない『うつほ物語』や『堤中納言物語』などに取り組んだらどうかとアドバイスされていましたが、その研究会で『源氏物語』を読んでいるうちにすっかり魅了されてしまいました。最初は先輩方の議論にまったくついていくことができませんでした。それでも自分で『源氏物語』を通読し、議論にでてきた先行研究などを読んでいくうちに、少しずつその面白さがわかってきました。研究対象としてはもちろんのこと、とにかく文学作品として面白いので、ならばこの『源氏物語』に生涯をかけて真正面から取り組んでいこうということで大学院へと進み、思えば、それからもう四十年近くになるのですね(笑)。
『源氏物語』にどのようにアプローチするか。自身の方法を模索していく過程で、国文学者であり民俗学者でもある折口信夫の考え方に、しばしば刺激を受けてきました。折口信夫は民俗に古代を見ようとしましたが、この折口の方法は、現在の私が平安時代の物語を読む場合にも有効だと考えました。折口には「古代の顕現」という短いエッセイがあります(『全集』19巻所収)が、そこでは庭に咲く山茶花に現れてくる古代について書かれています。山茶花はそこに咲いているにすぎないが、それを見るものに古代の記憶が現れ出て来るということを述べています。『源氏物語』もまたそれを読むもののなかに顕現するものと考えることができます。ただし、その現れ方は思い込みであってはいけません。『源氏物語』の「読み」は緻密に織り込まれた表現の秩序に従わなければならないのです。物語が成立した時代をふまえるのはもちろんのこと、物語が読み継がれてきた歴史をもおさえながら、表現を丹念に読み込むことにとって、はじめてその表現世界を生き生きとした姿を現してくるものだと考えています。折口信夫、そして折口に師事した国文学者・高崎正秀先生の方法も踏まえながら、私は『源氏物語』を読んできているのです。

そうした視点で、『源氏物語』のひとつの場面を取り上げてみましょう。「梅枝」巻には、かねて光源氏との仲について噂のあった、朝顔の姫君という女性が登場します。光源氏からの恋情は拒みながらも、しかし完全に心を閉ざすことはない、という独自の立ち位置を保ってきた人物です。
そんな朝顔の姫君は、「梅枝」巻に、こんなかたちで描かれます。
光源氏の娘である明石姫君が、東宮のもとへ入内するにあたり、光源氏は、姫君に持たせる薫物(たきもの)の調合を、六条院の女性たちのほかに、朝顔の姫君にも依頼していました。しかし、梅の満開の折、朝顔の姫君から送られてきた薫物には、なぜか「散りすきたる梅の枝」(花がほとんど散ってしまった梅の枝)につけた文が添えられていました。そして「花の香は散りにし枝にとまらねどうつらむ袖にあさくしまめや」(梅の花の香は散ってしまった枝には留まりませんが、たきしめる姫君の袖には深く染みつくことでしょう)という歌も記されていました。
さて、この場面で気になるのは、梅の花が満開の折に、朝顔の姫君がなぜわざわざ「散りすきたる梅の枝」を送ってきたかということです。歌のなかには「花の香は散りにし枝」ということばも見えますので、歌の内容を可視化したものであったのでしょうが、なぜ入内のお祝いの品に「散りすきたる梅の枝」なのか。
現在、朝顔の姫君の歌のなかの「散りにし枝」には、朝顔の姫君自身の老いの哀感がこめられているとも解釈されます。朝顔の姫君は、その歌に、自分はもう老いて花が散った梅の枝のようだという気持ちをこめて送ってきたとする解釈ですが、どうでしょうか。
朝顔の姫君は、あくまでも薫物を送る折の挨拶としてこの歌を送ってきたのにすぎないわけで、そこに個人的な感傷などが入る余地はありません。では、なぜ「散りすきたる梅の枝」を送ってきたのか。光源氏は、朝顔の姫君に対して、庭先の満開の梅の枝をつけて返事をします。散った梅の枝に満開の梅の枝を返す。そのふるまいは、散った梅の枝が満開になっていくさまをあらわすことになります。散った梅の枝が、ふたりのやりとりを経ることで満開になっていく。つまりこれは、明石の姫君の裳着と入内を祝う、いわば儀礼的なやりとりなのだというのが、私の考えです。
このふたりの儀礼的なやりとりには相手に対する信頼が必要です。朝顔の姫君は光源氏がどのような反応を示すかを予期して、花の散った梅の枝を送り、光源氏も朝顔の姫君の意図を瞬時に理解して満開の梅の枝を返しているのでしょう。
ふたりは阿吽の呼吸でそうしたやりとりをしているのですね。こうしたことができることが朝顔の姫君の魅力であり、朝顔の姫君が光源氏と絶妙な距離を保ちながら長年交流できた理由にもなっていると考えています。
折口信夫は逆説的な意味合いをこめ、自身の方法を「文学をおもしろくなくする方法」だと述べていたといいます。「梅枝」巻に引きつけて考えれば、朝顔の姫君の歌を儀礼的なやりとりのなかで解釈するのは「文学をおもしろくなくする」ことかもしれません。けれども、朝顔の姫君の歌に老いの哀感などを読みとるのは、やはり近代的すぎる解釈のように思います。そして、そうした解釈は、平安時代という時代を背景とした『源氏物語』という文学作品の本質を見えなくしてしまうのではないか、ということなのです。現代人である読者が、現代の価値観をそのまま表現世界に持ち込むことは慎重であるべきだと思います。『源氏物語』の「読み」は緻密に織り込まれた表現の秩序に従わなければならない、というのはそのようなことをさしています。「文学をおもしろくなくする方法」は、実は『源氏物語』を「おもしろく」読む方法でもある、といえるのではないでしょうか。
なかなか難しいことですが、私たちは、私たちの方から『源氏物語』に近づいていくほかはありません。『源氏物語』の時代、人びとは何を見、何を聞いて、どのようなことを思い、感じていたのか。物語の表現はもちろんのこと、他の文学作品のほか、史料なども丹念に読み込み、近接の諸科学の成果をもふまえながら、表現世界を生き生きととらえる「読み」を、これからも実践していきたいと考えています。
<<前編は「一匹の猫から始まる悲劇 源氏物語の表現世界そのものを見つめる」
| 1 | 2 |
竹内 正彦
研究分野
中古文学
論文
明石の鐘の声―明石一族物語の原風景―(2026/02/01)
指貫の裾を濡らす光源氏―『源氏物語』「蓬生」巻の常陸宮邸訪問をめぐって―(2025/12/20)

