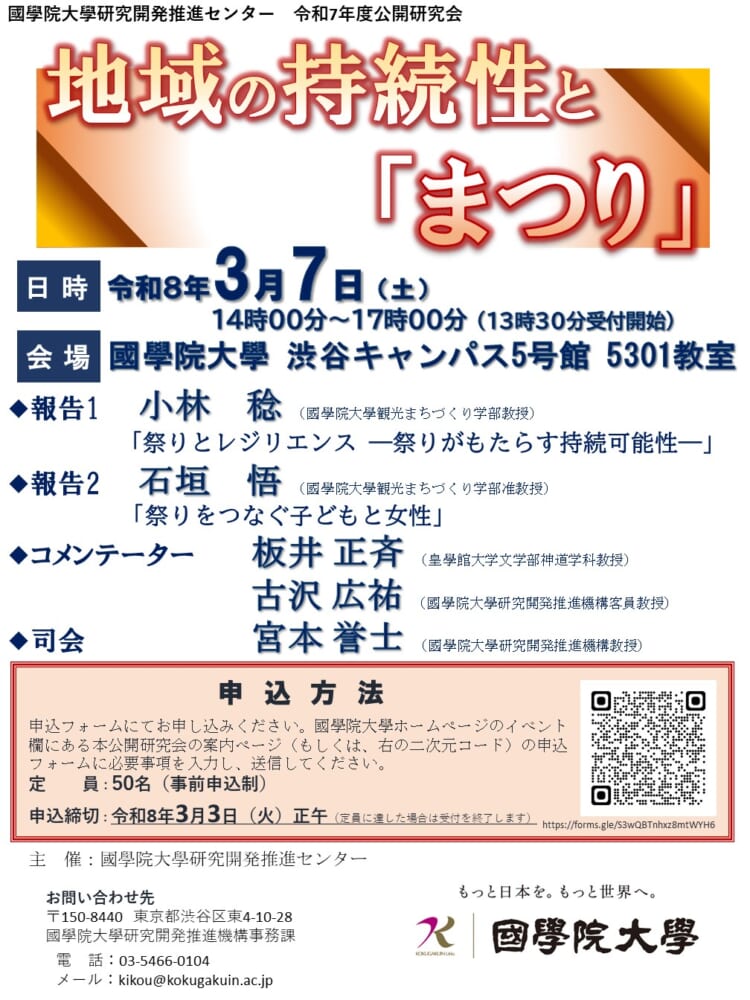水面下にある水中遺跡を調査・研究する、水中考古学。海のなかのみならず、その学問分野自体に、池田榮史・研究開発推進機構教授が“ダイブ”したのには、どんな理由や経緯があるのだろう。
水中考古学の最前線について尋ねたインタビュー前編を踏まえつつ、後編で詳らかにされるのは、偶然に偶然が重なるような、ひとりの水中考古学者の誕生譚である。自分の目の前も見通せない水中でさえ、遺跡や遺物が見つかるように、研究者の歩みもまた、ふとしたきっかけで大きく転じるものなのかもしれない。
水中考古学という世界に私が足を踏み入れ、しかもここまで深くかかわるようになるまでには、縁が縁を呼ぶような、ある経緯がありました。
もともとは、本学で助手をしていました。その頃は、陸の考古学をやっていたんです(笑)。私は熊本県天草の出身であり、学生時代は九州の古墳のことを研究していました。古墳時代の後半期になると、朝鮮半島からの影響のもと、日本の古墳の中に遺体を収める部屋=横穴式石室がつくられるようになるのですが、これがどのようなプロセスを踏みながら日本に広がっていくのかを研究していたんです。
ところが助手になって3年が経つ頃、師匠である先生が、琉球大学でポストの募集が出たぞ、と願書を持ってきたんです。「先生、すみません、私は一度も沖縄にいったことがないのですが……」といったのですが、これはもう時効だからお伝えしてもよいでしょう、先生は「こういうのは宝くじと一緒だ」とおっしゃったんですね(笑)。出してみなければわからない、ということで応募してみたら、これもご縁なのでしょう、沖縄行きが決まったのでした。1984年のことです。
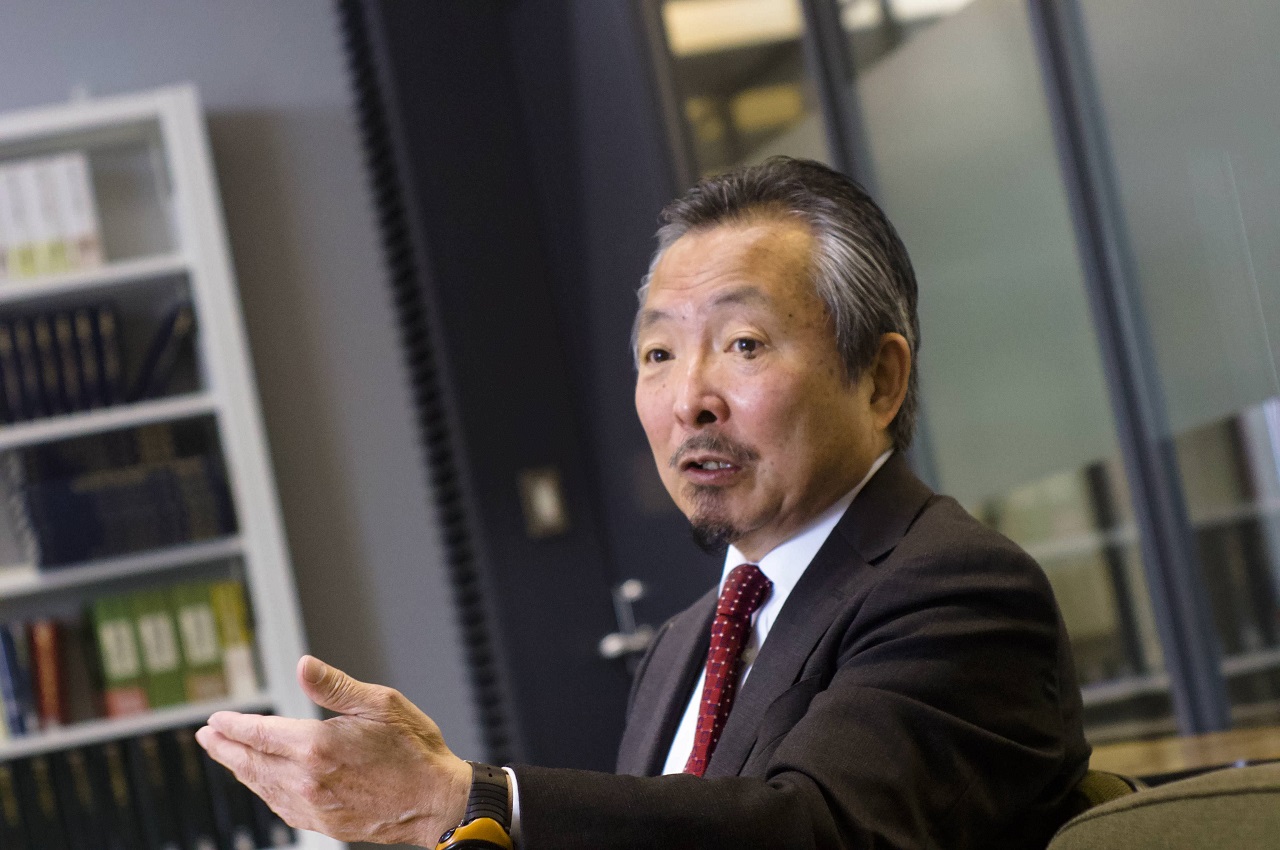
沖縄には古墳はなく、この地域だからこそ可能な考古学というものを探究していた最中である、1989年。卒業論文の指導をしていた中のダイビング好きだった学生が、水中考古学で卒論を書きたいといいだしました。
沖縄ですから周囲は海で囲まれていますし、天草生まれの私にとっても海は身近な存在でしたが、研究対象としてはとらえていませんでした。学生の希望には沿いたい、しかし自分は水中のことはわからないということで、わたしもダイビングのライセンスを取得することに。学生の指導のためには自分自身がまず水中考古学を理解せねばいけないと、いくつかの調査現場で潜水作業を体験し、学生に引きずり込まれる形で後に「鷹島海底遺跡」と呼ばれる一帯の調査に参加させてもらい……という日々を過ごすうち、当初遊びにいっていたようなものだったわたしが、現地の報告書作成を手伝うような状況になっていき、いつの間にか水中をフィールドにするようになっていました。

「鷹島海底遺跡」の一帯では、かねてより漁師さんの網に蒙古襲来を物語る遺物がかかることがあり、1980年からはさまざまな先達の方々により、調査研究が断続的に進められてきていました。そのうちのおひとりが、北海道江差町・江差港沖合で発見された旧江戸幕府軍艦「開陽丸」の調査研究で知られていた、荒木伸介先生です。1970年代から一貫して、日本の水中考古学研究のパイオニアでいらした先生でした。荒木先生とのご縁で、1992年以降に私も「鷹島海底遺跡」の調査研究に深く関係するようにもなり、水中考古学についてもますますのめりこんでいくことになったわけです。
とはいえ、最初からすべてが順調だったわけではありません。沖縄でダイビングしているときは、水中も透明で綺麗なものなんです。しかし、沖縄を離れればまったく事情は異なってきます。鷹島で初めて潜ったときはびっくりしました。自分の目の前もほとんど見えない、まるで味噌汁のなかにいるような状態。海中に張ってあるロープを辿りながら発掘地点までたどり着くのですが、慣れるまでは怖かったですねえ。

それでも何とか携わっていくうち、荒木先生から、今後の調査は君がやれ、という話をいただきました。沖縄行きのときもそうでしたが、先生や先輩からそういわれたら私は「はい」と言わざるをえません(笑)。2006年からは、自分なりに調査手法の模索を繰り返しながら、松浦市と私たちの研究チームで共同調査するようにまでなりました。
何が、そこまで自分を動かしたのでしょうか。鷹島にしたって、当初は指導している学生が調査に参加するというので、引率がてら一緒にいき「お魚が美味しいなあ」くらいに思っていたような状態から、真正面から取り組むに至ったのですから、不思議なものです。
しかし、いざ自分で取り組むとなれば、まずは調査のための基礎情報を取得する方法を考えていくようになりました。その手始めとして音波探査によって、地図と地質の情報をできるかぎり正確に取得するやり方を試行錯誤していったんです。そうしたひとつひとつの積み重ねのなかで、沈没した二艘の元軍船の発見がありましたし、インタビュー前編でお話したような海底からの遺物の引き揚げから保存処理をめぐる試行までの過程があるのです。
正直なところ最初は決して、水中の「ロマン」に胸を高鳴らせる、というようなことではなかったわけです。「一体これは、どうすりゃいいんだろう」と頭を抱えて、ジタバタすることからはじまっていく(笑)。しかし、何か試すたびに、次の課題が出てくる。そしてその課題にまた取り組む、という作業がエンドレスで進んでいく。そうした事態の連続、それらと向かい合うプロセスが、まるでらせん状に連なるようにずっと続いています。
それはきっと、新しい学問領域であるからこそ起こるようなことなのだと思います。そうした刺激的な“場”に、私は研究者として遭遇できている。それはとても幸せなことなのだろうと、これまで続けてきて感じているところです。

水中考古学の最前線について、池田榮史教授が語る前編「潜って見つけるだけではない、水中考古学がおこなう未知なる挑戦」はこちらをタップして進んでください。