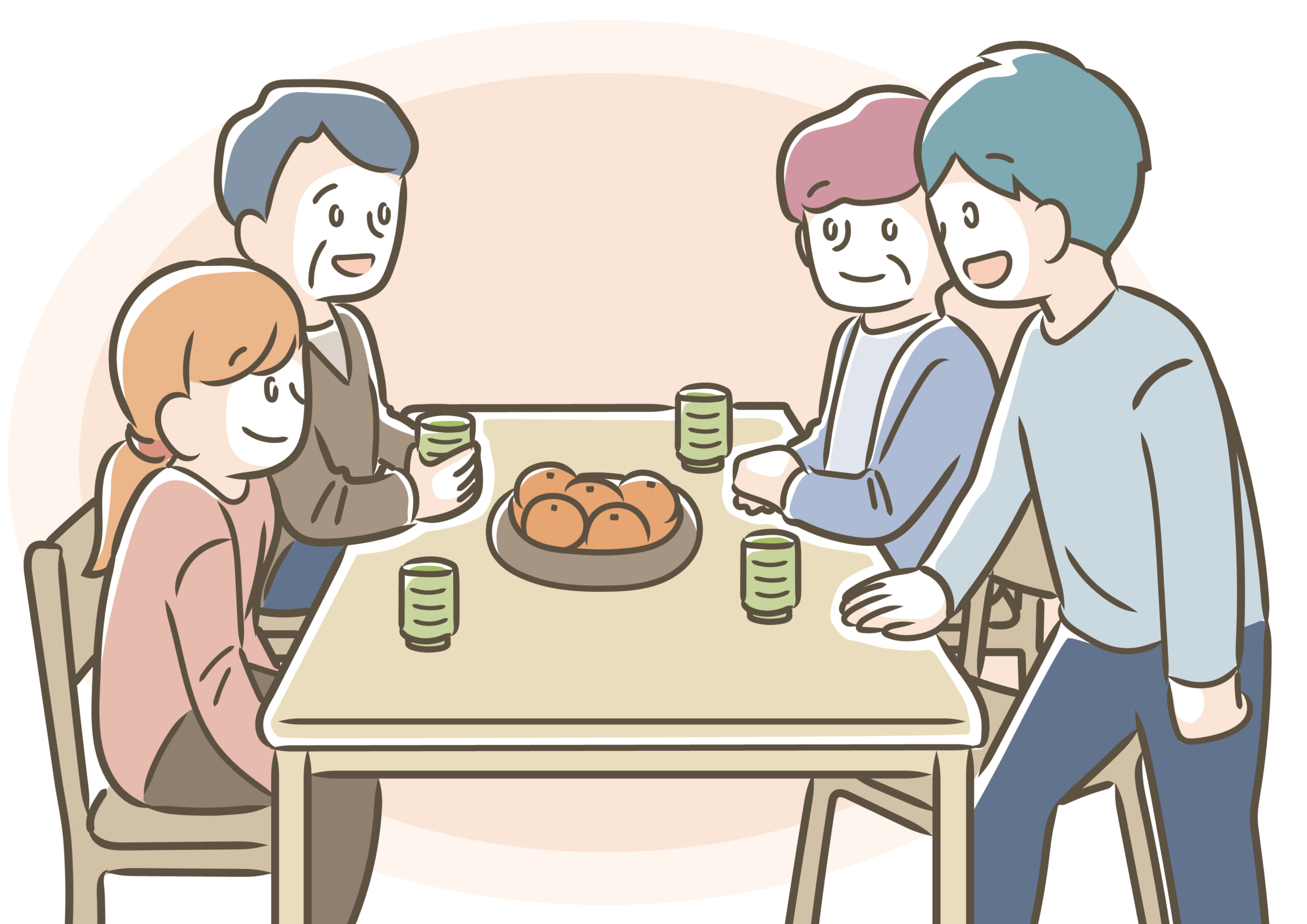近くて遠い? 遠くて近い? そんな親の気持ちや大学生の子どもの気持ちを考えます。
「たった一人しかいない自分を」
山本有三の『路傍の石』の中で、吾一少年は、鉄橋の欄干にぶら下がるという行為に対して教師から厳しく叱責されます。
「たったひとりしかいない自分を、たった一度しかない人生を、ほんとうに生かさなかったら、人間、生まれてきたかいがないじゃないか。」
吾一という名には、世界中に我=吾ただ一人の存在であるという意味が込められている、と諭されます。まさに「尊在感」づくりの一コマです。
今回は、尊在感づくりについて「持ち場づくり」の視点で考えましょう。
「場を得て、子どもは光る」
あなたの子どもの「席」(ポジション)はありますか?今日、社会で、職場で、学校で、そして家庭で、掛け替えのない存在としての持ち場が得られているでしょうか。
「場を得て、子どもは光る」。私自身、この言葉を使って、荒れた中学校を地域やマスコミに評価されるまでに立ち直らせたことがあります。
それは、学校訪問時に目にした壁新聞の表題の一つから始まりました。
「あなた班長、私ただの人」。
班長には存在感がある。だが、自分のような「その他」の人間は、「お客さん、おまけ、付録」の存在でしかない、という人生諦め宣言に思えました。
ここから、生徒一人一人の持ち場づくりに向けた教育活動の全面見直しの戦いが始まりました。
それは、「班長の居ない班づくり」(班長中心の「アーモンドチョコ班」(アーモンド=班長が無くなればただのチョコレート)から、誰もがリーダーの「金平糖班」(場面場面に応じて突起がリーダー)へ)、「一人一役活動」、1日1回は教師の声かけが保障されるよう授業毎に授業者が出席簿に書き込む「スキンシップ大作戦」など、です。
校長が「殺人以外は何でもある」と豪語した学校が、3年後には、挨拶が行き交い、街を花いっぱいにするボランティア活動などで表彰される学校へと変貌しました。
家庭は本来「ガラスの城」
コロナ禍の中、学生たちは社会で持ち場失い、「損在」感に陥っています。
例えば、昨年「学報」11月号で、彼らが、就活で「ガクチカ」(学生時代に力を入れたことや頑張ったこと)が語れず、言い換えれば「自分探し」ができず、大変困惑をしていることを報告しました。
それでは、家庭ではどうでしょうか。
実は、家庭はそれでなくとも、社会学の視点から言えば、その原初形態としてはとても壊れやすい「ガラスの城」なのです。
なぜならば、家庭ほどの、男女(性差)、親子(世代間)という異質な者同士の結びつきの社会集団はありません。しかも、その異質性故に結びつきの意味や根拠を持つという社会集団は他に例がありません。
しかし、多くの人は、家庭は同質性の高い集団、と思い込んでいます。実は、家庭における同質性は、本来的に存在するものではなく、家庭を構成するメンバーが各自の持ち場を通して「獲得」しているものなのです。
「あなたの子さんの『席』はありますか?」
我が家では、幼児期の「いただきます係り」から始めました。3歳の長女が「いただきます」
と言わなければ、誰も箸を持てません。5歳の長男は、「玄関大臣」。玄関の靴並べは彼の「仕事」。彼は、起床すれば直ぐに、この「業務」に就きます。「一人一役」です。
女優で重度障害児学校「ねむの木」養護学校長だった宮城まり子氏は、ねむの木園児がユネスコ図画コンクールで優勝した際、「どうしてあのような素晴らしい絵が描けるようになったのですか」という記者団の質問に、次のように回答しました。
「みんなに愛されている、みんなに信じられている、みんなの役に立っているという自信が、あの絵を描かせたのです」
「あなたのお子さんの『席』はありますか」。もう一度、自問してみてください。
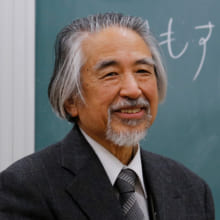 |
新富 康央(しんとみ やすひさ) 國學院大學名誉教授/法人参与・法人特別参事 |
学報掲載コラム「おやごころ このおもい」第14回