 「羅生門絵巻」巻一(17世紀半ば、國學院大學図書館蔵)烏帽子、侍烏帽子を被り、ひげをはやした大人に対し、子どもたちは頭の被り物はない
「羅生門絵巻」巻一(17世紀半ば、國學院大學図書館蔵)烏帽子、侍烏帽子を被り、ひげをはやした大人に対し、子どもたちは頭の被り物はない
成年年齢が令和4年4月1日から、18歳に引き下げられる。成年の定義が見直されるのは約150年ぶりになる。日本で「成年」という考え方はいつ始まり、定義はどう変わってきたのか。民俗学を専門にする文学部の小川直之教授は「庶民世界には3つの『大人』の基準があった」と話す。
庶民は男子15歳、女子13歳が成年だった
なぜ成年という考え方があるのだろうか。小川教授は「国家制度として義務と権利を考える時に一定のところで線を引かねばならない。男女、年齢をもとにした線引きが必要だった。これが法令としての『成年』で、こうした考え方はすでに奈良時代以降の『元服』にもある」と解説する。
一方、法令ではなく庶民生活の中でみていくと「男子15歳、女子13歳を成年とすることが戦後社会まで続いていた。女性は初潮、男性は精通が始まり、肉体的に大人となる時期を成年とした」(小川教授)
この年齢に達すると男性は「若者組」、女性は「娘組」と呼ばれる組織に入る。若者組は明治時代以降、青年会、青年団への展開していくが、これは消防活動などを行う地域の自衛組織で、地域社会の一員として育っていった。「若者条目」と呼ばれる組織ごとの決まりがあり、船の遭難や出火では、若者たちが駆けつけて対処しなければならないとされていた。厳しさがある一方、村の祭りを受け持つなど楽しみもあった。これへの加入が「ムラの大人」入りであった。
娘組も男性と同様、一つの場所に集い裁縫などを教え合い、家事技術の向上を目指した。
小川教授は「若者宿といって男女別々に集まり、寝泊りをする場所があり、男女の交流もあった。若者組や娘組が強い地域は恋愛の自由度が高かった」と説明する。
庶民世界の「大人」には「3つの基準」があった
また、江戸時代までの絵巻物を見ていくと、成年の年齢に達していることが視覚的に明確だった。武家社会では男性は烏帽子をかぶるのが成年の証だったし(記事上部「羅生門絵巻」図)、女性は13歳になると眉毛をそり、お歯黒を塗った。身分や年齢が可視化された時代だった。いわゆる加冠式などと呼ばれる儀式はこの考え方である。
小川教授は「大人と判断される基準はもう一つある」と話す。それは「一人前」という基準だ。例えば男性の場合は、鍬で田畑を1反耕すことができれば一人前とされた。女性は反物を1反織ることが一人前の証だった。
整理すると戦後社会までの「大人」の基準には①年齢に基づく基準、②肉体的な成熟による基準、③「一人前」(実力主義)かどうかの基準。という3つがあったことになる。
小川教授は「国家が定める『大人』と、地域が認める『大人』が異なり、多様な社会だった。現代が無理に年齢という一つの基準に当てはめようとしているのでは」と話す。
大人とは何か深く考えて 信頼できる人とのつながりも大事
成年年齢の引き下げについて、小川教授は、「世界の多くの国々が18歳を成年とする流れの中で、日本も18歳を成年とすることに違和感はない」とした上で「もっと自分の知識や技を磨き、実力を思考する若者たちが出てきてもいいように感じる。国家制度としては18歳という一つの年齢にせざるをえないかもしれないが、学生たちには一つに考えずに大人とは何かを考えてほしい」と訴える。
現在も職人などのように「技(わざ)」を重視する世界では「一人前」を重視し、これを目標としている。自分自身の「大人」の要件は何か、そのためにどんな目標を立て、どんな課題をクリアしなければならないのか考えてほしいということである。
小川教授はまた、自分の親や家族だけではなく、自分の周りで信頼できる相手を見付けることも大切だと指摘する。戦後までは、男性は15歳の成年となった時に「烏帽子(えぼし)親」などといって、親以外の別の「親」を立てる習慣があったという。
小川教授は「成年を迎えるということは、自分をどう成長させるかということと、新しい人間関係を構築すること。未来に向かって進んでほしい」とエールを送る。
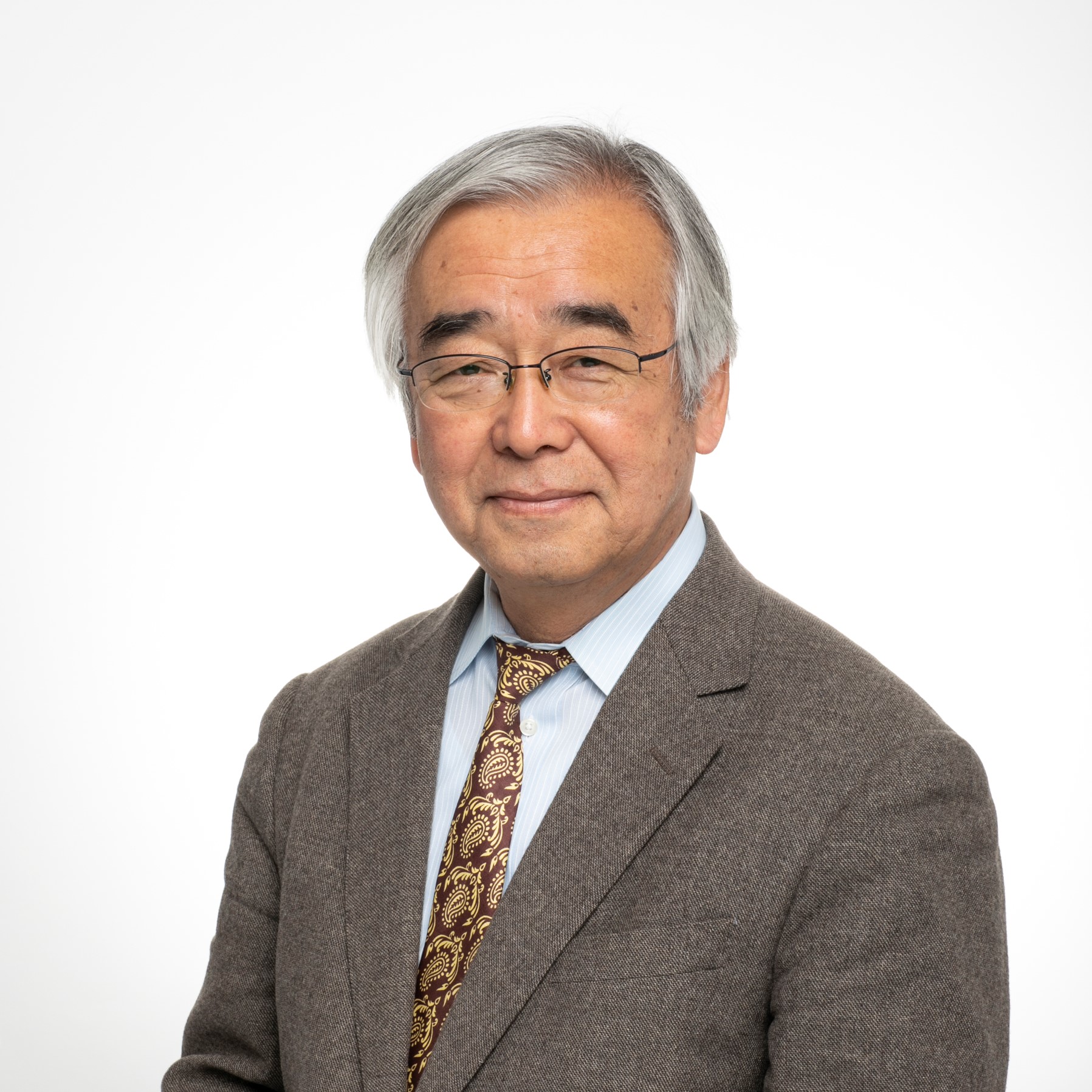
小川 直之
國學院大學名誉教授、柳田國男記念伊那民俗学研究所長。博士(民俗学)。
研究分野:民俗学
主な著書:『地域民俗論の展開』、『摘田稲作の民俗学的研究』、『歴史民俗論ノート』(岩田書院)、『日本の歳時伝承』(アーツアンドクラフツ、角川ソフィア文庫)


