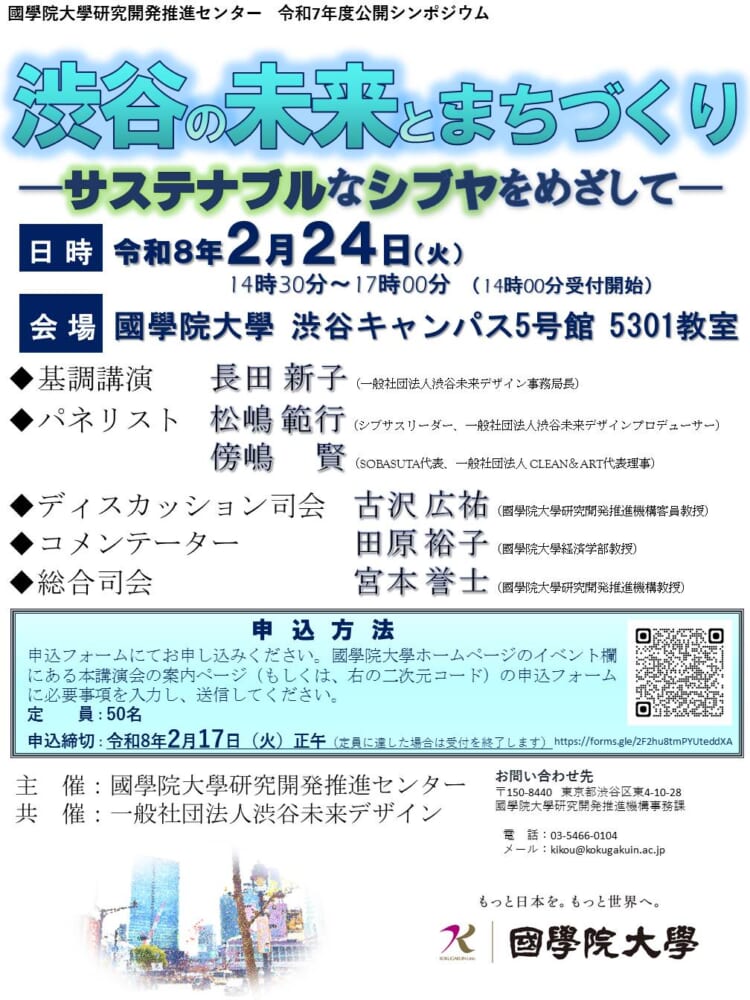神道文化学部の大道晴香助教(専門:宗教学)は「メディアとは、2つの離れた領域の中間にあり、この2つのコミュニケーションを媒介するものだ」と語る。宗教とメディアの歴史を紐解くと、神霊の言葉を人間に伝える「巫女」や、天国や地獄のような見えざる世界を描いた「絵画」など、五感で感知できない宗教的な領域と、私たちはいつでもメディアを通じて交流してきた。そして、カメラやインターネットなどのテクノロジーを擁した新メディアの誕生は、単なる「既存の手段の代替」や「選択肢の増加」にとどまらず、私たちと世界との関わりを抜本的に変容させている。
【前編】「映える」聖地の「見えない」場所
―― カメラの登場は宗教とメディアの歴史を揺るがした
聖地に撮影禁止の区域を設ける行為や、神仏にレンズを向ける行為を「不謹慎」と捉えるような感覚は、ごく自然な、当たり前の現象と思われるかもしれない。しかし、これらはカメラが登場した近代以降、特にカメラが人々に広く普及したここ数十年で定着した、新しい宗教文化である。複製可能な写真を通じ、カメラは被写体を不特定多数の人の視線にさらす。また、被写体を写真や画像データという個人の「所有物」へと変えてしまう。しかも、被写体の「分身」である写真には、呪術性が生じる。
例えば、遺影は不要になっても、ゴミとして廃棄することは憚られるという人は少なくない。ただの写真でしかないのだが、カメラのまなざしが映し出した写真を媒介として、対象物に何かしらの影響を与えたり、霊媒的な作用が写真というメディアに付与されていると感じたりする人が多い。人間の目とは全く異なるまなざしをもつカメラの登場は、宗教とメディアとの歴史において、インパクトをもつ出来事だったに違いない。
―― 宗教文化が視覚に敏感になったのは、カメラの登場が影響したのか
聖なる場所では、人間の目は問題ないが、カメラのまなざしはNGというケースもある。しかし、「聖なるものをみだりに視線にさらしてはならない」という考え方は、カメラが登場する前から存在していた文化や秩序性である。信仰上の理由により非公開とされている秘仏の存在や、「見ると祟られる」という俗信など、その例は枚挙にいとまがない。
聖なるものは「見ること」「見られる」ことに対して非常に敏感な文化事象だといえる。宗教に内在していた視覚を重んじる伝統の延長線上に、聖なるものをメディアで写してはいけないという秩序があり、それを後押ししているのが、カメラというメディアの特殊性と考えられる。

―― 新しいメディアの誕生は、人と宗教とのかかわりをどう変えるのか
新しいメディアは、古いメディアの代わりをするのではない。例えば、電子書籍は本の機能を代替しているだけではなく、私たちに全く違った経験をもたらしている。紙の本は光を当てて読むが、電子書籍は自ら光を発する。ページは手でめくるのではなく、指でスライドさせる。新たなメディアは、聖なるものと人との関わり、そしてメディアに媒介される聖なるもの自体のあり方を変容させる存在に他ならない。だからこそ、そこにコンフリクト(葛藤)が生じ、議論が立ち上がる。
ネット参拝は、村の中でお金を出し合って、代表者に参拝してもらう「代参」や、遠くから聖地を拝する「遥拝」とどう違うのか。何かしらの媒介を挟んで、聖なるものに参拝するという意味では、ネット参拝も変わらない。
コロナ禍では、ネット参拝の評価にも変化が表れているように思われる。学生に意見を求めると、「神前に出向くことが重要だ」と否定的な意見がある一方で、「行きたいけど行くことができないのだから、むしろ、ネットを通してでも参拝する行為は強い信仰心の表れではないか」という声もある。ただし、肯定派も正規の参拝とネット参拝の経験を区別し、あくまで仮の手段と捉えているのは興味深い。

―― 新メディアが次々と登場する時代に、人間と宗教の関係性の今後は
新しいメディアの登場は、聖なるものと人との関係性を再考するには良い契機になる。伝統が崩れてしまうのはダメなことと思われる向きもあるが、そもそも宗教は人々の希求に応える役割を果たしてきた「生きた文化」であり、その時々の人間社会を反映している。社会の価値観やあり様が変わる中で、宗教文化もまた姿を変えていくのは当然の流れだろう。
大道 晴香
研究分野
宗教学、宗教とメディア
論文
スーパー戦隊シリーズ初期作品に見る敵と〈宗教〉 : 「バトルフィーバーJ」と「太陽戦隊サンバルカン」を中心に(2025/08/15)
異境から〈秘境〉へ―南洋一郎の冒険小説に見る戦後の改訂作業をめぐって(2024/03/20)