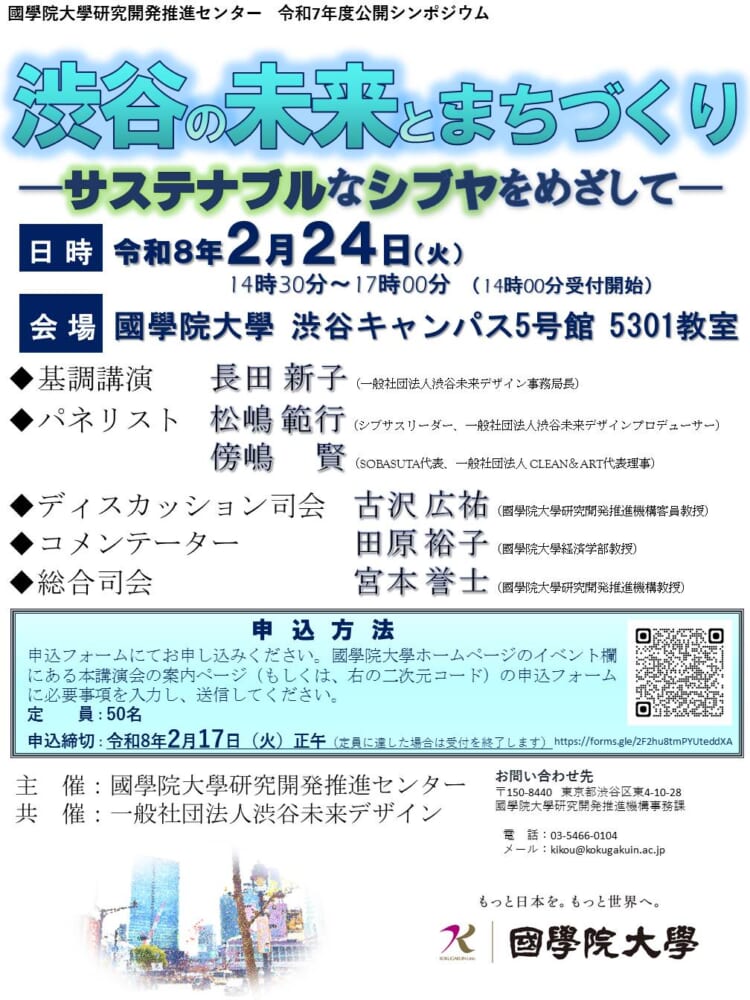エンドースメント契約という言葉をご存じだろうか?
「かみ砕いていえば、スポンサーシップの一環です。特に企業とアスリートのパートナーシップというとらえ方になります」
そう教えてくれるのは、人間開発学部 健康体育学科の備前嘉文准教授。昨今、スポーツにおけるアスリートへのスポンサーシップは、スポーツマネジメントの観点から鑑みて必要不可欠な時代となっている。スポンサーシップといっても、“プロ/アマチュア”、“資金援助/用具提供”という具合にさまざまな契約形態があり、アスリートへのサポートは多岐にわたる。「アスリート自身がアスリートとしての価値をどれだけ高めていけるか――、そういった課題とも密接にかかわってきます」と説明するように、 新しい時代のスポーツとアスリートを語る上で欠かせない存在が、“エンドースメント契約”だ。東京2021オリンピック・パラリンピックが迫る中で、現在のスポーツを取り巻く環境と、スポーツとお金・スポンサードの関係性はどうなっていくのか。備前嘉文准教授に、契約の視点から考えるアスリートの立ち位置を聞いた。
エンドースメント契約には、主に3種類の契約形態があるという。
「一つ目が、広告・宣伝活動やメーカーが主催するイベントへの参加、商品開発についての助言など広範囲にわたってメーカーに協力する「専属契約」。二つ目がシューズやウエアだけといったように個々の商品のみと契約する「アドバイザリー契約」。そして、契約金は発生しないもののメーカーがアスリートに用具の提供を行う「用具提供契約」があります」
企業とエンドースメント契約を結ぶアスリートのことを“エンドーサー”と呼び、ここ日本におけるエンドースメント契約の歴史は、「1970年代、80年代から徐々に普及し始めていきました」と、備前先生は見解を述べる。
「アメリカでは、19 世紀後半にはすでに食料品やタバコなどの商品の広告に有名人が推奨者として起用されていたといった報告があるように、エンドースメント契約は、アスリートに限った話ではありません。ミュージシャンや芸能人、研究者などの文化人などが企業と契約を締結しているケースもあります」
“エンドーサー”はアスリートだけではない──。一般人も企業とパートナーシップを結べばエンドーサーになりえる……「これってインフルエンサーじゃないの?」。その疑問に対する回答については後述しようと思う。というのも、まずは我が国のエンドースメントの変移をたどっていくと、今につながり、いろいろな答え合わせができるからだ。
日本のスポーツは企業スポーツ(実業団)が主流だった
「分かりやすい例でいえば、読売ジャイアンツの選手たちが『オロナミンC』 の CM に出演したり、大相撲の力士がCM に出演したりするようになったのが、70年代、80年代です。当時は、野球、 相撲といった国民的なスポーツの選手たちだけがエンドーサーとしてスポットを浴びていました」
当時、プロ化していたスポーツは野球をはじめ数える程度。裏を返すと、日本はアマチュアスポーツ、つまり企業スポーツ(実業団)が主流だったのだ。
「企業スポーツにおいては、選手は自社の広告塔という位置づけもあれば、社員たちが総出で応援するという社員の一体感を生み出す福利厚生、イベントという側面もありました。自社のイメージを向上させるためのエンドーサー像……そういったものを企業側もあまり求めていなかったのです」
言われてみれば、企業スポーツは日本と韓国と台湾など局地に限定され、欧米ではあまり見かけない。「一般社員と同じように定期的に給料を貰いながら競技に専念することができるため、選手も企業に守られていたところが多分にありました」。日本のエンドースメント契約があまり進展しなかったのは、企業スポーツが一般的だったという背景が深く関係していたという。
プロ化のターニングポイント“90年代”
ところが、この流れが90年代以降、劇的に変わる。備前先生は、ターニングポイントを次のように説明する。
「一つは、バブル崩壊による資金不足から派生した企業スポーツの衰退。そして、その最中に企業スポーツだったサッカーがプロ化、Jリーグとして生まれ変わったこともエポックメイキングな出来事でした。三浦知良選手など、CMやテレビ番組に登場する新しい時代のアスリートが登場しました」
さらに、バルセロナ五輪(1992年)で銀メダルを、4年後のアトランタ五輪で銅メダルを獲得した元女子マラソン選手・有森裕子さんの存在も大きいと話す。
「1996年以前までは、オリンピック種目のアスリートの肖像権はJOC が一括で管理していました。そのため、JOC のスポンサー企業に対してのみ、CM 起用などを行うことが可能だった。ところが、有森さんは異を唱え、JOC のシンボルアスリートから外れる道を選び、自ら自分の肖像権を管理するようになりました」
事実上、日本のプロランナー第1号となった有森さんは、JOCとは一切関与せずにCMに出演。その後、JOCは選手の肖像権の一括管理を断念するまでになった。こういった動きが重なり、1990年代の後半から2000年代にかけてプロアスリート化が加速。当然、企業広報やスポーツマーケティング支援を行うPR会社も増加した。さらには、企業やスポンサー、あるいは球団に対して自身の価値をきちんと対等に伝えるために、欧米では一般的だったスポーツエージェント(代理人)という存在に光が当たるようになった。アスリートの契約の歴史は、日本スポーツ界の変遷と非常にリンクすることが分かる。
プロ化とは競技がプロリーグ化していることではない
選手のプロ化とは、「競技がプロ化することではなく、選手が自立すること」、そう備前先生は伝える。
「エンドースメント契約を結ぶということは、自立の第一歩です。スポンサーシップを結んだ企業から遠征資金の提供や生活のサポートを受ける。対価として、アスリートは結果を出して、表彰台などで企業名が見えるように用具を見せたり、日ごろからウェアを着用したりするなどして、企業のイメージを伝えていく役割を担う」
たしかに、私たちも世界で戦っている選手のウェアに記載されている企業名を見ると、「グローバルな取り組みをしている企業なんだろうな」なんて、選手を通じて企業を感じることは少なくない。錦織圭選手とエンドースメント契約を結ぶユニクロなどは、最たる例だろう。
「エンドーサーの身体的な魅力や、エンドーサーが発するメッセージの信憑性などが、消費者の購買行動に影響を及ぼすことが、研究でも明らかになっています。強い選手、魅力的な選手……そういったアスリートと企業はエンドースメント契約を結びたいと考えている」
“契約を結べるような選手になる”ことがプロだと考えると、新たな視点が生まれてくる。そこには競技のメジャー性、マイナー性はあまり関係ないとも付言する。
「テレビや新聞などのマスメディアで頻繁に取り上げられる=メジャースポーツという認識がありますが、今は SNS を含めてメディアが多様化しています。
メジャー、マイナー関係なく、誰もが発信できる時代。企業に対しても、自身をアピールできる機会が豊かになっています。だからこそ、いかにして自分たちから積極的かつ魅力的に発信することができるかが重要になる」
日本ではマイナー扱いされるかもしれないスポーツも、ひとたび海を渡れば人気スポーツとして周知されていることが珍しくない。「マイナーとは唱えずに、積極的に良いポイントを伝えたほうがいい」と笑い、「結果も大事ですが、協会、競技団体、チームを含めてどうアクティベートしていくかを考える。世の中に対してアピールしていくことが、最終的にビジネスとして結びつく時代になりつつある」と続ける。
アスリート自身にも自己プロデュース能力が求められる
アスリート自身にも自己プロデュース能力が求められる──、ということでもある。
「アスリートは競技力を高めるためにトレーニングをしていますから、なかなか自分たちの価値に気付きづらいところがあります(笑)。しかし、健全さのあるアスリートであれば教育的な面と相性がいいし、国際性のあるアスリートであれば海外展開を視野に入れている企業などと相性がいいわけです。自身のプロデュース力だけでは難しいところもあるでしょうから、そういったことをサポートするエージェントやエンドースメント契約も増えていくのではないでしょうか」
アスリートがいかにして自立し、契約を締結してきたか、という歴史をたどってきたが、その進化は今でいうところのインフルエンサーに近いものがあるようにも感じてしまう。冒頭で感じた疑問、違いは何なのだろうか?
「場合によっては主婦の方や読者モデルも、エンドーサーに含めるという考えもあります。洗剤を使ってみた実感や新着のバッグを使ってみた感想を発信するなどは、言うなればアドバイザリー契約に近い形としてのエンドースメント契約でしょう。インフルエンサーとの違いを挙げるとすれば、エンドースメント契約の場合はスポンサーシップの範囲が広いということくらいでしょうか」
インフルエンサーも、メディアの多様化によって生み出された“伝え手”であることは間違いない。一般人でもプチエンドーサーになれることを考えれば、SNSなどメディアの多様化がもたらした功績は大きいだろう。「マイナースポーツだから……」、だからこそ、そんな消極的なマインドは時代遅れなのかもしれない。
アスリートとしていかに価値を高めていけるか
「自ら発信装置を持つことで、企業の意図やイメージにそぐわない言葉を発信してしまう恐れもある。企業はアスリートのイメージに対してお金を払っている部分もあります。ビジネスという観点から考えれば、「結果を出せばいい」というわけではなくなってきていると思います。アスリートは競技力を高めることを求められますが、これからはそれだけでは厳しくなるかもしれない。スポーツの現場で、社会との向き合い方なども教えていく必要があるのではないか。自らの頭で「どう生きていくか」ということを学ぶことは、引退後のキャリア形成ともつながってきますから」
ともすれば、スポーツ先進国である欧米に学べるところがありそうなものだが、「そうでもない」と微苦笑する。
「プロになった直後、大金である契約金を手にすることで、人生が狂ってしまうアスリートは世界各地にたくさんいます。自立し、いかにしてキャリア形成を育んでいくか……欧米でもなかなか先進的に教育できていないところがある」
契約を介してアスリートを考えていくと、“自らのアスリートとしての価値をどれだけ高めていけるか”という分岐点があることが分かった。スポーツを取り巻く環境は着実に進化し、選手の意思決定によるところが大きくなってきている。「アスリートファーストといった言葉が登場するようになったのは、そういった時代の流れもある」。
自立、ひいては引退後のキャリアのたくわえにもつながるだけに、その下地となる学生時代のスポーツ観も大切なのではないか? そう尋ねると、最後にこんなアドバイスを送る。
「スポーツの目的は大きく分けて二つあります。一つは、今は勝利至上主義がとかく否定されがちですが、競技スポーツであればやはり“勝つこと”です。説明したように、結果を出すことで選択肢が増え、価値を高めやすくなります。もう一つが、スポーツを通じて人生を豊かにしていくという側面です。子どもがスポーツを始めるきっかけのほとんどが、親の意思という研究調査があります。親のエゴになりがちになると、自立心や自制心は養われづらくなります。子どもの自主性を尊重することが、必ず将来に活きてくると思います」
子どものスポーツを見守る親御さん、口を出したくなる気持ちはわかりますが、スポーツをしている子どもを第一に考えること。スポーツをしている子ども、アスリートファーストです(
後編につづく)。