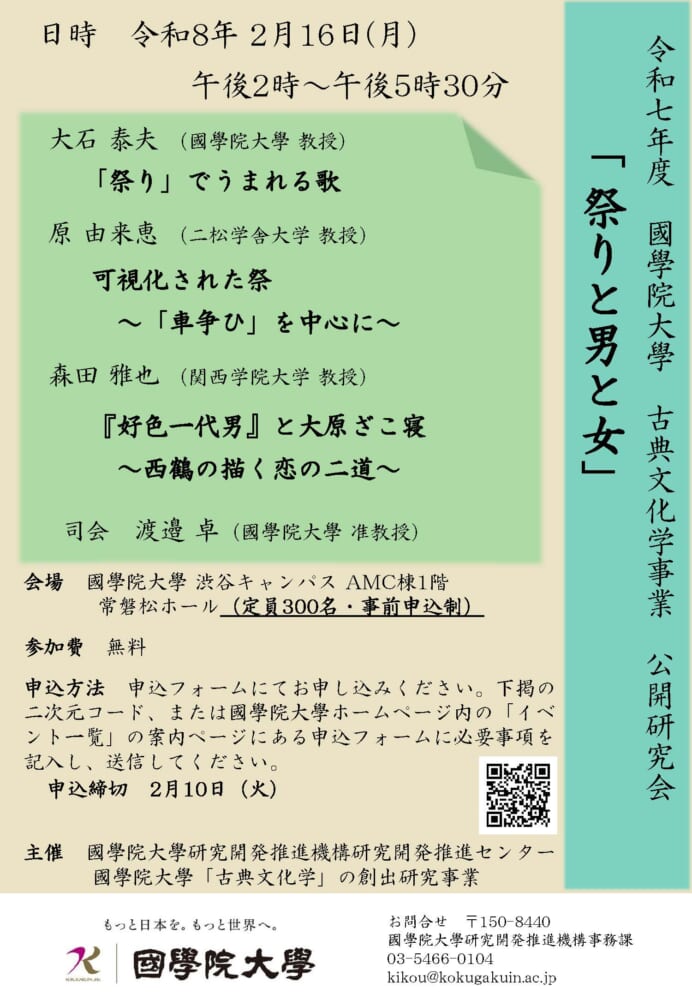(※画面の右上のLanguageでEnglishを選択すると、英文がご覧いただけます。This article has an English version page.)
Q.日本はとても治安がいいように感じますが、これは昔からなのでしょうか?
A.治安がよくなったのは江戸時代からです。
近世の江戸は、18世紀ころに人口が100万を超え、うち半数が武家屋敷や寺社の構成員、半数が町人と呼ばれた庶民といわれています。
町人を支配したのが町奉行所で、南北2つあり、職員は各与力25騎・同心140人(ただし幕末)でした。与力・同心300人余りで50万の町人を支配し、治安を守っていました。ちなみに現在警視庁の警察官は4万3千人です。
江戸は治安がよかったといわれますが、理由は2つあります。1つは、近世は戦乱の世を経て成立しましたが、それは武士たちが合戦と征服を重ねて統一政権を作ったわけではなく、戦乱に巻き込まれて逃げまどっていた人びとの平和への願いを取り込みながら、暴力による紛争の解決を禁止して成立した社会であることです。近世には暴力が悪という社会観念がありました。
もう1つは近世の町や村が自治組織をもち、江戸の町には木戸があって夜間には閉じられ、木戸番や自身番などが設置されたことです。また多く発生した火事に対し、町火消が設置されていたことも、治安にとって大きな役割がありました。

|
名誉教授 根岸 茂夫 研究分野:日本近世史 主な著作:『近世武家社会の形成と構造』(吉川弘文館,平成30(2018)年 |

2015年10月14日付け、The Japan News掲載広告から