子どもの表現を科学する データから見る造形の世界
子どもの造形表現を探究する −後編−
2024年10月15日更新

子どもたちをめぐる課題は、数多い。子どもの造形表現を専門とする島田由紀子・人間開発学部子ども支援学科教授が、子育て支援をめぐる制度的観点にまで踏み込んでいることは、その証左だといえるかもしれない。
前後編で、島田教授が自身の取り組みを語るインタビュー。この後編から伝わってくるのは、子どもたちと触れ合う保育現場からデータ・サイエンスの領域にまで至る、驚くほどの活動範囲の広さ、手法の多様さだ。それはそのまま、子どもたち一人ひとりの多様さへとつながっている。
インタビュー前編でもお伝えした通り、私がこれまでに取り組んできたテーマのうち、保育の実践で役立てていただけるような方法や、そうした視点に立った保育者養成などは、重要な部分を占めてきました。一方で、より研究者的とでも言えばいいのでしょうか、子どもの造形表現をデータの観点から相対化していくような取り組みもいくつか進めています。ときにそのテーマは、子どもの造形表現という枠を超えて広がってもいるのですが、すこしずつご紹介させてください。
研究者としてスタートしたときから取り組んでいるのは、子どもの表現における男女の「性差」です。これは非常にセンシティブな領域でもあるのですが、小さな女の子がお姫さまの絵を描き、男の子は電車や自動車の絵を描くことについては、これまで、実際に見受けられる現象で、国や文化を超えて共通しているという報告もあり、とても不思議に感じています。そういった表現の違いの要因のひとつとしては、家庭や幼稚園、保育所などでのジェンダー観といったものが影響され、描画表現に反映している可能性があります。他方では、そういった表現の違いはある程度は生まれもった性質である可能性もあると考えられています。国立成育医療研究センター研究所で内分泌を専門とされている先生方をはじめとしていくつかの研究の場があり、そこに参加させていただきながら探究を続けているところです。最近では、性別による教育について見直されているので、子どもの絵をはじめ、さまざまな表現がこれまでとは変わってくるのかもしれません。リボンが好きな女の子も、ピンクが好きな男の子も、子どもの表現したい気持ちが尊重されるよう、大人は見守り支えていくことが大切だと改めて考えています。
あるいは、こんな研究にも取り組んでいます。子どもたちの取り組みを「年齢による発達」という指標から見るべきかどうかをめぐっては、本当にさまざまな議論があります。私も年齢による発達段階によって一概に子どもたちのことを判断するべきではない、という意見は理解できます。一方で、幼稚園や保育所等の集団における造形活動を考えてみれば、年齢に応じて、保育者が素材を用意することが必要になると考えています。
たとえば、これぐらいの年齢の子どもには、画材の色数をこれだけ用意すれば、その創造性が十全に発揮できるという観点はあってもいいのではないでしょうか。牛乳パックを乗り物の形に見立てて動かすという工作をする場合でも、紐を通しさえすれば前後にスムーズに動くわけですが、もうすこし年齢が上がれば車輪をつけるということも可能になっていきますよね。保育者が用意した素材のうち、子どもたちがどのような素材をどのくらい使用するのかといった検討は、幼稚園や保育所等の協力を得ながら続けています。
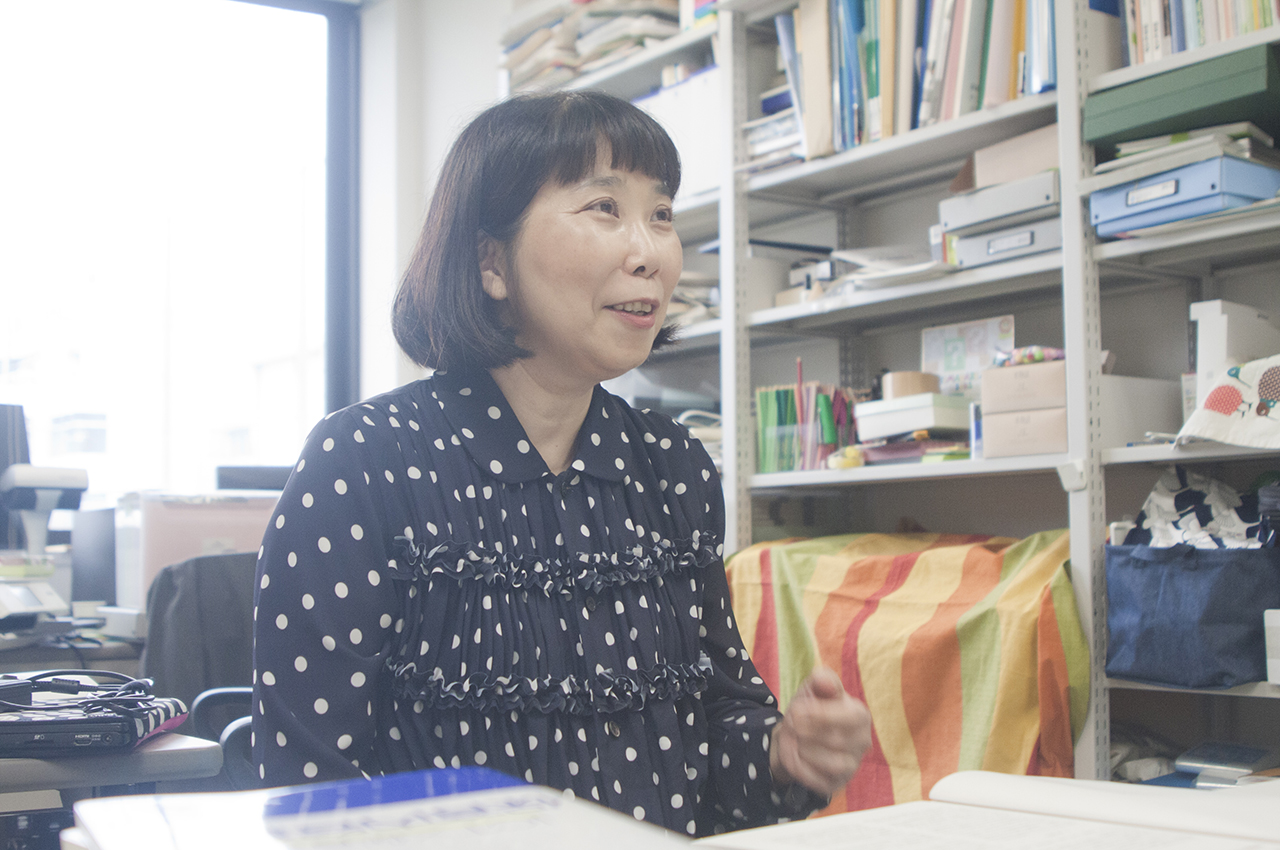
同様に共同研究に参加させていただいて取り組んでいるものに、インクルーシブな画材の開発というものがあります。目の見えないお子さんが色を楽しみながら絵を描くには、どんな画材があればいいだろう、という研究ですね。ここではいろいろな問いと技術的な課題があって、私としては触ったときの体感温度の違いが色の違いとなれば──たとえば熱く感じれば「赤」というような──いいのではないかなどと考えてしまうのですが、なかなか技術的に難しいようです。
絵具の色によって感触が違ったり温度が違ったりしたら、面白そうな気がしませんか?今まで視覚的な印象で選んでいた色彩が、感触や温度の印象も加わり、絵の表現も変化するような気がします。また、描いた絵を視覚的な鑑賞だけではなく、感触によって鑑賞することができると、鑑賞する心の動きもこれまでとは変化するように思います。例えば、赤い太陽の部分を触ると熱く感じる、青い海を触るとひんやりした感覚が味わうことができる。現実的には難しいかもしれませんが、諸感覚を使って絵を描く、鑑賞することができたら、これまでとは違った絵画表現の楽しみ方が増えるように感じています。

他方で、現在、同じく子ども支援学科の教授で乳幼児を専門としていらっしゃる塩谷香先生と一緒に進めているのが、「幼稚園における2歳児保育と子育て支援」というテーマです。文部科学省は幼稚園における2歳児の受入れを推進することで、待機児童の解消や3歳以降の幼稚園教育への円滑な接続、家庭との緊密な連携や保育者の資質向上をめざすとしているのですが、実際の保育の現場で、あるいは保護者のニーズという観点において、どういった課題があるのかといったことを調査してきました。今後は、保育内容、特に表現遊びについて幼稚園の2歳児保育ではどのように考えられ実践されているのか研究をすすめていきたいと思っています。
気づけば、取り組むテーマが四方に広がっていて、慌ただしくしてしまっているのですが、どれも誠実に取り組むべき課題です。できる限りのことをしていきたいと思っているところです。
<<前編は「色と形を探求し、子どもたちの造形教育と創造性の発展を考える」
| 1 | 2 |
島田 由紀子
研究分野
幼児の造形表現、美術教育、保育者養成
論文
子どもの造形表現と保育者のジェンダー意識(2025/03/31)
Machine learning trial to detect sex differences in simple sticker arts of 1606 preschool children(2024/06/01)


